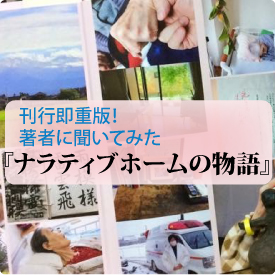かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

第4回 「患者の気もち」とは・・・
2017.6.10 update.

にしむら げんいち(左) 1958年石川県金沢市生まれ。消化器外科医として30余年臨床に従事する傍ら、いしかわ観光特使など多彩な活動で知られる。2006年金沢大学付属病院臨床教授、2008年金沢赤十字病院外科部長、2009年同副院長。2012年石川県医師会理事。2015年3月切除不能進行胃がん発見,数々の啓発活動を経て2017年5月31日逝去。2016年「元ちゃん基金」創設、NPO法人「がんとむきあう会」設立・理事長。「元ちゃんハウス」オープン・運営基金創設。著書『余命半年、僕はこうして乗り越えた!』(ブックマン社)。「がんとむきあう会」ウェブサイト
むらかみ ともひこ(右) 1961年北海道歌登町(現・枝幸町)生まれ。2006年から財政破綻した夕張市の医療再生に取り組む。2009年若月賞受賞。2012年NPO法人「ささえる医療研究所」理事長。2013年「ささえるクリニック」創立。岩見沢・栗山・由仁・旭川周辺の地域包括ケアに従事。2015年12月急性白血病発症。再発を経て2017年2月退院。5月、再々発・闘病を経て11日逝去。著書『医療にたかるな』(新潮新書)『最強の地域医療』(ベスト新書)。「ささえるクリニック」ウェブサイト
北陸と北海道、病院勤務と地域開業――対照的なそれぞれの現場にあって、それぞれの姿勢で医療に尽くされてきた2人のベテランドクターが、同じ時代にがん患者となって闘病生活を続けられるなか再会を果たされ、ともにケアの意義を語る盟友になりました。
その2人の「患者医」 西村元一氏と村上智彦氏に、毎回がん医療にまつわる、共通の「お題」(テーマ)に回答いただき、彼らをささえる人たちとのコラボレーションとともに紹介する特別連載、第1回「がんと向きあう」・第2回「死の受容」・第3回「患者の居場所」に続く第4回は...
*5月11日に逝去された村上氏・31日に逝去された西村氏より、ともに本連載への回答遺言を託されています。継続して更新してゆきます。【本文中敬称略】
テーマ●「患者の気もち」とは......
患者の本当の気もちは
患者になってみて初めてわかる
家族、ましてや 医療者には はかりしれない
西村元一
【解説――北陸の地域ではたらく同志として】
他人の事なんてわかるはずがない。
わかったような軽い綺麗な言葉は、
きっと見透かされていて、
患者を傷つけてしまっているのだろう。
次のような一節がある。
人は誰でも、他人に理解されないものを持っている。もっとはっきり云えば、人間は決して他の人間に理解されることはないのだ。親と子、良人と妻、どんなに親しい友達にでも――人間はつねに独りだ。

(病気が完治するのが厳しいと言われた時の気もち?)
村上智彦
【解説――ともにあゆむ仲間として】
村上はこの時期に、白血病の再々発を宣告されていました。
第4回ゲストコメンテーター●佐々木淳 「ふたりの言葉に誓う」
 僕はおふたりの言葉を知って、実は内心、少しほっとした。
僕はおふたりの言葉を知って、実は内心、少しほっとした。

次回予告:「人生のものがたり」とは・・・
[医療者と患者・家族のふたつの目線で、なっとくのケアを探そう]

編:村上 紀美子
患者の目線で話してみませんか
患者の本当の声を聞くことから始まる「患者が主人公」の医療。それがわかっていても、なかなかできないのが現実である。本書では、医師、看護師、看護教員、医療ジャーナリストなど、20名の医療関係者が、自身の患者・家族体験をもとに〈医療者のおかれている事情〉と〈患者・家族としての本音〉のふたつの“目線”から、「なっとくのケア」へのヒントを医療者に向けて語りかける。