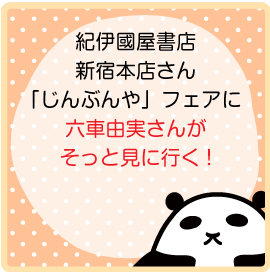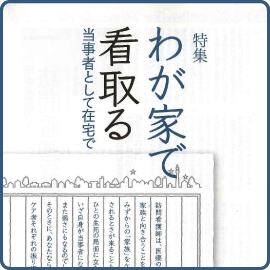かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

【第8回】リネン庫での決意~そうだ、京都へゆこう
2013.6.15 update.
いとう かよこ:千葉県千葉市在住。法律事務所勤務後、国立病院機構の介護職員として勤務。2008年りべるたす株式会社設立、代表取締役(在宅障害福祉サービス事業所管理者)。介護福祉士・社会福祉士・相談支援専門員。千葉大学大学院人文社会科学研究科博士前期課程修了,立命館大学大学院先端総合学術研究科博士後期課程在籍中。第47回NHK障害福祉賞第2部門(障害のある人とともに歩んでいる人)優秀賞受賞。 「りべるたす」ホームページはこちらから
おおやま りょうこ:千葉県千葉市在住。本連載のイラストレーター。 2009年特定非営利活動法人リターンホーム設立、代表理事(長期療養者へのエンパワメントを行うための研修事業等)。SMA(脊髄性筋萎縮症)療養のため、1978年大和田小学校から下志津病院隣接の四街道養護学校転入。1983年同小学部卒。86年同中学部卒。89年同高等部卒。 「リターンホーム」ホームページはこちらから
大山良子さん――“大山ちゃん”は、病院で心を開かない患者さんでした。
通りいっぺんの話はしてくれても、スタッフと真情のこもった言葉を交わすようなことはありませんでした。
大山ちゃんはSMA(進行性筋委縮症)で、7歳から病院で入院生活をしていたそうです。病院併設の養護学校に通うためには入院は必須だったし、自宅からとても遠かったので、親許を離れて病院で暮らしながら通学していたそうです。(第1回)
ただ、そんな大山ちゃんも小学校1年生と2年生の夏までは地元の学校へ通っていました。お母さんが毎日付き添って登校していたそうですが、当時“障害児は養護学校へ”という風潮が強くあったようで、それは続けられないことでした。
この生い立ちを聞いても、私にはにわかに信じられませんでした。自分の人生は、もっと「自由」が当たり前にありましたから。
そう、大山ちゃんと私は2歳しか年齢が違わないのに、私がもつ自由を、彼女は何一つもっていないと感じたのです。
学校を選ぶとか、受験とか、住む場所とかそういうものを選んできたことはないと彼女は言っていました。
「同級生はどうしているの?」と聞くと、「みんな死んでしまった」と言うのです。
「病棟で仲間が順番に亡くなっていくのが何より辛い」とも聞きました。
私たちアラフォー世代では、同級生が亡くなるということは滅多にありません。しかし、大山ちゃん曰く、「病院で暮らすということは、療養仲間の死を知らされることの連続」だというのです。
養護学校高等部を卒業してからも家に帰ることなく、療養病棟で暮らしてきたそうです。では、その病棟ではどんな治療を受けているのかと聞けば、貧血の薬を飲んでいるだけとのこと。そんな大山ちゃんが、病院からどうしても帰りたいという様子にも見えず、今の生活に疑問を持たずに日々淡々と暮らしているように見えることに、違和感を募らせていきました。
数ヶ月勤めるうちに、私はだんだん筋ジス病棟のあり方がわからなくなっていました。どうして彼らが暮らす場所が、「病院でなくてはならないのか」。(第3回)
どうしてこのような暮らしをする必要があるのかが理解できないのです。
私が介護職として直接ケアしている感触では、彼らがどうしても病院で暮らさなくてはならない理由があるとは思えず、それは「社会的入院」だとしか思えなくなりました。
ただ、私には医療技術や医療的ケアのことがよくわからないので、病院で出会う患者さんたちは、私が思う以上に医療が必要で、病院でないと絶対に生きられない人なのかもしれないとも思いました。それがどちらなのかわからないのです。
面会者がきて“お見舞い”という形式で話をしていることにさえも、違和感を覚えるのでした。大山ちゃんたちの病院暮らしは、「生活」というには生の感覚が足りないし、「医療」というほどに濃密な治療を受けてもいない中途半端な状態だと私には思えました。
それを国家公務員が「政策医療」として担っていることへ疑問を感じてしまうのです。
日本の医療は国民の保険料等でまかなわれる国民皆保険制度であり、国民の理解が得られない長期入院は厳に慎むべきです。
法学部で学んだ私は、民間ではできない医療を担う「政策医療」の病棟で、まさか社会的入院はあり得ないと思っていました。もし本当に社会的入院をしているのなら、地域に社会資源がないからかもしれません。しかし、そうだとしても病院で入院という形をとることがどうも不自然に思うのです。
民間筋ジス病棟の歴史を調べると、2007年に民間で初めて鹿教湯三才山病院に筋ジス病棟ができることになっていたし(現在はできています)、同じく政策医療として行われている重心病棟が国立から民間に経営移譲しているケースは過去にもいくつかありました。
2001年 国立療養所足利病院から、社会福祉法人〔全国重症心身障害児(者)を守る会〕へ移譲
2002年 国療日南病院から、社会福祉法人へ移譲
2003年 国立療養所南愛媛病院、国立療養所美幌病院、国立療養所小樽病院から社会福祉法人へ移譲
公でなく民間でもできることは、すでに何年も前に証明されていたのです。
このような事実は、私がみずから福祉事業所を立ち上げて、政策医療として行われている「重度障害者の生活支援」の一端を引き受けていくことの後押しをするには十分でした。
私はインターネットで公開されているブログを通じて、24時間人工呼吸器を装着している筋ジストロフィー患者さんで、在宅で一人暮らしをされている田中正洋さんを知り、連絡を取らせてもらいました。
聞けば、田中さんは16年ほど筋ジス病棟で暮らしてから、在宅で独居を始められたとのこと。病院でなくても在宅でも充分に暮らせるのではないかと感じていた私には、実際に病院から在宅へ移行した方がいたことは、とても大きなニュースでした。
田中正洋:地域での自立生活をはじめるには ~病院から自立,そして地域活動へ,難病と在宅ケア13(5): 47 -49 2007.
田中さんは、「僕でよければ協力はできる限りさせて欲しいです」と、力強い言葉をくださいました。そうしてメールや電話でやり取りを重ねて情報提供を受けられるようになりました。 24時間鼻マスク人工呼吸器をつけて病院で暮らしていたデュシェンヌ型筋ジストロフィーの彼が、在宅のお医者さんに片っぱしからお手紙を出して往診医を探して一人暮らしを始めた経緯を聞くと、病院で決まった薬も飲んでいない大山ちゃんの在宅生活は、もっとずっとハードルが低いのではないかと思うのでした。
後はこうした情報を直接患者さんに伝えて、勇気と覚悟を持ってもらえたらきっと病院から出られるだろうに……、と。
※田中さんは病院の医師から「重病人」と言われてお風呂に入れてもらえなかったのですが、ご自身ではそれを疑っていたそうです。食事形態も食事介助の時間の都合でペーストに変えられていましたが、もっと食べられると思っていたそうです。それが病院を出たらやはりできたというのです。在宅に移行することで、病院に入院している重病人というレッテルは見事にはがすことができたという話は、私が「筋ジス病棟の患者さんたちは病院で暮らさなくてはならないのか」という疑問に見事に応えてくれているものでした。
ふたりきりのリネン庫で
そんなあるとき,病院のリネン庫で大山さんと二人だけになる機会がありました。
いつも通りいっぺんの話しかせず、肝心のところになるとわざとのように話題をそらし、絶対に本心を明かしてくれない大山さんに、ここぞとばかりに私は少しきつい語調で話をしました。
「外にはもっと色々な自由があるし,重たい障害のある人でも,一人で暮らしている人もいるのに,大山さんはなんで病院なの,ずっと病院に居続けたいってことなの?」
と聞いた私に,そのときばかりはいつも表情を変えない大山さんが少し怒ったような顔つきで、
「きっかけがないだけで,みんな病院を出たいのです。私もずっと考えてきました」
と、きっぱり答えたのです。
私は、そのときはじめて大山さんの本当の思いを聞けたと思いました。
“やっぱり! この場所を選んでいるわけじゃないんだ!”
病院から出たいというなら、出られるように絶対にするべきと思っていた私の口から、
「本当なの? 大山さんが本気で病院を出るなら,私は在宅で仕事をしたい」
という言葉が思わず出てきました。
私は、この病院にいる人たちは地域に社会資源がないからここにいるのか、治療等のため病院で暮らさなくてはならないのか、それがどちらなのか知りたかったのです。それを知るためには、大山さんが本当に思い描く生活を実現してみたいと思ったのです。
大山さんは,「本気です」とだけ答えてくれました。
やがて,私たちは1年半後に病院を出るため準備をする約束をしました。
私は、スタッフとコミュニケーションをとるのがあまり好きではありませんでした。スタッフは、私の人生には関わりのない人だと思っていたのです。
そんなスタッフの一員だった伊藤さんに、
「なんで病院にいるの? いたいの?」と聞かれたとき、
“いたい人なんかいるわけないじゃん”と、どこか冷めた気持ちでいました。
伊藤さんの「自立生活の支援をしたい」という思いも、どこまで信じたらよいのか、半信半疑で聞いていました。 大山良子
勢い半分で約束はしたものの、私にはこれから大山ちゃんが病院を出るにあたっての知識も経験も確かさもありませんでした。でも、絶対に何とかできるはずだという確信に似た何かがありました。
私は、その在宅生活を支える準備のために、その年、2007年12月に退職することになります。
24時間支援の事業所がない…ならつくればいい!
大山ちゃんとは、「2008年4月1日」に退院するという計画を進めることを約束しました。
そして、まずは既存の障害福祉サービス、大山ちゃんをケアできるヘルパー事業所を探しました。私もそこでヘルパーとして働けばよいと考えたのです。
しかし、24時間体制で支援をしている事業所は千葉市内には見つかりませんでした。
また、長期療養者を家族がいない状況で引き受けることや、そもそも「難病患者」というと抵抗があるようで、短時間でさえも引き受けてくれる事業所が見つからないのです。
(難病で)座薬をつかうことがあるとか、これから鼻マスク人工呼吸器をつけるかもしれないという医療ニーズがある人は、「ヘルパーでやってはならない行為があるから、家族がいなければ入院のほうがよい」のだということばかりを説明されました。いざというときの責任の所在が話題の中心になったわけです。
大山ちゃん自身も、では東京にでも引っ越そうかと真剣に考えたりもしていたようでしたが、病院から距離的に離れることも心配なようでした。
それなら彼女が住みたいところに住めるように、そこに事業所がないなら、つくるしかない――。私は市内で事業所を立ち上げることを決心しました。
具体的に、障害者自立支援法(現在は障害者総合支援法)の障害福祉サービスの1つである「重度訪問介護」として事業所をつくろうと色々なところに相談に行きました。
ただ、「24時間の事業所なんてヘルパーが集まらない」とか、「支給決定を市町村が何時間するのかわからない」などと不安要素ばかりを聞くことになりました。ところが、東京で実際に同様の事業所を立ち上げておられた川口有美子さん(さくら会)に聞くと、「何とかなる」というのです。
その言葉を頼りに、深く悩むことなく着々と準備を進めることにしました。
そうだ、京都で学会発表しよう
そんな準備期間の1年間には、大山ちゃんとはずいぶんとメールでやり取りをしてきました。
ちょうど病院を出る1年前に、彼女は「自分を開発したい」からと、研究などに進んで協力したいと言ってくれました。私は大山ちゃんや、いまや仲間となった田中さんに障害学会というオープンなイベントに参加して一緒に報告をし、今の状況や環境とこれからすることを整理していこうということを相談しました。
計画をはじめたとはいえ、とても荷が重い「医療的ニーズがある人の地域移行」を実現するために、まずは問題を外在化して、整理したいと思ったのです。
そうして参加した2007年障害学会第4回大会でのポスター発表が、私にとって生まれて初めての学会発表になりました。
ここで、大山ちゃんが自分の置かれている環境をいろいろ整理していくプロセスの一部をご紹介します。
2007年に大山ちゃんが病院で書いていた下書きメモ
この下書きをもとに、大山ちゃんとのディスカッションを重ねて、課題を整理していきました。
例えば、「病院での生活は、待ち時間との戦い」というので、一日の待ち時間を積算してみました。寝てないけど起こしてもらうまでの間にベッドで横になって寝かさせられている時間、排便にまつわる待ち時間、車いすにのるまでの待ち時間をシミュレートすると5時間くらいになりました。
また、病院では日課が決まっていることについて、これは一般社会ではありえないことなので、それについてどう思うか、また、そのほかに病院での生活で違和感を覚えることについても考えてもらいました。
・何も考えなければ楽だけど、変化のない日課に飽きること
・着替えが週に2回しかないために一日中パジャマで過ごしていて、ずっと患者のようであるのに、元気であり、治療は特に受けていないことについては、実はとても違和感をもっていること
・外出は許可制になっていて、外部の人との接点がほとんどもてないでいる、日光に当たらないので、ビタミンD不足といわれていること
・病院の中では患者同士のトラブルも、スタッフが間に入るので困ることはないけど解決したこともないこと
・貧血の薬以外は飲んでいないのに入院していること
・医療スタッフ以外の人とのかかわりは、親族、病棟の友人、それから以前養護学校で一緒だった友人が一人いるのみで、月に一度会うかどうかで世界が狭いなと思っていること
・生活全般にわたってほとんど自己決定する部分がなく、いつも自分のことを周りの人が決めていたり、ほかに行くところもできることもなく、選択肢がなかった人生だったこと
この学会発表の準備を通じて、大山ちゃんは病院生活への思い――これまで黙っていた本音を話してくれるようになりました。
そうしたメールや会話のやり取りから、日増しに大山ちゃんから感情や思いがあふれ出してくるのが、私にはとても嬉しいことでした。
そして、医療と福祉の「谷間」におかれている人の困難さ、今までやっていた制度や暮らしが変わることの難しさなどを、本当に深く考えるようになっていくのでした。
在院中の福祉制度~お金の話~
ところで、大山ちゃんの病院ではその性質上、外出への支援は行われることがありませんし、数日外泊をして何日か病院を空けても、入院中は常に診療報酬が15%請求されており、福祉サービス費の併給はできないという理由から、自宅に帰っても居宅介護支援を使うことができません。
だから、自由に外出する機会がほとんどなかったのです。
障害福祉サービスに係る費用と収入(大山ちゃんの2007年7月分)
病院に払う費用(自己負担額)は 月に54,110円
(7月分自己負担額内訳:介護給付費24,600円 療養介護費15,110円 食事療養費14,400円)
・ 介護給付費総額(療養介護) 265,670円
自治体等請求額 241,070円
利用者負担額計 24,600円
・ 療養介護医療に係る費用
療養介護医療費総額 609,150円
保険者等請求額 594,040円
利用者負担額計 15,110円
・ 食事療養費総額 59,150円
保険者等請求額 44,750円
利用者負担額計 14,400円
8万ちょっとの障害基礎年金ではお金を貯めることが難しく、毎月少しずつためたお金で外出するのが楽しみだそうでした。入院していると障害基礎年金のほとんどを病院への支払いに充当しなくてはならず、貯金をしてそれを元手に生活を変えていくことはどうも難しそうでした。
学会発表でひらけた展望
私たちは2007年9月に1泊2日で障害学会へ行くことを約束して、新幹線のチケットを取りました。二人で旅行なので、介助も含め少しだけ不安もありましたが、せっかくの機会だから、ゆっくり2日間を過ごそうと決めていました。
新幹線では多目的室を貸してくれたので、お弁当を買って二人で分けたり、おやつを食べたりしました。私たちの胸はドキドキでいっぱいでした。京都に着いたら、まず学会会場であった立命館大学の近くでお好み焼きを食べて、ポスター発表に乗り込みました。
私たちの学会発表の目的は、筋ジス病棟のことを障害学に関心のある方へ伝えることと、どうやって地域移行できるかの情報を得るためでした。
会場で初めて田中さんや自立生活センターのスタッフに会ったり、その他、様々な障害のある当事者、学者、支援者の発表を見ることができました。
自立生活運動の話やベーシックインカムなどのテーマが多く出ていて、そうした話題は病院という閉ざされた世界の中で暮らす障害者のそれと大きく隔たりのあるものでした。
そうしてポスターセッションの時間を迎え、現地で準備をして、誰か話しかけてくれる人を待ちました。まず立命館大学の立岩真也教授(社会学,生存学)に出会えて、初めての発表で緊張している話をすると「いいね。この勢いでどんどん発信しなさい」とエールをいただきました。

それから、早稲田大学の岡部耕典教授(社会福祉学,社会運動家)がポスターの前で足を止めてくださいました。
岡部教授は、大山ちゃんに「地域移行の発表か、すごくよいね。あなたが病院を出たいの?それは是非諦めずに頑張ってほしい!できる限りの応援をするから、困ったことがあったら何でも相談しなさい」といって名刺をくださったのです。
病院での暮らしのことも、一つずつ丁寧に話を聞いてくださいました。岡部教授のことをそのときは存じておらず、後で調べてビックリでした。
こんな有名人が話しかけてくれた! やっぱり障害学会、ちゃんとこんな私たちを拾ってくれる人がいるのでした。
はじめて参加した学会で、“障がい者の人も大学に行って難しいことを話するんだな”と感心して拝聴していました。
「ベーシックインカム」なんて言葉を初めて聞きました。
いろんな方に会い、名刺をいただきました。
ずっとそんな機会が無かったので、大人になった感じがして嬉しかったことを思い出します。 大山良子
岡部先生は、「千葉なら淑徳大学の山下幸子准教授(社会福祉学、障害学)がきっと力になってくれると思う」といって紹介してくれました。
この旅の後、私は早速会いに行って、お話をすることができました。
そこで山下先生に、大山ちゃんが地域に出るにあたっての「ボランティア集めに協力したい」と、2007年11月7日に、淑徳大学で介助者と引っ越しボランティアを集めることができるよう、350人の学生の前でスピーチをする機会をつくっていただいたのです。
また、私はその後、青土社から執筆依頼をいただき、「筋ジストロフィー患者の医療的世界」(『現代思想』2008年3月号)を寄稿発表することになりました。
学会発表は、大山ちゃんが心を開いていく1つの大きな過程になり、私にも実際にさまざま準備すべきものについて考えさせられる貴重な機会となりました。
そこで出会った人たちから得られた様々な協力が、こうして私たち二人を本格的に地域移行に向かわせる大きなきっかけとなったのです。
*「おうちにかえろう 30年暮らした病院から地域に帰ったふたりの歩き方」は,
隔週で連載予定です*
■医学書院にはこんな本もあります■

だから障害学はおもしろい。
「看護は感情労働だ。しかし同時に,感情労働の破綻に惹かれる人にしかできない職業だ」……16歳で両眼の視力を失い,現在第一線の社会学者/プログラマとして活躍する著者が,できないこと,弱いことがひらく可能性について考え尽くす話題作。「これなら人とつながれる」と思えてきそうな,ちょっと楽しい障害学。