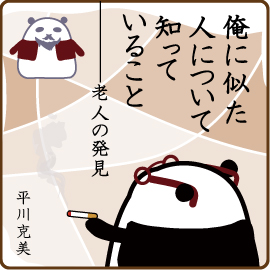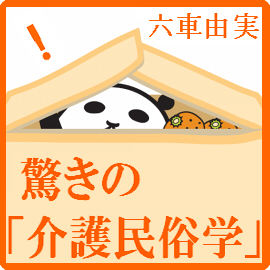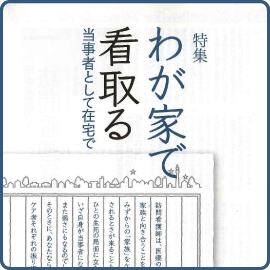かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

【第1回】医療と福祉の「谷間」で
2013.2.18 update.
いとう かよこ:千葉県千葉市在住。法律事務所勤務後、国立病院機構の介護職員として勤務。2008年りべるたす株式会社設立、代表取締役(在宅障害福祉サービス事業所管理者)。介護福祉士・社会福祉士・相談支援専門員。千葉大学大学院人文社会科学研究科博士前期課程修了,立命館大学大学院先端総合学術研究科博士後期課程在籍中。第47回NHK障害福祉賞第2部門(障害のある人とともに歩んでいる人)優秀賞受賞。 「りべるたす」ホームページはこちらから
おおやま りょうこ:千葉県千葉市在住。本連載のイラストレーター。 2009年特定非営利活動法人リターンホーム設立、代表理事(長期療養者へのエンパワメントを行うための研修事業等)。SMA(脊髄性筋萎縮症)療養のため、1978年大和田小学校から下志津病院隣接の四街道養護学校転入。1983年同小学部卒。86年同中学部卒。89年同高等部卒。 「リターンホーム」ホームページはこちらから
看護師と介護職が「連携」する、その果てなき遠さ
「かんかん!」を読まれている方は、看護師さんが多いことでしょう。
介護職(事業所管理者)の私は、在宅ケアの現場で訪問看護師さんとよく接しています。
昨今、流行り文句のように“医療と福祉の連携”といわれますが、私には現実にはほど遠い、果て遠き向こうのことのように思います。
最も悩んでいることは、何といっても「連携」のその難しさです。最近は、連携を「契約で」行うべきではないかという考え方も出て、「看護・介護職員連携強化加算」(介護保険)付けることも行われるようになりました。そうした一種の‟縛り”がなくては、患者を取りまく協働者たちの連携は現実に困難だということでしょうか。
連携とは「同じ目的を持つ者が互いに連絡を取り、協力し合って物事を行うこと」(広辞苑,第6版)という意味だそうですが、ケアの現場では、介護職が看護師さんに「連絡を取る」ことはできても、本当の意味で「協力する」ところでつまずいてしまっている場合もしばしあるようです。
私の事業所(りべるたす)の利用者は、ALS(筋萎縮性側索硬化症)や筋ジストロフィーといった難病当事者が多いことから、吸引等の医療行為が必要な方もいます。
そのとき、例えば、介護職が手を洗って部屋に入ってきて、「さて、吸引…」という段になってカテーテルを持ったのだけど、テーブルにほんの少しぶつけてしまう。しかし、それがタブーということが、最初わかりません。同席している看護師さんにそのことを指摘されると、衛生の知識の乏しい介護職は「なんて細かいことをいう看護師さんかしら……。ちょっとくらいいいのに」とネガティブに捉えてしまうこともあります。その様子を見た看護師さんは、「この人たちに任せていては危険だ」と不安になることでしょう。こうして、お互いを信頼することができなくなります。
このケースはそれぞれが受けてきた教育の違いが原因ではありますが、些細なことでさえ、正しいことがうまく伝わるのは困難なものです。
では、‟介護職も衛生の知識や医学的生活管理の知識をバッチリ身につけられたらよいのではないか?”と考えることもできます。でも、生活の場である自宅で、医学的管理を行うことで、度が過ぎると患者さんの現実の暮らしの上で相当なストレスになることがあります。
あるとき、在宅ケア関係者の連携会議で「毎日の尿量を計ったものを壁に張って、すぐに確認できるようにしましょう」という意見がでて実際にそのチェックシートをつくったところ、当の患者さんに、
「私は病院にいるんじゃない! ここで生活しているんだ」
介護職はあくまで‟生活支援”が仕事であり、そこを求められているのですよね。
そんな中で医療を日常的にする、いわゆる医療的ケアと呼ばれる医療と生活支援の行為の中間のようなものを、介護職があまりに医療を意識し構えてガチガチに行いすぎても、生活支援が消えてしまうのですよね。
このように、医療的ケアについての考え方や役割分担は、まだ現場レベルでは確立されていないように思うのです。
ニーズ増す「暮らしの中の医療」と足りない「訪問看護」
現在、私の事業所には60名ほどの痰の吸引の認定を受けたヘルパー(社会福祉士及び介護福祉士法に基づく認定特定行為業務従事者)がいます。研修を受けたとはいえ、医療行為を行う介護職は、豊富な知識と経験を持つ看護職の皆さんの目には、「危なっかしくて見てられない」と映ることでしょう。どう考えても看護師さんご自身が吸引をされる方が早く、安全、確実です。
そんな危なっかしい私たちが、どうして医療行為を行わなければならないのか。
超高齢社会を迎えたこの国では、同時に医療の発展による医療機器の普及が進み、日常的に人工呼吸器や酸素をつけている方が増加し、「暮らしの中の医療」が増えてしまったからです。地域で今、そこかしこに暮らす患者さんが増えているからです。ところが、現在、訪問看護ステーションの数は約6000か所。全国に約1700市町村があるうちでこれだけの数ですから、単純に割れば、1つの自治体あたりわずか3.5ステーション。看護師さんの数として潤沢に在宅サービスが提供されることが、当然難しい状況です。
こうした医療職と家族だけではどうしても手が足りないという現状を解消するために、国としても「医療行為をする人」の拡大を目指さなくてはならず、患者さん・家族といった当事者がその手を伸ばしたすぐ先にいたのが、介護職でした。
それに応えるべく私たちも最大限の努力をしていかなくてはならなくなったのですが、その道のプロである看護師さんから見れば、歯がゆさ、いらだたしさは計り知れないものでしょう。また、医療職の責任においてこれをやらせてよいのだろうかとお悩みのことでしょう。
後の回で触れますが、私が勤めていた病院では、ある医療行為が必要であるがために病院から退院できないとか、医療職と家族だけでは療養体制がとれないために「生存」そのものを選択することが難しい方たちがいました。
どんなに重たい病を抱えていても、どこに住むかは当人の自由であり、憲法でも、居住の自由(何人も公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。日本国憲法第22条第1項)は認められています。医療が発達し、医療が生活や人生の自由の全てを覆い尽くしてしまうことが最善とも限らなくなっている中で、当事者に医療をどこまで受けるか、どう生きるかという覚悟と、どこで暮らすかということの決断を求められる時代となりました。
そうした流れから、介護職の私たちは、このように医療依存度の高い方のケアに携わることを余儀なくされる時代となってきたのです。
看護師に暮らしの中の医療コーディネートをお願いしたい
介護職は患者さんの自己決定を支援したい
このような「介護職が当事者の自己決定に沿う」という支援の仕方は、もしかして看護師さんの医療的介入という支援の仕方から見たら、まるで危険なことを“ほう助”しているように見えるかもしれません。自己決定に基づくケアは、場合によって医療の安全を逸脱することもあるかもしれません。
それでも、そこを単に医療の安全だけを押し付けずに、本人の覚悟や生き方も含め考えなくては、家に帰りたくても病院から退院できなくなるとか、療養体制がとれずに生存を選択できないとか、家族が介護倒れするという状況が起こり得るのです。
そんな場合には、看護師さんには暮らしの中の医療を生活の延長でうまくやれるようなコーディネートをぜひお願いしたいです。看護職にしてみれば、もしかすると病院で医療を行うより、在宅での医療コーディネートを介護職までも入れて行うことはよほど大変なことでしょう。しかし、それこそ看護の専門性でしかできない部分であると思います。
時に介護職と意見がぶつかって衝突することもあるかもしませんが、お互い患者・当事者の幸せのために何がよいのかということを考えるという点で共通していますから、どちらが上とか下でなく、当事者を中心に話し合えたらよいと思います。
近年は特に現場での戸惑いの多い介護職ばかりかもしれません。どうか看護師さんたちの励ましをよろしくお願いしたいのです。
これから本連載で紹介するのは、介護職の私(伊藤)が、重度障害を持つ、医療と福祉の谷間に挟まれた方々の世界で見たことです。それはあくまで私――介護職の視点に偏ったものかもしれません。その中で、看護職の方、また全国それぞれの現場で葛藤する介護職の仲間、そして当事者の方たちに伝えられたら幸せです。
そしていつか、当事者を囲んでみんなでうまく連携できることを願っています。
こんにちは。私の病名はSMA(脊髄性筋萎縮症III型。クーゲルベルク・ヴェランダー病)。身体の筋肉がだんだん動かなくなる、治療法がない病気です。ALS(筋萎縮性側索硬化症)という病気もこの仲間です。子どもの頃は何かにつかまってヨチヨチと歩いていましたが、徐々に進行して、今のように車椅子生活になりました。 趣味は、平凡過ぎるけど絵を描くこと。デジタルアートと言って、パソコンを使って絵を描いています。タブレット(ペン型のマウス)で、こんな絵を描きます。
私は今、千葉市でヘルパーさんを利用して生活をしています。
…が、ついこの間まで病院に入院していました。
「入院」と言うと、どのくらいだと思いますか? 30年ですよ!
ここでは、その話や退院後の生活をちょこっと知ってほしくてやってきました。
伊藤さんと初めて病院で会ったときのこと..は、覚えてないです。
‟ また1人、新しいスタッフが来たな~”ぐらいの印象しかありません。
「ピピッと運命的なものを感じました!」…と言えたら、物語的には素敵なのですが。
でも、病院の体制を変えようと一人果敢に戦う彼女に、いつしか夢をみるようになりました。
それが、30年暮らした「病院を出る」という夢です。
彼女は、夢をみることがなかった私に、神様が与えてくれた‟相棒”です。
大山良子
*「おうちにかえろう 30年暮らした病院から地域に帰ったふたりの歩き方」は,
隔週で連載予定です*
■医学書院にはこんな本もあります■

多くの「気づき」を与える、臨場感あふれる闘病・介護記――16歳で膠原病(皮膚筋炎)と診断された著者が、地道なリハビリやさまざまな症状との折り合いをつけながら、パーキンソン病の父を介護して看取った闘病・介護記。著者や周囲で支えとなった人たちの前向きでひたむきな姿の描写は、患者・介護者の気持ちはもちろん、医療系学生や医療者に「気づき」を与える場面が豊富かつ臨場感をもって展開される。今後求められる“助け合う”介護についても示唆深い。