かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
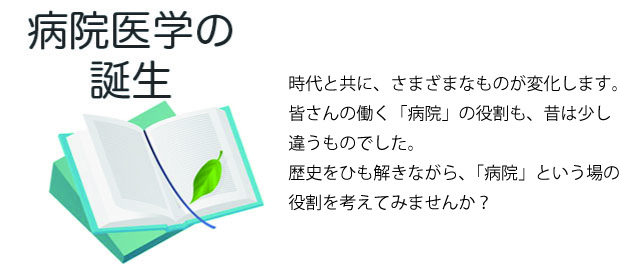
その1 病院は死ぬ場所だった
2013.4.03 update.

東京女子医科大学名誉教授、メディカルクリニック柿の木坂院長。
「人」に対する興味に端を発して、東京大学医学部へ入学。その後、東京女子医科大学神経内科主任教授、同大学医学部長を歴任し、現在に至る。人を「観る、診る、視る」神経内科医。
文学や音楽といった芸術にも造詣が深く、著書も多数。主なものに、『神経内科医の文学診断(白水社)』、『見る脳・描く脳(東京大学出版会)』、シリーズ『脳とソシアル』などがある。
今日、誰かが病院に行くといえば、それはほとんどの場合病気の治療を受けるために行くことを意味するが、中世以来の西欧社会においては、長い間、病院とは死ぬ場所であり、そこに赴くのは死ぬためであった。人は死する存在であるということがごく当たり前のこととして、人々に受け入れられていた時代、病に冒されるということは、ほとんどの場合、即、死を意味するものであった。したがって、病に陥った人々の唯一つの願いは、神の見守る中で安らかな死を迎えることだけだったのである。そのような死にゆく人を迎え入れる場所、それが病院、すなわちhospice, hôpitalである。これらの語は、ラテン語のhospitiumに由来するが、これは旅人を接待する宿泊所の意味であり、死への旅に出る人を受け入れる宿泊所というのが、本来の意味であった。今日でも、客を呼んで接待する主人をホスト(host)と言うが、これも元はといえば宿屋の主人を意味している。
そんな病院の姿を今に伝えるのは、フランスのブルゴーニュにあるワインの集積都市、ボーヌに残るオテル・ディユー(Hôtel Dieu de Beaune)病院である。この病院は、15世紀に、この地方を治めたブルゴーニュ公の宰相として権力をふるったニコラ・ロラン(Nikolas Rolin)によって建設されたものであり、今日でも5世紀半前の建設当時の姿をそのままにとどめており、博物館として一般に公開されている。この地方独特の、美しいモザイク模様の瓦屋根は、外の街路側からは全く見えないが、これは外から見ただけでは普通の民家のように見えるようにと考えられたものであり、夜盗などが侵入しないようにするための一種のカムフラージュであったと言われている。何かと物騒だった当時の世相をよく物語っている造りである。ここを訪れる人を迎えるのは、なんと言うことはない街路に開いた、すすけて目立たない入り口の扉だが、そこを抜けると、目にも鮮やかなモザイク模様の屋根に囲まれた美しい中庭に立つことになる。その変化は、わが目を疑うほどである。
ボーヌのオテル・ディユーの中心は、“貧者の間”と呼ばれる大きな病室である。両側に15床づつ、合計30床の木製のベッドが並び、正面中央には礼拝堂、そしてその奥には天井まで届く大きなステンドグラスから漏れ入る柔らかな光が、美しく室内に差し込んでいる。木製のベッドは、それぞれが側壁と天蓋をもち、カーテンで仕切られていて、個室化することができるようになっている。
一見、実に落ち着いた居心地のよさを感じさせる空間だが、ふと振り返って今入ってきた入り口に眼を移すと、そこには、両手を縄に縛られ、茨の冠に血を流すイエスの木像が置かれている。安らかな空間に置かれたこのイエスの凄惨な像が、ここはやはり、死ぬ場所だったのだということを伝えてくれている。茨の冠をかぶせられて血を流し、縄目の辱めを受けるイエスの姿を目の当たりにした病人たちは、その姿に慰められ、自らの苦しみと痛みを耐え抜く力を得て、従容として死に向かっていったのであろう。
中世のフランスでは、いずれもオテル・ディユー(Hôtel Dieu)、すなわち“神の宿泊所”と呼ばれるこのような病院が各都市に作られたが、それらは全て死ぬための場所であった。Hôtelという語はラテン語のhospitaleに由来し、Hôpitalと同じいみである。中世の病者たちにとって、ここは神の元へと旅立つため最後の宿泊所だったのである。


