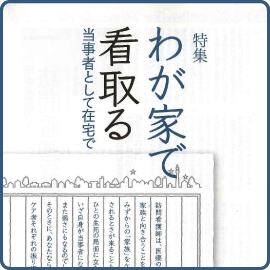かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

【第6回】難病当事者たちの願い
2013.5.15 update.
いとう かよこ:千葉県千葉市在住。法律事務所勤務後、国立病院機構の介護職員として勤務。2008年りべるたす株式会社設立、代表取締役(在宅障害福祉サービス事業所管理者)。介護福祉士・社会福祉士・相談支援専門員。千葉大学大学院人文社会科学研究科博士前期課程修了,立命館大学大学院先端総合学術研究科博士後期課程在籍中。第47回NHK障害福祉賞第2部門(障害のある人とともに歩んでいる人)優秀賞受賞。 「りべるたす」ホームページはこちらから
おおやま りょうこ:千葉県千葉市在住。本連載のイラストレーター。 2009年特定非営利活動法人リターンホーム設立、代表理事(長期療養者へのエンパワメントを行うための研修事業等)。SMA(脊髄性筋萎縮症)療養のため、1978年大和田小学校から下志津病院隣接の四街道養護学校転入。1983年同小学部卒。86年同中学部卒。89年同高等部卒。 「リターンホーム」ホームページはこちらから
【第5回】はこちらから *読者からの質問回答upしました(2013.05.14)*
筋ジストロフィー(筋ジス)病棟ができた当時から、その病棟に入れる喜びについて「親の会」は語っています。しかし、当事者は必ずしも同じ思いではありませんでした。
病棟が整備されてまもなく、病棟に入院していた患者たちによる筋ジスの患者運動が国立西多賀療養所から全国的に起こり始めました。それは「筋ジス運動」と呼ばれていました。
わが国の障害者運動に先駆けて、“筋ジス3兄弟”(1960年代後半から相次いで入院した山田寛之・秀人・富也の3兄弟)が起こした大旋風から、今回は説明します。
筋ジス3兄弟の活動
それは国立療養所西多賀病院における「西友会」という患者自治会の設立(1969年)から始まりました。病院内での詩集出版(山田秀人『車椅子の青春』1971年,1977年に同名映画制作)といった活動がやがて地域を巻き込み、全国への展開も夢見た運動体として、地域福祉研究会仙台(1971年)となりました。
彼らも、最初は親の会と同じような内容で要望を上げていたのですが、それがだんだんと変わってきたと言うのです。
運動の中心であった山田富也氏の言葉です。
国では十数年前から患者を国立病院に収容するようにしていますが、しかし患者が一番に願っていることは、自宅で家族と生活ができ、充分医療を受けられる体制ができることなのです
山田富也:はしがき(わたしたちはなぜこの本を出版したのか),国立療養所西多賀病院詩集編集委員会編『車椅子の青春』(エール出版,1975年)3-5頁

筋ジス患者が、身動き一つできずに病棟の白い壁と小さな窓から見える限られた風景という悲惨な生活を強いられていることについて訴えているのです。
その後、彼らは仙台ありのまま舎をつくり、民間の障害者自立ホームもつくります(1987年)。ところが、自立ホームでは限界があったと言うのです。
みんな医療の中で生きてきて、ますます重度化・重症化が進んできて、これから更に医療的ケアが必要となろうとしているときに、それに対応できる体制が整っていないところに出て行くだけの決断がつくはずがない。(中略)結局私たちはやはり病院でしか生きられないのか、そんな諦めが頭を支配し始めた。病院を出るために、病院を出て自分の人生を全うするために、私たちはまず行動を始めたけれど、結局医療からは逃れられなかった。医療から逃れられないことは、わかっていたが、現実の前に無力な自分たちを恨めしく思った
山田富也『全身動かず』(中央法規出版,1999年)198頁
しかし、その後、彼らは1994年に難病ホスピス「太白ありのまま舎」を設立する偉業を成し遂げます。時代は重度障害者を病院に押し込めなくてはならなかったときから変化していったのです。
彼らの運動とは別に、府中療育センター入所中の重度障害者たちの中に、1972年9月18日から東京都庁前にテントを張り、座り込みの運動を始める人たちが出てきました。府中センターには障害別に施設を分ける計画があったのです。「管理する」側はそのほうが楽であるために、そのように考えたのですが、「管理される」側の患者は、ここは生活の場であるのにそれは勝手だと主張したのでした。
「朝日ジャーナル」1972年11月17日号に、新田絹子さんの手記「わたしたち人形ではない」が掲載されています。ここでは“障害者は施設に入るべきで、施設で幸せに暮らしたほうがよいというけど、それを世の中の人は分かっていない、施設では自分の思いは押し殺されてしまうのだ”と主張しています。
こういった障害者運動の先人が障害者の制度をつくっていきます。施設の費用だけでなく、在宅のホームヘルプサービスをつくる交渉をも始めていくのです。
「施設から地域へ」という時代の変化
筋ジスは医療という問題があり、施設から地域への動きが制度化するのが出遅れました。そんな中、介護量が多いためALS患者はほとんどの病院で長期療養の受け入れをしてもらえず、在宅が主流にならざるを得ませんでした。ALS患者は療養体制をつくるための運動をはじめて、痰の吸引などの難病患者の在宅制度をつくってきました。そこから、ALS以外の患者たちも施設から地域への動きが出てきました。
例えば、痰の吸引の問題はALS協会から動き始めました。
先に紹介した筋ジス3兄弟末弟の山田富也氏は、国立療養所西多賀病院(現・独立行政法人国立病院機構西多賀病院)で6年間の療養生活を過ごした筋ジス患者です。
その著書の中で筋ジス病棟を「刑務所」として表現しています。
入院年齢は様々だけれど、多くの患者は10歳前後に入院している。甘えたい気持ちをいかにして抑えるのか、そのはけ口さえない入院生活は、刑務所以上に残酷でもある。なぜならそこには刑期がないからだ。表現が適切ではないかも知れないが、多くの患者が亡くなって退院していくことを思うと、全員が死刑執行を待っているようなものだ。選択肢のない人生は辛さより、悲しさに満ちていた。
山田富也『筋ジス患者の証言「生きるたたかいを放棄しなかった人びと」』(明石書店,2005年)129頁
筋ジス病棟ができた当時、1965年の筋ジス児の就学調査では67.1%が就学猶予、養護学校へ通う子供が15.1%でした。
参考:『筋ジストロフィー患者の現状と課題2003概要』(社団法人日本筋ジストロフィー協会,2003年)
このような状況下で、病院併設の養護学校の歴史が始まります。
1978年の養護学校義務制の施行までの間、筋ジス児の教育の権利を勝ち取るまでの運動がありました。1964年に病弱教育を位置づけたからです。それから、1967年に第1回筋ジス教育研究大会意を開催し、そこから筋ジス教育についての課題と問題について検議を重ね、教育の向上推進を目指していきました。
参考:福澤利夫「日本筋ジストロフィー協会のあゆみ」『あしたを信じて』(社団法人日本筋ジストロフィー協会,2004年)25頁
病院併設の養護学校が整備されることで、病院に収容された筋ジス患児たちは学びの機会を得ることができるようになります。
筋ジス病棟は全県にあるわけでもないし、病院に入院していることが原則通学の条件になっているところもあり、養護学校を希望する患児は学校に入学する頃から入院生活が始まるのです。筋ジスをもつ子どもを受け入れしてくれる普通学校はほとんどありませんでした。少なくとも、1992年3月13日付神戸地方裁判所の筋ジス少年の高校入試判決(学力以外の部分で入学を拒否したことを不当とした)までは、かなり難しかったといわれています。
そのようなわけで、病院へ移設の養護学校への入学をきっかけに入院生活が始まることが多かったのです。
当時私たちに選択の余地などなかった。病院で生きるしか生きる方法がなかった。その是非を議論することもできないなかでの、入院であり、専門病院での生活だった。しかし、何度も言うようだが、当時はそうすることでしか家族の崩壊を避ける方法はなかった。私たちは、それまで放置されてきた筋ジスの居場所がようやく定まったことを大きな前進と考えている。したがって、筋ジス病棟の存在そのものを否定しているのではないし、その必要性は認めるし、現在なお重要な意味をもっている。問題はそのあり方で、患者自身の生き方とも相まって、今なお大きな課題ではないかと思っている
山田富也『全身動かず』(中央法規出版,1999年)196-197頁
病院療養の経験者である山田氏の言には重みがあります。当時は、病棟生活しか生きる方法がなく、しかし、病棟で一生患者として仲間の死を見送るばかりの人生を過ごすしかないと言うあり方を問題提起しています。
山田富也氏の活動に大きく影響を受けた、当時国立下志津療養所に療養していた高野岳史氏は、1979年に地域生活を千葉で試みようと宮崎障害者生活センターをつくります。
彼は療養所の生活をこう語っています。
『療養所の中では、昼は電動車いすで移動はできるけども、長い間座ることはできないのでほとんど寝たきりの生活。僕の病棟だけで40人の患者のうち20人は全面介助が必要なのに、介護の職員は15人で三交代なんです。夜なんか、二人しか居ない。衣食住と医療までは何とか手がまわるけれども、書き物をしたいと思ってもできないし、電話もかけられない、絵も画けない。自分でやりたいことはいっぱいあるのに、何にもできなかった。焦りばっかりが胸の中をかけめぐってたんです』 そう言う生活は、生きているのではなく生かされているのだと彼は思った。
小林敏明「攻めに生きる 高野岳史と共同生活者たち」『そよ風のように町へ出よう』9号(40),1981年
そうして、支援者たちと無理やり病院を出ようとセンターに住みだした高野氏は父に大反対を受けます。父は、息子は15年も施設に居て、正常な判断能力がないと言い、周囲の人間にそそのかされていると主張するのです。そうして、支援者たちを告訴するとまでいうのでした。同じ療養所の仲間は親の手で強制的に病院に連れ戻されているものもいたそうなのです。しかし、高野氏は自分の生き方を粘り強く主張しました。
ここで退院できなければ、僕はもうここから出られずに一生を終わるだろうと思ったんです。一つの生命体としてではなく、一人の人間としての人生が、ここから出られないんだと観念した時に終わってしまうんだとね。でも親父は、話を持ち出すと、頭っから『できるわけがない』『絶対だめだ』と怒鳴りだすんです。ドクターも『心臓がかなり弱っているから一週間以上は出ちゃだめだ。無理をすると心不全を起こす』と言うしね。でも僕は本当の意味で生きたかったんです。攻めの生き方をしたかったんです。
小林敏明「攻めに生きる 高野岳史と共同生活者たち」『そよ風のように町へ出よう』9号(41),1981年
やがて彼は仲間と暮らす生活を始めました。“一つの生命体でない生き方”が始まっていくのです。彼はぎりぎりまで、地域でボランティアと暮らしながら過ごしました。
当時、彼の介護に入っていた人に伺ったところ、急に夜の介護者が来られなくなり、座ったまま横になって眠ることもできず、一晩座り続けたこともあったそうでした。地域のボランティアだけの生活では不安定だったというし、ボランティアとの関係も困難な部分があったのだけれども、彼は病院へは戻らなかったのです。
『こんな夜更けにバナナかよ』の反響
最後に紹介しましょう。筋ジスをもつもっとも有名な人は、鹿野靖明氏かもしれません。
鹿野氏は、まだ在宅で暮らす制度も何もない1980年代から、親の介護を受けずに24時間他人介護で独居していました。その生活を北海道新聞社の渡辺一史氏が取材し、『こんな夜更けにバナナかよ』にまとめました。同書は第35回大宅壮一ノンフィクション賞、第25回講談社ノンフィクション賞をダブル受賞し、社会的に大きな反響を呼んだのです。
鹿野氏は12歳から国立療養所八雲病院(現・独立行政法人国立病院機構八雲病院)に11年間入院生活をした経験があります。
多くの『死』を身近に感じながら、それを決して口に出して言ってはならないと言う環境で、鹿野は思春期を過ごしている。また、大学病院や医療関係者の見学も多かった。そんな視線にさらされるたび、『オレはモルモットじゃねえ』と言う思いを募らせた。…八雲での生活は規則づくめだったと言う。夕食は、夕方4時だった。育ち盛りの子供は、夜になると当然腹を減らす。しかし、小遣いを禁じられ、いつも空腹だった。…鹿野は、何度か療養所からの『脱走』を試みている。そこは療養所なのだが、なぜかみんな『収容所』のように思っていたと言う。『食べたい』『飲みたい』『ここから出たい』 12歳から15歳までの多感な時期、鹿野はそんなことをただ一心に思っていた。こうした八雲の体験は、鹿野に二つのことを強烈に植えつけることになった。一つは『病院暮らしはもうたくさんだ』と言う思い。そして、もう一つは、『どんなことをしても生きたい。生きるんだ』と言う生への強い執着である。
渡辺一史『こんな夜更けにバナナかよ 筋ジス・鹿野靖明とボランティアたち』(北海道新聞社,2003年)50-52頁

本書のタイトルになった、夜更けにバナナ食べたいと頼むエピソード。
ある意味、こんな“常識はずれ”といわれそうな筋ジス患者は、私のいた病院にはいませんでした。そんな彼が、「家族の拡大解釈」や「緊急避難」という考え方で医師法違反の網の目を潜り抜け、たんの吸引等の医療行為をボランティアにさせるのです。
「ボランティアを集めるために有名になりたい」という彼にとっては、病院から出ることが至上命題で、けして地域で安心して暮らしているといえる状態ではないにしろ、病院に戻らないために手段を選べなかったのでしょう。これは鹿野さんの患者としてではなく、人間としての生き方への挑戦です。
こういった患者さんが世の中に出てきて歴史をつくってこられたことが、実際に、障害が重たくとも地域で暮らすことを可能にし、常識とする世の中に変える力になっています。
そういった鹿野氏の生き方に、私は非常に感慨深い印象を受けました。
*「おうちにかえろう 30年暮らした病院から地域に帰ったふたりの歩き方」は,
隔週で連載予定です*

「当事者主権」を実現するためのデザイン! ビジョン!! アクション!!!
「こうあってほしい」という構想力をもったとき、人はニーズを知り、当事者になる。この《当事者ニーズ》こそが次世代福祉のキーワードだと考える研究者とアクティビストたちが、安心して「おひとりさまの老後」を迎えられる社会を目指して、具体的シナリオを提示する。時代は次の一歩へ。