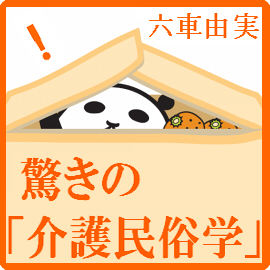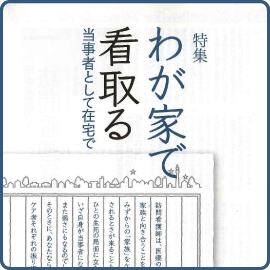かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

【第2回】「子どもや家族を思えばこそ死にたい」
2013.3.06 update.
いとう かよこ:千葉県千葉市在住。法律事務所勤務後、国立病院機構の介護職員として勤務。2008年りべるたす株式会社設立、代表取締役(在宅障害福祉サービス事業所管理者)。介護福祉士・社会福祉士・相談支援専門員。千葉大学大学院人文社会科学研究科博士前期課程修了,立命館大学大学院先端総合学術研究科博士後期課程在籍中。第47回NHK障害福祉賞第2部門(障害のある人とともに歩んでいる人)優秀賞受賞。 「りべるたす」ホームページはこちらから
おおやま りょうこ:千葉県千葉市在住。本連載のイラストレーター。 2009年特定非営利活動法人リターンホーム設立、代表理事(長期療養者へのエンパワメントを行うための研修事業等)。SMA(脊髄性筋萎縮症)療養のため、1978年大和田小学校から下志津病院隣接の四街道養護学校転入。1983年同小学部卒。86年同中学部卒。89年同高等部卒。 「リターンホーム」ホームページはこちらから
病院でないと本当にダメなのだろうか
「福祉」とはまったく無縁な人生だった私が現在、重度障害のある方に対して24時間体制で支援することができる訪問介護事業所をつくることになったのは,大山良子さんとの出会いが始まりでした。
いま私のところに来る相談は、「長期療養している病院から出て1人で暮らしたい」というものや、ALS(筋萎縮性側索硬化症)など難病当事者から、「気管切開をするにあたり、また人工呼吸器をつけてから療養体制をどうつくるか知りたい」という差し迫ったお尋ねが多いです。その療養体制によって、今後の生存の選択を検討したいということですね。
そうした方たちと接しているうちに、重度な障害、とりわけ医療的ケアが必要な方が地域で暮らすことは、現状とても難しいということ。また医療と福祉の連携とはいうものの「誰がどこまでやるのか」という業務範囲からして現場は混乱していることが明確になってきました。
医療や多くの介護を必要となると、とかく「専門家」と呼ばれる他者がその当事者の自己決定の主導権を握ってしまうことがあります。それには少し危うさがあって、権利擁護されないことさえも「仕方がない」と片づけられてしまって、当事者自身もそう思い込んでしまっているような状態が起こってしまう。
そこから抜け出して、自分の希望を追い求めることは、かなりの勇気がいることだと、私は思うのです。
ずっと病院の中だけで過ごす患者さんは、
いったい何を考えているのだろう
人はいちど思ったことを語らない癖がついたら、嫌なことや、変えたいこともあえて語らなくなるものかもしれません。ただ一般社会では、何か嫌なことがあってもそれに反対の声を上げない・主張しないということは、往々にして「それでよい」(消極的同意)とみなされて、物事が進んでゆくものです。やがて、その人は思うこと自体をなくしてしまうのかもしれません。
私が介護職として病棟に勤務したとき、少ない介助者を取り合うような長期療養の患者さんたちの生活の質の低さを目の当たりにしました。病院のスタッフたちは「こんな身体になったら終わりよ」とよく言っていました。それは、まるで病気になったら生活の質が落ちても仕方がないということのようで、私も、自分が健常者で本当によかったと思ったものです。そんな完全なる不平等な世界でした。
また患者さんたち自身が、医療管理のレールに乗っているだけで、主体的に暮らしているようには見えませんでした。自分の病について一度も告知は受けたことがないという方ばかりで、例えば、別に「筋ジストロフィー」(筋ジス)と言う病名を知らないというわけではなくて、病気について誰かと詳しく話したことがないと言うのです。
ただ、患者さんのほとんどが「帰れるものなら家に帰りたい」と言っていました。しかし「自分の病気では家族も大変だし病院からは出られない」とも同時に言うのです。
病院の患者は管理される存在。
それが先天性の障害者であればあるほど、そのアイデンティティは「患者である自分」とだけになってしまうように思います。
筋ジス患者の多くは養護学校へ転入する時に、筋ジス患者を集めた病棟へ入院をすることが多いそうです。そうしてカーテンのない見通しの良い大部屋の中に置かれ、自分の病を主体的に語ることのない中で、「安全・安楽」の医療的生活管理を受けて生きていくことになります。
私は、何かから束縛されている状態から解放されることって、その当人の意思さえあれば何でもできると思っていました。だから、物言わない病院患者さんたちは、そもそもの感覚から健常者と違うのだろうか?と想像したりするしかありませんでした。
でも、本当にここで生きていることに納得されているのかしら?と、疑問に思う部分がぬぐえず、その本心が知りたい思いは募るばかり。
彼女らにいろいろ話しかけてみるのですが、返ってくるのは、やっぱり通りいっぺんの言葉だけでした。
小学校2年生の8月31日、2学期の開始を前に、私は地域の長期療養型病院に入院しました。病院に隣接された養護学校(現・特別支援学校)に通うためです。
現在は、普通学校でも障害児を受け入れてくれるところは増えましたが、私が子どもの頃は、“障害児は養護学校へ…”というのが世間一般の考えでした。1学期までは、「両親のどちらかが常に付き添う」という条件付きで普通の小学校に通っていましたが、付き添う母が毎日のことで疲労してしまったことと、そうした背景から病院で暮らすことになったのです。
入院時の持ち物は少しの着替えと歯ブラシと、担任の先生からプレゼントしてもらった人形だけでした。
身体の不自由な子どもを受け入れる養護学校は数が少なく、その養護学校には静岡や埼玉、栃木など遠方から来ている子もたくさんいました。
その日から病院が私の家で他の入院患者さんたちが家族になったのです。
病院には日課があり、毎日毎日、朝から晩まで時間割が決まっていて、平日や休日も関係なく規則正しく進んでいきます。
朝食は7時から。自分で箸やスプーンを持って食べることができる人には個別のごはんが出されますが、誰かが食べさせないといけない人は、食事介助するスタッフの手が足りないので、高カロリー栄養ドリンクを飲みます。
朝食が終わったら一斉にトイレの時間。
ここでも、トイレで用を足せるのは、自分で行ける人のみ。7時30分過ぎから、スタッフが学校に行く人から順に便器を準備してゆきます。大概の人は動けないので、ベッド上での排泄となります。そうして学生の準備が終わったら、次に卒業しているより年長者たちの便器の処理・始末にかかります。
それが終わったら、スタッフは患者を車椅子に順番に乗せていき、ひげそりや整髪の身支度を順番にしていきます。これだけで午前が終わり、昼食になります。
学生も昼食を食べに病棟に戻り食べ終わったらまた学校に向かいます。
午後は、曜日によって入浴やリハビリの時間になります。入浴もリハビリも週2回ずつでした。
着替えは、入浴時以外にはしません。寝る時も同じ洋服で寝ます。車いすから降りる時間も決まっています。端の部屋から順番に降りていきます。その後は夕食になります。
夕食の後は自由時間ですが、テレビを観るくらいの過ごし方です。
21時から、またスタッフが順番に就寝準備に入って1日が終わります。
曜日により多少の違いはありますが、みんながこの流れで過ごしていました。
団体生活では、この日課の流れが一番大事なものになります。車椅子を降りる時間に部屋にいないとか、夕食を食べ終わる時間が遅いとか、少しでもスタッフの流れを狂わすような行いをしたら、‟自分勝手な患者”というレッテルが貼られ、嫌味を言われたりします。また一度でもそういうレッテルを貼られると、そこでの生活がしにくくなります。
入院生活をしているときに一番に気を使ったのは、トイレのことでした。
私は、トイレは自分ではできません。スタッフの全介助で尿器を使って「おトイレをお願いします」。朝10時にしたら、午後の15時30分までは排尿はしないのが日常のことでした。
でも、みんな人並みの人間ですので、時間どおりにはいきません。涼しくなったりすると、お昼頃にたまに用を足したくなります。ただ、その時間帯はスタッフも昼食タイムであって、人数が少なくてナースコールの対応で一杯一杯になっています。そんな状況の中で、『いつも』しないトイレをお願いすることは、日常の流れに反するのです。スタッフから、なかなか言葉にはしないけど、「なんで今の時間にするの?」みたいなオーラを出されてきます。
昔に比べたら最近はそうした雰囲気は少なくなってゆきましたが、それでも決められた時間外のトイレ介助は敬遠されるものです。
「悪い子」のレッテルを貼られたくない私は、なるべくおしっこがしたくならないように水分コントロールをしていました。決められた時間まで何とかもつようにがんばるのです。日常の流れに背かないように、そしていつもニコニコしていることが病院で生きていくコツでした。
30年間、そうやって過ごしてきました。
大山良子
終わりのない療養が「死亡退院」まで続く
私は、日本に暮らす人たちはもっと自由になんでも選ぶことができると信じてきました。日本国憲法には平等権(日本国憲法第14条1項:すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない)や、自由権(日本国憲法第22条第1項:何人も公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する)があるのだから、たとえ病気であろうとも、どんなに重たい障害があろうとも機会の平等はあるべきだし、自分の住みたい場所に当然住めるはずだと思っていました。
ところが、病棟にいる患者たちは、帰れるものなら家に帰りたいと言うのに、なぜだか出ることは難しそうなのです。彼らを待つ未来はみな「死亡退院」であり、死ぬまでそこにいるのがほとんどなのです。
治る病気なら、「療養」と言うこともできるかもしれないのですが、そこには終わりのない療養があり、終の棲家が病院という状況なのでした。
国立療養所西多賀病院(宮城県)で1968年から6年間療養生活をされた山田富也氏は、当時は選択の余地などなく、病院で生きるしか方法はなかったといいます。その是非を議論することもできなかった、と(山田富也『全身動かず』中央法規、1999年、196頁)。
いわば、病院の中で「構造化された選択肢」としての「患者」であるしかなかったのです。それから45年。
国が「障害者の自己決定・施設から地域へ」との指針(2000年施行の社会福祉法等でこの基本方向が示された)を打ち出し、障害者の生き方について、『生の技法』 (この本では身体障害者、中でも全身性の障害を持つ、重度とされる人たちの自立生活について書かれている。家族や、施設の管理された生活から抜け出した人たちについて書かれている。1995年出版。現在はこの時代よりも在宅独居できる制度が整ってきた)のような成書も世に出て久しいのに、ずっと筋ジス患者たちを取り巻く環境は続いています。
日本に在宅医療が必要な人は、何人?
調べていくと今の日本では、身体がほとんど動かない状態になったり、あるいは人工呼吸器をつける必要があったり、痰の吸引が常時必要であるとか、経管栄養で食事をとらねば生きられない身体になるようになると、世話ができる「家族」がいなければ、多くの場合、施設か病院で一生を終えるしかない現実がわかってきました。
では、この国に何人そのような人たちがいるのかと、在宅の吸引、経管栄養が必要な方の推計を色々と計算してみました。
しかし実数はどうしても把握できません。
例えば在宅障害者の数でいうと、下記の数字が調査報告されています。
ALS:たんの吸引が必要な人4,001人、経管栄養が必要な人4,143人
脊髄損傷:たんの吸引が必要な人2,573人、経管栄養が必要な人1,387人
遷延性意識障害:たんの吸引が必要な人4,412人、経管栄養が必要な人5,253人
重度心身障害者:たんの吸引が必要な人1万867人、経管栄養が必要な人1万283人
・筋ジス:調査対象外
出典: 厚生労働省平成22年度障害者総合福祉推進事業「訪問系サービス利用者のサービス利用状況などの実態把握に関する調査報告書」(平成23年3月 株式会社ピュアスピリッツ発行 249-253頁)
また在宅高齢者の根拠としては、厚生労働省の資料(3)「介護現場等におけるたんの吸引等を巡る現状」が発表されています。
そこでの数字は下記です。
たんの吸引が必要な人:2万4,000人
経管栄養が必要な人:3万人
出典:平成22年7月5日第一回介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会「資料」より
在宅障害者で医療的ケアが必要な実数は、他の疾患の部分を考えるとできていません。
また高齢者も、介護保険を使っていない人も除かれていると考えられます。
在宅の障害者と高齢者が一緒になっている場合もあり得るのですが、たん吸引が4万6,000人、経管栄養が5万1,000人かと推計されます。この両者を足して、もし医療的ケアのある人が例えば10万人としたとしても、日本人の約0.078% 〔平成25年2月20日総務省統計局平成25年2月1日現在:(概算値)総人口1億2740万人〕に相当します。
この少数者がなぜ、この国の現状の中できちんと支援を受けられないのでしょう。
筋ジス患者の多くは、実は、別に体調が悪くて入院し始めたわけではないそうです。
ひと昔前、筋ジス患者は現在よりさらに普通学校に受け入れられなかったために、まず病院に入って、病棟併設の養護学校(現・特別支援学校)に通う目的で入院していた人が多かったようです。今もその人たちがそのまま現存しています。
彼らが学校を卒業する18歳の頃には、その親も高齢になり、また家族が既に子どものいない生活に慣れていることもあり、家に帰ることになる人はほとんどいません。帰ることができる家が、なくなっているためです。
また、「病名を知っているのに、予後について等はあまりよく知らない」、家族や医師と病気について話し合ったことがない人たちが多い点が、とても気になりました。
筋ジスは、その多くがほんの小さい子どもの頃に発症・判明する病気であり、親と医療者との話し合いで治療方針や療養の仕方が決められています。そして、患者が大人になってもその本人不在のまま、意思決定・療養生活が継続しているケースが多いのです。
患者自身がその人生をどう過ごすか決めることにつながらず、受身的に「療養」を継続してしまう、そんな有り様でしょう。
また、日本では遺伝性のデュシャンヌ型筋ジストロフィーと血友病から着床前診断が始まりました。そのため、このような重篤な病をもつ子どもの母の幾人かは、遺伝子検査の結果から、次の子どもを産まないようにすることがあります。これは患者自身が、自らが筋ジスであることを知らない(告知されない)うえに、その遺伝子情報をその母により他者へ知らせることにもなります。
玉井真理子氏(臨床心理士)は、筋ジス患児の遺伝子情報を本人に承諾なく親や医療者が知ってよいのかと言う疑問を投げかけています。
参考:玉井真理子「筋ジストロフィー患者である子どもの遺伝情報を家族の出生前診断に際して利用してもよいか?」ケーススタディ
当事者団体の1つ、神経筋疾患ネットワーク では、「着床前診断を反対する会」をつくって、「自分たちは不幸でないのに、病が重篤だからと言って、殺さないでほしい」と訴えています。
「生きたい」と、安易に言えない―ALSをとりまく状況
他方、ALS――筋ジスと似た症状で進行性に身体が動かなくなる。神経が原因の病気。眼球なども動かなくなり、コミュニケーション障害がおこる場合もある――では、あまりに介護量が多いため病院や施設に入ることが難しいのです。筋ジス患者は長期療養ができるのに、ALS患者はその受け入れができる施設からして少ないのはそのためです。立岩真也氏(社会学者)の『ALS 不動の身体と息する機械』、川口有美子氏(ALS患者会)の『逝かない身体 ALS的日常を生きる』にも、こうした事情は詳しく書かれています。
ALS患者のように医療依存度の高い重度障害者たちは、例えば気管切開をしたり人工呼吸器をつけて生きたくても、療養環境が整わないために死ぬしかないのです。

ご主人と3人暮らしの核家族で、ある時突然ALSになってしまったSさん。彼女には、わが子と同い歳のお子さんがおられます。彼女は、「いよいよ息ができなくなった時点で、私は死にます」ときっぱりおっしゃっていました。
地域の保健所からは「事前の意思確認で呼吸困難に陥っても、『気管切開はしない、人工呼吸器は装着しない』とご本人は表明しておりますので、本人の意向を尊重したケアをお願いしたい」という説明をされていました。
私は大変驚いて、Sさんにどうして死にたいのか?を尋ねると、「気管切開したら痰の吸引(の介護)があるので、家族にもうこれ以上の負担をお願いできません。ですから、子どもや家族を思えばこそ死にたいです。『では病院で生きたらいい』と言われますが、子どもと離れるくらいなら死んだほうがましです」と言うのです。
そこで「もし、在宅で家族以外がケアできるサポート体制が整えば、生きていてもよいと思う?」と聞くと、それには「うん」とうなずくのです。
では「それを早く(保健所と病院に)伝えよう。先日もたんが詰まったことがあったでしょう、間に合わなくなったら困るでしょう」と勧めるのには、「患者は、生きたいということを安易に言える状況にないということを理解してほしい」と返事をされました。
真の“本人の意向”が守られない恐ろしさと、重度障害者の生きにくさに愕然としました。
ALSの場合、このような「痰の吸引」や「経管栄養」という医療行為の問題が出てきます。医師法第17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない」と医療の業務独占を明文化し、医療職以外の医行為については禁止されています。しかし、“法律は家族に介入しない”という慣習があり、それにより家族による医療行為のみは認められてきた経緯がありました。
特にSさんの場合は、週に平日の5日、1日数時間しか来られない訪問看護師さんとご家族だけで、一日中絶え間なく断続的に起こる痰の吸引や、人間が必ず摂らねばならない食事や水分の経管栄養をケアされる介護を受けることはその時の状況では難しく、病院に入院するしかないと思ったのでしょう。そして、それは彼女が選ばない選択肢なのでした。
また、家族がいないALSの方等はどうなるのでしょうか。
自分だけで生きることは経済的にも難しい、そんなことから、ALS当事者のKさんはケアホームを構想し始めます。居住支援を合わせてすることで生きられるALS患者が増えるのではないかというものでしたが、家族以外の者によるケア体制でケアホームという小規模な居住支援を行うことには専門職による偏見が多々ありました。
家族以外がたんの吸引をすることについては、2003(平成15)年にALSに対しては家族以外のものが吸引をするための違法性阻却の通知が出ており、さらには2005(平成17)年にALS以外の疾患にも同様の通知が出されました。それは当時、東京で一人暮らしをされていた橋本操さん(日本ALS協会。当時会長。現顧問)が始めた署名運動からその願いが叶ってできたことです。
しかし、違法性阻却の通知だけでは法的根拠ができたわけではないということもあり、実際に痰の吸引を請け負うようになった介護事業所はとても少なかったのです。
そして現在、2012(平成24)年4月1日の「社会福祉士及び介護福祉士法」一部改正により、介護職員等によるたんの吸引が法制化することになりました。
これは業務として、医療と介護の枠組みを変えることに踏み込んだ大きな改革です。
在宅ケアは、単に、街が病院に・家が病室になったのではありません。
医療的ケアのある重度障害者が地域で暮らすためには、単に制度があればよいわけでもありません。医療者も周囲の人も、そして何より患者と家族が在宅で暮らす覚悟を持つ必要があり、そしてその覚悟には、本人が暮らしやすく、周囲の人が支援しやすい「寛容さ」が持ち合わされなければできないことであることが見えてきました。
繰り返しですが、それはとても難しいことです。でも、それができたら、どんな人も地域で普通に生きることができる―。
*「おうちにかえろう 30年暮らした病院から地域に帰ったふたりの歩き方」は,
隔週で連載予定です*
■医学書院にはこんな本があります■

●第41回大宅壮一ノンフィクション賞受賞作●究極の身体ケア――言葉と動きを封じられたALS患者の意思は、身体から探るしかない。ロックトインシンドロームを経て亡くなった著者の母を支えたのは、「同情より人工呼吸器」「傾聴より身体の微調整」という即物的な身体ケアだった。かつてない微細なレンズでケアの世界を写し取った著者は、重力に抗して生き続けた母の「植物的な生」を身体ごと肯定する。