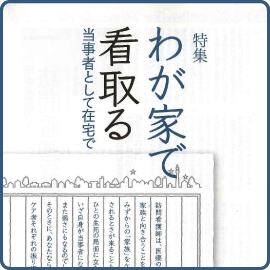かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

【第10回】退院の日~それぞれの前夜と朝に
2013.8.02 update.
いとう かよこ:千葉県千葉市在住。法律事務所勤務後、国立病院機構の介護職員として勤務。2008年りべるたす株式会社設立、代表取締役(在宅障害福祉サービス事業所管理者)。介護福祉士・社会福祉士・相談支援専門員。千葉大学大学院人文社会科学研究科博士前期課程修了,立命館大学大学院先端総合学術研究科博士後期課程在籍中。第47回NHK障害福祉賞第2部門(障害のある人とともに歩んでいる人)優秀賞受賞。 「りべるたす」ホームページはこちらから
おおやま りょうこ:千葉県千葉市在住。本連載のイラストレーター。 2009年特定非営利活動法人リターンホーム設立、代表理事(長期療養者へのエンパワメントを行うための研修事業等)。SMA(脊髄性筋萎縮症)療養のため、1978年大和田小学校から下志津病院隣接の四街道養護学校転入。1983年同小学部卒。86年同中学部卒。89年同高等部卒。 「リターンホーム」ホームページはこちらから
難病患者 大山良子の「退院前夜」~その強さ,意志と希望
私(大山良子)は、病院をいつ出るかについての具体的な話し合いを、2008(平成20)年の年明け頃から担当の医師,看護師長,児童指導員と始めました。
といっても、一緒に親や相談員が来て同席してくれるわけでもなく、自分一人でこれからの生活の希望や、伊藤さんとの間で決まっていることの報告をするのみでした。
その頃から、私が病院を出るということが病棟スタッフの間にも噂になって、病院に居づらさを感じ始めました。例えば、私が読んでいる福祉の本を片づけながら、看護師さんが、「伊藤さんに、だまされているんじゃない?」とか「病院を出たら、一生、面倒を看てもらいなさい」とか嫌味を言われ始めたからです。当人たちは、冗談のつもりかもしれませんが、私はまさか、このような言葉を言われるとは思っていなかったので、なんと受け答えしたらよいのか、困ってしまいました。
まるで自分が、いけないことしているような気持ちになりました。
「死亡退院が当たり前」(第2回)というこの病院で、なかなか経験できない「生きたままの退院」という行為に、私自身が後ろめたさを感じていたからかもしれません。
仲の良い患者さんたちは、「がんばってね!」と励ましてはくれていましたが、自分だけが病院生活を抜け出し、仲間を置いていく感じがして辛かったのです。
伊藤さんにしても、介護や退院の手続きをとるだけで大変な私をだましたところで、何の得もないだろうし、‟病院を出られるならだまされてもいい! このチャンスをモノにしなかったら、私はずっと病院にいなくてはいけない。こうやってずっと病院の生活を続けるくらいなら、もうどうなってもいい”と覚悟を決めていました。
心の片隅では、自分が退院することで病院の体制が一歩でも変わればよいのにと祈るような気持ちでいました。そのためには、自分がしっかりと生活をつくって、元気でいなくてはならなくて、どんなことがあっても失敗をしてはならないと思っていました。
なんとなく一度病院を出たら、もう二度と戻って来られないものなのだとも感じていました。
母も、退院についてはとても心配していました。私には同病の兄がいて、今よりもっと制度が整っていない時代にボランティア支援を受けて自立生活を10年続けたけれど、人手不足と体調不良で実家に戻っていたという(それで手一杯になった)事情があったのです。
だから、‟自立生活“というのはどこかで必ず破綻するというイメージが母には強く残っていて、それが安易に私の自立生活を賛成できなくしていました。
でも、私の強い意志を感じてか、「良子がここまで思うならいいよ」と最後には認めてくれました。
また、私がとてもお世話になったAさんのことが心に残っています。入院患者仲間のお母さんで、お子さんの面倒を看るのに毎日病院に来ている方でした。
Aさんは、自分の子どものことだけでなく、私たち他の患者さんのことまで親身にお世話をしてくれていました。病院では洗えない服の洗濯をしてくれたり、サイズの合わない服を直してくれたり、ちょっとした買い物をしてくれたり。病院のスタッフでは、日常生活の細かいところまではフォローされないので、Aさんは私にとってありがたい存在でした。
しかし、私が病院を退院することを知ったときから、そのことを喜んでくれると思ったAさんの態度が少し変わったような気がしました。なんとなく態度がよそよそしくなってしまい、「あなたは、病気が軽いからね!」と言われてしまいました。
今までの仲間という一体感がなくなって、繋がっていた糸が、プッツンと切れてしまったような感じになってしまいました。Aさんは、私が退院するということで、「入院患者の仲間はみんな、病院でなければ暮らすことはできない」という神話を壊すことになり、そうでない生活が可能であると証明できる日がくることをまるで恐れているように感じました。
もしかしたら、「退院できる私」が許せない気持ちだったのかもしれません。
Aさんは私と同じ病気仲間のMさんに「大山さんは病気が軽いから退院できるけど、あなたは無理なのよ」と言っていたと聞きました。そんなAさんの態度がとてもさみしかったです。Aさんとも、どこにいても仲間でいたいと思っていましたから。
Aさんは、子どものために本当に一生懸命でした。でも、そのお子さんを病院から出してあげたい、家に帰らせてあげたいと思っても叶えてあげられないというジレンマで、罪悪感を抱いていたのかなと、今は思います。
同時期に、病院スタッフのある方からいただいたお手紙には、こんな一節がありました。
「退院おめでとうございます。大山さんが病院を出たいと思ったのは、私たちスタッフの頑張りが足りなかったということなのかな? もし、病院生活がもっと快適だったら、病院にい続けたいと思ったのではないかと思うのです……」
私はAさんのことも、病院スタッフの誰のことも否定したいと思ったことはありません。
皆さんとても一生懸命やっていたと思います。しかし、私はそんなみんなと同じようにおうちに帰りたかったし、病院で暮らし続けたくはなかっただけなのです。
もっと自由に生きたかっただけなのです。
独立事業者 伊藤佳世子の「退院前夜」~その弱さ,眠れない不安と葛藤
この時期、私(伊藤)の頭の中には、
大山ちゃんがこれだけ長期療養をしていたということは、「長期に治療を受けなければならない、やむにやまれぬ事情」があって病院にいたということでなければならないんじゃないか。もし、昨日今日できたばかりの私の事業所で大山ちゃんの在宅生活を支えることができてしまうのなら、大山ちゃんの30年間は一体何だったのかということになる――。
あらためて、そんなくどくどしい思いがぐるぐると駆け巡っていました。
当時(2008年)には、表立ってこのことを口にすることはなかったのですが、病院スタッフも患者を入院させているご家族の一部も、そして地域の関係者も、この「国立病院機構が政策医療として筋ジス患者の長期療養を担っていることは正しいこと」という方程式をみんなで肯定したい(絶対に否定されたくない)という暗黙の圧力があり、私と大山ちゃんはそれに押しつぶされそうになっていたのでした。
しかし、だからこそ、どんなに(一時的には)嫌われても、たとえ邪魔をされても、これに挑むことが重要なのだと思っていました。ここに挑み、前例を作ることができれば、長期療養している筋ジス患者さんたちが病院を出るきっかけとなり、筋ジス病棟のあり方を変える糸口になると思えたのです。
退院が近づくにつれて、大山ちゃんからのメールは、段々と気持ちが上がっていく内容のものとなっていきました。
予定前々日(4月14日)に届いたメールでは
「病院を出るにあたって、色々なことがあってとてもつらい時期も長くありました。でも、いよいよ出られるんだと思ったらとても嬉しい気持ちになりました。私は病院で入院しているみんなにも是非この気持ちを味わってもらいたいと思うのです。
辛いことやたくさん面倒な手続きをしなくてはならなかったけど、そのぶん喜びもひとしおになるという感情の起伏や達成感を味わってほしいと思う」
と書いてありました。私はこのメールを読んで、
‟もう達成感を感じているなら、まだ早い! ここからが本番なのに……”
と歯がゆく思っていました。私にとってはそれからが勝負で・・・・・・でも、大山ちゃんにとっては、当然ながら「病院を出る」ことが一つの大きな節目なのでしたが、そのときの私には、その気持ちをじっくり一緒に味わってあげられるような余裕がなかったのです。
大山ちゃんも眠れなかっただろうけど、私も前の晩は眠れなかったです。
大山ちゃんは当時、病院の所在地である自治体で生活保護の申請をしたけれど「入院中ということで却下」されていました。
ケースワーカー「最初はしばらく過ごせるだけのお金を貯めたほうがよいと思う。20万円程度は貯金をつくって、(生活保護)決定まで時間がかかることも想定して病院を出るべきだ」
との意見でした。大山ちゃんが病院生活の中でお金を貯められるとしても、毎月1万円ちょっと…。退院は1年以上先になります。
また、住居となる区の担当者と1か月以上前から何度も交渉を詰める中で、
役所担当者「常時介護の必要な長期療養の難病の人が、在宅で一人暮らしですか…。でも、こういう方のために療養介護という制度があるのですけれどもね。病院も市外だし、そこから出られるとなると、病院を出てからでないと支給決定は無理ですね。急に言われても困るのですよ」
というような回答しか返ってこなくて、私の不安は払しょくできないままでした。
相談支援専門員に相談しても進展はなく、私はもうどうしてよいのかわかりませんでした。担当者には「介護給付の時間数がどれだけ出るのか?」と何度も聞いてみたのですが、「標準支給量は出るけどそれ以上はどれだけ出るかわからない」ということでした。
病院を出ないと、介護給付(重度訪問介護を申請していたのでその時間数)を決定できないというので、見通しをもっての退院ということはできないシステムになっていました。生活保護課でがこういった前例のないケースは難しいと言われ、しまいには、「制度的に無理があるのでは?」という意見もみられました。
このような仕組みでは、重度障害者が介護の見通しも経済的な見通しもない中、退院できる勇気をもてるはずはないわけですから、退院は冒険となってしまう怖さから、家族などの手助けがない人は病院に居続ける状況であることもよく理解できました。
私はもしも何事もうまくいかないときには、当面は私の家で大山ちゃんを引き取ろうと決意もしていました。でも、私が一人で抱え込んでケアをするのは、危険きわまりない関係となります。ですから、できるだけ公的制度を使って、彼女と対等な関係を続けていけるようにしたいと思っていました。
そうした中で、地域の訪問看護ステーションはいちおう引き受けてくれました。ただ、
訪問看護師「生命の責任主体はどこですか? 何かあったときに結局訴えるのは残された家族なのだから、そういったときにどうするのかはっきりと決めているのか?」
といったことをしきりに聞いてこられ、私の不安は、そうはいっても、ただでさえ大山ちゃんの家族も不安だらけで、消極的なのにいきなりそんなこと話し合えそうもありませんでした。
どうやったら大山ちゃんが地域で暮らすことができるか? という前向きな視点よりでなく、問題点ばかりを突き付けられていたような気がしていたのです。
今となれば、それらは、私や大山ちゃんにどれほどの覚悟を持っているのかを試されていたことでもあり、周囲との丁寧な合意形成の必要性を伝えてくれていたことなのだと思います。
でも、2008年の私にはそういった周囲の皆さんの意味あいが通じなくて、言葉の意味がわからなかったのでした。
また、こういったケースの最初の一人は、周囲との合意形成は必ずとれるとは思えません。同じような事例がいくつも出てきて初めて、周囲との合意形成ができ上がっていくのでしょう。
また、この当時に私が憤慨していた、もう1つのこと。
それは周囲から、病院を退院させた「私・引き受けた事業所の責任」ばかりを言われ、大山ちゃん本人は「長期療養者だから、責任をもてるような状態にない」と言われ、真の当事者である大山ちゃんに、誰も何も突きつけられてなかったことです。それをむしろ「ずるい」とも思っていました。
今、この連載の読者の方も、ひょっとしたら「大山ちゃんに責任を負わせるなんてかわいそう! 伊藤は無責任!」と思われるかもしれません。
でも、大山ちゃんのような長期療養をしてきた難病患者は、本当に責任をとれない、「客体」であるだけの存在なのでしょうか?
2008年の大山ちゃんは37歳で、私より2歳年上でした。そうして、彼女は30年暮らした病院から、こうして思い切って出る決断を自ら付けられるだけの強さと、いわば社会性をも持っていたではないですか――。
そもそも、医療職が言われる「いのちの責任」というのは何でしょう?
そういうものの責任の取り方が、私にはどうしてもわからないのです。
例えば、その当事者が死んでしまったときに生命保険に入っているのかという民事(損害賠償)的な問題なのか。刑事(罰)的な問題なのか。それとも、あくまで形式上、「誰か」によって行われたという「一人の名前」を書面に記載することが必要……??
世の中に‟モンスター患者”と言われる人がいて、医療者側の思いもよらない訴えを起こす人たちもいるような時代ですから、もうさまざまなところで、こうした手続きが必要な事態が起きているのかもしれません。
でも、どうもそのあたり業界の常識がわからない私には戸惑うことばかりで、とても冷たい世界に思えてなりませんでした。
いざ退院の日に~2008年4月16日
2008(平成20)年4月16日の朝。
大山ちゃんがいよいよ退院する日がやってきました。
彼女から「今日からよろしくね」というメールがまず届きました。そんなメールを読むにつけても、最高潮に胃の痛い朝なのでした。
まず子どもを保育園に送りに行った私は、足取り重く、病院の近所の社会福祉協議会にリフト付きの福祉車両を借りに行くところから行動をスタートしました。
退院手続きに際し、病院スタッフから何か(答えられないようなことをまた)聞かれるのかなぁ?と思い、暗い気持ちを抱えながら病院に向かいました。今は何も聞かないでほしいと思っていました。このときに一度でも、自信をもって答えられないようなことを聞かれたら、私はもうそこで、何もできなくなってしまっただろうと思います。
深呼吸をして病棟に入り、まず大山ちゃんに「おはよう。大丈夫? 昨日眠れた?」と聞くと、「大丈夫。寝たよ」と返事が返ってきました。
お互いに不安を口にするようなことはありませんでした。彼女はいつものようにニコニコしていました。
この日は水曜日。病棟のお昼ごはんは麺の日でした。大山ちゃんと事前の相談で、退院の日はお昼ごはんを外で買って食べようと言っていたのですが、この最後の病院食が「‟引っ越しそば”になったから」と、彼女はやはり病棟で食べることに決め直したのだそうです。
一刻も早くここから立ち去りたい私は、彼女や病棟仲間の話を、ほとんどうわの空で聞いていませんでした。
大山ちゃんは30年暮らした病院からの退院手続きのやり方がわからず、受付の方の説明を受けて1つずつ手順を済ませてゆきました。それから、スタッフや病棟の皆さんに挨拶をして、病棟を後にすることになりました。
私たちは両手に荷物をいっぱい抱えて、一緒に玄関に向かいました。筋ジス病棟は昔、結核病棟だったところを便宜上改修してできたために、いまや隔離される必要もないのに一般病棟とは離れたところにありました。だから、いざ外に出るまでだけでも、長い廊下を歩かなくてはならないのです。その長い廊下も、半分外界に面していたりするのですが、その廊下では昔、筋ジス病棟の子どもたちが「リハビリ」といって行ったり来たりする歩行訓練を行っていた場所でした。大山ちゃんも、何度何度も歩いた場所です。
私は足早に進み、隣で大山ちゃんは電動車いすを走らせていました。私たちは一緒に玄関へ向かっていました。
「ちょっと待ちなさい」と誰かに止められて、何か言われるのを恐れる気持ちが強く、一刻も早くここから抜け出して、もう二度とここに来たくないと思っていました。

車に乗るとき、彼女の顔を見ると、目からポロリと涙が出ていました。
いつも感情を出さない大山ちゃんが、泣いていました。この涙を見ると、にわかに自信がなくなりました。やっぱり大山ちゃんは病院を出るのは淋しいのかな、これからが不安なのかな、やっぱり止めたいというつもりかしら……。
でも、それを聞く勇気は私にはありませんでした。そういう顔を見れば見るほど、また胃が痛くなっていくのです。
立岩真也氏の言葉を借りれば、「いい加減でも、引き受けないよりはまし」なのだそうで、病院で一生暮らすより、失敗してもチャレンジしなければ何も変わらないのだ。見通しのない介護体制や経済状況だけれども、一歩を踏み出さなければ何もかわらないからと自分に言い聞かせることにしていました。
不安いっぱいの中、でも、きっと大丈夫なはずと信じて、玄関まで見送ってくれた大山ちゃんの病棟友だちに手を振り、30年の入院生活にピリオドを打つ彼女を、車に乗せて走りだしました。
4月16日(水) 退院。
この日のために、新しい洋服を買っていました。
いつものスエットの服ではなく、きちんとした姿で病院を出たかったのです。
スタッフがお化粧をしてくれました。なんだか胸がいっぱいになりました。
病院で最後の昼食を食べました。味なんかわからないくらい緊張していました。
伊藤さんが迎えに来て、部屋に残っている荷物を片付け、病院とさようならする時がきました。
病棟のスタッフや車いすに乗っている患者さんたちが見送ってくれました。
みんな、笑顔で送ってくれました。
いつも、見送っていたのはストレッチャーの上に白い布をかけられている患者さんだったので、生きたままの退院がどれだけ喜ばしいことかが身に染みました。
病院の外来まで、仲の良かった患者さん達が送ってくれました。
笑顔の目から、涙が出てきました。みんなも泣いていました。
嬉しいんだけど悲しい。
退院できる喜びと、自分の半分を置いていくような寂しさと、これからの生活の不安がいっぺんに吹き出てしまいました。でも、私は負けてはいられないのです。見送りに来てくれたMちゃんに、私は宣言しました。
『絶対に、迎えにくるからね!』
みんなが、病院を退院できる社会にする!
そう決意した4月16日でした。 大山良子

病棟・外来看護師必携! 今日からはじめる「生活目線」の退院支援
在院日数短縮に伴い注目が高まる退院支援。医療依存度の高い患者の退院・在宅療養生活への移行には、入院早期、ひいては外来通院中からの、看護師による「生活目線」の退院支援がカギとなる。退院調整部門はもちろん、すべてのスタッフ、看護管理者に求められる退院支援の考え方、知識、方法論を、退院支援の第一人者の著者がナビゲート。