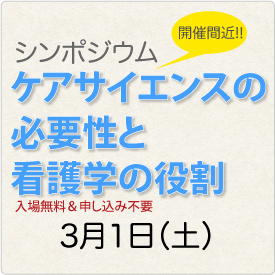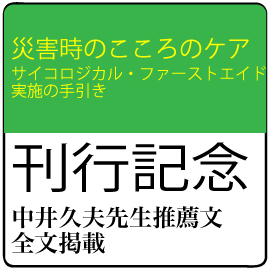かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
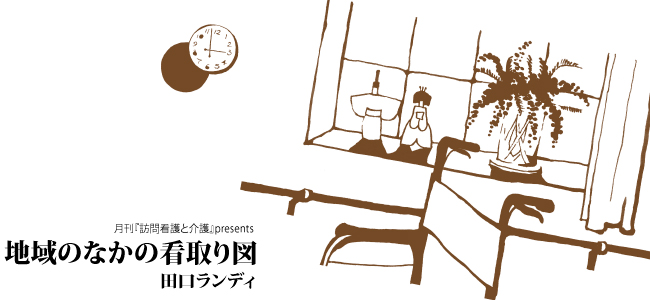
12-2 崖っぷちでの出来事 家で看取るということ〈その5〉
2014.2.12 update.
なんと! 雑誌での連載をウェブでも読める!
『訪問看護と介護』2013年2月号から、作家の田口ランディさんの連載「地域のなかの看取り図」が始まりました。父母・義父母の死に、それぞれ「病院」「ホスピス」「在宅」で立ち合い看取ってきた田口さんは今、「老い」について、「死」について、そして「看取り」について何を感じているのか? 本誌掲載に1か月遅れて、かんかん!にも特別分載します。毎月第1-3水曜日にUP予定。いちはやく全部読みたい方はゼヒに本誌で!
→田口ランディさんについてはコチラ
→イラストレーターは安藤みちこさん、ブログも
→『訪問看護と看護』関連記事
・【対談】「病院の世紀」から「地域包括ケア」の時代へ(猪飼周平さん×太田秀樹さん)を無料で特別公開中!
「未来のない人」?
ああ、この人の顔色が変わった。自分は今よほどひどい状態なんだろう……と。とくに女性は、自分の容貌が変容していくことに絶望します。
がんであろうと、認知症であろうと、老衰だろうと、同じだと思います。
自分が変わってしまうつらさは、年齢と関係ありません。
相手の顔が引きつっている。自分は変だと思われている。自分は相当に弱っている。ああ、自分はそんなにみすぼらしい姿をしているのか。そんなに痩せてしまったのか。自分の言っていることは変なのか。自分の行動は変なのか。自分はもう、以前の自分ではないのか?
実際に、肉体は死に向かって変化しています。それを目の当たりにすれば、どんなに平静を装っても、動揺は隠せません。隠せませんけれど、人間というのはすごい適応力もあって、時間が経てば慣れるんです。しばらく一緒にいると、以前と同じ相手だと感じるようになります。
そうなると、今度は「以前と同じ話題」をしようとします。
会社の同僚なら会社のこと、学友なら学校のこと、親族なら家族のこと。
でも、余命宣告をされている相手が以前と同じ会話をしたいかといえば、そうではないんです。
相手はこれから、まったく別の世界に行こうとしているわけです。この世界とはお別れするわけです。会社を退職する人に、来年の事業計画を話してもしょうがないでしょう。それと同じです。
変化している相手の姿の背後に、不変の本質を見る。
しかし、変化し続けている相手の心に添う。
私は、それがよくわかっていなかった。柳原さんの病状が進行しても、ずっと彼女と共通の話題である執筆のこと、出版のこと、それから医療問題の話などをしようとしていました。
話題が途切れるのが怖くて、猛烈な勢いで昨今の医療問題についてまくしたてて議論して、別れたあとすごくむなしくなるんです。いったい、彼女とどんな会話をしていいのかわからない。なにか、とても不誠実な気がしてくる。自分が、もう彼女を「未来のない人」と見ているのがわかる。
どう対応していいのかわからない。絶対治るよ、と空々しい希望を語ることもできない。かろうじて、病気であることを度外視して、以前と同じ話題を続けることで、その場をやり過ごす。
こんな友人の見舞いは、いちばん疲れるでしょうね。
違うんですよね。
もっと切実で、もっと大切な話があるはずなのに、ゆとりがなくて、何が相手にとって必要なのかを考えることができなかったのです。
老いても、病んでも、心は不変です。
心は、どんなときでも、
みずみずしいままです。
ずっと、みずみずしいままです。
黒岩さんとは、20歳代のころ、同じ会社で机を並べていました。彼女のすい臓がんは、検査時にはもう転移が始まっていました。大学病院は、もはや治療の施しようのない彼女に緩和ケアの充実した病院への転院を催促してきました。病院の対応はとても厳しいものでした。家族に緩和ケア病棟のある病院のリストを一枚渡しただけ。「あとは、自分で探してください」ということなのでしょう。
出ていけと催促されているような対応に、彼女は傷ついていました。
「このごろ、看護師さんがあまり来てくれない」
「以前は尿検査をしていたのに、このごろしてくれない」
見放されている感じは、強かったと思います。
ようやく、緩和ケアの充実している病院に転院できたとき、医師の「これから何がしたいか?」という質問に対して、
「また、食べられるようになって、元気になりたい」
と答えた彼女。もう水やゼリーしか口にすることができなくなっていました。
転院したのは、12月の初旬でした。私は彼女の部屋に家から持ってきたクリスマスツリーを飾りました。ちょっとはやいけれど、たくさんイルミネーションをつけて、ふわふわの綿で雪の飾り、てっぺんには金色の星。
彼女の弟さん・妹さんと3人で、クリスマスの思い出とか、子どものころのことをおしゃべりしながら、時間をかけてツリーを飾りつけました。小人の楽団のオーナメントを、小さなものが大好きな黒岩さんは「かわいい」と言って見つめていました。
その翌朝に、彼女は旅立っていきました。
がんであろうと、認知症であろうと、老衰だろうと、同じだと思います。
自分が変わってしまうつらさは、年齢と関係ありません。
相手の顔が引きつっている。自分は変だと思われている。自分は相当に弱っている。ああ、自分はそんなにみすぼらしい姿をしているのか。そんなに痩せてしまったのか。自分の言っていることは変なのか。自分の行動は変なのか。自分はもう、以前の自分ではないのか?
実際に、肉体は死に向かって変化しています。それを目の当たりにすれば、どんなに平静を装っても、動揺は隠せません。隠せませんけれど、人間というのはすごい適応力もあって、時間が経てば慣れるんです。しばらく一緒にいると、以前と同じ相手だと感じるようになります。
そうなると、今度は「以前と同じ話題」をしようとします。
会社の同僚なら会社のこと、学友なら学校のこと、親族なら家族のこと。
でも、余命宣告をされている相手が以前と同じ会話をしたいかといえば、そうではないんです。
相手はこれから、まったく別の世界に行こうとしているわけです。この世界とはお別れするわけです。会社を退職する人に、来年の事業計画を話してもしょうがないでしょう。それと同じです。
変化している相手の姿の背後に、不変の本質を見る。
しかし、変化し続けている相手の心に添う。
私は、それがよくわかっていなかった。柳原さんの病状が進行しても、ずっと彼女と共通の話題である執筆のこと、出版のこと、それから医療問題の話などをしようとしていました。
話題が途切れるのが怖くて、猛烈な勢いで昨今の医療問題についてまくしたてて議論して、別れたあとすごくむなしくなるんです。いったい、彼女とどんな会話をしていいのかわからない。なにか、とても不誠実な気がしてくる。自分が、もう彼女を「未来のない人」と見ているのがわかる。
どう対応していいのかわからない。絶対治るよ、と空々しい希望を語ることもできない。かろうじて、病気であることを度外視して、以前と同じ話題を続けることで、その場をやり過ごす。
こんな友人の見舞いは、いちばん疲れるでしょうね。
違うんですよね。
もっと切実で、もっと大切な話があるはずなのに、ゆとりがなくて、何が相手にとって必要なのかを考えることができなかったのです。
老いても、病んでも、心は不変です。
心は、どんなときでも、
みずみずしいままです。
ずっと、みずみずしいままです。
黒岩さんとは、20歳代のころ、同じ会社で机を並べていました。彼女のすい臓がんは、検査時にはもう転移が始まっていました。大学病院は、もはや治療の施しようのない彼女に緩和ケアの充実した病院への転院を催促してきました。病院の対応はとても厳しいものでした。家族に緩和ケア病棟のある病院のリストを一枚渡しただけ。「あとは、自分で探してください」ということなのでしょう。
出ていけと催促されているような対応に、彼女は傷ついていました。
「このごろ、看護師さんがあまり来てくれない」
「以前は尿検査をしていたのに、このごろしてくれない」
見放されている感じは、強かったと思います。
ようやく、緩和ケアの充実している病院に転院できたとき、医師の「これから何がしたいか?」という質問に対して、
「また、食べられるようになって、元気になりたい」
と答えた彼女。もう水やゼリーしか口にすることができなくなっていました。
転院したのは、12月の初旬でした。私は彼女の部屋に家から持ってきたクリスマスツリーを飾りました。ちょっとはやいけれど、たくさんイルミネーションをつけて、ふわふわの綿で雪の飾り、てっぺんには金色の星。
彼女の弟さん・妹さんと3人で、クリスマスの思い出とか、子どものころのことをおしゃべりしながら、時間をかけてツリーを飾りつけました。小人の楽団のオーナメントを、小さなものが大好きな黒岩さんは「かわいい」と言って見つめていました。
その翌朝に、彼女は旅立っていきました。

いよいよ高まる在宅医療・地域ケアのニーズに応える、訪問看護・介護の質・量ともの向上を目指す月刊誌です。「特集」は現場のニーズが高いテーマを、日々の実践に役立つモノから経営的な視点まで。「巻頭インタビュー」「特別記事」では、広い視野・新たな視点を提供。「研究・調査/実践・事例報告」の他、現場発の声を多く掲載。職種の壁を越えた執筆陣で、“他職種連携”を育みます。楽しく役立つ「連載」も充実。
1月号の特集は「『新生在宅医療・介護元年』の成果と展望」。厚生労働省は2012年度を新生在宅医療・介護元年」と位置づけ、「在宅医療連携拠点事業」を行なった。本事業には訪問看護ステーションも9拠点が取り組んだ。本特集では、事業の成果を概観するとともに、2025年へ向けて、いかに「多職種連携」を行ない、「在宅医療」を充実させていくのか。各拠点の本事業への取り組みから、2014年への示唆を得る。