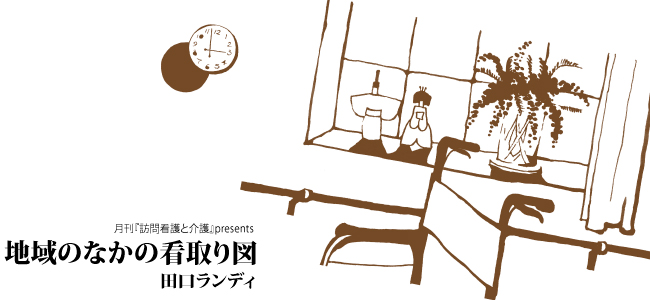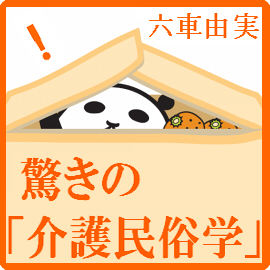前回まで
家で家族を看取るのは、本当に難しいです。
自分の両親と夫の義母、3人の看取りを経験して、やっと最後に義父であるおじいちゃんを、家で看取ることが(かろうじて)できました。家で看取ることが良いとか悪いとか、そういうことではありません。家での看取りは、家族にさまざまな責任がのしかかってくる。それを受け止めるのは、やっぱりしんどい。えっ、こんなことまで私が決断しなくてはならないの?って、思ってしまうこと、多々ありました。
死のリアリティー
在宅で看取るために、一番大切なことは「亡くなっていく方の意思の確認」だと思います。本当に病院での延命治療をしなくていいのか。それをていねいに確認して、看取る側と看取られる側の合意ができていなければ、たぶん、納得のいく在宅看取りは難しいと思うのです。
でも、90歳を超えたとはいえ、身のまわりのことは自分でできる元気な義父母に、嫁の私から「死ぬときは家がいいか、病院がいいか?」という話題をもちかけることは……ためらいがありました。まるで、死ぬのを待っている鬼嫁みたいだなあ、と。
こんな話をして気を悪くしないかしら。
気まずくなったらいやだな。
気の重い話題です。こんなことをいつ言い出していいのかわかりません。でも、元気なうちに聞いておかなければ、倒れて昏睡したり、認知症になってからでは、本人の意思が確認できなくなってしまいます。
私の父が末期がんで入院したとき、やっとチャンスが訪れました。義父母は父の姿を見て、自分たちにもいつかこういうことが起こるのだ……ということを痛感したようでした。
父は70歳代で亡くなりましたから、義父母は「まだ若いのに気の毒になあ……」と、何度もつぶやいていました。入院先のホスピスに見舞いに来てくれたときも、やせ細った姿を直視できず目を伏せたままの義父母。父に声もかけることができず、ショックを受けている様子を見て、ああ、自分たちの死ぬときのことを考えているのだろうなあ……と思いました。
父の入院と看取りをきっかけにして、やっと義父母に「あのね、もし、おじいちゃんたちが具合が悪くなったら、どこで死にたい?」と、ストレートに質問できるムードができあがってきました。死のリアリティがない場に、いきなり看取りの話題はできないですね。何事にもタイミングというのがあるのだとつくづく痛感します。
延命を、するか、しないか?
この選択はできれば、頭がボケないうちに本人たちにしてほしい。私は心底そう思っていました。決めるのは本人であってほしい。だから、2人には私が体験してきたことを、正直に話しました。
「私の母は脳出血で倒れて、そのまま救急病院に運ばれ、病院で亡くなったんですよ。知らせを受けて病院に駆けつけたとき、最初に医師から聞かれたことは『もう助かる見込みがないとわかった場合、人工呼吸器を外していいか』ということだったんです。そりゃあびっくりしました。なんてひどい医者だろうって。私はとっても動転していて、『そんな大事なことを突然に聞かれても答えられない』って怒ったんです。母が本当に死ぬなんて考えられなかった。だって前の晩は元気だったんですから……。結局、母は病院で点滴と人工呼吸器の延命治療を受けて、4か月の間、植物状態で過ごして亡くなりました。付き添っていると本当に苦しそうでした。
父は、母にずっと付き添っていたから、病院で人が死ぬのはどういうことかわかっていて、それで、自分のときは延命はしなくていいと、そう言っていたんです。私も、あの母の姿を見て同じことを感じていたから、父のときはホスピスに入ってもらい、食べられなくなったら点滴もしなかったのです。でも、父は自分が末期がんだということを忘れてしまったので、本当に父をホスピスに入れてよかったのかどうか、ずっと悩んでいました。おじいちゃんとおばあちゃんは、父の最期も見ているから、延命しないというのが、どういうことか、少しわかると思うんですよ。だからね、自分たちのときはどうしたいのか、今のうちから考えてみてほしいんです」
2人は真剣に私の話を聞いてくれました。それぞれに「死ぬときは、いろいろやらんでいい。なるべく人に迷惑をかけずに死にたい」というようなことを言っていました。でも、それはとても曖昧な言い方で、自分たちもどうしていいかわからないみたいでした。それに、2人はとても信心深い人たちで、信仰をもっていましたから、信仰していればなんとかなる……と確信していたみたいです。その、なんとかなる……というのが、具体的にどうなるのか……は、判然としないのですが、とにかく、なんとかなる。信仰さえあれば大丈夫だ。そう思っていたようです。
そして、おばあちゃんが脳梗塞で倒れ、病院で亡くなりました。肺炎になって、あっけない最期でした。
おばあちゃんの死を目の前にしたとき、おじいちゃんには死がリアルに自分の問題として立ち上がってきたようでした。だからと言って、「死ぬときはどうしたいか」をはっきりとは伝えてくれていませんでした。
なんとなく、この話題はいつも投げやりな感じで終わるのです。
「なんもせんでええ」とか「迷惑かけとうない」とかです。
家族が死の話題を共有して真剣に話し合うのは、とても難しいと実感しました。テレビドラマや映画のようなわけにはいかないのです。やっぱり、みんな「死」は怖い。いくつになっても「死にたくない」し、あんまり考えたくない事柄なのです。だから、本当は第三者に……たとえば、訪問医の方などが、往診時にさりげなく聞いてくれればいいのかもしれません。
それが理想的なのでしょう。
ああしたほうがいい、こうしたほうがいい……ということはたくさんあるのですが、ものすごいスピードで事態が展開していくので、だいたいいつも間に合わないのです。なにもかもが後手後手に回っていく……。それが在宅介護、在宅看護ってものなのだ……とすら思えてきます。