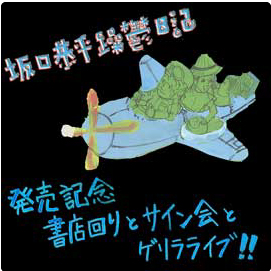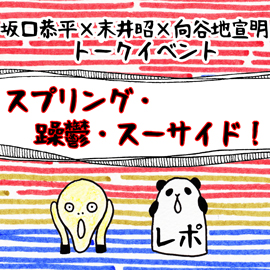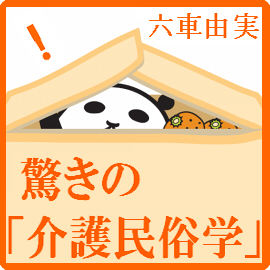かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
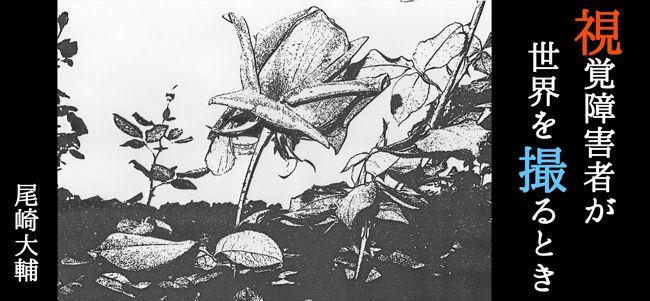
〈第1回〉見えなくっても写真は大事
2015.1.28 update.
1983年三重県生まれ。早稲田大学社会科学部在学中にファッション雑誌での編集の仕事を経て、写真家として活動を開始。卒業後、渡英。2007年、London college of communication(ABC diploma in photography)卒業。2011年より視覚障害者を中心に知的障害者、精神障害者などを対象としたワークショップを多数主催。日本視覚障碍者芸術文化協会(Art for the Light)副会長。『写真は私たちの記憶を記録できるのですか?』(発行:PLACE M、発売:月曜社)、『無』(同)、『ポートレート』(月曜社)を出版。
http://www.daisukeozaki.com/
私は尾崎大輔といいます。これまで写真家として、障害のある方を含め、さまざまな方のポートレートを撮影していたのですが、2011年、ひょんなことから視覚障害のある方を対象にした写真教室を始めました。活動を始めてから数年が経ちますが、初めて会った人に「視覚障害者に写真を教えている」と言うと必ず、「どうやって?」「そんなことできるの?」と聞かれます。
この連載では数回にわたって、視覚障害者に写真を教えることの実際、また「見えないこと」と「目に見えるものを写すこと」の関係などをお話ししていこうと思います。
★視覚障害者はどうやって写真を撮るの?
私たちが写真を撮るときは、「被写体を目で見て選び、カメラをその方向に向けてシャッターを指で押す」という一連の行為が行われます。それでは、“見る”ことができない視覚障害者は、いったいどうやって写真を撮るのでしょうか。
視覚障害者は“見る”という視覚の代わりに、声や音を聞く聴覚、触って物を認識する触覚をもとに、自分自身が興味をもった被写体にカメラを向けてシャッターを押し、写真を撮ります。また、撮りたいと感じた被写体の方向に手や白杖を伸ばし、その方向を目指して真正面を向くことで正確に写真を撮るという工夫もあります。
写真:白鳥ボートを撮るために伸ばされた白杖
私が2011年から主催している視覚障害者向け写真教室では、デジタルカメラを使っています。最近のデジタルカメラは性能が非常によいものです。ピントは勝手に合わしてくれるし、機種によってはスマイルシャッターといって、人が笑顔になったのをカメラが認識してタイミングよく写真を撮ってくれたりもします。少し前には数秒だけ音声記録のできるレコーダーつきの物もありました。デジカメならば枚数を気にしないでたくさん写真を撮ることができ、視覚障害者の方も気軽に写真を始められるようになったという面もあります。
★凹凸にした写真を触って、“見る”
私の主催する視覚障害者向け写真教室では、撮った写真を特殊なペーパーと熱が出る作成機を使って凹凸の立体写真に仕上げています。3Dプリントをイメージしてもらえればよいかなと思いますが、3Dプリンターよりもずっと簡素な機械で、やり方さえ覚えれば誰でも簡単に使えます。視覚障害者は、その凸凹の浮き上がった部分を触りながら触覚と健常者からの説明によってイメージを得て、写真を認識することができます。
もちろん、視覚情報である平面の写真を立体の凹凸にしたからと言って、視覚障害者に写真の情報がすべて伝わるわけではありません。ただ、この凸凹によって写真を“触って”認識できるようになったことで、先ほどのデジカメと同じように、視覚障害者の方たちに写真をより身近なものとして感じていただけている気がします。
写真:凹凸加工した写真。表面がボコボコしている。
★写真は記憶の大きなパーツ
写真教室には、視覚障害者の方がご家族で参加されるというケースも多くあります。ある日、中途失明の全盲のお母さんと、小学6年生の息子さんが2人で写真教室に参加されました。ご主人にも視覚障害があるということでした。彼女には2人のお子さんがいますが、2人のお子さんの顔を見たことは一度もないと話していました。
私自身も現在子育て真っ最中で、自分の子どもの写真を撮ることも増えたので、視覚障害のあるご夫婦、お子さんの家族アルバムはどうなっているのかが気になり、お聞きしてみました。
お母さんは、自分で撮った写真はないものの、学校の運動会などの行事でカメラマンが撮った写真は必ず購入して、それを集めて子供のアルバムをつくっていると話しました。「子供の写真は見える、見えない関係なく欲しいです」という彼女の気持ちは、同じ1人の親として、十分わかります。
しかし彼女は、ヘルパーさんに「子供が写っている写真を見つけて、買ってきてほしい」と頼んだときに、「見えないのにどうして必要なのですか?」と言われたことがあると言います。これはヘルパーさんの素朴な疑問だったのでしょうが、彼女はすごく傷ついたと話していました。
その日写真教室で、彼女は初めて自分自身で息子さんの写真を撮りました。その写真を凹凸にして差し上げたところ、彼女はその写真を指で撫でながら、「今まで見たことのない、息子の顔がなんとなくわかりました!!」と、とても喜んでいました。彼女の記憶の中に、触覚としての「息子の顔」が付け加わったのです。
写真:お母さんが初めて撮った息子さんの写真
このお母さんとの会話は、私にとって非常に興味深い出来事でした。
お母さんは凹凸にした写真を触ったことで息子さんの顔をイメージすることができ、とても喜んでくれました。しかし、写真を凹凸加工して触ることは一般的には特別なことだと思います。もしも写真を触れるように加工しなかった場合、前述のヘルパーさんが言うように、見えないのにどうして写真は必要なのでしょうか?
この社会の大多数の人は晴眼者であり、写真を目で見ることができます。写真が存在し、それを見ることができれば、そこから言葉が生まれ、コミュニケーションが始まります。これは昨今のSNSにおける写真画像の広がりを考えればよくわかると思います。
撮影した当人が視覚障害者の場合や、視覚障害者当人がその写真に深く関係する場合はどうでしょうか。彼らは自分自身では写真が見えなくても、晴眼者とその写真を介してコミュニケーションをとることによって、その写真に写っている当時の記憶を呼び起こすことができます。実際、別の全盲のご夫婦から、「子供の写真を撮るようになってから、介助者も含めての会話がとても増えた」と喜びの声を聞いたことがあります。
写真は、見えなくてもコミュニケーションの大事なツールになり、思い出を形づくる役割を果たすという点で、晴眼者、視覚障害者関係なく、記憶の大きなパーツなのです。
★「見えないから」でなく共に見る
このページの読者は医療者の方が中心かと思いますので、最後に、先ほどのお母さんが、子供が病気になった際に感じたことを紹介したいと思います。
子供がまだ幼い頃には、急な発熱などでどうしても初めての病院に行かざるをえない時があります。このお母さんは、介助者と子供と一緒に病院に行った場合、細かい質問のほとんどが介助者に振られるという経験を何度もしてきたと言っていました。
子供の状況を一番知っているのはやはりお母さんなので、結局お母さんが答える形になるのですが、当時、点字の母子手帳をもらうためには県庁での手続きが必要であったことや、病院や役所での必要書類を全盲の視覚障害者が1人で全て記入するということはなかなか難しいということもあり、病院側も介助者ありきの対応になってしまったのだと思います。
ただ、お母さんは「子供の母親は私です。私を1人の母親として対応してもらいたかった」と話していました。別の人はレントゲンを撮った際に、「見えないから」とほとんど説明すらされないこともあったそうです。言葉での説明によって、見えなくてもイメージは湧きますし、「イメージできましたか?」と会話を重ねれば理解に至ることもできるはずです。
このような、視覚障害者とのコミュニケーション不足は、多忙な医療現場のみならず日常生活でも起こることです。「見えないからわからない」と思い込んでしまうのではなく、何がわかって何がわからないのか、何を知りたいのかといった、個人の物語に注目することが求められると、「見えない」写真を撮る写真教室で多くの視覚障害者の方に接する中で感じています。
次回は、なぜ視覚障害者に写真を教えるという活動を始めたのかについて紹介したいと思います。