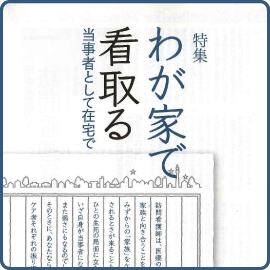かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

【第12回】あとに続いた真由美さんのはなし
2013.9.13 update.
いとう かよこ:千葉県千葉市在住。法律事務所勤務後、国立病院機構の介護職員として勤務。2008年りべるたす株式会社設立、代表取締役(在宅障害福祉サービス事業所管理者)。介護福祉士・社会福祉士・相談支援専門員。千葉大学大学院人文社会科学研究科博士前期課程修了,立命館大学大学院先端総合学術研究科博士後期課程在籍中。第47回NHK障害福祉賞第2部門(障害のある人とともに歩んでいる人)優秀賞受賞。 「りべるたす」ホームページはこちらから
おおやま りょうこ:千葉県千葉市在住。本連載のイラストレーター。 2009年特定非営利活動法人リターンホーム設立、代表理事(長期療養者へのエンパワメントを行うための研修事業等)。SMA(脊髄性筋萎縮症)療養のため、1978年大和田小学校から下志津病院隣接の四街道養護学校転入。1983年同小学部卒。86年同中学部卒。89年同高等部卒。 「リターンホーム」ホームページはこちらから
真由美さんは栃木県出身。筋ジストロフィー症(筋ジス)の女性です。彼女は小学校1年生までは普通の学校に通っていてそれから入院、以降は併設の養護学校に通っていたそうです。

お母様の話では、入院からしばらくして医師に「この病気は進行するから、専門病院へ転院したほうがよい」とすすめられたそうです。そのとき、選択肢にできた施設は仙台と千葉。雪の多い東北でもし家族が病院へ行ってやれないときがあったら困るから…と、千葉への転院を決めたとのこと。
地元栃木の病院は、自宅から車で5分くらいのところで、毎週末に家に帰ることもできました。しかし、千葉となるとそういうわけにもいかず、面会は月に1回程度に。彼女はそのとき10歳でした。こうして家族から遠く離れての生活が始まるのですが、真由美さんはそこで大山ちゃんと出会い、「22年間、寝食を共にする」という、家族以上の関係となるのでした。
大山ちゃんがいざ退院する1か月ほど前に、「やっぱり病院を出るのをもう少し延期したい」と話してきたことがありました。理由を聞けば、「真由美さんが最近夜に落ち着かないから」と言うのです。
真由美さんが夜間に鼻マスク人工呼吸器を装着するようになってパニックを起こすことが多くなり、ナースコールで看護師さんが来ないと不安でいたたまれない彼女の様子に、向かいのベッドに寝ていた大山ちゃんが気遣いの声をかけていたのですが、自分が退院したら、一人で恐怖の夜を過ごすことになるであろう真由美さんを思うと……置いてはこられないと思ったようでした。
病院や施設のいわゆる集団処遇では、少数の介助者が複数の被介助者をケアするので、筋ジスのように介助量の多い患者は不利になります。進行性疾患の機能低下は少しずつゆっくりと進みます。そして、昨日はすんなりできていたことが今日はうまくできなくなります。そのことに当事者はどんなにか落ち込むことでしょう。さらに、それに追い打ちをかけるかのように、時間に追われる介助者に‟手のかかるめんどうな患者”とレッテルを貼られてしまいます。
病いが重度になれば、その「進行」と「面倒と思われること」の二重の苦しみを、入院患者は味わうことになってしまうのです。
筋ジス病棟は頻繁に入院患者が入ってくるわけではないのですが、全体的に病状が日々進行し、介助量は多くなっていきます。しかし、スタッフの人数が増えるわけではないので効率を上げるしかありません。
私(伊藤)が病棟で働いている頃、大事にしていたのは‟時間”でした。朝7時までに全員起床しなくてはならないので、たとえ昨日までできていた座位が、今日できなくなっている人がいても、そこに費やす時間はありません。あと3部屋回って全員を起こさなくてはならないというときには、時計を見て「そのまま寝ていてください」といい放ち次の人へと判断したことがありました。今にして思えば大変に申し訳ないことでしたが、限られた時間の中で人手もなく、一人ひとりをゆっくり見ることができないのです。
それでも、病院の中で看護師を呼べばすぐに来てくれる場所でこのまま人生を過ごすか――少数の看護師が多くの患者をみることとなります――、在宅で潤沢に介護職をつけてケア量を確保するか――これですと医療体制は訪問診療や訪問介護となり、病院ほど手厚い医療は受けられません。大山ちゃんは悩み、在宅ケアを選んだほうが、自分自身にはあまり医療的ケアが必要ないため、まずは生活の上でのケア量を確保して過ごしたほうがよいと判断したようでした。
また、自分だけでなく真由美さんも同様に、それほど「医療」の比重は高くせずとも、介助するヘルパーの人手が潤沢にいれば大丈夫だという確証をもっていたようです。
そうした思いもあって、まずは大山ちゃん自身が地域に出る実践をして、その後、妹分の真由美さんをも病院から地域に出そうと決断したようでした。
1985(昭和60)年ごろの事。
病院の筋ジス病棟は、二階建ての鉄筋のとても古い建物で、畳の部屋とベッドの部屋があり、40人くらいの患者さんが入所でき来るようになっていました。
畳の部屋には、まだ病状が軽く自分でトイレや食堂に行くことができる患者さんがいました。ベッドの部屋には、自分では動けない重度な患者さんがいました。
移動方法は、車いすではありません。自分で動ける患者さんが病棟内を移動するときは、四つん這いやお尻を床につけていざり方法で動きます。病棟は縦長で、食堂から自室まで約30メートル。自分の動きやすい方法で1時間かけて移動します。歩ける人ならば、30秒もかからず進める距離です。動いても動いても、食堂までたどり着けず遠く感じる日もありました。
床は、コンクリートです。冬はとても冷たく、足にしもやけができてしまうほどでした。
自分で動くのはとても辛いけど、ベッドの部屋にはなりたくないと思っていました。
ベッド≒進行。私は長く病院にいるので、「ベッドの部屋になった」その先のことが理解できていました。
寝たきりになり、死を待つのです。
体を動かすのは大変だけれども、まだ動けるという望みを持っていたかったのです。
でも、確実に私の病状も進行していました。
動きたいという望みと、現実に動かない体が悲しい。
その頃に、「柴山真由美」ちゃんという女の子が入院してくることになりました。
真由美ちゃんの入院を機に、私はベッドの部屋に移ることになりました。
とうとうベッドの部屋になってしまった…。
体はとても楽になった代わりに、自由に動くことを失いました。
柴山真由美ちゃんとの出会いは、複雑でした。
1986年4月から、2人部屋で過ごすようになりました。時々、部屋替えがあり別室になることもありましたが、女子の患者は少数なのでまたすぐに同室になりました。年齢は真由美ちゃんが6歳下でしたが、歳とか関係なく何でも話せる仲となっていきました。寝食を共にし、トイレも共にし、あうんの呼吸で育っていきました。実のきょうだいでもトイレは一緒にしません。密度の濃い間柄です。
職員の事。学校の事。ここでは書けない事。色々と話をしました。大山良子
「迎えに来るよ,半年経ったら・・・」
大山ちゃんはその退院の日、真由美さんに「迎えに来るから、半年たったら(真由美さんも)退院だよ」と宣言していました。
それに対して、彼女はただニコニコしているだけで何も答えませんでした。「私は大山ちゃんみたいじゃないから無理」と私に言っていたこともあり、真由美さんは、自分は病院から出ることはできないと思い込んでいるようでした。
ところが、大山ちゃんが病院を退院してから4ヶ月が過ぎた頃、真由美さんから私の会社あて(個人あてでなく!)にメールがきました。「病院を出ようと思うけど、相談に乗ってもらえませんか?」という丁寧な文章でした。尋ねてみると、ある夜、眠りにつこうとしたときに、ふと「病院出ちゃおうかな」と思ったそうです。そこから、なんだか楽しくなってきたと言うのです。
彼女は、その更に4か月後にアパートを借りて、退院を実現することになります。
当初、真由美さんは夜間のみ鼻マスク人工呼吸器をつけているので、その装着は「医療者もしくは家族でなければできない」ということで、彼女のように、遠方に親が暮らしている場合は退院できないと病院から断られていました。
また、退院のためのケア会議では「命の保証は誰がするのか。医行為を介護職がすることは違法であり、それを確実にクリアしないと病院としては退院を許可できない」との発言が出されました。それを聞いて、当初引き受け予定の訪問看護ステーションが撤退したとき、真由美さんは無表情になり、何も語らなくなってしまいました。
医行為の制限と、憲法で保障された真由美さんの「自由権」をどう考えるか。
大学法学部を卒業して法律事務所で働いていた経験のある私には、それは違法性阻却(違法と推定されることでも、特別の事情があるケースには犯罪とみなさない)が適用されると思われ、また2003年に同様の解釈から、ALS患者の在宅療養支援のため厚生労働省通知(平成15年7月17日医政発第0717001号)が出されています。しかし、このとき、会議の参加者たちや周囲にそれがなかなか伝わらないことに困り果てました。
結局、その後で解決策として、真由美さんのお母様が来院され、鼻マスク人工呼吸器の使い方を学ぶことになりました。そのうえで、「せっかくアパートを借りたから、年末年始だけの限られた時間だけでも退院します」いう主張を通されることになりました。
このときも病院側からは「退院したら命の保証はない」と言われたそうですが、それでも、真由美さんのお父さんとお母さんが「本人がこれほど希望しているのだから、叶えてやりたい」と熱い思いを抱かれていたのでした。
こうして、年の瀬が迫り、退院についての明確な許可が出ないまま、「一時退院」という形で、真由美さんはアパートに引っ越しする運びとなりました。訪問看護ステーションと往診医からも、「一時的な期間でお引き受けできます」という形で返事をもらい、また行政サービスについても、「一時的な暫定措置」で介護給付の支給の決定をしてもらいました。
窓から見たふたりの再会
真由美さんの一時退院の日、病院でお世話になった方々に挨拶を済ませた後、大荷物と一緒に車に乗り、すぐに用意していたアパートに向かいました。
はじめてそのおうちに入った頃は、まだ最低限の家財しかなく、中はがらんとしていました。全部の部屋を見たいというので、車いすでぐるりとまわりましたが、カーペットが車いすのタイヤに絡んでしまい、しわになってしまいました。
それを見た真由美さんは、「絨毯なんだね~」と、笑ってつぶやきました。寝室は和室でしたので、襖を引いて、その部屋に入ると、「襖(ふすま)の音か、懐かしいな。小さいころ家で聞いたことあったよ」と言いました。病院には襖も絨毯もない。それをとても新鮮に感じたのでしょう。小さなことにも感慨深げになっている彼女に、私には驚きました。
それから、私たちは寝室にある腰の高さほどの窓から、一緒に外を眺めました。
ちょうどそこには、大山ちゃんが通りを横切りながら、差し入れ袋を車いすに括り付けて介護者と共にこっちに向かっている様子が見えました。彼女たちは手こそ振れないですが、心の中でお互いいっぱい手を振っていたように感じました。
その後、不思議そうな顔で彼女は「ここは私のおうちなんだね。大山ちゃんが来るね」と、窓から外を眺めて、つぶやいていました。大山ちゃんがアパートに向かってくる坂を上り、どんどん近づいてきて「真由美、来たなー!」と笑っていました。
その日がはじめて、二人が一緒に在宅生活になった、記念すべき第一日目となったのでした。
退院当日、真由美さんはカレーを食べたいと言ったので、介護者と一緒に夕食のために作りながら、これからの生活を語っていました。そこに真由美さんのお母さんも来て、カレー作りに参加しました。見事に母の味になったカレーはとても懐かしかったことでしょう。
真由美さんの夜の不安は、退院してからもしばらく続いていました。夜になると半分寝ながら「助けてー、看護師さーん」と叫んでしまうのですが、隣にすぐいる介助者が「大丈夫だよ」と手をさすると、すぐに寝つきました。
そういう安心して眠る経験を一晩、また一晩と重ねていくことで、いつしか静かに眠れるようになったのです。
さて、「一時退院」という名目の真由美さんでしたので、障害福祉サービスの支給決定などが追い付かないことと、病院からも一度戻るように言われていたので、1か月が過ぎた頃にいったん病院へ帰ろうかという話になりました。そのとき、彼女は「やだな。でもどうせ私はきっと病院なんだよ」と悲しい顔をしていました。そこで、市役所に電話をして、どうにかならないのか、手続き上の問題なら何とかしてほしいとお願いをしました。
その甲斐があったのか、ある雪の日に市の担当者がアパートを訪ねて来て話を聞いて下さり、在宅継続できるよう制度を整えてくれました。病院側にも、このまま在宅生活でお願いしたいと、この1か月お世話になった訪問看護ステーションのスタッフや往診医の先生が説得してくれたのです。
その後、真由美さんが地域での暮らしになじんでいく中で、いろんな事件が起きました。けれど、真由美さんのお母さんの「真由美はね、病院でいっぱい我慢してきた人生だったけど、今あんなに楽しそうじゃない。これを取り上げるわけにはいかない」との決意が大きな支えになりました。
20年間、離れる事のない2人でしたが、私が、病院を出る決意をしました。
呼吸器の導入が上手く行われていない真由美ちゃんは、夜になるとパニックになり、
『りょうちゃん!』『りょうちゃん!』と何度も私を呼びました。
パニックになるのは、ナースコールを押しても、スタッフが来ないからです。
私は、ただただ『大丈夫だよ』としか言えませんでした。
誰かが側に付いていられればパニックにはならないのにと思うばかりです。
呼吸器をつける辛さだけではなく、真由美ちゃんは、病気の進行が少し進み介護度が増していき、‟面倒な患者さん”と思われている自分と戦っている感じがしました。
戦っているその痛みは、十分に私に伝わりました。
退院の日が決まっていた私は迷いました。
このまま、柴山真由美ちゃんを置いていっていいのか?
せめて、呼吸器が不安なく付けられるまで側にいた方がいいのではないか?
人生で、はじめて悩みました。
でも私は、決めていた日に退院しました。
自分が、道を作らなければいけない。
誰かが、常に側にいてくれる在宅ケアでの生活は、柴山真由美ちゃんにピッタリ合うはず。
病院じゃない生活を実践し、重度な障がい者でも地域で生きていけると証明しなければと強く思いました。
私の自立は、柴山真由美ちゃんのためだけでなく、これからの患者さんのためになると奮い立たせました。
退院の日、『半年後に、迎えに来るね!』と柴山真由美ちゃんと約束を交わしました。
今は、同室とはいかないけれど、スープの冷めないほど良い距離で暮らしています。
大山良子
彼女は今日もアパート暮らしを続けています。
大山ちゃんに続いて真由美さんが退院したことは、重度な人が地域生活できる勇気を入院患者に与えたようです。
その後、現在までに、30年の間ほぼ誰も退院することのなかったその病院から、続けて5人の長期療養者がそれぞれの地域へかえっていきました。
*「おうちにかえろう 30年暮らした病院から地域に帰ったふたりの歩き方」は,
ほぼ隔週で連載予定です*
・・
・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・

小学4年の時に、高校生の良子さんと出逢いました。
優しいお姉さん的存在で、イタズラしても怒らず遊んでくれました。
病院支給の朝ごはんがミルクだけの私を気にして、病室でこっそり外を見ながら(スタッフに見えないように内緒で)チョコを口に運んでくれて一緒に食べたり、散歩したり。愚痴大会をひらいたり。私の頭にボンドを飛ばしたことがあるし、病棟建て直しで部屋が別れたとき、遊びに行った私が男の子に間違われているの見て笑うし…。楽しい思い出がたくさんあります。人には言えない事もたくさんあります(笑)。
ある日、2人でなんでか分からないけど泣いた事がありました。
悲しかったわけでも笑い泣きでもなく、「泣けてくるね」と言いながら一緒に泣いてました。
【大山ちゃんから病院を出ると聞いたときの心境】
「退院する」と聞いて……ずっとそばにいるのが当たり前に思っていたから、そうなると、友達だけど頻繁に逢えたりしないし、逢いに来てもきっと何処かぎこちない風が私たちの間に吹きそうな気がしました。
良子さんが退院生活の参考にするため、(院外から)友達と実際に自立生活をしている方を病院に招いて話を聞いてる様子をみながら、‟自分より仲良しだし、(その人たちとのほうが)年も近いから…”と、ヤキモチからか冷たい態度をとっていた気がします。1人ぼっちになってしまうと思ってスネた気持ちでした。
そうして良子さんの本格的に退院に向けて準備が始まる頃、自分は夜間に鼻マスクを着けることになり、そのショックと彼女の退院話で精神的に弱くなっていたから、応援するような気持ちにもなれませんでした。
でもその後、院内スタッフの心理カウンセラーの先生と話すようになり、良子さんが自立することに少しずつ、嬉しく思ったり、その家に早く遊びに行きたいと考えたり……期待することの中に、良子さんの恋を考えたりしちゃったかな(笑)。出掛ける場所が増えることを楽しく思いました。
でもやっぱり、色々考えて寂しさを紛らわせていました。心配をかけてはいけないから大人になった私を見てもらいたい(笑)、嬉しいことだから応援しなきゃね!
退院の日は、泣かずに送り出してあげたいと決めました。
【大山良子さん退院の日】
退院の日、良子さんは「迎えに来るからね」と泣きながら言ってくれました。
でもどうして、(「また来るね」じゃなくて)「『迎えに』来るね」なんだろう? と不思議に感じていました。
良子さんの退院の日は、嬉しいけど、やっぱり寂しいから落ち着つかなかったです。「明日は何する?」とかの話しはできないし、何を話そうか迷いました。また逢えるけど、やっぱりそばにいるのとは違うから、何をするにもつまらない日が続くのかと考えてしまいます。
支えてもらっていたんだなぁと改めて実感する日にもなりました。
荷物がまとまり正面玄関に向かうと、お見送りの人がたくさん来ていました。
良子さんが電動車いすごと、みんなに胴上げのように祝ってもらっているのには驚きました。それを見ながら‟照れ臭いより怖かっただろうな”と笑っていました。
良子さんは泣き虫だからやっぱり泣いていて、私も泣かないと決めたのに泣きそうになりました。
部屋に帰り、ぽっかりと空いたスペースが寂しかったです。夜も話し相手もいないし消灯までの時間が長く感じました。
【真由美ちゃん自身の退院のこと】
ある夜、消灯時間も過ぎて、寝られずに考え事をしていて、ふと「…出ようかな」と思いました。夜間に鼻マスクを着けるようになり、微調整も多くスタッフの対応が昼間と違うところに心は折れました。着けてないときとの差があり過ぎでした。ナースコールも(昼と比べて)対応が遅いのは仕方のないと解ってはいるものの、不安で気持ちが落ち着かない私の口癖は「呼んだら来るよね?」と言ってました。在宅でヘルパーさんがそばにいてもらえるのなら、夜も安心して寝れるかなと思うようになりました。
病院だけの生活で終わりたくなかったのも一つの理由でもありました。自分の生活を変えてみたくなり、りべるたすに相談に乗ってもらいました。
その代表の伊藤さんのことは、はじめ特に印象に無くて、病院スタッフ時代は手際が遅いひとだと思ってました(笑)。
退院する朝は、‟本当に自分は退院するのかな?”と思いながら、いつも通りに過ごしていました。普通にいるつもりでも、どこかそわそわというか、ドキドキしてました。
母が来たり、お手伝いに来てくれた方と片付けを始めましたが、ただ何週間かの「外泊」の準備をしてるような感覚でした。その割にはダンボールが幾つかできて、部屋にいっぱいあった荷物がなくなりました。明日から片付けの日々だと苦痛になることなく、むしろ楽しい気分でもありました。
それが落ち着いたころ(院内の)友達に挨拶をするのに、「行ってきます」でもないような、「お世話になりました」なのかわからず、「また来るね」と言ってた気がします。
お世話になったスタッフに挨拶をしながら、「喜んでもらえてるのかな?」と考えてしまいました。スタッフの方やみんなとは離れるのは寂しかったです。
でも、長年いた「場所」なんだけれど、寂しいと思わないのは何故なのかな?
病院にいたくている人はいないからですよね。
正面玄関までの廊下を「頑張らなきゃ」とつぶやきながら歩き、母に感謝をし、ともに病院を出発しました。
柴山真由美(友情出演)
■医学書院にこんな本があります■

●本書を推薦します!《これは、人がその人らしく生き抜くのを支える新たなケアのあり方を構築してきた熱い実践の手記だ》?柳田邦男氏(ノンフィクション作家)
三〇代に経験した姉のがん死。秋山さんのモチベーションは鮮烈だ。看護教師から在宅ホスピス看護師へ。さらにメディカルタウン構想や日本版マギーズセンター構想へ。発想の柔軟さとフットワークの強靭さで、活動の輪を広げていくエネルギーは凄い。医療人が看護の新境地と自らの人生を切り拓いた記録として感銘深く読んだ。