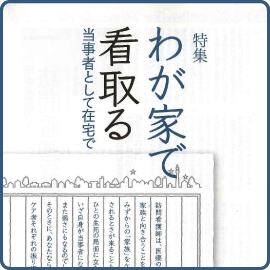かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

【第11回】早回しのように1日が過ぎればいいのに
2013.8.26 update.
いとう かよこ:千葉県千葉市在住。法律事務所勤務後、国立病院機構の介護職員として勤務。2008年りべるたす株式会社設立、代表取締役(在宅障害福祉サービス事業所管理者)。介護福祉士・社会福祉士・相談支援専門員。千葉大学大学院人文社会科学研究科博士前期課程修了,立命館大学大学院先端総合学術研究科博士後期課程在籍中。第47回NHK障害福祉賞第2部門(障害のある人とともに歩んでいる人)優秀賞受賞。 「りべるたす」ホームページはこちらから
おおやま りょうこ:千葉県千葉市在住。本連載のイラストレーター。 2009年特定非営利活動法人リターンホーム設立、代表理事(長期療養者へのエンパワメントを行うための研修事業等)。SMA(脊髄性筋萎縮症)療養のため、1978年大和田小学校から下志津病院隣接の四街道養護学校転入。1983年同小学部卒。86年同中学部卒。89年同高等部卒。 「リターンホーム」ホームページはこちらから
「何が食べたいかな?」「お寿司!」
病院を出た私たち(伊藤・大山)は、まず車で区役所に向かいます。障害福祉課と生活保護課に行って、在宅サービスと必要な支援を申請しました。
障害福祉課では決められた書類を淡々と書いていきます。生年月日と住所と名前を何度も書きました。また、生活保護課でもたくさんの申請書類を書くことになります。他人介護料(加算)について、引っ越し後の日用品をどう判定するかなど色々と話し合いました。
この他人介護料を使って訪問入浴もう1回分を認めてもらうことをお願いしたりしたのですが、このときは認めてもらえず、その後の審査請求を経て実現できました。
申請をしてから、40日以上たってはじめて決定が下りるのですが、この日の私たちは、一体この先どうなるのかの具体的なお話をまったく聞けないままで、不安たっぷりでした。
そうして夕方にようやっと、大山ちゃんの新しい‟おうち”に着きました。
既に17時頃です。大山ちゃんが降車してすぐ、私は福祉車両を返却にまた出かけなければなりませんでした。でも彼女は、病棟で16時40分(毎日ぴったり決まった時間!)に夕食を食べていたので、すでに空腹だったようです。
「何が食べたいかな?」と聞くと、「お寿司」とのこと。病院では生ものが出ないので、なるほどと思い、社会福祉協議会からの帰りにチェーン店に寄って買ってきました。
その晩、はじめて入る夜勤のヘルパーさんが到着。いざケアの手順について説明をしようとすると、ヘルパーさんは目をぱちくりさせて、「『30代後半』と聞いていたのに、中学生みたいな子どもじゃないの!? 大丈夫かしら…」なんて言うのです。
大山ちゃんは、たしかに若く見えたのでした。
退院した日は、とても忙しい日でした。
社会援護課や福祉課に行って、色々と手続きを済ませました。福祉用具の方がベッドを搬入して組み立てました。組み立てが終わるころ、外はもう夕日になっていました。
‟あー、病院のみんなは、夕飯を食べてるなー“と、病院の夕食時のことを思い浮かべていました。そして、
‟あら? 私、いつ夕ご飯を食べたら良いの?”と思いました。
まだ冷蔵庫には食べ物は何もないし、どのタイミングで言い出したら良いのか…と思っていた頃、伊藤さんに 「何食べたい?」と聞かれました。
私は迷わず「お寿司」と答えました。
‟お祝いっぽいのは、お寿司かな?”と思っていたのです。
味は……、もちろん緊張していて、美味しいとか味わっている余裕がありませんでした。 大山良子
そうして始まった、‟おうち“でのはじめての夜は不安だらけでした。

大山ちゃんは、眠っていても寝返りを打つわけでもないし、寝息もないのです。‟もしかして、息が止まっているのでは?“と、寝ているその口と鼻のあたりにティッシュをそっと当てて息吹を確認してみたり。
朝はちゃんと起きるかしら。朝ごはんはちゃんと食べるかしら。とにかく大丈夫かしらだらけ、心配だらけの1日目が終わっていったのでした。
早回しのように1日が過ぎればいいのに
大山ちゃんが病院を出た最初の時期、私が最も注意を払ったのは、水分でした。
彼女には「とにかく、水分制限をしたらダメだ」と伝え、「少し無理をしてでも、大目に水分を取ってほしい」とお願いしました。また、「トイレも一切我慢しないでほしい、いくらでもできるから」といい、トイレを我慢する癖を止める努力をしてもらいました。しばらくは水分の変化のせいか浮腫んでいました。でも、数か月すると浮腫も取れました。
今の彼女は在宅で、入院時の2~3倍くらい、水を飲んで暮らしています。
はじめて大山ちゃんが発熱した日には、そのときは「点滴しなくちゃ」と彼女が訴えてきました。病院ではいつも発熱すると、水分は点滴で補給していたようなのです。
「(在宅では自由に)水を飲めるから大丈夫だよ」と言って、初めての発熱をこなしました。
退院してからの数年間、私は、毎日昼間のだいたいの時間を大山ちゃんと過ごしていました。交代勤務で入ってもらうヘルパーさんたちに、大山ちゃんの介護の方法を伝えるためです。
私の子どもは大山ちゃんを見ると、「お母さんが『行ってきます』と言ったら行くところ」といっていたくらいでした。
夜勤さんは、その日、はじめて会った人が泊まりました。
とっても小柄で、とっても力がないような人に見えました。
「こんな人で、私の介助ができるのか?」 不安になるくらい弱そうでした。ただ救いなのは、病院で(患者仲間の)付添いをしていたことです。私は、この人がどんな人なのか? 注意深く観察しました。
どんなふうに接したらよいのか、わからなかったのでドキドキしていました。とにかく夜が早く明けて、朝になって伊藤さんが来るのをひたすら待ちました。
毎日が、新しい人だったので観察とドキドキの繰り返しでした。 こんなドキドキがなくなって、普通に暮らせるようになりたい!
早回しのように1日が過ぎればいいのにと思っていました。
大山ちゃんは、ヘルパーさんにご飯を作ってと頼むタイミングがわからないことや、洗濯は「普通」いつするものなのか、また買い物と献立の因果関係など、色々なことを悩んでいたようです。お金も毎日家計簿をつけて、彼女が自分で管理していました。毎日夜になると、明日の服をあれこれこっちの引き出しあっちの引き出しと、開いては閉じて考えるようになりました。

入院中は週に2回しか着替えがなく、食事も出されたものを食べていたのに、食べたい献立も毎日自分で考えることに。決まった時間に病院では介護者が来てくれていたのに、いまや、自分からいちいち具体的にすべての介護をお願いしていかなくてはならないのです。
それまでの受け身な姿勢から180度生活の指針を変えていくという困難さがありました。
大山ちゃんは社会経験がなく、しかし30代後半の年齢であるというギャップがある状況で、はたから見ると、片意地張って生活をつくっていっているようにも見えました。
毎日自分の服を考えること、こんな当たり前なことを30代後半になってやっと習慣づけるのです。パジャマに着替えるタイミング―そのパジャマを洗濯するのは、冬は2日に1回で、夏は毎日とか――それぞれのルールを、今から一つずつ決めなくてはならないことに、ヘトヘトになっていました。
それまで、「車いすの上では寝たことがない」と言っていた彼女も、日中に疲れて、ベッドに移らずにそのまま昼寝をしていることもありました。「早く慣れたい。数か月早く過ぎてほしい」とよく言っていたものです。
ある人が、「病院を出てからたくさん経験できていいじゃない。これからいっぱい楽しみがあるってうらやましい」といったことがありました。それに対して大山ちゃんは無言で、目にいっぱい涙をためていました。
帰る‟おうち”もなかった大山ちゃん。家を探して、そこで、いちから生活をつくって整えていくことは並大抵のことではなくて、経験のない彼女には、それが“楽しみ”といえるような余裕は到底なさそうでした。
むしろ、その取り返しの大変さにぶち当たってはじめて、自分が置かれてきた環境を理解しているようでした。
「私は、大人としてちゃんと対応できているのだろうか、会話は子どもっぽくないだろうか。一般の人と同じ生活をしているのだろうか。常識はずれなところはないだろうか……」
そういったことをいつも気にして暮らす、彼女の退院後の新生活が始まっていったのでした。
「私には何もない」
「家に帰りたい」と、入院仲間はみんな思っていたはずです。
私も思っていました。幼少の頃は、特に思っていました。
病院併設の学校が休暇期間になる夏や冬には、2週間ほど実家にかえる機会がありました。お母さんの手料理が並ぶ食卓。父や兄との触れ合いは、子どもの私には天国でした。もう病院に戻りたくなくなります。
病院に戻る日は、わざと遅く起きて、少しでも帰る時間をずらそうと必死でした。
子どもの頃は自分のことが少しできていたし、父も母も若く、介護は苦労していませんでした。でも、年齢とともに私の病状も重度になり、両親ともに白髪が生え始める頃には、介護も大変になってきました。
そのうちに、実家にかえること自体も困難になってしまいました。長く病院にいるうちに、実家が「自分の家ではなくなって」しまうのです。自分がいない生活に、家族も慣れてきてしまっているからです。
そこに、かえりたいとは言えるものではありません。おうちにかえりたいけど、かえる方法がなかったのです。
そして病院を出て、180度、生活が変わりました。病院では流れ作業で進んでいた介護が、自ら進んでやってもらいたいことをお願いする介護になりました。
私は、困りました。
今まで、スタッフの顔色をうかがって嫌われないように介護をお願いしてきたので、いつどのタイミングで、自分のしてもらいたいことをお願いしたらよいのか? 「こんなこと、お願いしたら嫌われないかしら?」とオドオドしていました。
30年染みついた病院臭は、直ぐには消せません。少しぐらい体の体勢がつらくても、つい我慢をしてしまうこともありました。
今まで、周りには車いすの人ばかりいる環境だったのが、自分だけが車いすユーザーの状態になりました。
退院した時の年齢は、37歳。この年齢なら、社会的にはある程度の地位(働いていれば、肩書)があるだろうし、お子さんがいる人もいるでしょう。 私の介護にあたってくれるヘルパーさんも同世代が多く、その人たちはちゃんと仕事をし、子育てもしています。私には何もない。自分がとても落ちこぼれに感じました。
今まで感じたことのない気持ちです。
世の中の37歳とかけ離れすぎている自分が悲しく思えました。
なんとかしなくちゃ!

‟これから自立生活をしていくんだから、ヘルパーさんや地域の人たちに馬鹿にされないようにしなくちゃ!“
‟「可哀そうな車いすの人」と思われないように、身なりをきちんとして、『生活を楽しんでます』ってしないと!”
そんな「周囲に子どもって思われないように!」の気持ちばかりが膨らんで、心がパンパンになってしまいました。病院を出て1年くらい、私は愚痴もこぼさず涙も流すこともなく、この自立生活が失敗しないように生活していました。
今(2013年)の大山ちゃんは、講演の席で、「だから、長期療養はできるだけしてはならないんです。そして、病院にいたい人なんていないのです。それを強いられて、そこからまた新しく生活をつくり直すことは、本当に本当に大変なことなんです……」と、よく話をしています。
近所の人たちとのお付き合いでは、最初は窓から様子を覗かれたり、いろんなことがありました。あまり歓迎されてないと感じることもたくさんありましたが、徐々に、じわじわとなじみました。
そうして、1日がたち、2日がたち、ゆっくりと確実に毎日が進んでいき、大山ちゃんが地域で生活することになじんでいくのでした。
*「おうちにかえろう 30年暮らした病院から地域に帰ったふたりの歩き方」は,
ほぼ隔週で連載予定です*
■医学書院にはこんな雑誌があります■

ますます強まる「在宅」の時代に、現場の視点を重視した専門職・当事者による情報を精選して提供。在宅ケアに携わるすべての方に。(ISSN 1341-7045) 1部定価 1,365円 (本体1,300円+税5%) 電子ジャーナル http://ej.islib.jp/ejournal/top-13417045.html
特集PIC UP!!
2013年02月号 (通常号) ( Vol.18 No.2)
特集 住まいで医療も最期まで いろんなかたちの「24時間」
2013年8月号 (通常号) ( Vol.18 No.8 )
特集 来たれ! 新卒訪問看護師!−千葉県訪問看護実践センター事業の試み