かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
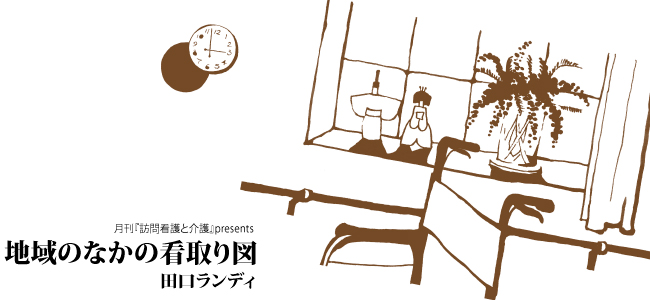
5-2 死ぬ場所? 生きる場所?--「看取り」のかたち〈その2〉
2013.7.10 update.
『訪問看護と介護』2013年2月号から、作家の田口ランディさんの連載「地域のなかの看取り図」が始まりました。父母・義父母の死に、それぞれ「病院」「ホスピス」「在宅」で立ち合い看取ってきた田口さんは今、「老い」について、「死」について、そして「看取り」について何を感じているのか? 本誌掲載に1か月遅れて、かんかん!にも特別分載します。毎月第1-3水曜日にUP予定。いちはやく全部読みたい方はゼヒに本誌で!
→田口ランディさんについてはコチラ
→イラストレーターは安藤みちこさん、ブログも
→『訪問看護と看護』関連記事
・【対談】「病院の世紀」から「地域包括ケア」の時代へ(猪飼周平さん×太田秀樹さん)を無料で特別公開中!
人がどんどん死ぬ奇妙な場所
12月の初めだったので、ピースハウスには大きなクリスマスツリーが飾ってありました。院内には賛美歌のような音楽が流れていました。エントランスはリゾートホテルのようで、父は「ずいぶん高級そうなところだなあ、高いだろう?」と、しきりと入院費を気にしていました。たしかに高いです。一日の入院費が都内の高級ホテル並のお値段です。
友人で『がん患者学』という本の著者でもあった、故・柳原和子さんの言葉が忘れられません。
「ホスピスにはせいぜい3か月くらいしかいないんだから。お金を全部つぎこんで、気持ちのいい場所で死にたい」
彼女は、聖路加国際病院の緩和ケア病棟で亡くなりました。柳原さんを見舞うために、初めて聖路加国際病院に入ったとき、ホテルのような内装、たくさんの絵画、熱帯魚の泳ぐ水槽、オレンジ色のやわらかな間接照明、何もかもがお洒落でびっくりでした。こんな病院があるのか……と。
そして、緩和ケア病棟にはパーティールームがあり、ピアノがあり、午後3時にはボランティアの人たちによるお茶の時間があり、家族が調理もできました。部屋にも調理器具が設置されていて、長期滞在型のリゾートホテルのようでした。大型のテレビがあり、柳原さんと一緒に映画を観ました。
実母が死んでいった脳神経外科病棟の暗いイメージと、あまりにかけ離れた豪華さにあっけにとられました。救急で運ばれた脳神経外科病棟は、家族が泊まる場所もなく、私は何日も待合室のベンチで寝ました。蛍光灯に照らされた廊下は青みを帯びて冷え冷えとしていました。担当医師もいつも疲れ切った顔をしていて、しゃべり方もぶっきらぼう、母に話しかけることもしませんでした。
あの陰うつな病棟から一歩も出ることなく亡くなっていった母が不敏でした。だから、父の時はせめて……と思ったのです。ピースハウスは、柳原さんが入院していた聖路加国際病院と同系列の独立型ホスピスでした。聖路加よりもさらにグレードアップした「ひと足お先の天国」のような場所でした。
大きな窓から燦々と太陽の光が差し込みます。庭には冬でもシクラメンなどのきれいな花が咲いています。たくさんのボランティアの方たちが、話し相手になってくれます。看護師さんも、医師も、家族の話をとことん聞いてくれます。ソファなどの家具や調度品も立派で、オーディオルームや読書コーナーもありました。ここで死ねれば本望だろう……と、看取る側の人間である私は思ったのです。でも、死んでいく父は、この場所があまり好きではないようでした。
父は、自分が末期がんであることを拒否し、がん告知されたことすら忘れてしまっていました。そんなに生きる気力満々の人が、ホスピスに入ったらどうなると思いますか?
転院してすぐに父から電話がかかってきました。
「おい、この病院はなんかおかしいぞ、毎日、人が死ぬんだ」
父は恐ろしそうに声をひそめてそう言ったのです。
毎日、人が死ぬ。
それはそうでしょう……だって、ホスピスなのだから。
私は絶句しました。ホスピスでは毎日、人が死んでいく。この当たり前の現実が私の頭からは抜けていたように思います。
「昨日も、今日も、同じ部屋の人が死んだんだぞ、死にすぎるだろう……。なんか変だ。この病院は、よくないことをやってるんじゃないか?」
私は入院費用をケチって、父を相部屋に入れたことを後悔しました。病院に相談して、すぐに空いた個室に移してもらいました。でも、父の病院に対する疑惑をぬぐうことはできませんでした。
「おい、なんでこの病院には治療する部屋がないんだ? 病院らしい器械が何もないぞ」
「え? そうかな。きっと目につかない場所にあるんじゃないの?」
「そうかなあ……。なんか変だ」
私はほとほと困ってしまって、また、院長先生に相談しました。
「父が、この病院では人が死に過ぎると疑っています……。どうしたらいいでしょう、やっぱりここがホスピスであることを、告げたほうがいいんでしょうか」
ホスピスにいるのに、ホスピスだと思っていない父にとって、この病院は「人がどんどん死ぬ奇妙な場所」でした。みんな優しいし、対応はていねいだけれど、まわりの人間が自分を「これから死ぬ人」として接していることが、父にはわかったのです。
父は船乗りとして大海原を生き抜いてきた男ですから、動物的な勘だけは並外れてあるのです。危機管理能力も高く、サバイバルには強い人でした。でも、そういう父のもっている能力は、一般社会ではほとんど発揮されることはありませんでした。だから、私も父を弱者のように扱ってしまったのです。荒れる北洋の海で命がけでマグロを捕っていた父は、生きることに対する信じられないような力をもっていました。私はそんな父を、ホスピスに入れてしまったのです。
そうこうしているうちに、父はだんだんうつになってきました。顔から笑みが消えて、じーっとベッドに座ったまま何時間もうつむいていました。夜になっても眠らず、ロダンの彫刻「考える人」のような姿勢でうつむいているのです。そういう父の傍らで私と娘は黙って一緒に座っていました。そばにいることしかできませんでした。父は必死で何かと戦っているみたいでした。何と戦っているのか……、私にはわかりませんでした。
転院したことで、精神状態が不安定になってしまったのだろうか。私は悩みましたが、だからと言って別のどこかへ行けるわけでもありません。父のがんは肝臓に転移しており、臓器の機能はどんどん弱っているのです。
個室に移ってから、私や娘が泊まり込みで一緒に長く過ごすようになっても、父は低く安定しつつ、日々、揺れていました。機嫌のいい日もあれば、黙りこくってしまう日もある。徘徊する日もあれば、落ち着いている日もある。寄せたり引いたりの波が繰り返しながらも、ゆっくりとこの世という岸から離れているように感じました。それでも、父の生きようとする意志は強く、私は父の「生きる力」を目の当たりにしてたじろぎました。
父は長いことアルコール依存症で酒ばかり飲み、自暴自棄な生活を送っていました。傍目には、まるで死に急いでいるかのように見えたのです。でも、アルコールが抜けてシラフになった父は、生命体としての強さを取り戻したかに見え、その生に対する強靱な意志こそ、戦争や海での長い生活を乗り越えてきた父の本質であることに気づきました。ようやく本当の自分に戻れたのに、父の死期は近づいていました。
ピースハウスはすばらしいホスピスでした。看護師さん、院長先生、チャプレン、ボランティアの方々に、父は本当にお世話になりました。私たち家族も励まされ、このホスピスへの不満はありません。終末期の方たちに寄り添い最期の時間を穏やかに過ごせるように、みんなが心を尽くしていました。面接の時は、家族が納得するまで話を聞いてくれました。こんな病院は他にありませんでした。家族にとっては本当にありがたいホスピスでした。
でも、父がここに来るのは早すぎました。そう思うのです。
父は、もっと普通の暮らしがしたかったのだと思います。でも、それができませんでした。アルコール依存症で肺がんの末期、肝臓にも転移して多臓器不全になっていた父。それでも父は生きたかったのです。生きようとしたのです。だから、「がん告知」すら忘れてしまいました。父が欲したのは「生きるための場所」だったと思います。
もし、ホスピスでもなく、緩和ケア病棟でもなく、もっと自由な場所で、ふつうに暮らすことができたら……、父はもう少し長く生きたのではないか……と、そんなことを感じました。ホスピスに入るのは死ぬ前の1週間でいいんじゃないか……と、私は思いました。

いよいよ高まる在宅医療・地域ケアのニーズに応える、訪問看護・介護の質・量ともの向上を目指す月刊誌です。「特集」は現場のニーズが高いテーマを、日々の実践に役立つモノから経営的な視点まで。「巻頭インタビュー」「特別記事」では、広い視野・新たな視点を提供。「研究・調査/実践・事例報告」の他、現場発の声を多く掲載。職種の壁を越えた執筆陣で、“他職種連携”を育みます。楽しく役立つ「連載」も充実。
6月号の特集は「高齢者虐待を防止する−そのとき医療・介護にできること」。「在宅」は本人にとって最も暮らしやすい場所であると同時に、「虐待」の温床にもなりかねない“密室性”をもっています。そこに踏み込んでいけるのが「訪問」の仕事です。時に、適切な医療・介護を受けられないことが虐待の要因にもなっています。すなわち、医療・介護は、虐待が起こってしまう構造を“骨抜き”にもできる。では、どうやって?






