かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
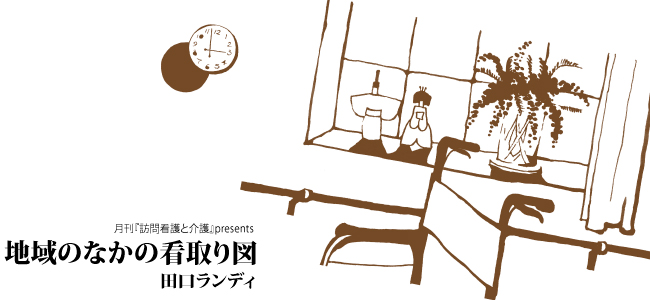
5-1 死ぬ場所? 生きる場所?--「看取り」のかたち〈その2〉
2013.7.03 update.
『訪問看護と介護』2013年2月号から、作家の田口ランディさんの連載「地域のなかの看取り図」が始まりました。父母・義父母の死に、それぞれ「病院」「ホスピス」「在宅」で立ち合い看取ってきた田口さんは今、「老い」について、「死」について、そして「看取り」について何を感じているのか? 本誌掲載に1か月遅れて、かんかん!にも特別分載します。毎月第1-3水曜日にUP予定。いちはやく全部読みたい方はゼヒに本誌で!
→田口ランディさんについてはコチラ
→イラストレーターは安藤みちこさん、ブログも
→『訪問看護と看護』関連記事
・【対談】「病院の世紀」から「地域包括ケア」の時代へ(猪飼周平さん×太田秀樹さん)を無料で特別公開中!
父が精神科病院からホスピスに転院する朝のことは、今でもとてもよく覚えています。夏の間、緑色に繁っていた木々がすっかり葉を落として、丸裸の冬木立になっていました。朝霧がたちこめる山道を、淋しい気持ちで父の病院に向かいました。
在宅ではなくホスピスへ
父は、自分が転院するところがホスピスであることを知りませんでした。自分はどうやら具合が悪いらしい、これから転院するのは以前に往診してくれた先生の病院で、そこに移ると痛みがとれる……、それくらいの認識でした。精神科病院に入り、アルコール依存症の治療をした父は一週間ほどで記憶を回復し、認知障害もすっかり治ったのです。病院の夏祭りなどに私たち家族と参加して、孫娘にお菓子を買ってあげたりしていました。その頃にはアルコールが抜けて、父の生涯のなかで一番、優しい顔をしていました。笑顔が光り輝くようで、私は初めて父の本質に触れた気がしました。
長い年月、お酒は父の心をすっかり蝕んでいたことを知りました。アルコール依存症という病気は……本当に恐ろしい病気です。精神科病院の先生は、もし父がまた一滴でもお酒を飲んだら、きっと歯止めがきかなくなるだろう……と言っていました。
私は父の心が穏やかになった頃合いを見て、父にがんであることを告げました。自分はあとどれくらい生きられるんだと問う父に、「余命半年」という医師の言葉は伝えることができませんでした。
「一緒にがんばって治療していこう」と言うと、父はぽろぽろと涙をこぼして言いました。
「これまで、ずいぶんひどい生活をしてきたもんなあ……」
父は、自分がかなり進行したがんであるという現実にショックを受けていましたが、なんとか受け止めてくれました(くれたように見えました)。ところが2日後、病院に行ってみると、そのことをすっかり忘れていたのです。
最初はふざけているのかと思いました。
「お父さん……、私が話したこと覚えてないの?」
父は私の顔を見ました。黒目には光りがなく淀んでいました。
「なんだっけかなあ……? 忘れちまったな……」
笑うでもなく、困っているふうでもなく、無表情に父は言いました。
「父は本当に忘れてしまったのでしょうか?」
主治医の精神科の先生に相談すると、先生も困った顔をしています。
「どうしても受け入れられないことを忘れてしまう患者さんは、たまにいらっしゃいます」
「でも、でも、本当に忘れてるんですか?」
「人間は、知りたくないことは知らないことにできるんです。記憶を封印してしまうんです」
私には信じられないことでしたが、父はほんとうに忘れているみたいでした。
ピースハウス(ホスピス)に入院するには、本人が末期のがんであることを自覚し、入院を納得していることが前提です。忘れてしまったのでは、入れてもらえないかもしれません。どうしたらいいものか、ピースハウスの院長先生に相談しました。告知したのだけれど、父は全部忘れてしまったようだ、もう一度、同じことを伝えるのはあまりに酷ではないだろうか……と。院長先生は「一度、告知したのだから、二度はいいでしょう……」と、言ってくれました。
転院できると知ってほっとはしたものの、まだまだ生きる気力が漲っている父を、ホスピスに入院させるのはなんだか残酷な気がしました。でも、父の肺がんは肝臓に転移しており、肝臓が固くなって腫れて激しく痛むようになっていたのです。精神科病院では充分な緩和ケアができません。麻酔医がいないので、量を調節しながらのモルヒネの投与もできません。かといって、一般の病院では家族が泊まり込むような看取りはできません。
在宅看護……は、最初から私の選択肢にはありませんでした。92歳と93歳の夫の両親と同居しながら、実父を家で看取るということが私にはできませんでした。できたかもしれないけれど、しようと思いませんでした。父が病院から出たがっていることは、わかっていました。でも、精神科病院に入院している間、ショートステイで私の家に帰宅したのですが、父が家にいると私はとても義父母に気を遣い、くたくたになってしまいました。義父母は良い人たちでしたが、長年、船乗りをしていた父とは、生活文化、価値観、人生観が違いすぎました。そして、彼らは信仰をもっていました。私は、義父母が父に信仰を強いるのでは……と、内心びくびくしていました。そんなことをされたら父は怒って何を言い出すかわかりません。
在宅看取りができなければ、一般の病院の緩和ケア病棟かホスピスか、という2つの道しかありませんでした。他の道を探しましたが、私が住んでいる地域では見つかりませんでした。だから、ホスピスを選択したのです。
一般の病院で看取りたくなかった。実母を脳神経外科病棟で看取った経験が私にホスピスを選ばせました。実母は72歳のときに脳出血で倒れ、4か月間の植物状態を経て他界しました。点滴、気管切開、人工呼吸器……。母は人工物に囲まれてどんどん浮腫んでいき、本当につらそうでした。ああいう看取りは……もうしたくない……という思いがありました。

いよいよ高まる在宅医療・地域ケアのニーズに応える、訪問看護・介護の質・量ともの向上を目指す月刊誌です。「特集」は現場のニーズが高いテーマを、日々の実践に役立つモノから経営的な視点まで。「巻頭インタビュー」「特別記事」では、広い視野・新たな視点を提供。「研究・調査/実践・事例報告」の他、現場発の声を多く掲載。職種の壁を越えた執筆陣で、“他職種連携”を育みます。楽しく役立つ「連載」も充実。
6月号の特集は「高齢者虐待を防止する−そのとき医療・介護にできること」。「在宅」は本人にとって最も暮らしやすい場所であると同時に、「虐待」の温床にもなりかねない“密室性”をもっています。そこに踏み込んでいけるのが「訪問」の仕事です。時に、適切な医療・介護を受けられないことが虐待の要因にもなっています。すなわち、医療・介護は、虐待が起こってしまう構造を“骨抜き”にもできる。では、どうやって?






