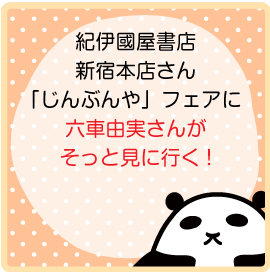かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
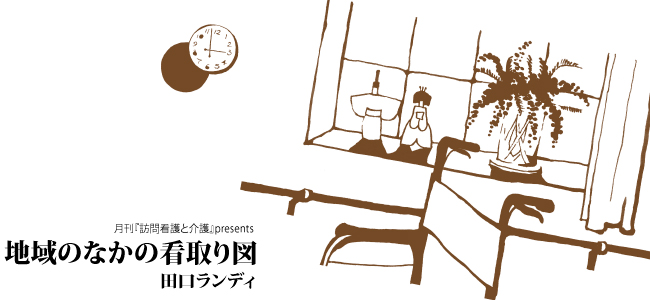
4-3 がんの治療を断念するまで―「看取り」のかたち〈その1〉
2013.6.19 update.
『訪問看護と介護』2013年2月号から、作家の田口ランディさんの連載「地域のなかの看取り図」が始まりました。父母・義父母の死に、それぞれ「病院」「ホスピス」「在宅」で立ち合い看取ってきた田口さんは今、「老い」について、「死」について、そして「看取り」について何を感じているのか? 本誌掲載に1か月遅れて、かんかん!にも特別分載します。毎月第1-3水曜日にUP予定。いちはやく全部読みたい方はゼヒに本誌で!
→田口ランディさんについてはコチラ
→イラストレーターは安藤みちこさん、ブログも
→『訪問看護と看護』関連記事
・【対談】「病院の世紀」から「地域包括ケア」の時代へ(猪飼周平さん×太田秀樹さん)を無料で特別公開中!
「これが医療なのか!」
次に私は、都内の精神科病院を訪れました。
その病院は内科の入院病棟をもっていて、同時にアルコール依存症の治療に積極的に取り組んでいたのです。ホームページには、人間愛に満ちた理念が謳われていました。
この病院の理事長をたまたま友人が知っていて、そのつてを頼りに藁をもすがる思いで来院しました。約束の時間に待合室に座っていると、アルコール依存症科の室長という医師がやって来ました。
この人の顔を見た瞬間に、私は「ああダメだ」と思いました。私の願いを断るつもりで来ているという硬い表情をしていました。すでに心のシャッターが下りていたのです。それでも私は、ほんの5 cmあいている隙間に足を突っ込んででもこじ開ける……という姿勢で、父の状況を説明しました。
すると、その精神科医はまったく無表情に聞いていましたが、仕方なく「では、内科に相談してみよう」と私を内科医の診察室に連れていきました。私は、その内科医にまた同じ説明をしました。すると、「どれどれ」と私の持ってきたレントゲン写真をライトボックスに載せてまじまじ見てから、こうおっしゃったのです。
「あなたね、こんなひどい状態のお父さんを、本気で精神科に入れるつもりなの? これは末期の肺がんだよ。うちじゃ面倒みれるわけないじゃないの。何考えてるの? あなたが受診すべきは呼吸器内科だよ。ちゃんとがんの治療をしなくちゃ、死んじゃいますよ」
頭ごなしの言い方でした。
「ま……、そういうわけですから、どうかお引き取りください」と精神科医は、どこかへ行ってしまいました。
私は、病院の事務室の片隅にぽつんと取り残されました。何だこれは?と思いました。医者がそれでいいのか?本当にそれでいいのか? と怒りが湧き上がってきました。
その部屋には、数人の事務員と看護師さんたちが出入りしていました。私は思わず立ち上がって、その場にいる病院のスタッフの人たちに大声で訴えました。
「みなさん、私も父はアルコール依存症で末期がんです。だけど、どこの病院も受け入れてくれません。今、お聞きになったとおりです。私は本当に途方に暮れています。だけど、誰も私がどうしたらいいか教えてくれません。病院は、病院の都合を説明するだけです。これでいいんですか? みなさんは本当にこれでいいと思っているんですか? これが日本の医療なんですか?」
みんな下を向いて、じっと聞こえないふりをして仕事をしていました。でも、たった1人、看護師長という名札をつけた男性が近づいてきて言いました。
「わかりました。一緒に病院を探しましょう……」
そう言って、神奈川県の病院リストを持ってきて、片っ端から病院に電話をかけてくれました。10件、20件と電話をかけました。私は看護師さんのアドバイスに従って父の状況を説明しましたが、結局、父を受け入れてくれる病院は1つもありませんでした。
とうとう、その看護師さんが言いました。
「自分も甘かった……。こんなに厳しいとは……思わなかった」
その一言を聞いたとき、私は納得しました。もういい、と思いました。それで、その看護師さんにお礼を言って病院を後にしたのです。
あのとき、あの病院のスタッフの人たちもつらかったろうなと思います。制度というもののなかで、個人ができることは限られているのです。しかも、仕事に追われています。それでも、看護師さんが自分の仕事時間を削って病院探しを手伝ってくれたことは、私にとって救いでした。ご迷惑をかけたことを、本当に申し訳なく思っています。
ここが最後の頼みの綱だったのです。このとき父が入院していた整形外科の病院からは、3日後には転院するようきつく言い渡されていました。毎日ひたすら電話をかけ続けましたが、入院させてくれる病院はありませんでした。もし転院先が決まらなかったら、まだギブスをつけてまったく動けない、しかもアルコール依存症で末期がんの父を、家でどう看護していいのか見当もつきませんでした。わが家には90歳になる夫の両親がいました。連れて帰れる状況ではなかったのです。
病院を出た足で、私は電話をかけました。相手は、知人の大学病院教授でした。
「3日後に転院を迫られています。でも、受け入れてくれる病院がありません……」
電話口で私が泣いているので、さすがに教授は窮状を察したのでしょう……。
「3日後とは厳しいですね……」と言い、「知り合いの救急病院の理事長にかけ合うので、お父さんを救急扱いで運び込むように」、そうでなければ、正規のルートでの入院は難しいと言われたのです。
この救急病院に精神科はありませんでした。せん妄のある父を静かに(安静に)させるために、大量の向精神薬が投与されました。
「この病棟には重篤な患者が多く入院しているので、騒がれては困ります」
父は、廃人のようになってしまいました。よだれを流し、しゃべれなくなって、認知症が一気に進行してしまいました。それまでは、せん妄はあっても、私とは会話ができていたし、自分の状況も把握していたのに、どんどん意識がぼやけていってしまったのです。
このままこの病院にいたら、何もわからないまま死んでしまう。そう思いました。これが医療なのか……。その疑問は私の中でどんどん大きくなっていきました。
「医療コーディネーター」との出会い
そんなとき、ちょうどこの連載の担当編集者である友人が紹介してくれたのが「医療コーディネーター」の存在でした。どんな助けでもいいからと、さっそく日本医療コーディネーター協会にSOSのメールを送ったところ、1人の医療コーディネーターである女性が父の病院を訪ねてくれました。
初夏の、とても暑い日でした。駅まで迎えにいくと、ワンピース姿の女性が汗だくになって立っていました。
この方の存在が、どれほど私に勇気を与えてくれたことか。彼女は長く看護師として大学病院に勤務していた方で、私の状況をよく理解し、まず私自身をとてもねぎらってくれました。そのうえで「一緒にがんばりましょう」と励ましてくれたのです。彼女はまず、私の要望をよく聞いてくれ、私がすべきことを整理してくれました。
①アルコール依存症の治療を優先する
②短期的な入院先を探しつつ、在宅看護の準備を始める
③本人が望むなら、少しの間だけでも自宅に戻れるようにする
④がんが進行したときのため、終末期医療の準備をする
私はこのとき、とても大きな決断をしました。それは「がん治療を断念する」という決断でした。投薬で廃人のようになってしまっている父の心を“今ここ”に連れ戻し、人生最後の時間を私たち家族と共に過ごせるように回復させることを、がんの治療を捨てて選んだのです。
少しして、父は自宅から車で1時間ほどの山奥の精神科病院に転院することができました。「がんの治療はしない」という条件で、医療コーディネーターの友人である看護師さんが勤務する病院へと受け入れてもらえたのです。
転院しアルコール依存症の治療を始めて1週間後には、父は記憶を取り戻し、私と普通に会話ができるまでに回復していました。アルコール依存症のせん妄状態から認知症に移行することがあること、その治療にはビタミンB群の投与が効果的なことは本を読んで知っていました。でも、まさかこんなに効果があるとは……。父は当初こそ閉鎖病棟に入っていましたが、数週間後には開放病棟に移り、緑の多い涼しい環境で、社会復帰に向けたリハビリをしている人たちと過ごしました。自由な雰囲気がよかったのか、父は心も身体もみるみる回復し、一時帰宅しながら退院の時期を探っていました。
人間は、どうしても自分の都合のよいほうに、物事を考えたがる傾向がありますね。もし医療コーディネーターさんのアドバイスがなければ、私は楽観的に構えてホスピスの心配などしなかったと思います。
でも彼女は、「来るべき時は来ますから、準備だけはしておいたほうがよいですよ」と言い、家から近い独立型のホスピスがあるから見学に行っておいたらよいのではないかと、紹介してくれたのです。
秋が深まるころ、父の容体はがくんと悪化しました。痛みが出始めたのです。肝臓にがんが転移していました。その精神科病院では、痛みの緩和はできません。いよいよホスピスでの緩和に踏み切らなければならなくなりました。しかしホスピスは、ベッドの空きを待っている状態でした。そんなとき、ピースハウス病院の院長先生が、父の入院している精神科病院まで往診してくれたのです。そして、父の主治医と話し合って、鎮痛剤の投与についてアドバイスしてくれました。
多くの病院は病院間の連携はできない……と言いました。ですが実際には、「ホスピスの医師が往診に来てくださると言っています」と申し上げると、がん患者など担当したことのない精神科の先生は「それは本当にありがたい」と喜んでくださったのです。
考えてみれば、まったく専門外の末期がん患者を担当して、この精神科医の先生はさぞ心細かったろうと思います。そんな父をこの精神科病院はよくぞ受け入れてくれた……と今となれば感謝の気持ちしかわかないのですが、当時は次々と変化する父の状況にただただ対応するのがやっとで、医師や看護師、病院への不満と怒りばかり感じていました。
もっとああしてほしい、こうしてほしい。どうしてできないんだろう……。
私は、ずいぶんわがままな家族だったと思います。でも、わがままだから変えられたこと、気が強いから押し通せたこともたくさんあるのです。へこんだり、気がねしていては、乗り越えられないことが多く、図太くなりました。父のように複数の疾患を抱え、しかも精神的にも問題があると、医療・福祉とお付き合いするのは、実に苦しい、つらい、忍耐のいる、落ち込むことです。でもその分、出会うべき人と出会ったときの喜びは大きく、運命というものが必要なものをいつもちゃんと用意していてくれることは神秘的でした。ただそれは、精根尽き果て、何もかも諦めたようなときにしか与えてもらえないのですよね……。

いよいよ高まる在宅医療・地域ケアのニーズに応える、訪問看護・介護の質・量ともの向上を目指す月刊誌です。「特集」は現場のニーズが高いテーマを、日々の実践に役立つモノから経営的な視点まで。「巻頭インタビュー」「特別記事」では、広い視野・新たな視点を提供。「研究・調査/実践・事例報告」の他、現場発の声を多く掲載。職種の壁を越えた執筆陣で、“他職種連携”を育みます。楽しく役立つ「連載」も充実。
5月号の特集は、ステーション経営を安定・向上させる秘訣がいっぱい。時間もお金もかかる大規模化やネットワーク化などはさておき、まずは明日からでもできる“工夫”を集めました。それらは、利用者さんの満足度にも直結! 制度の枠も飛び越えて、夢を叶える経営戦略を“企業ヒミツ”ギリギリのところまで明かしていただきました。