かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
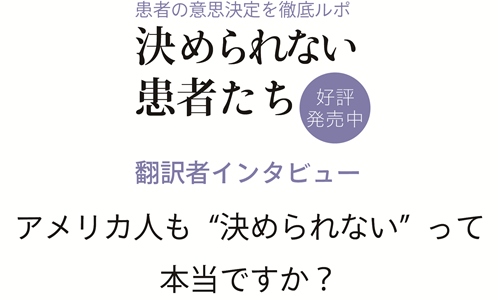
『決められない患者たち』 インタビュー
2013.4.25 update.

医療上の決断を迫られたとき、患者の心はどう動く?
悩む患者。主義を貫く患者。いつまでも決められない患者。医療上の決断に際して、患者は何を考えているのか? 心理学、統計学などの研究を紹介しながら、患者の内面を分析していく。ハーバード大学医学部教授による患者と医師に密着したルポルタージュ。
(http://www.igaku-shoin.co.jp/bookDetail.do?book=84726)
医学書院より『決められない患者たち』が発行されました。『How Doctors Think』(邦訳『医者は現場でどう考えるか』[石風社])で好評を博したベストセラー作家による、患者と医師のためのルポルタージュです。今回は、翻訳を担当した堀内志奈先生(消化器内科医、洋書が大好き!)にお話を伺いました。
■自分が患者だったらこういう先生にかかりたい
―――この本を翻訳しようとしたきっかけは?
堀内 アメリカ留学中にたまたま書店で本書の著者であるジェローム・グループマン先生の著書『How Doctors Think』を見つけて読んでみて、とてもいい本だな、と思ったんです。既刊本も全部読んで一気にファンになりました。続いて発行されたこの『Your Medical Mind –how to decide what is right for you』も多くの方の役に立つだろうと確信しています。
―――どういった部分に魅力を感じたのでしょうか?
堀内 著者のグループマン先生はハーバード大学の医師で、バックグラウンドとしてはアカデミズムの頂点に立つような権威をもった立場の方なのに、向き合う姿勢は患者さんの側なんです。医師とはまさにそうあるべきだし、血の通った温かい人だと感じました。「もし自分が患者だったらこういう先生にかかりたい」という人です。
―――アメリカではこのようなルポルタージュなど医師の書いたものは多いんですか?
堀内 多いですよ。ノンフィクションに限らず、(亡くなられてしまいましたが)マイケル・クライトン※とか人気作家もいらっしゃいますね。一般の方を意識した医学の読み物を書いている人は日本より多い印象です。いわゆる学術的な医学雑誌ではなく「Newsweek」「Time」といった一般誌に寄稿することも多いですね。医学情報のニーズもアメリカの方が多いのかもしれません。
※ 『ジュラシック・パーク』(原作小説)、自身の医学生時代をモデルとした、ドラマ『ER緊急救命室』の制作総指揮・脚本などを手がけるアメリカの作家。
■アメリカ人だって“決められない”
―――今回の『決められない患者たち』も翻訳書ですが、アメリカの医療事情や、意思決定に対する考え方に違いはあるのでしょうか?
堀内 アメリカの方が、一般の人のリテラシーというかベースとなる医学の知識が多いかもしれません。高校の授業でも習いますしね。
一番の理由は、保険制度の違いにあると思います。アメリカでは簡単に病院にかかれません。まずは、Self-diagnosis(自分自身で診断)をして、それで「これはいかん」となってから医者にかかります。ファーストスクリーニングを自分でやらないと経済的に大変なことになってしまうという状況があります。
―――プラクティカルな理由が背後にあるんですね。
堀内 例えば、そのへんのおばちゃんでも、血栓溶解薬のことなど、たとえ自分自身が病気でなくても知識として知っています。そこには大きな差があると思います。賢いというわけではなく、医学知識に触れる機会が多く、また必要なのです。

―――欧米の人は、自分で物事を決断していくというイメージがありますが。
堀内 アメリカはまさに「自己責任」の社会。自分の身は自分で守る必要があります。日本みたいに社会がやさしくないので、誰も責任を取ってくれません。失敗したら受け皿がないので、そうなると自分で決めざるを得ない。意志力が強いとかでは決してないし、決然としているわけではないと思います。同じ人間ですもの。
(編集)本書を翻訳するにあたり、あるドクターに意見を求めた時にも同じことをおっしゃっていました。医療事情の違いなどで、日本でこの本が役に立たないということはないかを聞いたところ、「変わらないよ、患者さんは」と一言。ひとりの人間としたら当然迷うし、決められないものですよね。
そこで彼に尋ねてみた。「それだけしっかり知識を得た結果、自分の決断により自信が持てるようになりましたか?それとも、かえって不安が強くなりましたか?」
「両方ですね。」と彼は答えた。
―本書8頁より
■すれ違う医師と患者
堀内 この本のひとつの柱は「コミュニケーション」。医療者と患者ないしは患者の家族と、同じ場面で話していても使っている言語は実は違うんじゃないかと感じることがあります。
わかりやすい例としてSay back方式という方法があります。「帰ったらこれこれしてください」「わかりました」と言った後で、「では、あなたが家に帰ってからすることはなんですか?言ってみてください」と聞くと「えーと」となる。伝えた、伝えられたと思っていても実はわかっていないんです。コミュニケーションとしてあえて言い返しをさせることは効果的です。
このようなすれ違いを解消するためにも、共通言語を身に着けてほしいと思っていますし、この本がその助けになるものだと思っています。
―――本書をどんな人に読んでもらいたいですか?
堀内 この本は、患者側と医療者側の両方の視点で書かれた本で、様々な立場から読める本です。患者側という意味では患者さん本人はもちろん、家族の方にも読んでほしいと思っています。「どうしよう」と困るのは自分のことだけでなく、家族で意見が分かれるような場面も多いと思います。本書はいくつものケースを紹介することで、様々な示唆を与えてくれるでしょう。
―――では、医療者側では?

堀内 医療者側だと、もちろん決定を下す医師が中心になります。ただ、この本のもう一つの側面が「臨床心理学的に心がその時どう動いているか」を考えさせる内容なので、心理学分野の人も興味を持っていただけると思われます。また、私はコミュニケーションの最前線にいるナースにこそ読んでほしいと思っています。実際、本書の中にはナースの発言が選択に強い影響を及ぼした例がいくつか出てきます。現場のナースにとっては、ケーススタディの勉強にもなるのではないでしょうか。本書で紹介されるケースは、珍しい場面というよりも、「あるある、こういう場面」「難しいのよね、こういうとき」といったよく目にする、耳にする日常診療でよく遭遇するケースばかりです。自分だったらどう対応するかを考えながら読んでみてください。また最初は血圧の薬を始めるかどうかといった、だれでも関心のあるようなところから、癌の治療法、延命処置に至るまで医療におけるさまざまな「決定」について書かれています。
公衆衛生の問題という枠組みで考えるとき、スタチンの使用は必要不可欠なものにも思われる。しかし、個人の健康問題という枠組みで考えると、スタチンを服用する利益はそれほど絶対的なものには見えなくなる。
―本書37頁より
(中略)健康になるためにたった一つの「ベスト」の方法がある、と言うことなど彼にはとても考えられなかった。
グレーブス病やその治療に関する予備知識は全くなかったが、あまりにも簡単かつ断定的に「ベスト」の治療法はこれ一つだ、といわれたようにパトリックには感じられた。実のところ、彼の感覚を裏付ける臨床研究がある。
―本書71頁より
■後悔をしない選択をいかにするか
―――本書のテーマの1つに「(自己)決定」があると思います。
堀内 この本には「こういう場面ではこのようにしなさい」というような明快な解答はありません。医学には純粋科学と異なり「絶対的な解」はありません。以前のように、程度の差こそあれ医師の決定に患者が基本的に従うという関係は成り立たなくなり、患者は情報と選択権とともに、その責任の一端を負うことになっています。自分にとってのより良い選択をするのに重要なこととして、正しい情報を得ること、またその情報の解釈、選択の過程で心理学的な罠にはまらないということ、そしてコミュニケーションの大切さをあげています。
―――答えがないからこそ悩み、選択に後悔するんですね。
堀内 「医学的な正しさと患者の満足はイコールではない」と思います。その決定に納得しているか、後悔しない選択なのか、その選択のために医療者は何ができるか。
もしリスクとメリットが等しい選択肢があったとして、その患者さんが後悔しないための道筋をつけてあげるには、客観的に見える第三者が、すでに患者さんがどこかに持っている結論、そっちの方に押していってあげることだと思います。
しばしば「先生のお母さんだったらどうしますか?」「先生だったらどうします?」という質問を受けます。つまり「私の立場に立ってみてください」という意味だと思います。患者さんは医療者に寄り添う者としての役割を求めているのかもしれません。
―――インターネットなどで医療情報があふれている今だからこそ、コミュニケーションの重要性も増しているのかもしれません。
堀内 先ほどアメリカ人の方が医療的なリテラシーが高いということを言いました。それは、保険制度の違いもあり、自分で自分の身を守る必要があるからです。しかし、情報が溢れ、専門的知識にもアクセスが容易になり、価値感も多様化している状況は、日本も同じです。だからこそ多くの日本人にこの本を読んでほしいと思っています。共通言語を持つことで、お互いのすれ違いも少なくなるでしょうし、非常に大切なことだと思っています。
ゆくゆくは日本の高校レベルでの医学知識の底上げをやってもらえば、長い目で見れば医療費の削減などにつながるのではないかと期待しています。
―――ありがとうございました。











