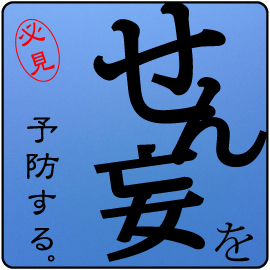かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
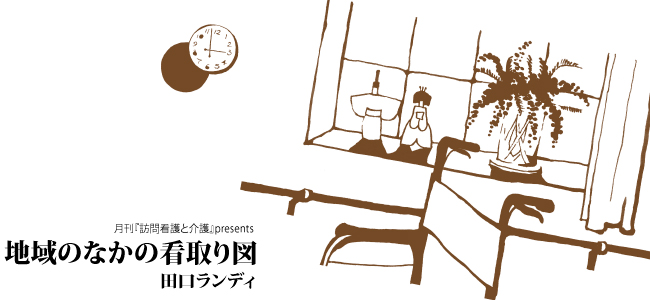
13-3 「看取りの時間」 家で看取るということ〈その6〉
2014.3.19 update.
『訪問看護と介護』2013年2月号から、作家の田口ランディさんの連載「地域のなかの看取り図」が始まりました。父母・義父母の死に、それぞれ「病院」「ホスピス」「在宅」で立ち合い看取ってきた田口さんは今、「老い」について、「死」について、そして「看取り」について何を感じているのか? 本誌掲載に1か月遅れて、かんかん!にも特別分載します。毎月第1-3水曜日にUP予定。いちはやく全部読みたい方はゼヒに本誌で!
→田口ランディさんについてはコチラ
→イラストレーターは安藤みちこさん、ブログも
→『訪問看護と看護』関連記事
・【対談】「病院の世紀」から「地域包括ケア」の時代へ(猪飼周平さん×太田秀樹さん)を無料で特別公開中!
死んでいく人からのプレゼント
おじいちゃんは92歳でした。
老衰……で亡くなっても納得がいく年齢、という言い方をしたらおじいちゃんは怒るかもしれませんが、家族には「90を超えているし、もうしょうがないか」というあきらめがありました。
では、もし72歳だったら?
私の実母は72歳で亡くなりました。脳出血でした。
母が植物状態になっても、父と私は延命を望みました。母はたいへん苦しかったと思いますが、生かされ続けました。肉体は消耗し傷みました。でも、母は生きたのですから、それは母の意思かもしれないと、このごろは思うようになりました。
母は、植物状態の4か月の間、父につきっきりで介護してもらいました。ずっと父の面倒を見続けた母にとって、父に自分の世話をしてもらう4か月は必要だったように思います。
死は個別です。
そして、死ぬのは本人です。
まわりの人間は死を体験できません。
私も死を体験したことがありません。だから、死が何かはわかりませんし、死んでいく人の心もわかりません。とにかく、その瞬間にできることを精いっぱいやるだけです。
それしかできないんです。命を伸ばしたり、縮めたりすることは、実は科学の力でもできないのかもしれません。
延命しようがしまいが、人は生きたいだけ生き、死ぬ時に死ぬのかもしれないなあ。そんなことを思ったりもします。
これは、私の経験から導かれた私の考えです。10人親族がいれば、それぞれの考え方があります。そういうものなのです。どうしようもありません。他人の考えを強引に変えさせることはできません。もしそれをしたら、のちのちにねじれた思いが残ります。
死ぬのは自分ではない。
けれども、死を前にした人のことをみんなで考えなければならない。
これは、実に素晴らしいことです。
こういう機会をもてるということが、ほんとうにありがたいのです。死んでいく人たちからの、プレゼントと言ってもいいかもしれません。
一生忘れない「ばんざい、ばんざーい!」
お姉さんたちは、あまりに慌てて来てしまったから一度家に戻っていろいろ用事を片づけてきたい、と考えていました。母として、嫁としてやるべきことを放って飛んできたのですから、気持ちは理解できます。ですが、私としては「もし、お姉さんたちがいない間におじいちゃんが亡くなってしまったら……」と思うと不安でした。
そんなときに背中を押してくれたのが、訪問看護師さんでした。
訪問看護師さんは、親族の会話からお姉さんたちが一度帰宅したがっていることを感じとったのです。そして、仕事の合間に私だけを呼んで、こうアドバイスしてくれました。
「奥さんは、できるなら、ご親族で看取りたいですよね。お姉さんたちが、一度自宅にお戻りになりたいようですが、私の経験では、お父様のそばを離れないほうがよいのではないかと思うのです。こんなことは私が言うことではないし、お気に障ったら申し訳ないのですが、もし可能なら、お引き止めしたほうがよいような気がします……」
私は今でも、この訪問看護師さんの助言に感謝しています。こう言ってもらえなければ、私はお姉さんたちを引き止められなかったろうと思うのです。
一緒にお父さんを看取りたい。それは、私が1人で看取るのが不安だったからでもあります。みんなで看取りたい。おじいちゃんは、実の親子であるお姉さんたちにこそ看取ってもらいたいだろう。
そこで、私は看護師さんの言葉をそのままお姉さんたちに伝えました。お姉さんたちは、覚悟を決めて家に残ってくれました。
そこから、私たちの看取りの時間が始まりました。
みんなが腹をくくった瞬間から、場が急に和やかになりました。どこか祝祭的なムードすら漂うようになってきました。
私たちは、おじいちゃんのベッドを囲み、おじいちゃんを見つめながらいろんなことを語り合いました。子どものころの思い出がたくさん共有されました。
訪問介護の方たちと一緒に、おむつをとり換えたり、身体を拭いたりしました。みんなで看取るんだという、一体感のようなものが育っていくのがわかりました。
そうなると、不安とか、悲しみというよりも、なにか、おじいちゃんが生まれ変わるのを見守っているような……。そう、赤ちゃんが産まれるのを待っているような、不思議な感覚になってきました。
おじいちゃんのそばに寄り添いながら、お姉さんたちと一緒に靴下を編みました。編み物をしながら冬の陽が注ぐ部屋で、おじいちゃんと、親族と、みんなで過ごした1日を、私は一生忘れないです。
それは、なんだかとても温かで、優しい1日でした。
お姉さんたちと、本当の姉妹のような気がしました。
みんなの心が、だんだんおじいちゃんの意識と共鳴していきます。
深刻でもなく、さりとて不真面目でもなく、私たちはおじいちゃんの子どもとして、その場にいました。
自然で、透き通ったような気持ちでした。
そういうなかで、おじいちゃんの息が荒くなっていきました。呼吸するのが苦しいらしく、顎がだんだん上がっていきます。
「ずいぶん、顎が上がってきたね」
「先生に連絡したほうがいいかもしれない」
在宅医からは「呼吸の感覚が長くなって顎が上がってきたら、そろそろですから連絡をください」と教えられていたので、夫が先生に電話をしました。
みんなで、おじいちゃんのベッドを囲み、おじいちゃんに声をかけました。おじいちゃんは、とても堂々としていて、神々しいようでした。
ああ、死ぬときは1人なんだ……と、その姿を見て思いました。
「お父さん、おつかれさま。よく生きたね」
「がんばって働いたね、本当にごくろうさま」
そう言って、おじいちゃんに声をかけているうちに、みんな泣いていました。
おじいちゃんが息を大きく吸い込んで目を見開いたとき、
「おとうさんの人生、ばんざい、ばんざーい!」と、お姉さんが泣きながらバンザイをしました。
みんなも「ばんざーい、ばんざーい」と手を上げてバンザイをしました。
親族のバンザイに見送られて、おじいちゃんは旅立っていったのです。
「おとうさんの人生、ばんざーい」
そう叫んだお姉さんは、本当にすごいと思いました。すばらしい素直な人です。身近な人のもっている人間としての尊厳を、看取りの場面は教えてくれます。
バンザイで、看取れて、本当によかった。
おじいちゃんは、すっと、あちら側に行ってしまいました。
何が起こったのか、今でもよくわからないのです。
死って、何でしょう?
つづく

いよいよ高まる在宅医療・地域ケアのニーズに応える、訪問看護・介護の質・量ともの向上を目指す月刊誌です。「特集」は現場のニーズが高いテーマを、日々の実践に役立つモノから経営的な視点まで。「巻頭インタビュー」「特別記事」では、広い視野・新たな視点を提供。「研究・調査/実践・事例報告」の他、現場発の声を多く掲載。職種の壁を越えた執筆陣で、“他職種連携”を育みます。楽しく役立つ「連載」も充実。
2月号の特集は「在宅だからICF 『生活を支える』を具現化する」。訪問看護と介護の仕事は、利用者さんの「生活」を支えること。とはいっても、生活はあまりに幅広く複雑で捉えどころがありません。さらに、多職種連携が基本となる「在宅」では、目標や課題を共有のための共通言語も必要です。その両方に効くのが、「生きることの全体像」の「共通言語」であるICFです。生活を支えるのに「いま本当に必要な支援は何か」を具現化します!