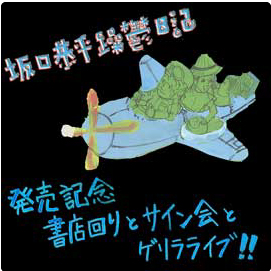かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
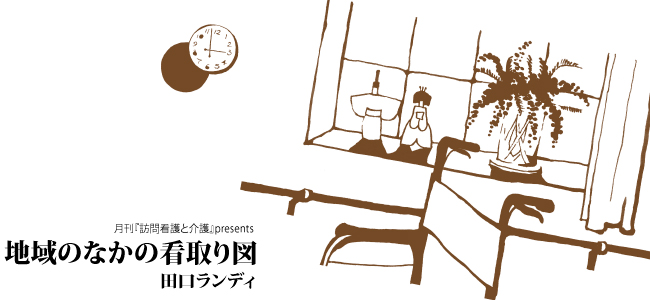
12-1 崖っぷちでの出来事 家で看取るということ〈その5〉
2014.2.05 update.
『訪問看護と介護』2013年2月号から、作家の田口ランディさんの連載「地域のなかの看取り図」が始まりました。父母・義父母の死に、それぞれ「病院」「ホスピス」「在宅」で立ち合い看取ってきた田口さんは今、「老い」について、「死」について、そして「看取り」について何を感じているのか? 本誌掲載に1か月遅れて、かんかん!にも特別分載します。毎月第1-3水曜日にUP予定。いちはやく全部読みたい方はゼヒに本誌で!
→田口ランディさんについてはコチラ
→イラストレーターは安藤みちこさん、ブログも
→『訪問看護と看護』関連記事
・【対談】「病院の世紀」から「地域包括ケア」の時代へ(猪飼周平さん×太田秀樹さん)を無料で特別公開中!
「私は、田口さんのようには看取れなかった」
読者の方からこういう感想をいただいて、私の思いは複雑です。
お気持ちはわかる。痛いほどわかる。でも……、看取りに、「こうあるべき形」はないということを、伝えたい。
同じ指紋の人がいないように、同じ死に方の人もいない。死は、指名制なんです。呼ばれた人が手を挙げて前に進み出る。指名されたら歩き出すしかない。そして、一人で崖っぷちに立つ。バンジージャンプみたいです。
だから、私がつづる「看取り」は、バンジージャンプを見物している側の主観であって、真実、亡くなっていった家族がどんな体験をしたのかは、永遠に謎なのです。
生まれるも、死ぬも、一人。そのことを実感させられます。
病院で、ご親族にずっと寄り添うことは難しいですよね。
施設に入所していた場合、健康状態が悪くなるとまず病院に運ばれ、在宅での看取りの準備をする間もなく、亡くなられてしまうことも多いのではないかと思います。
私も、家で看取ったのは義父一人。実の父母も義母も、病院で看取りました。3人看取ってやっと在宅に踏み切れた……というのが正直なところです。
「在宅看取り」は、不安でした。
戦後の高度成長期に育ち、病院で死ぬのが当たり前の社会で生きてきました。人が死ぬのに立ち会ったことなんて、なかったのですもの。でもね、場数を踏む、なんていう言葉は不謹慎ですが、誰かを看取るたびに、送り出すための“覚悟”が決まっていくんですね。
怖かった友人の死
見送ってきたのは、家族だけではありません。すでに少なからぬ友人たちが旅立っています。
夭逝した友人たちから、多くのことを教えてもらいました。
とくに『がん患者学』(中公文庫)の筆者である作家の柳沢和子さん、そして、同じく作家の黒岩比佐子さんとの交流を通して、友として「死んでゆく人とどう向き合うか」を問われ続けました。
年の近い二人の女性の闘病。これは、両親の看取りとは違う切なさがありました。彼女たちの死は、「私の死」とまっすぐに地続きなのです。いつだって、私にも起こる出来事としての切実さをもって迫ってきました。
ちょうど実父の末期がんが発覚したころ、柳沢さんも再々発のがんの治療中でした。
柳沢さんは率直な人で、私の弱腰に容赦なく蹴りを入れてきます。
「あなたも一度、がんになってみたらおもしろいわよ」
さらっと笑って言ってのけるのです。
私は、がんを患っている方と、がんについて会話などしたことがなかったので、みっともないくらいたじろいでいました。
「いやよ、がんなんてなりたくないわよ」とは言えませんでした。
でも、がんになりたい人がいるわけありません。
では、がんの人の前で「がんになりたくない」と言えるか。時と場合によると思いますが、あのときは言ってよかったんじゃないかと思います。だって「あなたの身体」と「私の身体」は別ですし、あなたが痛いからって、私が痛いわけではない。
それはそれ、これはこれ。この線引きは「人情」を切断するように感じられるため、多くの人は躊躇します。よく「共感」とか「共苦」が大切だと言われますよね。そのとおりです。でも、人と人との間にはどうしようもなく深い亀裂がある。それをわかっているかどうか。超えることのできない「他者性」を、悲しく諦めているかどうか。
そこを踏まえたうえでの共感・共苦でなければ、それは「同情」だ、と彼女は言うのです。他人からむやみに同情されるほど情けないものはない……と。
私の無自覚な欺瞞を、彼女はあぶり出してくる。
どれだけ切実で、どれだけ率直なら、相手と向き合えるのか。柳原さんから試されたような気がします。
「ホスピスに行くのは、最後の最後。高級ホテル並に高いけど、どうせそんなに長くはいないから最後の贅沢よ」
実際に、そのとおりなんですよね。
なんていうのかな、「ホスピス」に入ると、なにかもう、「さようなら」という気分になるんじゃないかと思います。そういう“雰囲気”というのがホスピスにはある。彼女は、それをよくわかっていました。
人間が死ぬ場所が、本当にそれでいいのかな。「医療」というのは、生きているかぎり患者に一緒に寄り添ってくれるべきものじゃないのか。治療方法がない、って見放していいのか。
柳原さんは、黄疸が出て、苦しくてつらくてがまんできなくなって、自分で緩和ケア病棟のある病院に電話して入りました。私は、彼女が緩和ケア病棟に移ってからは、3、4回しか会っていません。面会に行っても具合が悪くて会えなかった……というか、会ってもらえなかったのです。
その理由がわかるんですよね、自分でも。
もし、私が彼女の立場だったら、やっぱり私には会いたくないと思うんです。それは……、私が怖がっていたからです。
死んでゆく人は、相手の顔色で自分のことを知ってしまう。他者は自分を映す鏡なんです。それはたぶん何歳になっても、同じだと思います。たとえ、80歳でも90歳でも、相手が自分を見て脅えている、恐れているのがわかるんです。
そして、そのことで一番、悲しむんです。

いよいよ高まる在宅医療・地域ケアのニーズに応える、訪問看護・介護の質・量ともの向上を目指す月刊誌です。「特集」は現場のニーズが高いテーマを、日々の実践に役立つモノから経営的な視点まで。「巻頭インタビュー」「特別記事」では、広い視野・新たな視点を提供。「研究・調査/実践・事例報告」の他、現場発の声を多く掲載。職種の壁を越えた執筆陣で、“他職種連携”を育みます。楽しく役立つ「連載」も充実。
1月号の特集は「『新生在宅医療・介護元年』の成果と展望」。厚生労働省は2012年度を新生在宅医療・介護元年」と位置づけ、「在宅医療連携拠点事業」を行なった。本事業には訪問看護ステーションも9拠点が取り組んだ。本特集では、事業の成果を概観するとともに、2025年へ向けて、いかに「多職種連携」を行ない、「在宅医療」を充実させていくのか。各拠点の本事業への取り組みから、2014年への示唆を得る。