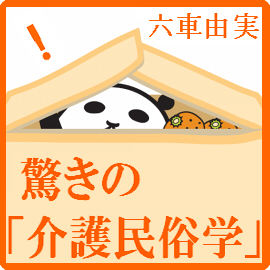かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

【第3話】 無音劇場
2010.11.20 update.
1946年岐阜県生まれ。お茶の水女子大学大学院修士課程修了後、駒木野病院勤務などを経て、現在に至る。臨床心理士。アルコールをはじめとする依存症のカウンセリングにかかわってきた経験から、家族関係について提言を行う。
著書に『アディクション・アプローチ』『DVと虐待』(ともに医学書院)、『母が重くてたまらない』(春秋社)など多数。最新著に『ふりまわされない』(ダイヤモンド社)、『ザ・ママの研究』(よりみちパン!セ、理論社)がある。
[前回まで]
健康そのものだったポスカン(ポスト還暦)の売れっ子カウンセラーの嘉子は、ある日心臓がギュッと締め付けられるような違和感を覚えた。あわててH医療センターを受診すると、即刻検査入院を命じられた。
「今度新しく入院なさる木川さんです。よろしくお願いします」
担当の女性スタッフが、病室の入口に立ち、明るい声であいさつした。たぶん、患者が新しく入院するときのしきたりなのだろう。
午前10時近いというのに、カーテンは閉じられたままである。嘉子は小さな声で「よろしくお願いします」と言い、見えない相手に向かっておじぎをした。嘉子の挨拶に対して、返事はおろか身じろぎの気配すらうかがえなかった。
カーテンを開け放てば、病室のすべては見通せるだろうし、窓の外の景色も見えるはずだ。しかし室内は天井から吊るされた四枚のクリーム色の布できっちりと四分割されている。
カーテンが四つのベッドを包囲しているが、よく見ると、足の部分と天井近くは網状になっており、床に立つ足だけは見えるようになっている。姿は隠れていても音は聞こえてくるし、足の数からベッドサイドに何人いるかが把握できるようになっている。
嘉子はシーンとした病室を観察しながら、まるで想像力を掻き立ててくれといわんばかりの仕掛けだと思った。
記憶の病院
H医療センターの入院予約時に、医師から個室か四人部屋かを問われたとき、嘉子は迷わず四人部屋を選んだ。お金がもったいないのがいちばんの理由だったが、ひとりでぼんやり横になっているより、大部屋で患者仲間がいたほうがずっと楽しいことをよく知っていたからだ。
嘉子自身二回の入院経験がある。ふたりの子どもをいずれも帝王切開で出産したので、それぞれ十日間入院した。個室の入院だったので、家族が面会に来ないときはひどく寂しかった記憶がある。
そのとき床頭台に置いたラジオからイヤホン越しに聞こえてきたのが、デビュー直後のオフコースの「さよなら」だった。一九七四年のことなのに、今でもはっきりと覚えている。
嘉子のふだんの楽天的な話しぶりからは想像できないが、過去に夫と二人の子ども、つまり家族全員が別々の時期に命の危険にさらされるような事態に遭遇し、長期にわたり入院をした。そのつど毎日のように病院に通ったので、実は嘉子は入院生活のベテランといってもいい。
娘の真衣の一か月の入院経験は鮮烈な記憶となって今も残っている。
先天性心疾患だった真衣は、小学校一年で手術に踏み切った。心臓専門のA病院は、一九八〇年代の日本では最先端の治療技術を誇っていた。
しかし嘉子と真衣が今でも思い出話に花を咲かせるのは、入院中に出会った心臓病の子どもたちと、若い看護師の女性たち、そして早朝から出勤してひとりずつベッドを回って問診をしてくれた医師たちの姿だった。
真衣は病棟で出会った同年齢の子どもたちのことを、今でもひとりずつくっきりとした輪郭とともに、パジャマの色やデザイン、好きな食べ物までも思い出すことができる。病院という環境は、ひとの個性を際立たせる装置に満ちているのかもしれない。
A病院ではその当時すでに、子どもの心理的ケアのためにいくつかの工夫がこらされていた。ICUで意識が回復したとき最初に目にするだろう玩具を渡しておき、消毒して準備するのもそのひとつだった。
真衣はずっと大きくなるまで、消毒薬の匂いがしみついた熊のぬいぐるみに鼻をすりつけ匂いを嗅ぐのが大好きだった。ICUの記憶はうすぼんやりしているのに、なぜかその匂いは真衣を心の底から安心させてくれるのだった。
窓に舞う桜
嘉子は入口から向かって右側の窓際のベッドに案内され、備品の説明を簡単に受けた。そのあいだもコトリとも音のしない残りの三つのベッドのことが気になってしかたがなかった。
窓にかかったレースのカーテンを、思い切って沈黙を破るようにシャーッと音をたてて開け放った。
五階の窓からは都心の高層ビル群と白っぽく霞んだ四月の空が見えた。ななめ下に視線をやると、病院付属の看護大学の寮らしい古い建物が見える。すぐ脇にあるこんもりとした緑の公園は桜の木に囲まれていた。
突風が吹いてきたのか、樹木の緑がさわさわと揺れた。そこから不意に白い煙のような渦巻がいくつも湧き上がり、まるで這うように病院の建物に沿って下から吹き上げてきた。
驚いてよく眺めると、それは桜の花びらだった。
すぐ目の前を風のように登っていく無数の桜の花びらは、嘉子の病室を超えてはるか屋上のあたりまで舞い上がっていった。もっと上の階に入院中の患者さんも、窓越しにこの花びらを見ることができただろうか。
嘉子はしばらく呆然とみとれていた。
衣擦れとうめき声
これから始まるいくつかの検査があるので、嘉子は昨晩詰め込んだ荷物を早めにカバンから出して、整理を始めた。
広い収納庫や最新のテレビ設備は、さすが新築されて間がない病院だと思わせるのに十分だ。おまけによく見渡すと、ひとりあたりのスペースも広く、嘉子はけっこう満足していた。
パジャマに着替えると、嘉子の気分は不思議なもので少しずつ狭心症の入院患者らしくなっていった。
どっさり持ってきた読了する予定の本や、書きかけの原稿が保存されたパソコンを棚から取り出す元気もなく、ベッドに横になった。白い天井を見上げていると、前夜までの慌ただしい仕事の段取りの疲れが出たのか、眠気が襲った。
……うとうとしていると、入り口わきのベッドのあたりから、突然「ガ、ガーッ」と音がした。びっくりした嘉子は眠気も醒めてしまった。病室で初めて聞いた音は、ものすごい高いびきだったのだ。
午前十時を過ぎたばかりなのに、あんなに眠っていて大丈夫なんだろうか、他人事ながら心配になった。
こんどは、隣のベッドからかすかな物音が聞こえた。
サッ、サッ、という音は、衣擦れのようにも思えた。嘉子は聞き耳を立てながら思わずカーテンの下部に注目した。網の目越しに、椅子に座っている女性の靴が目に入った。靴といっても、中年女性がよく履いているウォーキングシューズだ。それもかなりはき古している。
女性はベッドの上の誰かに話しかけている。
「どう?」「う〜ん」
「このあたり?」「……」
唸り声とも溜息ともわからない声だが、ベッドの上に寝ているのはどうやら20代の女性のようだ。とすると二人は親子だろうか。
再び沈黙が始まり、サッサッというひそやかな音だけがカーテン越しに聞こえてくる。ときどき、娘のうめき声らしいくぐもった声も聞こえる。
いったい何をしているのだろうか。姿が見えないぶん、嘉子の想像力だけがフル稼働する。
そうか、きっと母親が娘の背中をさすっているのだ。
嘉子は確信した。どこをさすれば楽になるのかを娘に確かめながら、ひたすら母親はサッサッとパジャマの上から体をさすり続けているのだ。絶えることなく、もう何分間、いや何十分間その動作を続けているのだろう。
嘉子は自分だったら、と想像してみた。
ベッドわきの椅子に腰かけて不自然な姿勢でベッド上の娘の体をひたすらさすり続けるなんて、とうてい無理だ。たぶん五分でギブアップするだろう。肩凝りのひどい嘉子はそう思った。
(第3回了)
[次回は12月1日(水)UP予定です。乞うご期待。]
信田さよ子先生の著書
|
アディクションアプローチ もうひとつの家族援助論
定価 2,100円 (本体2,000円+税5%) ISBN978-4-260-33002-2
|
|
DVと虐待 「家族の暴力」に援助者ができること
A5判・192ページ・2002年03月発行 |