かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
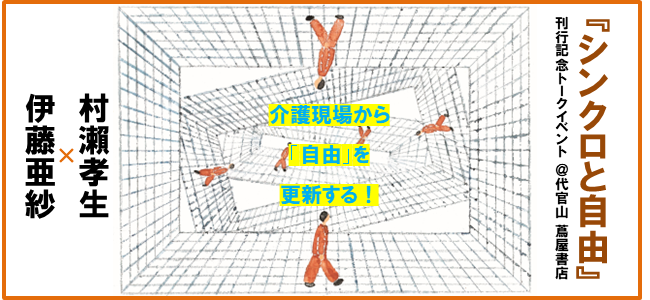
1 介護と「わたし」
2022.8.23 update.
村瀨孝生(むらせ・たかお)
特別養護老人ホーム「よりあいの森」、「宅老所よりあい」、「第2宅老所よりあい」の統括所長。大学卒業後、特別養護老人ホームに生活指導員として8年勤務。その後福岡市で、「宅老所よりあい」にボランティアとしてかかわる。
著書に『おしっこの放物線』(雲母書房)、『ぼけてもいいよ』(西日本新聞社)、『増補新版 おばあちゃんが、ぼけた。』(よりみちパン!セ、新曜社)など。
伊藤亜紗(いとう・あさ)
東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター長。専門は、美学、現代アート。
著書に『ヴァレリー 芸術と身体の解剖』(講談社学術文庫)、『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社)、『どもる体』(医学書院)、『記憶する体』(春秋社)、『手の倫理』(講談社)など。
第13回(池田晶子記念)わたくし、つまりNobody賞(2020)受賞。第42回サントリー学芸賞受賞。
2022年7月23日、東京・代官山 蔦屋書店にて、「シリーズ
ケアをひらく」の最新刊、村瀨孝生さんの『シンクロと自由』の刊行記念トークイベントが行われました。
お相手は、同シリーズで『どもる体』を刊行している伊藤亜紗さん。村瀨さんの最高の理解者である伊藤さんは『シンクロと自由』をどう読むか――注目の対談を、当「かんかん!」では4日連続更新でご紹介します。
.............................................
【目次】
1 介護と「わたし」(8月23日更新)
................................................
(1 介護と「わたし」)
伊藤 村瀨さんとお話しするのは、若干気まずいような気が......(笑)。
村瀨 意外とあまり話したことないですよね。お手紙はかなりやりとりしましたけど。
伊藤 ミシマ社という出版社のサイト上で、すごい密度で往復書簡を交わしていて。だからわたしの中で勝手に村瀨さん像が出来上がっちゃってるんですよね。
村瀨 僕もずっと伊藤さんの文章で、濃密な時間を過ごしてました。でも肉声でやりとりするのはすごく緊張する。
伊藤 なんか近すぎる感じがして(笑)。この場でも手紙のように、ちょっと考えながら話したいなと思っています。
賞を獲るなら芥川賞!
伊藤 この『シンクロと自由』は、手紙を交わしているときに同時並行でご執筆されていたんですよね。
村瀨 そうなんです。だから伊藤さんの影響をすごく受けてるんですよ。
伊藤 本が出て、まだ1週間ぐらいのタイミングですね。これから読もうという方もいらっしゃると思うので、内容についてもこの場で語っていただけたらなと思います。
最初に、わたしが読ませていただいた感想を僭越ながらお話しすると、この本がもし賞を獲るとしたら、芥川賞かなって。
村瀨 ハハハハッ。
伊藤 小見出しを抜いて読んだら小説、っていう感じがして。それはいろいろ理由があります。まずわたし自身の関心からいくと、「文学をケアの問題として読む」ということが最近ちょっと流行ってますよね。古典と言われているような作品を、「ケア」という視点から読み直す。ただわたしが文章を書く中で最終的にたどり着きたいと思っている場所は、ちょうどその逆なんです。ケアの問題の中に、文学じゃなければ語れないものがあるんじゃないかと。そこがめちゃくちゃ面白いと思っているんです。
わたし自身の本だと『手の倫理』(講談社選書メチエ)のいちばん最後に「不埒な手」という章があります。最初はあの章がない状態で終わりそうだったんだけど、「なんか足りない......文学が足りないんだ!」と思ったんですよね。それで最後に付け足したのが、ケアをしている人がいろんな体に触れあう中でどうしても性的な自分の記憶がよみがえってしまうこと。つまり職業倫理上あってはならないことが、その線を体が踏み越えていく。それがどうしても消せないこととして起こるという話なんです。
そういう世間的な正しさ、道徳、倫理みたいなものを踏み越えてしまう力が、おそらくケアという体を介したコミュニケーションの中には絶対含まれている。そこをないことにすると、逆にとても危険なことになると思います。怖いんだけどそこを解放すると、なにか新しい可能性が見えてくる。そういう意味でも、文学的な部分を絶対言葉にするべきじゃないかって思っているんです。
村瀨 なるほど......。
伊藤 今回の村瀨さんの本は、ダイレクトに「わたし」という問題が扱われていますね。ぼけの世界は「わたしじゃなくなる」とか「わたしがいなくなる」みたいなイメージがあると思いますが、実はお年寄りたちと関わる側の人たちの「わたし」、ケアする側の「わたし」が、お年寄りとの関わりの中ですごいところに行ってしまう。そういう、ある種のすごい逆説があると思うんですけれども、そこに踏み込まれた。
もうこの本を読んでしまったからには元には戻れない。つまりそういうヤバさ、「淡々とヤバい」みたいな感覚が読んだあとに残ったんですよね。
村瀨 僕がお年寄りの仕事をしてきて、いちばん感じてきたことって、それなんですよね。自分というものが、それこそ「ヤバいわたし」がお年寄りに引き出されていくんですよ。本当は隠しておきたかったとか、誰にも知られずにそっとしておきたかった「わたし」が、どんどん引っ張り出されちゃう。そういうことをこの本では結構書いているのかもしれないですね。
「ヤバいわたし」が引っ張り出される
伊藤 「わたし」というものを一つの軸として本を書こうという構想は、最初から意識的にあったんですか。
村瀨 どうしても介護って「わたしが介護する、あなたは介護される」「あなたは介護する、わたしは介護される」という「わたしとあなた」の関係だったような気がするんです。だけどずっとお年寄りと関わっていると、これは「ふたりのわたし」だなと思うようになったんですよね。
伊藤 あぁ。
村瀨 お年寄りは、機能障害が出て体が不自由になっていくじゃないですか。あと、いわゆる認知力が落ちていくと、体はいろんなことができるはずなのに、行為を失っていく。その最中にたぶん、行為によって支えられていた「わたしらしさ」みたいなものが失われていくように感じちゃうんですよね。
「男衆が先に入らないとダメ」とか言って、なかなかお風呂に入ってくれないおばあちゃんってたくさんいます。じゃ男が先に入ったんなら後で入ってくれるんだなと、ちょっと髪を濡らしてバスタオルかなんか掛けて「僕、先に入ったからどうぞ」と言っても、「わたしは風邪をひいております」とか、結構平気で先に入らないウソをたくさん並べられるんですよね。
食べきれない量のごはんが盛られてくると、最初から手をつけない人もいます。「箸をつけたら最後まで食べないと申し訳が立たない」みたいな感じなんですね。そういう人は小鉢で出さないといけないし、あとからお代わりができる量でつぐみたいなことをするわけですが。
本当に、「ずっとこうやってこの人生きてきたんだなぁ」って思うことがたくさんあります。その行為の中に「わたし」がたぶん宿っているんですね。でも結局、歳を取ってできなくなる。それを一緒にもう一回再生することになるんですよ、ふたりでね。
伊藤 ああ、ふたりで。
村瀨 はい。でも僕には僕の食べ方がある。それが最初ぶつかり合いながら、それぞれの「わたし」が抗い合いながら、やがて両方の食べ方が統合されていくみたいな感じです。もちろんお年寄りの行為を取り戻すのを僕が手伝うわけだから、その方寄りの食べ方にはなるんだけど、どこか「こっちの食べ方も吸収せざるを得ない」みたいなところもある。そんなふうにして一つの行為が成り立つので、僕の中には「ふたりのわたし」だなぁていうイメージがずっとあったんですよね。
それでも最終的には「ふたりのわたし」でも破綻が来るので、最後は他のスタッフも含めた「わたしたち」で乗り越えざるをえない。そのあたりを書けたらなっていうのがありました。
伊藤 お話をうかがうと、ちょっと結婚っぽいですね。結婚も、違う何十年かの習慣を背負ってきたAさんとBさんというのが、それぞれの習慣を統合させるような形で新しい習慣をつくり出して一緒に生活しはじめるところがありますよね。気づくとそれがもう一体になっていて、「ふたりのわたし」になっていくみたいなプロセスがある。
村瀨 なるほど、たしかにそうですね。
家族介護は、隠したい「わたし」が漏れ出してくる
伊藤 村瀨さんは今お母様の介護もなさってますね。この本は、家族の介護をしてる人たちにすごく響くのでは?
って思ったんですよね。家族の介護をしているときの、その「ふたりのわたし」の輪郭が切り離せなくなってくる苦しさと、「一体だったと思ったらバラバラだった」というせつなさと、そこの部分を書いてくださってるので。
村瀨 それはすごくうれしいです。家族のことって、なかなか書けないんですよね。これを読むことで何か伝わるものがあったとしたらうれしいですね。母の介護ってまた違うんですよね。他人の介護は最初から受け入れられるんです、変なことが起こってても。
お年寄りがみかんを皮ごと食べていても、ちょっとためらいながら「あれぇ、皮食べてるけどどうしよう」みたいに思う。その人が嫌な気持ちにならないようにあの皮をどう取り去ることができるんだろうかとか、あるいは「放っておいていいのかな」とか。赤の他人だと、そんなためらいがある。だけど家族ってストレートだから、皮のまま食べてたら「なにしよっとね!!」みたいな感じについ(笑)。
逃がれがたい情実があるからこそ、そこにどういう余白を入れ込むか、どうやって距離を取って赤の他人になれるかという意味では、家族介護というのは面白い。本当に出会い直しをしていくといく感じなんです。
伊藤 往復書簡の中でも、お母様のことを書かれるときは全然テンションが違いましたもんね。
村瀨 そうなんですよ(笑)。もうね、それこそ秘匿しておきたい「わたし」が漏れ出すんですね。特に夜は、赤の他人のおじいちゃんおばあちゃんの介護ですら漏れ出しますから、それはもう......。
やっぱり人間って生身の限界を超えられないんですよ。お腹が空いたとか、寒いとか、暑いとか、眠れないとかっていうのはね。介護する側もされる側も、そこにいちばん「わたし」が漏れ出す。

文学の夜、申し送りの朝
伊藤 夜っていうのも、この本の中の大事なモチーフですね。夜勤ですよね。すごく小説的な時間だなぁと思うんです。夜勤は基本、おひとりでなさるんですか。
村瀨 我々が運営している施設でも宅老所のほうは、通ってこられる人数も12人ぐらいがマックスです。その中で必要に応じて、1人2人泊まられるんですよね。そういうとき夜勤はひとりなんです。特養になってくると、夜勤者は1階と2階に分かれてふたりいるけれども、それぞれひとり10~18人ぐらいに対応することになっている。なので、基本やっぱりひとりなんですよ。孤独なんです。
伊藤 だから、よりコントロールしなきゃっていうマインドになりますよね。誰かおひとりが騒ぎ出してそれにつられて他の人も目を覚ましちゃったら、手に負えなくなるとか。
村瀨 夜勤者がいちばん恐れてるのはそれです。おばあちゃんがひとり起き出して、他の人の部屋とかに入っていったりする。自分は昼になっちゃってるから、大きな声で歌ったり他人のベッドに入り込んだりする。それがどんどんどんどん広がって、起き出す人が出てきたら、もう自分ひとりでどうしようか......と大パニックになる。
予測するからなんですね、「そうなるんじゃないか」って。予測しちゃうとパニックになって、なんとかその予測にならないようにしたい。だからお年寄りがひとりで溌剌と夜起きてくることに対して、どうしても予防的対応をしていく。そのときに自分が崩壊するっていうことが起こるんですよね。......僕はそれがすごく楽しい。
伊藤 えぇぇぇ。
村瀨 そのときは冷や汗ものなんですよ(笑)。だけどそれを朝の申し送りで職員が話したりするのを聞くのが大好きで。自分もそれを話すのが好きだったんですよ。
伊藤 申し送りという制度が毎朝あるところが、文学とは違いますね。夜はすごい文学なんだけど、それが終わると、共同体という場の中で、自分の孤独が共有される。自分が経験した怖さみたいなものを成仏させる場所でもありますね。なんか最後に「集団の時間が来る」というのが文学と違うところで、面白いなと思ったんですよね。
村瀨 夜が文学的だっていう話はすごく共感しますね。本当にそうだと思います。太陽が昇ってきて白々としてきますよね、あのね、陽の上がる安堵感っていう、ふふふ、そして人が来る安堵感。「もうちょっとで来る!」っていう。
伊藤 もうちょっとで来る......ハハハハハッ。
村瀨 あの時間は至福なんですよ。日頃は「あの人とはなんかちょっと介護観が合わない」とかね、「目指すべきケアが違う」とか言ってても、白々と夜が明けて、その人が早出で来るときにもう喜びをもって迎えますよ。
伊藤 ふふふふふ。
村瀨 よく「どうしたら意識が合うんでしょうか」とかいちばんよく聞かれるんだけど、どうやっても意識が合わないっていう人もいるんですよ。でもそんな気の合わない人ですら、あの白々とした夜が明けていくときにやって来たときには、もう堰を切ったように「こんな夜だったぁ!」「おばあちゃんが帰る帰るって言ってね!!」みたいなことをいきいきと話すんだよね。人との接点って、もしかしたらそこなのかもしれないなと思ったりします。
「キミは何回目で叩きたくなった?」
伊藤 「怖いけど楽しい」っていうのは村瀨さんの真骨頂ですね。怖いもの見たさというか、そこに何か大事な宝物を見つけていらっしゃるんだと思うんです。
『シンクロと自由』の中で、新人さんがただの報告のように申し送りを終わらせようとすると、村瀨さんが所長力を発揮して(笑)、結構すごい質問をされてますよね。なかなか眠らないおばあさんがいて、何回も起きてくるんだけど、「ところでキミは何回目でおばあさんを叩きたいと思ったの?」とか。
村瀨 そうそう。これホントはね、書いちゃいけないことかもしれないぐらいのことなんですよね。でもねぇ、それはないだろうと思うんですよ。寝なかったおばあちゃんに淡々と明け方まで付き合ってですね、それでなおかつですね、おばあちゃんの昼の睡眠状態を心配してるっていうのは......「いや、それは違う!」って。そんなふうに人のことを大切にできるだろうかって。そこにかなり過剰な無理があるというふうに僕はどうしても思ってしまう。
「過剰なわたし」を演出しなきゃいけないのは、この仕事が倫理性の高い仕事であるということだし、人間を本質的に大切にしなきゃいけないっていうことが課せられてるからです。寝ないおばあちゃんに付き合ったことで自分を見失って、ヘタしたら突き倒すんじゃないかっていう怖さを抱えた......みたいなことは、誰も言えないんですよ。それ言っちゃったら「自分はこの仕事をする資格がない」ってまた自分を責めるし、周りから責められるんじゃないかっていう怖さもある。それでみんな言えないんですよ。
だからね、22歳ぐらいの若い職員が、「むかつきました」とか、「もう顔を見たくない」「おばあちゃん、しばらくいいです!」とか言ってる姿を見ると僕はホッとする。職員たちもクスクスクスクス笑いながら聞くんですよね。笑いながら聞いて、「あぁよかった、自分のときじゃなかった」とか思ってるわけ(笑)。なんて言ったらいいかなぁ......そういう形でみんなで迎え入れてるんですよね。
それを聞いて、決して「あのおばあちゃんひどいから、みんなでいじめよっか」みたいにはならないんですよ。「じゃぁ、あのおばあちゃんをみんなでシカトしようか」みたいなことにはならないのが僕は逆に不思議なんです。倫理的な言葉で縛らなくたってそうなるんです。
村瀨孝生×伊藤亜紗『介護現場から自由を更新する!」第1回了
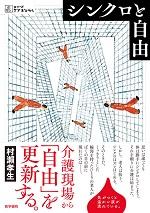
介護現場から「自由」を更新する!
「こんな老人ホームなら入りたい!」と熱い反響を呼んだNHK番組「よりあいの森 老いに沿う」。その施設長が綴る、自由と不自由の織りなす不思議な物語。
万策尽きて、途方に暮れているのに、希望が勝手にやってくる。
誰も介護はされたくないし、誰も介護はしたくないのに、笑いがにじみ出てくる。
しなやかなエピソードに浸っているだけなのに、気づくと温かい涙が流れている。






