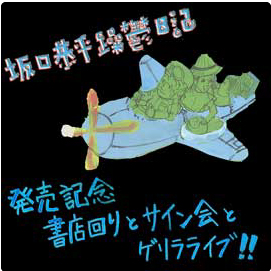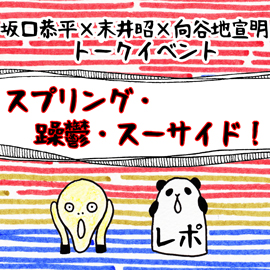かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
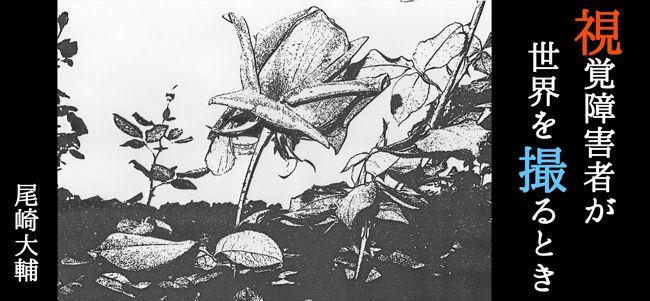
【座談会】新しい「表現」としての、視覚障害者が撮る写真
2015.5.29 update.
連載の第5回は座談会です。写真評論家・ライターのタカザワケンジさん、若手クリエイター支援に重点を置いている銀座のギャラリー「ガーディアン・ガーデン」プランニングディレクターの菅沼比呂志さんをお迎えし、「表現としての写真」という観点から視覚障害者の撮影した写真について語り合います。
★「視覚障害者の撮影した写真は、誰の作品?」
尾崎大輔(以下、尾崎):連載第3回でもお話したように、私は今、視覚障害者の山口さんが撮っている写真や他の視覚障害者の方達が撮った写真で展覧会を行おうと構想を練っています。ところが、この話をすると、よく「それは誰の作品なのですか」と聞かれます。今回はまず、この「視覚障害者が撮影した写真は誰の作品になるのか」というテーマについてお聞きしたいと思います。
タカザワケンジ(以下、タカザワ):そのテーマは法律的には答えがあるんですよね。著作物の権利は、「誰の思想やアイディア、創作性がそこにあるか」に左右されます。例えば尾崎さんが山口さんに簡単なテーマを出していても、撮影において山口さんの方が創作的内容を多く担っていれば、それは山口さんの作品です。
スロバキアに、ユジェン・バフチャル1)という有名な盲目の写真家がいます。彼は、協力者に自分のアイデアを伝えてセッティングし、撮影するという方法で創作活動を行っています。この場合も、創作の中心にいるのはバフチャルなので、写真はバフチャルの作品となります。
一般的な写真の世界でも、森村泰昌さん2)の作品のように、シャッターを押した人間と作者が別の人間であることはよくあります。アイデアと撮影全体を取り仕切った人が責任者であり、作者です。
タカザワケンジ氏
菅沼比呂志(以下、菅沼):私もタカザワさんと同感です。また、例えば山口さんが、篠山紀信さん3)にお金を払って「こういうイメージの作品を撮って、著作権は私に譲ってくれないか」という契約をすれば、それは「山口さんの著作物」になります。著作物の権利自体は売り買いできてしまうものですが、このような法律的な解釈が特に重要視されるのは、その写真が作品として売買されたり、広告に使われたり、作品集になって販売されたりする場合くらいでしょう。
★編集者としての介助者と、主体性を持った撮影者
タカザワ:視覚障害者の作品で晴眼者の作品と異なる点をあげるならば、例えば写真を選ぶ段階で、見えないがゆえに自分でOKが出せないということは特殊かもしれません。
しかし、視覚障害者と介助者の間に協力・信頼関係があり、撮影した視覚障害者が「この介助者が自分の目の代わりになってOKを出してくれればよい」と認めていれば、最終段階で介助者が写真を選んだとしてもそれは撮影者の作品なのではないでしょうか。
晴眼者の写真家でも、撮った写真を編集者やデザイナーに渡して取捨選択してもらい、作品集にすることが多くあります。「他人の写真は選べるけど自分の写真は選べない」という写真家もいます。むしろ、他者がその写真を見たときに何かを思い出したり、感じたりする反応を元に組んだ方が、写真家自身も「自分」という枠の外に出られる。これは写真ならではのことだと思います。
そもそも写っているものすべてをコントロールできないことも写真のおもしろさですよね。だから、視覚障害者の写真を作品として考えるとき、介助者は編集者やデザイナーのような働きをしているとも言えます。
菅沼:荒木経惟さん4)も、現像したフィルムをそのままポンっとデザイナーに渡して作品集を作ったりしていましたね。やはり、自分にはない視点から写真を見たいという気持ちがあるのではないでしょうか。「視覚障害者は見えないから写真が選べない」ということを、晴眼者の写真家に対する弱みとして考える必要はないのだと思います。
菅沼比呂志氏
タカザワ:結局は、どこまで撮影者に主体性があるかということです。それは写真家全般に言えることで、花の写真を撮って「きれい」で終わるのではなく、そこにオリジナリティを入れていこうという主体性があれば、その写真はその人の作品になるのです。だから、「法律的には誰の作品か」なんてケチくさいことを言わないで、今はみんなで協力して活動の質を向上していけばいいと思います。「作品が売れた場合お金をどう分配するのか!?」という問題は、後で考えましょう(笑)。
★視覚的におもしろい写真、触覚的におもしろい写真
尾崎:視覚障害者が撮った写真を「作品」として考える中では、その写真を評価することが求められることもあります。この評価も難しいものです。
タカザワ:誰に向けての作品かということでも変わってきますよね。1つは、晴眼者に写真を見せる場合、もう1つは凹凸の立体プリントにして手触りでイメージしてもらうという場合です。前述のユジェン・バフチャルは、晴眼者向けに作品をつくっています。現実世界とは異なる頭の中にあるイメージをもとに、光に注目した写真作品を作り、晴眼者に見て感じて欲しい、晴眼者とコミュニケーションをとりたいという作家です。
対して、オーストラリアのブレンダン・ボレリーニという盲目のカメラマンは、凹凸の立体写真を用いた触覚中心の作品制作をしています。触覚系の写真はメディウムとして発展途上であり、手で触ったり、目で見たり、どのように楽しむかは今後の展開に期待しています。
尾崎:晴眼者には、「写真を触る」という感覚はほとんどありません。以前に開催した展覧会では作品として凹凸の写真を展示し、「触っていいですよ」と書きましたがほとんど誰も触りませんでした。
そのときにある視覚障害者の方が「晴眼者は『見る』ことに頼りすぎている」と言っていました。たしかに、表現としての写真に求められることは、現時点では視覚的面白さとされており、目で見て価値判断をするアートとしての枠を出ていません。視覚だけではなく触覚でも何かを伝えることができれば、面白いものができてくると思います。
尾崎大輔氏
菅沼:ただ、凹凸にするためには色情報などのさまざまな要素が落とされるし、現段階では写真と凹凸の立体プリントは別物ですね。今はまだ、表現としての価値を追求するよりは、凹凸プリントをきっかけに「視覚障害であっても写真が撮れる」ということを知ってもらい、活動を広げていくことの方が、発展性がある気がします。
尾崎:何度も写真教室に参加している方の中には表現としての写真を撮りたいと思われる方もいます。その中における、視覚障害のある写真家としてのパイオニアの出現も活動を広げる一歩だと思います。しかし、私が写真教室の活動を始めた当初も、表現としての写真ではなく家族や旅行など生活の中での写真に主眼を置いていましたし、やはり導入はそこにあると思います。
★言葉がいらない写真、言葉が必要な写真
尾崎:視覚障害のある撮影者の中には、凹凸にしたときに触ってわかる被写体しか撮らない方もいます。凹凸の立体プリントは、言葉による説明なしでは理解が難しいものですが、人によっては男女の差も髪の長さで判別したり、「歯が出ているから笑顔だ」とわかる方もいます。
タカザワ:逆に凹凸をすごく簡素化して、鑑賞者にイメージしてもらってもおもしろいのではないでしょうか。最近の写真のトレンドの1つに、「情報量をあえて少なくする」というものがあります。普通の写真は情報量が多すぎるので、情報量を減らした写真で攻めてみるのも可能性の1つかと。
尾崎:写真が持っている情報量の多さには驚かされることがあります。目で見てわかっていたつもりでも、視覚障害者が撮った写真に何が写っているのかを撮影者に言葉で説明しているときに、あらためて気づくこともたくさんある。それも踏まえて、言葉と写真の関係は難しい。先天的視覚障害者の方とやりとりをしているときには、同じ言葉を使っていてもギャップを感じたこともあります。
菅沼:言葉と写真という観点から言うと、写真を学校で教えているとき、教材に使う写真を説明する前後では見方が変わったという学生も多くいます。人間は何かを考えるとき、いつも言葉を使って考えているし、どうしても言葉からは離れられないですよね。
タカザワ:写真の中身を言葉で伝えることに関しては、伝達ツールとしての写真なのか、表現としての写真なのかによって違ってきます。伝達ツールの写真は情報量が多いほうがよいですが、表現としての写真は情報量の少なさが魅力になることもあります。
だから、先ほどの「写真を凹凸にすると言葉による説明が必要になる」という考えは、写真を伝達ツールとすることに引っ張られてしまっています。言葉じゃなくて、何枚かの凹凸写真を組み合わせたり、言葉がなくても触っただけで何かを感じさせようとしたりする工夫が、発想のしどころ。あくまで言葉が必要だという前提に立つと、失敗もあります。一般の写真家が撮る写真も一緒で、言葉と写真の関係を長々と書いてダメになる作品もいっぱいありますよね(笑)。
★写真の可能性を広げ、とらえ直す
タカザワ:写真評論家としての立場から言うと、視覚障害者の写真という分野は、写真の可能性を広げてくれるものとしても面白いと思うんです。
菅沼:以前に尾崎さんが話していた、カメラのレンズを触った視覚障害者の方が、「どうしてレンズは丸なのに、写真は丸じゃなくて四角なのですか」と言ったという話は、なるほどと思いました。私たち晴眼者にとって、写真は四角であることは自明なことで、そのような柔軟な発想は出てこない。私たちが立つことができていない別の視点があるのだな、ということに気づかされます。カメラも進歩しているので、その技術革新によって視覚障害者の方達の写真生活もよいように変わっていくと思いますね。
上記の話を聞いた尾崎氏がつくってみた、レンズのように丸いソフトクリームの凹凸写真。
タカザワ:視覚障害者の写真に関して、今日1つ問題がはっきりしたのは表現としての写真と伝達ツールとしての写真を分けたほうがいいということですね。個人的には伝達ツールとしての使われ方に興味があります。周りの人に見せることでもコミュニケーションツールになり、見える人と見えない人の壁に穴をあけるという役割を担う可能性があるということは発見でした。
尾崎:この活動は今後も続けていきますので、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
〈今回登場した写真家たち〉
1)ユジェン・バフチェル:スロヴァキアの盲目の写真家。13歳の時に失明。光を用いた白黒の幻想的な写真が特徴。
2)森村泰昌:日本の現代美術家。セルフポートレートの手法を使い、自ら世界の有名な絵画や有名人を表現する作品が有名。
3)篠山紀信:日本の写真家。宮沢りえのヌード写真集「Santa Fe」などのグラビアカメラマンとしても有名。
4)荒木経惟:日本を代表する写真家。「アラーキー」の名称でも有名。妻、緊縛ヌード、空、食事などさまざまな被写体の作品があり、写真集は私家版を含め400冊以上を発表している。
プロフィール
タカザワケンジ
写真評論家、ライター。1968年群馬県生まれ。雑誌に評論、インタビュー、ルポを寄稿。富谷昌子写真集『津軽』の編集と解説、『Study of PHOTO -名作が生まれるとき』(ビー・エヌ・エヌ新社)日本語版監修など。東京造形大学非常勤講師。
菅沼比呂志
ガーディアン・ガーデン/プランニングディレクター、武蔵野美術大学非常勤講師。1963年栃木県生まれ。’87年同志社大学文学部卒業、株式会社リクルート入社。’90年ガーディアン・ガーデンの設立に参加。以後、若い世代の新しい表現を求めた公募展『ひとつぼ展』(’92〜2008年)、「1_WALL」(’09年〜)、新たなドキュメンタリーを模索し、日本を記録するプロジェクト「フォト・ドキュメンタリー『NIPPON』」等の企画制作に携わる。