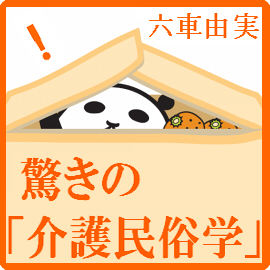かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
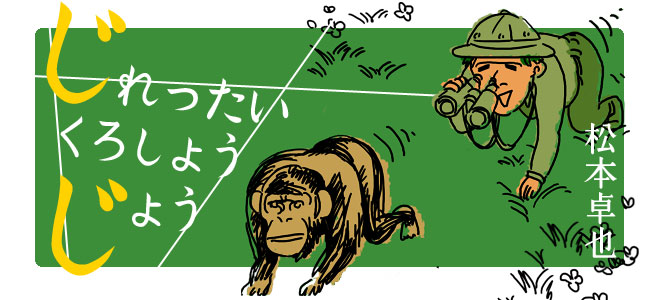
第2回 もれ出してくる個性
2014.4.21 update.
1987年生まれ。京都大学大学院理学研究科・博士後期課程在籍。2014年4月より日本学術振興会特別研究員(DC2)になる予定。タンザニアの森で約2年のフィールドワークを終え、現在は日本で博士論文を必死に執筆中。趣味は通学途中の読書(漫画を含む)と、大学の体育の授業で学部生に混じって楽しむバスケットボール。
『日本のサル学のあした』(京都通信社)のコラムを執筆。初連載です!
2010年7月8日、私はその日初めてタンザニア・マハレ山塊国立公園の森へ、チンパンジー調査に入った(※1)。時刻は午前7時35分、天気は晴れ。現地のアシスタントは慣れた様子で先陣を切り観察路を歩いていく。私は彼の後ろを歩きつつ、覚えたてのスワヒリ語を必死で駆使しながら、進んでいく道の名前、横切る川の名前、大きく実った果実の名前を教わる。「観察路R1を南へ。Kasiha川、Sinsiba川を渡って、地点M11に到着。途中で見つけたIkolyokoは桃大の果実。チンパンジーが食べるらしい。」私のフィールドノートの最初のページは、今では聞き慣れた名前とそのメモの羅列だ。
調査初日の7月8日は、タンザニアでは乾季にあたる。湖岸の落葉樹林を貫く観察路は落ち葉で覆われており、どこか日本の秋を思わせるような色合いだった。そして、ゆっくり歩調を緩めて立ち止まったアシスタントの背中越しに、私は初めて野生のチンパンジーを見た。単に印象を書いてしまえば、黒く大きな塊が藪を抜け、観察路に出てきた、という感じであった。想像より大きい(※2)。黒いチンパンジーは、びくつく私の脇を悠然と歩き去って行った。
「そいつが『アロフ』だ」と、アシスタントが教えてくれた。『アロフ』とは、チンパンジーの名前である。チンパンジー観察者として、私が一番初めに取り掛かった仕事は、観察対象集団に属する約60頭のチンパンジーの顔と名前を覚えることであった。覚え始める手掛かりになるのは、目立つ傷、ほくろ、毛のはげ、などである。しかし、『友達の顔をどのように覚えているか』という問題について改めて考えてみると、「このホクロの位置は……あ、○○さんか」と思い出している人はそういないだろう。チンパンジーを識別するのも同様で、あくまで初めの手掛かりは外的特徴でも、慣れさえすればもうアロフの顔を説明(記述)することはできなくなる。「アロフは……アロフだよ」と言うしかなくなるのである(※3)。
このように個体に名前(もしくは番号)を付け、その個体の行動を記録する手法は「個体識別」と呼ばれる研究手法である。もし仮に、集団に属する任意の個体が、同じ状況で同じような行動をするのであれば、個体識別をしたとしてもあまり意味がないだろう。しかし、例えば親子にのみ見られる行動や、高順位のオスが高頻度でする行動、といった「行為者の情報があって初めて納得のいく解釈ができる行動」は、個体を識別し、「誰が」「どうした」という対応をつけなければ知り得ない。霊長類学においては、その最初期から採用されている研究手法である(※4)。
動物の顔(外的特徴)を見分けるなんてできるのか、と質問されることがよくあるが、毎日顔を突き合わせていれば難なく覚えられるものだ(※5)。慣れてくると、例えば親子で顔が似ている、この家系はたいてい釣り目だ、このオスは体臭が強い、といったこともわかるようになる。
これから観察事例を紹介していくにあたって、なるべくチンパンジーの名前で個体の区別をつけることにしたい。登場人物(チン物?)の名前を記述することは、少なくとも科学論文においては稀なことかもしれないが、私にとっては「第3位オス」「オトナメス」といった表記よりは、『アロフ』『サリー』と呼ぶ方がしっくりくるのである(もちろん、必要な個体情報は補足する)。
さて、調査を開始して1ヶ月を過ぎたころのことである。
【観察事例①】イライラする「ルビコン」:2010年8月12日14時35分より
遊び盛りのコドモメス「フィンビ」が、観察路に座っている若いオトナメス「ルビコン」の近くの木に登り始める。4mほど登った後、隣の細い木を掴み、体重をかけてしならせ、枯葉のたくさんついた部分を地面のルビコンにぶつける。細い木は折れ、そのままルビコンにばさーっとかかってしまった。フィンビはさっと木の上へ。ルビコンは覆いかぶさっていた枝を払いのけ、ほんの一瞬フィンビを追いかける様子を見せるが、すぐにあきらめ、フィンビの登った木の幹を掴んでがんがんと蹴る。
私はこの『ルビコン』の凄まじい蹴りっぷりを見て、腹を抱えて笑ってしまった。
ルビコンがなぜあのような蹴りっぷりを見せたのか、解明することは容易ではない。木を揺らして、『フィンビ』との遊びを継続しようとしていた可能性もある。ただ私は、ルビコンが「イライラして物にあたったのだ」と、直観的にわかったような気がしてしまったのである。ひとしきり笑った後、子どものおふざけにイライラを露わにするようなチンパンジーを、私はほとんど初めて観察したのだ、ということに気が付いた。コドモ同士が遊んでいて、次第にエキサイトしてきて喧嘩になる、ということはままあるが、オトナのチンパンジーがコドモ相手に本気(マジ)になってしまう事例はほとんど観察したことがない。

この事例を観察したのは、アロフと初対面してから約1ヶ月後のこと。このころにはもうたいていの個体の顔を覚えていて、挨拶や毛づくろい、食物の分配などチンパンジーの一般的な行動パターンの輪郭を把握できつつあった。そして、このルビコンの事例を観察してからは、「一般(化)」だけでは語り尽くすことができない行動が、チンパンジー観察時にはいくらでも出てくる、ということに自覚的になったように思う(※6)。つまり、チンパンジーの「個性」と呼ぶべきものを、日々の観察で実感できるようになってきたのだ。
しかしそこには、ルビコンが「特殊な」「例外的な」「異端な」チンパンジーだったのではないか?そもそもルビコンについて知ることは、そのままチンパンジーについて知ることになるのか?といったジレンマが常につきまとうようになってしまった(※7)。つまり、チンパンジーを観察し、行動データをフィールドノートに書き入れながら「じれったさ」を覚えるようにもなったのである。
今では、チンパンジーの森で過ごした期間が約2年になった。『ルビコン』はおそらく再び別の集団へと移籍し、その後の様子を知るすべはなくなってしまったが、観察対象集団に属する約60個体のチンパンジーたちは、今なお私の眼に個性豊かに映っている。彼らの行動をどう記述・分析・報告すべきか、未だ確信の持てる方法論は確立できていないが、チンパンジーの個性や、果ては、その個体の歩んできた歴史、といったものに寄り添い、向き合えることこそ、長期フィールドワークの魅力なのだろうと実感している。その例としてはちょっとあんまりな気はするが、私と感動の(?)初対面をはたした『アロフ』は、緊張すると自分の乳首を手でいじる、という変な癖の持ち主だったことも明らかになっ(てしまっ)た。
【本文註】
(※1)この日私は、調査初日にしてチンパンジー観察用のマスクを忘れたことに森を歩いている途中で気付き、慌ててキャンプに引っ返すという失態を演じているが、本文では割愛する。ちなみに、このマスクはヒトからチンパンジーへ病気が感染することを防ぐためのもので、日本で広く売られている普通のマスクである。
(※2)チンパンジーの体重は、成熟したオスで40kgから50kg、メスで30kgから40kgである。毛を逆立てるとますます大きく見える。動物園のお客さんがチンパンジーを見て、ゴリラと間違えてしまうこともあるそうだ。
(※3)実際、新しく集団に加わったチンパンジーのことを他の研究者に伝えなければならない場面で、とても苦労する。その点、写真はとても便利である。
(※4)この個体追跡法によってニホンザルが複雑な社会を営んでいることが明らかになり、日本の霊長類学が注目を集めるきっかけとなった。
(※5)犬と一緒に生活している人が、その犬の顔を見分けられるようになる、のとほとんど変わらない。もっと言えば、人の顔を覚えるのとほぼ変わらないプロセスである。ちなみに、世の中にはキリンやワラビーの個体識別をしている研究者もいる。
(※6)現地のキャンプでは、他の研究者と生活を共にすることがある。夕飯のときなどに交わされる会話は、主にチンパンジーの噂話である。「あいつまたキーキー騒いでたよ」「ああ、あいつはそういうやつだよね」といった具合。
(※7)話を変に混ぜ返してしまうが、私から見てルビコンはかなり「変な」顔をしていた。私のノートには、ルビコンを識別する際のメモとして、とてもチンパンジーとは思えない似顔絵と共に「カエル顔」と記されていた。