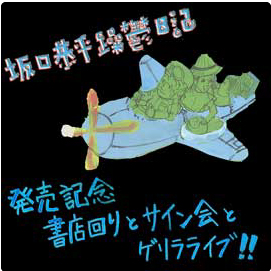かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
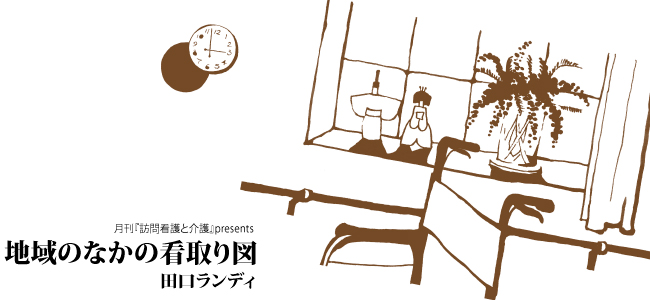
11-3 死にゆく人と対話する︱家で看取るということ〈その4〉
2014.1.29 update.
『訪問看護と介護』2013年2月号から、作家の田口ランディさんの連載「地域のなかの看取り図」が始まりました。父母・義父母の死に、それぞれ「病院」「ホスピス」「在宅」で立ち合い看取ってきた田口さんは今、「老い」について、「死」について、そして「看取り」について何を感じているのか? 本誌掲載に1か月遅れて、かんかん!にも特別分載します。毎月第1-3水曜日にUP予定。いちはやく全部読みたい方はゼヒに本誌で!
→田口ランディさんについてはコチラ
→イラストレーターは安藤みちこさん、ブログも
→『訪問看護と看護』関連記事
・【対談】「病院の世紀」から「地域包括ケア」の時代へ(猪飼周平さん×太田秀樹さん)を無料で特別公開中!
「どこで死にたい?」
私は、おじいちゃんの耳元で、つぶやいたんです。2人きりのときでした。
夫がいたら、とてもこんなことは聞けなかったと思います。私とおじいちゃんだけだったから、率直に聞けたんです。
「おじいちゃん、これから本当に大切なことを話すよ。これはね、どうしても聞いてもらいたいことなんだ。おじいちゃん、私の声が聞こえますか?」
おじいちゃんは、うんうんと小さくうなずきました。でもそれは、単に声に反射しているだけのようにも見えました。
「おじいちゃん。おじいちゃんはもうすぐ死ぬかもしれない」
そう言ったとき、ものすごく怖くなりました。背筋がぞくぞくして、どっと脇の下から冷たい汗が噴き出てくるのがわかりました。自分まで死んでしまうようなそんな気分になりました。
「おじいちゃん、亡くなるときは病院に戻る?」
おじいちゃんは、口をあんぐり空けて、ぼんやりしています。
「おじいちゃん、家にいる?」
なにか、とても静かだけど強い力がおじいちゃんの中に蠢いているような感じがしました。
「おじいちゃん、どこで死にたい?」
おじいちゃんは、ゆっくり顔を傾けて、初めて私の顔を見ました。そしてはっきりと言いました。
「病院はいやじゃ。家におる」
そうか、と思いました。そのときのおじいちゃんの目は、暗い小さな穴のように見えました。私はおじいちゃんと目が合うといつも怖かったです。なにか、とてもとても深い谷底をのぞき込んだような、足のすくむような、そんな感じがしたんです。
「わかった……。お家にいようね」
私は引き受けたんだ、そのとき、はっきりと自覚しました。
おじいちゃんの看取りを引き受けたんだ。
「おじいちゃんに、どこで死にたいかって聞いたの」
夫にそう言うと、夫は「ええっ?」と驚いていました。夫は私が実父を看取るときもずっと側にいたので、私ならそういうことを聞けるだろうと思ったと言います。でも、自分ではとてもそんなこと口に出せない……と。
そりゃあそうですよね、本当に死にそうな人に、死ぬときはどこで死にたいって、なかなか聞けないです。怖いですから。
「おじいちゃんは、病院はいやだって言ったよ」
「そうか、やっぱりなあ」
「家におるって……」
「そうだよなあ。でも、はっきりそう言ったの?」
「はっきり言った。私の顔を見てそう言った」
夫は「話ができるのかな」と半信半疑な感じだったので、2人でもう一度おじいちゃんのところに行きました。
「おとーさん、おとーさん、聞こえる?」
そのときは、おじいちゃんは夢の中にいて、意味不明のことを一生懸命に叫んでいました。夫は、耳の遠いおじいちゃんに大きな声で叫ぶように話しかけました。でも、それでは通じないことを、私はなんとなくわかっていました。
「話しかけるときは、耳元で、そっとささやくように、やさしく、ていねいに話しかけるほうがいいよ」
すると、夫は少し照れてしまうのです。男の人はそうなのかもしれません。なにか抵抗があるようなのです。それまで、自分の父親とそういう密なコミュニケーションをしてこなかったから、突然にはできないんだな、と思いました。
それはとてもよくわかります。私も自分の父親とはいろんな葛藤があったので、素直に父と向き合うことができるようになるまで、苦しかったです。相手がもう末期がんだとわかっていても、父との長い年月にわたるつらい思い出が邪魔をして、もうすっかりいろんな業を捨ててしまった父を、ありのままの清らかな者として受け止めるまでに時間がかかりました。
夫の父であるおじいちゃんは私とは血のつながりがないゆえ、かえってありのままに受け入れることができたのかもしれません。
せん妄状態の人に、怒鳴るような大声で話しかけてはいけない。
耳元で、ゆっくり、そっと、やさしく、ていねいに、語りかけなければいけない。
でも、多くの人は、たぶん気持ちが動転していることもあるのでしょうが、大声で叫んでしまいます。名前を連呼したり、おーい!と叫んだり……。これでは、コミュニケーションできないのです。
伝えたいことは明確でなければいけない。切実でなければいけない。そして、本心でなければいけない……。そうでなければ、もう、遠くに行こうとしている相手を呼び戻すことができないのです。
「何か伝えたいことは?」
私は、その後、もう一度だけお父さんと会話のようなものをしました。
やはり2人きりのときでした。もう息も荒くなっていたお父さんに聞きました。
「何か伝えたいことは、ある?」
顔をのぞきこむと、おじいちゃんの目がじっと私の目を見つめました。このときも、目の奥の暗い沼にすーっ吸い込まれていってしまいそうで、逃げ出したいような気持ちになりました。
何かあるんだ……と思いました。でも、おじいちゃんは何も言いませんでした。そのとき私が感じたのは、とてつもない淋しさでした。おじいちゃんは淋しいんだ、淋しくて淋しくてたまらないんだ……そう感じました。その淋しさは、おばあちゃんが亡くなって1人ぼっちになったからとか、そういうことではなく、もっとおじいちゃんの人生の根源的な淋しさのような、そんな気がしました。
私はいまでも、このときのおじいちゃんの目、あの暗い沼のような目を思い出すと、ものすごく淋しくなってしまうのです。私たちは一緒に住んではいたけれど、おじいちゃんは孤独だったのだろうな。その孤独を癒してさしあげることはできなかったんだな……と、そう思うのです。
もしかしたら、おばあちゃんと一緒にいてもおじいちゃんは孤独だったのかもしれません。
戦争で何があったかわかりませんが、おじいちゃんはときどき夜中に大声で叫んでは飛び起きて、家の中を走ったりしていました。私たちの知らない恐ろしいことを経験していたのかもしれません。それはとうとう語られることがなく、おじいちゃんの心の裡に秘められたままでした。
誰にも理解できない何か、を心に抱えている人は多いと思います。そういう重荷を亡くなる前に聞いてあげることができたらいいと思うのですが、私にはその力がありませんでした。
⦿
夫と相談して、他県に嫁いでいる2人のお姉さんたちに連絡しました。一刻もはやくお姉さんたちにこの状況を知ってもらい、家で看取ることを納得してもらわなければと思ったからです。
連載第11回了

いよいよ高まる在宅医療・地域ケアのニーズに応える、訪問看護・介護の質・量ともの向上を目指す月刊誌です。「特集」は現場のニーズが高いテーマを、日々の実践に役立つモノから経営的な視点まで。「巻頭インタビュー」「特別記事」では、広い視野・新たな視点を提供。「研究・調査/実践・事例報告」の他、現場発の声を多く掲載。職種の壁を越えた執筆陣で、“他職種連携”を育みます。楽しく役立つ「連載」も充実。
12月号の特集は「訪問看護の"プラットホーム"戦略?」。2009年度からの4年間で10億円が計上され、30道府県市が取り組んだ「訪問看護支援事業」。その結果は、新規利用者が増えた! 訪問件数が増えた! サービスの質が上がった! 何より訪問看護どうしのつながる力が強まった! これを礎とした次なる展開も続々! これらのディテールから、訪問看護のプラットホーム(基盤)をますます強固にし、そして拡げていく戦略を探ります。