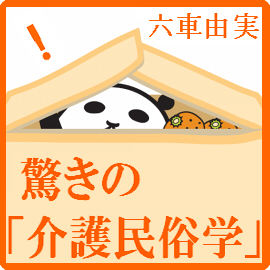かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
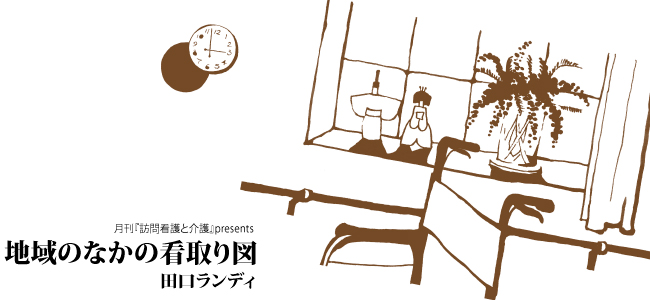
9-3 帰ってこれなかったおばあちゃん−家で看取るということ〈その2〉
2013.11.20 update.
『訪問看護と介護』2013年2月号から、作家の田口ランディさんの連載「地域のなかの看取り図」が始まりました。父母・義父母の死に、それぞれ「病院」「ホスピス」「在宅」で立ち合い看取ってきた田口さんは今、「老い」について、「死」について、そして「看取り」について何を感じているのか? 本誌掲載に1か月遅れて、かんかん!にも特別分載します。毎月第1-3水曜日にUP予定。いちはやく全部読みたい方はゼヒに本誌で!
→田口ランディさんについてはコチラ
→イラストレーターは安藤みちこさん、ブログも
→『訪問看護と看護』関連記事
・【対談】「病院の世紀」から「地域包括ケア」の時代へ(猪飼周平さん×太田秀樹さん)を無料で特別公開中!
東日本大震災と並行して
私はおばあちゃんがもっとゆっくりと過ごせる場所が必要だと思いました。それは、家以外にはありません。いよいよ在宅かなあ……と夫と話し合いました。
そのためには、家を改修しなければなりません。在宅サービスの手配なども必要です。経過を見ているうちに、4か月が過ぎました。その間に、3・11の東日本大震災がありました。
世の中が放射能でパニックになっているとき、おばあちゃんは失語症でパニックになっていました。私は、その両方でパニックになっていました。
計画停電もあり、町中が混乱していて、こんな時期に在宅介護に踏み切るなんて無理だ、と思いました。とてもそんな覚悟はくくれません。日に3時間の停電、それだけで生活がめちゃめちゃです。夕ごはんは、ロウソクを灯して食べました。信号機も動きません。スーパーの食材も、みんなが買い占めるので、棚ががらがらでした。
テレビでは繰り返し津波の映像が流れ、死者の数は日に日に増えていきます。でも、おじいちゃんはこの大災害にまったく興味を示しませんでした。
「なんや、大変なことが東北で起こってるなあ……」
朝ごはんのとき、テレビを見ながらぼんやりとつぶやきます。
「津波でたくさん人が亡くなったのよ」
「そうか、かわいそうになあ……」
おじいちゃんにとっては、おばあちゃんが治るのかどうか、それだけが気がかりのようでした。おじいちゃんの関心は、おばあちゃんにしかありませんでした。
「はやく家に帰してやりたいなあ……」
「でも、おじいちゃん、余震も続いているし、病院が一番安全かもしれないよ……」
救急で入院した病院からは、「もうこれ以上、退院を引き延ばすのは無理」と転院を言い渡されていました。最初はリハビリをがんばっていたおばあちゃんでしたが、次第にリハビリを拒否するようになっていました。やはりしんどいのだなあ……と思いました。
「田口さん、リハビリですよ」
と看護師さんに言われても、反応しません。口をぎゅっと結んで嫌だという顔をします。
「今日は具合がよくないみたいですね」
そんな日々が続き、おばあちゃんは転院することになりました。転院先は、リハビリ設備が充実しているという近所の病院です。その頃には、おばあちゃんは「胃ろう」になっていました。
「胃ろう」についても、私は抵抗しました。ですが、病院から説得されて押し切られた……というのが私の偽らざる心境です。
おばあちゃんが救急車で搬送されたとき、病院の医師から「興奮して点滴の管などを抜いてしまう可能性もあるので、夜間だけ拘束をさせていただけないでしょうか」と言われました。
おじいちゃんは、何を言われているのか意味がわからない……という顏で夫を見ました。夫は「しょうがないよね」という目で私を見ました。
「おばあちゃんをベッドに縛りつけるなんてイヤです」
正直に答えると、病院スタッフの方たちは困ったな、と顔を見合わせました。
「ですが、夜間にもし何かあった場合に、生命に関わることがあり……」
「それはわかります。たぶん、このような状態で運ばれてきた患者さんを拘束するというのは、この病院の決まりなのでしょう。ですから、イヤだと言ってもどうしようもないことでしょうし、先生の一存でどうなるというものでもないのでしょう。ですが私は、こんなに弱っているおばあちゃんを縛るのは、痛々しくてイヤなのです。拘束しないでくれ、と言っているのではありません。私の正直な気持ちをお話しています。従うしかないことなら従います。でも、好きで従っているわけではありません。それは家族の本意ではないことをちゃんとわかっていただきたいので、あえて言っています」
たぶん、まだ20歳代後半の若い医師は「そうですか……」と黙り、しばらくして「よくわかりました」とお答えになりました。
翌日、私が病院に行くと、昨日と同じ集中治療室におばあちゃんは眠っていました。そして、その日の午後には一般病棟に移りました。おばあちゃんの荷物を病棟に移す準備をしていると、昨日の医師がやって来ました。
「昨夜ですが、私たちで可能なかぎりおばあさんの経過観察をしていきました。極力、拘束をしない方向で努力したつもりです」
そうおっしゃったのです。
「それは、本当にありがとうございました……」
「いいえ」
その医師とは、病院に行っても二度と会うことはありませんでした。でも、うれしかったです。病院に勤務する人たちも、きっと良い医療、良い看護をめざしてこの仕事に就かれたのでしょう。ただ、合理的に物事を進めなければならない病院組織の事情というものがあり、個人ではどうしようもないことがあるんでしょう。ずいぶんといろいろな病院にごやっかいになったので、医療に従事している人たちが抱える矛盾もわかります。
日々の仕事のなかで、最初は疑問に思ったことがだんだん麻痺して当たり前になってしまうということもあるでしょう。だから、患者のほうも、わがまま……というのではなく、思いをしっかりと医療者に伝える努力を、続けなければいけないなあと思います。
たった一日の帰宅
転院する前に、どうしてもおばあちゃんを一度家に連れて帰りたい、と思いました。そこで外泊許可を申請しましたが、認められませんでした。なぜだろうと思いましたが、「何かあっては困る」ということでした。それで、日帰りの帰宅となりました。
その日は、秋を感じさせるやさしい風が吹いていました。よいお天気で、空気もからっとして、空は真っ青でした。夫がおばあちゃんを背負って家に入り、いちばん風通しのいい居間でおばあちゃんを囲んで家族で過ごしました。
なんだかこれが、生きてこの家に帰る最後になるような気がしていたのです。転院したら、もうおばあちゃんは家に帰ってこられないような妙な予感がしていました。とにかく、おばあちゃんの意識がはっきりしていて、気持ちが通い合ううちに、おばあちゃんを家に戻したい、と思ったのです。
なぜかはわかりませんが、私は身近な人が亡くなるときはわかります。兄が亡くなったときも、母が亡くなったときも、父が亡くなったときも、亡くなる前にサインがあり、「ああ、亡くなるのだ」と感じてしまいます。最初は、そういう自分をとても冷淡な人間なのではないか……と責めていました。もしかしたら私のなかに、家族の死を望むような恐ろしい一面があるのではないか……と怖くなったりもしました。
それは予感というような曖昧なものではなく、はっきりとした確信としてすとんと心に降りてくるのです。啓示のようなものです。そういうとき、なぜか少しも悲しくありません。あまりにも「すとん」と降りてくるので、「ああ、そうなんだな……」と、受け入れてしまうのです。
もうずいぶんと肉親や友人を看取ってきたので、この「啓示」のようなものが降りてきたときは、自分を責めたりせず、素直に受け入れて生きている時間を一緒に過ごそうと思うようになりました。
おばあちゃんのときも、おばあちゃんの転院先が決まった……と聞いたとき、ああ、そこからおばあちゃんは戻ってこない。リハビリなどできるわけがない。転院したら帰ってこられない……と思ったのです。
震災から半年が経っていました。
在宅看護は可能だろうか?
家で看取ることは可能だろうか?
世の中は、まだ放射能汚染や津波の不安でぐらぐら揺れていました。
きっと日本中に、同じように病気の人や老いたご両親を抱え、途方に暮れている人がたくさんいるのだろうなあ……と思いました。
生きていれば、いま目の前に起こっていることに精いっぱいです。それが人の生死に関われば余計です。原発は止めたい。でも、あの計画停電には本当にまいりました……。赤ちゃんや病人、老人のいる家はみんな大変な思いをしたと思います。
たった一日の帰宅。
私は、ずっとおばあちゃんのそばで編み物をして過ごしました。
編み物は、黙って人に寄り添うときに便利なのです。編み物や裁縫、刺しゅう……。こういう手作業をしていると、付き添うことが苦にならないのです。自然な気持ちでずっと何もしゃべらずとも、そばにいることができます。
私は家族の靴下を編んでいました。おばあちゃんが元気な頃には、おばあちゃんも履いてくれました。毛糸をたぐる手元を、おばあちゃんはじっと見ていました。娘や夫のことも、じっと見ていました。風がさわさわ吹いて、おばあちゃんは目を細めました。
そして、やっぱり、おばあちゃんが生きて家に戻ってくることはありませんでした。
第9回了

いよいよ高まる在宅医療・地域ケアのニーズに応える、訪問看護・介護の質・量ともの向上を目指す月刊誌です。「特集」は現場のニーズが高いテーマを、日々の実践に役立つモノから経営的な視点まで。「巻頭インタビュー」「特別記事」では、広い視野・新たな視点を提供。「研究・調査/実践・事例報告」の他、現場発の声を多く掲載。職種の壁を越えた執筆陣で、“他職種連携”を育みます。楽しく役立つ「連載」も充実。
9月号で大賞を発表した懸賞論文「『胃ろう』をつけた“あの人”のこと」。10月号では全国から多数ご応募いただいたなかから、訪問看護師さんの作品を中心にご紹介します。かけがえのない“あの人”との物語と個性豊かな地道な取り組みの数々から共通して見えてきたのは、一看護師として迷いながらも寄り添い続ける姿です。併せて「あなたは胃ろうをつけますか?」という問いにもお答えいただきました。