かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
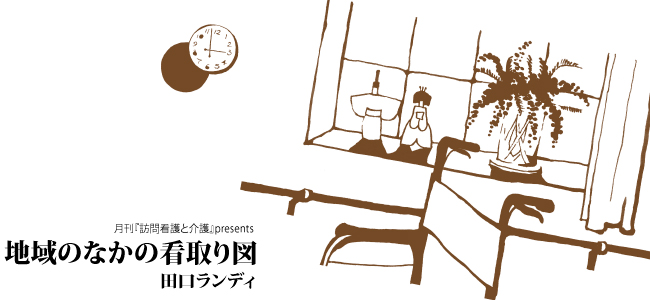
7-3 ホスピスは現世ではない−「看取り」のかたち〈まとめ〉
2013.9.18 update.
『訪問看護と介護』2013年2月号から、作家の田口ランディさんの連載「地域のなかの看取り図」が始まりました。父母・義父母の死に、それぞれ「病院」「ホスピス」「在宅」で立ち合い看取ってきた田口さんは今、「老い」について、「死」について、そして「看取り」について何を感じているのか? 本誌掲載に1か月遅れて、かんかん!にも特別分載します。毎月第1-3水曜日にUP予定。いちはやく全部読みたい方はゼヒに本誌で!
→田口ランディさんについてはコチラ
→イラストレーターは安藤みちこさん、ブログも
→『訪問看護と看護』関連記事
・【対談】「病院の世紀」から「地域包括ケア」の時代へ(猪飼周平さん×太田秀樹さん)を無料で特別公開中!
死の受容≠生きることの断念
私がホスピスを父の看取りの場として選んだのは、ここなら「父らしいままで死ねる」と思ったからでした。
でも、その判断は身勝手だったと、今では思っています。
父は、前回も書いたとおり、「がん告知」を忘れてしまうような人でした。彼には、信念があったのです。それは「生きる」という信念でした。私は父を理解していなかったのです。父という世代を。
あの第二次世界大戦を経験して生き残ってきた世代です。生きることへの強い意志があるのです。それに加えて、父は遠洋漁業に従事する漁師でした。つねに海の上で暮らし、生死をかけて生きてきた人なのです。のほほんと平和ボケしていた私とは違い、父の人生は死と隣り合わせでした。生きようという意志がなければ、生き残ってこれない人生を歩んできた人です。その父に対して「父らしいままで死ねる」場所を探した私は、父をナメていました。父に必要だったのは「父らしいままで生きる」場所でした。
これはとても大切なことだと思います。
おととし、私の友人であるKさんが、末期の肝臓がんで亡くなりました。彼女は主治医のいる大学病院から「もう治療できない、治療の可能性がなくなった。ホスピスに転院してほしい」と言われ、都内でも有名な緩和ケア病棟のある病院に転院しました。
転院して最初の医師との面談のとき、医師が彼女に「今、何を一番望んでいますか?」と質問したとき、彼女はこう答えたのです。
「また食事ができるようになりたい。もう一度、元気になりたい」
彼女が亡くなったのはその2日後、転院して3日目でした。
このホスピスへの転院を勧めたのは私です。転院に関してもアドバイスし、協力しました。彼女が死ぬまでの時間を過ごすのに、この病院なら十分なケアをしてくれると確信していました。
でも、彼女の答えを聞いたとき、複雑な心境になりました。
ここでは治療はしてくれないからです。緩和ケア病棟では、苦痛の緩和しかしてくれません。もちろん、患者が個人的に代替医療を受けることを禁止したりはしませんが、病院が治療をしてくれることはありません。
私は、自分がたいへんな考え違いをしていたと思っています。
「死を受容する」ことは「生きることの断念」ではないのです。人間は「生きることを断念」することはできません。「生きている限り」において「生きてしまう」のが生命です。
私たちは自分で息を止めて死ぬこともできないし、自分の手で首を締めて死ぬこともできないし、自分の心臓を意志で止めることもできません。
ブッダが言ったとおり、生きることへの執着は捨てることができないのです。それが人間なのです。
私の兄は、自殺して死んでいます。ひきこもりのまま衰弱死をしました。人間は食べないで死ねるのか……。兄の死は、私には謎でした。兄は死を受け入れたのだろうか、死のうとして死んだのだろうか。「死にたい」という、死への願望はなぜ起こるのか。人は死を受容できるのか。
兄がどのようにして亡くなっていったのかについて、私は小説にも書きましたし、いまだに何度も何度も繰り返し考えてしまいます。兄が死んでしまった以上、答えは出ません。永遠の謎です。
でも、兄のあと、母、父、夫の両親と看取ってきますと、だんだんと「死の受容」という言葉に対して自分が抱いていたイメージの貧困さが理解できてきました。人は少しずつ死という水に浸かっていくのであって、突然「死ぬ覚悟ができた」というようなことではないのだ……と。受容というのは、適切な言葉がないから便宜上、そのように表現しているだけであって、受け容れるというのとも少しニュアンスが違うのだ……と。
「看取る側」と「看取られる側」の間の蜘蛛の巣
私は「父が死を受け入れられるように」という間違った認識で、父の死に場所としてホスピスを選んでいたのです。私の側にとても大きな誤解がありました。それは、父がホスピスに入って最初にかけてきた電話によく表現されています。
「おい、ここの病院は変だぞ。毎日、人が死ぬんだ」
何度も繰り返しますが、私はホスピスの看護師さん他、スタッフのみなさんには本当に感謝しているのです。心からありがたいと思っているのです。その気持ちに偽りはありません。でも、それは家族の側の気持ちであって、父は私と同じではないのです。父は「生きる気まんまん」でしたから、生きる場所で生活したかったのです。私はそこがうまく理解できていなかったのです。
そして、なぜ理解できなかったかもわかるのです。
私のなかに「がん告知されたら、もう人生も終わり」というような、社会通念によって培ってきた価値観があったからです。それは頭でどんなに否定しても、かなり強烈に心に刻まれているため、考え方の癖として現われてしまうのです。
たとえば、今も、映画やテレビの主人公は「がん」を告知されたり、「認知症」になったりして、余命を必死で生きようとします。それは「余命」という特別な人生なのです。特別さゆえにドラマになるのです。そのドラマを観ている多くの人たちのなかに「余命」というドラマが刷り込まれるのです。
雑誌を見れば「若返る」「健康になる」「病気が治る」という宣伝広告が連なり、記事は「若くて健康なこと」に価値を置き、「老いて病気であること」から逃れるための方法を次々に提案してくれます。このような健康市場の宣伝戦略に、長いこと曝され続けてきた私は、健康光線に被曝していると言えます。私のなかに、私の心の深い部分に「健康でなければ意味がない、若くなければ価値がない」という思考が蜘蛛の巣を張っていて、払っても払っても、翌日にはまた同じ巣が張られているのです。
そういう生命観からなんとか逃れよう、そこから抜けようと、もがいても、気がつくと、またそこに戻っている……。そういう繰り返しで生きているのが私なのです。
何年も何年も、障害や、がん、認知症、水俣病、被爆者、そういうことがらと関わり、別の視点でものを考えるように訓練してきました。かなりできるようになりました。でも、ちょっと気を抜くと、社会の風潮にうっかり足を取られているのです。自分でも驚きます。こんなに勉強したのに、こんなに知識も豊富になったのに、それでもまだ、蜘蛛の巣が張るんだ……と。
ホスピスに父を転院させるときも、私は心のどこかで「父が安らかに死ねますように」と考えていたのです。それでいいと思っていたのです。もう、長くないんだから、なるべく気持ちのいい場所で最期を迎えさせてあげたい……と。この気持ちは、家族としての優しさだとも言えるでしょう。
私は、自分のなかにある「自分の偏向した価値観」に気づいていませんでした。だから、自分としてはできるかぎりのことをした……と思っていました。
今は、そうは思っていません。
父の気持ちになるべきだった……と思っています。最初から父の気持ちにもっと寄りそうべきだった……と。その余裕がなかったのだから、しょうがありませんが……。
あまりに目まぐるしく変わる父の状況に、現実的に対応するのに夢中で、父の内面に深く入っていく心のゆとりがありませんでした。ゆとりがないと、自分の思い込みに距離を置けないのです。
ゆとりができたのは、やっと父をホスピスに入れてからでした。父にとってホスピスは「人がどんどん死ぬ場所」だったでしょうが、家族である私にとっては「ようやく父と向き合える静かな場所」だったのです。
つまり、現在のホスピスは、患者よりも、患者の家族のための場所であるような気がするのです。スタッフは親切で家族にとってはありがたい……。だけど、患者にとってはどうなんだろうか。最後の最後まで生きることを投げないで済む環境が、必要なのではないか。その環境で、家族も精神的にゆとりをもてればベストではないのか。
しかし、在宅看護が難しい場合、ホスピスと在宅の中間のような施設が、私の父を看取る時にはありませんでした。制度が人間に寄り添っていないのです。ホスピスは「天国への旅立ち所」であって、現世ではない。それが私の実感でした。
第7回 了

いよいよ高まる在宅医療・地域ケアのニーズに応える、訪問看護・介護の質・量ともの向上を目指す月刊誌です。「特集」は現場のニーズが高いテーマを、日々の実践に役立つモノから経営的な視点まで。「巻頭インタビュー」「特別記事」では、広い視野・新たな視点を提供。「研究・調査/実践・事例報告」の他、現場発の声を多く掲載。職種の壁を越えた執筆陣で、“他職種連携”を育みます。楽しく役立つ「連載」も充実。
8月号の特集は「来たれ! 新卒訪問看護師!−千葉県訪問看護実践センター事業の試み」。「新卒に、訪問看護師は無理」。本当にそうなのでしょうか? 意外とそうでもないようです。実際に立派に務めを果たす3人の新卒訪問看護師の座談会には説得力が。もちろん、それにはステーション他のバックアップが必要です。行政・県看護協会・大学が公的・組織的に人材育成を支えた“地域連携型人材育成”に学びます。







