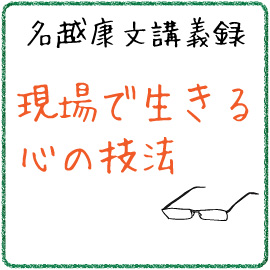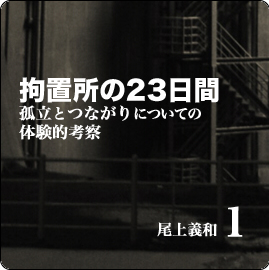かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

第9回 ノジマさんの生命力
2011.4.24 update.
1946年岐阜県生まれ。お茶の水女子大学大学院修士課程修了後、駒木野病院勤務などを経て、現在に至る。臨床心理士。アルコールをはじめとする依存症のカウンセリングにかかわってきた経験から、家族関係について提言を行う。著書に『アディクション・アプローチ』『DVと虐待』(ともに医学書院)、『母が重くてたまらない』(春秋社)など多数。最新著は『重すぎる母、無関心な父』(静山社文庫)。
[前回まで]
隣のベッドのノジマさんのもとへ、娘のアキコさんがやってきた。抑揚のない声、馬鹿丁寧な口調。高齢のノジマさんと距離をとろうとしているのが一目瞭然だ。二人のあいだに一体何があったのだろう――。嘉子と真衣はそっと目を合わせ、ロビーへ脱出した。
真衣と嘉子はラウンジにたどり着くと大きくため息をついた。
大きく開いた窓からは夕方の4時近い都心の空と高層ビル群が迫ってくる。少しだけ傾いた陽の光がビルの無数のガラス窓に反射して鈍く輝いていた。
窓際のカウンターのような椅子に並んで座り、二人はその静謐な光景を眺めたが、気分は正反対に波立っていた。とにかく話さずにはいられなかった。
「もう、全然勉強できなかった、予定が狂った!」
真衣は口をとがらせて訴えた。
「ほんとにねえ、次から次へとだもん。ロシア語でしょ、それからノジマさんとアキコさんでしょ」
「病室ってあんなに賑やかだなんて、誰も想像しないと思うよ」
「ほんとにびっくりした、想定外って感じだね」
できるだけ小さな声でひそひそと話すように努めながら、しばらくの間二人は病室で経験したことを次々と話した。ひとしきり語りつくすと、やっと落ち着いた。
真衣はポツリと言った。
「それにしてもノジマさん、かわいそうだね……」
「ほんとほんと、でも長生きしてもあんな風になるとしたらいやだなあ」
「大丈夫、ママは絶対ノジマさんみたいにはならないって。いくつになっても週刊誌を読んでると思うよ」
「マルジューで週刊誌買ってきてね」
ノジマさんのキーワードを決め台詞に使ってみたら、案の定、真衣は大声で笑った。それにつられて嘉子も笑いながら、頭の中で90歳近い自分が杖を片手に近所のコンビニで週刊誌を立ち読みしている姿を思い浮かべた。あまり絵になる光景じゃないな、と思いながら。
二人のアフターミーティング
「でもさ、アキコさんがあんな態度をとるようになったのは、やっぱり相当大変だったんじゃないの」
真衣は鋭いところを衝いてくる。
「うん、たしかにいえるかも」
「もういっしょに住みたくないって思ってんじゃないの? アキコさんって結婚してるのかな、それとも独身で仕事してるとか」
「そうか、全然想像もしなかったけどどうなんだろう、だいいち年齢もわからないし」
「ノジマさんの年齢が80歳前後だとすると、娘さんはもう50歳くらいってことにならない?」
「そうか、それにしちゃもっと若い印象だったよね、あの声」
真衣の言葉を聞きながら、この「推理欲」は生半可なものじゃない、おまけにかなりの確率で当たっている、ひょっとして自分より上手(うわて)かもしれないと嘉子は思った。
嘉子は仕事でいくつかのグループカウンセリングを実施しているが、終わってからスタッフ同士でアフターミーティングを行う。感想や気づきを経過に沿ってざっと話し合うのだ。そして最後はいくつかの視点に沿って総括し、次回に向けての課題を明確にさせる。
それはクライエントにとって重要であるのはいうまでもないが、実施するカウンセラーにとっても一種のフォローとクールダウンの効果をもっている。
真衣とのラウンジでのおしゃべりは、どこか「アフターミーティング」に似ていた。カーテン越しの母娘のドラマはそれほどまでに生々しかった。
病室に戻ってもノジマさんの隣ではなんとなく落ち着かないような気持ちがしたので、嘉子はいったん仕事のゲラを持ってきてそのままラウンジで夕食前まで校正をしながら過ごすことにした。
真衣はすっかり勉強をあきらめてしまったようで、一階の売店で買い物をしてくると言い残してエレベーターに乗った。
病室に入るとロシア人は再び高いびきをかいていた。
ノジマさんのベッドはぴったりとカーテンが閉められており、中からかすかにいびきが聞こえてくる。あれだけのことがあったのだからたぶん疲れて眠っているのだろう。
もうひとりの静さんは相変わらず不思議なくらい静かなままだ。
手提げ袋に入ったずっしりと思いゲラの束を持って、二種類のいびきが交錯する病室を嘉子はそっと後にした。
アザブ、アトリエ、ノボリガマ
ラウンジの窓から見る光景は、時間と天候によって大きく異なる。南側の空はうっすらと紅色がかっているが、西のほうを見やると太陽がじりじりと沈みかけている。
都心の空は一面に雲海のようなもやがかかっている。気温がかなり高くなっているようだ。しかしラウンジの中は、相変わらず快適な温度のままだ。
面会に訪れた人たちも減り、空いたテーブルも多くなっている。窓側の角のテーブルに目をやったとき、嘉子のアンテナがピンと立った。
そこに座っているのは、あの川久保玲似の女性だった。それも男性と向かい合って親しげに話しているのだ。男性は口髭をはやし、渋いグレーのたっぷりとしたシャツを羽織り、編み上げブーツを履いているのがズボンの裾からのぞいている。
嘉子は迷わずその隣のテーブルに二人と背中合わせに座り、おもむろに赤いボールペンで校正を始めた。もちろん耳はそのカップルの会話に集中している。
低い声で切れ切れに聞こえてくる内容は、単語と単語を結びつけて想像するしかない。まるで外国語を聞いているときのようだ。
西麻布、ブンカムラ、アトリエ、事務所、移転、仲間のオフィス……。
これらの言葉をつなぎ合わせれば、彼女の輪郭はかなりはっきりしてくる。嘉子の当初の想像はそれほど外れてはいなかった。やはりアート系の仕事に就いており、おしゃれなエリアに事務所をもち、つい最近移転したということなのだろう。
それにしても二人の関係は何だろう? 夫婦なのだろうか。いや、そうではないだろう。こんな場合、多くの夫婦は黙ったままか、どちらかが一方的に話すかのいずれかだからだ。その二人は静かに言葉を交わしながら話し合っていた。
では恋人同士だろうか。それにしてはあまりにも空気が淡泊すぎる。背後から漂ってくる気配は水のようにさらりとしている。
とすれば仕事仲間なのだろう。男性のかなりこだわった服装もそう推測させるに十分だった。
そのとき、川久保玲似の女性の口から出た言葉に嘉子の手は止まった。
「……それでね、登り窯がね……」
やはりそうだったのか!
前日に「陶芸家じゃない?だって指が太いもん」と指摘したのは真衣だった。またやられてしまった、と嘉子は苦笑した。そして何気なく隣のテーブルのほうに体をひねり、素早く川久保玲の指を見た。やはり、太かった。
病室に響き渡る生命力
真衣は、一階のコンビニでチョコレートクッキーを1箱買ってきた。それをかじりながら嘉子が夕食を食べ終わるのを傍で見届けて、急いで戻っていった。渋谷で待ち合わせの予定があるのだという。
驚いたことに、ロシア人女性はほとんど食事を摂らないままだった。実際に見たわけではないが、トレイ上の食事に手をつける音がしなのでそう推測した。
ナースが英語で「もう少し食べませんか」と尋ねても、「ニェット」と答えるだけだ。嘉子には、あのベッドがきしむ体とほとんど食事を摂らないという行動はどうしても不釣り合いだと思われた。
それに比べるとノジマさんは実に食欲旺盛だった。カーテン越しに食事を摂るときに発するさまざまな音が聞こえてくるのだ。真衣もそれを聞きながら目を丸くした。
ズズーっとポタージュを飲み干す音、お皿のチキンソテーを箸で突き刺す音、トレイにスプーンを置く音、ごはんの器の蓋を開け、そして閉める音……。
物を食べるとき、これほど多様な音が生まれるのかと驚くほど、ノジマさんはさまざまな音を盛んに生み出しながら食べている。その豊かさは、まるでノジマさんの生命力を表しているかのように思われた。
嘉子にとってはいつもどおり腹七分目しか満たされない食事だったが、これを機会に少し胃が収縮してくれないかと思いがまんした。
「薬じゃないの!」ふたたび
昼寝をし、食事を全部食べきったせいか、ノジマさんは心なしか隣のベッドで元気になったようだ。ナースが血圧と体温を測りにくると、いろいろ話しかけている。
「あのさ、さっき食べたほうれんそう、冷凍かい?」
「ほうれんそうですか? 私たちはあまりよくわかりませんが……どうかされましたか?」
「ええ?っ、知らないんじゃしょうがないね、アクがさ、あんまりアクがない味付けだったからさ、冷凍じゃないかって。そりゃあんまりしどくないかい?」
「アクがなかったんですね、そうですか」
ナースは一生懸命ノジマさんのアク無しほうれんそう事件に応対している。昼間のアキコさん失踪事件の際のナースとは別の担当者だ。おそらく申し送りがされているのだろう、ていねいに一つずつうなずきながら聞いているのが目に見えるようだ。
「そいでさ、しとつだけ頼んでいい、看護婦さん」
「ひとつだけですか(笑)。はい、いいですよ」
「ねえ、ここ見てくんない?」
相変わらず“ひ”と“し”の区別がつかない発音だが、昼間と同じように声のトーンは高くなっている。それにどこかナースに甘えながら、それでいてからかうような調子が聞く者に伝わってくる。
「どこでしょう?」
パジャマの衣擦れの音がして、ノジマさんは体の一部をナースに見せているようだ。どこなのか、カーテンを開けて見てみたいと思った。
「ほらね、こうなっちゃってんの、わかる? しどいでしょ?」
「ああ、そうですね、」
示された患部を見ているらしく5秒間くらいナースもノジマさんも言葉がない。しばらくたってナースが言った。
「先生から塗り薬が出ていますので、後で塗りますね」
「また薬? やんなっちゃうって言ったじゃないの。薬なんか効きゃしないんだから」
たぶん、この一連のやりとりはノジマさんがナースの関心を引くための取引に使う方法なのだ。体のどこか患部が炎症もしくはただれており、痒みか痛みを訴える。それに対して薬を塗るという対応がナースから提示されたとたんに、「薬じゃないの」と反論する。
多くのナースはそこでどうしていいのか困ってしまうだろう。その様子を見ながら、きっとノジマさんは自分に深く関心を惹きつけることができたという安心感・満足感を得ているのだ。
「薬を塗るのがおいやなんですね、でも一回試してみましょうか。そしてしばらく様子をみてみましょう」
ナースの発言を聞きながら、よく頑張っていると嘉子は感心した。嫌がっているノジマさんを尊重しながらも、必要な処置を試みるよう動機づけをしている。
このような場面でそれがすぐに実践に移せるというのは、なかなかできるものではない。日頃のカウンセリング業務のことを思い浮かべながら、けっこうやるじゃない、と内心でつぶやきながら、この病院のナースの対応がきわめて厳密にトレーニングされていることに改めて気づかされた。
しかし、これでノジマさんが納得したわけではなかった。
ノジマさんの訴えはだんだん痛みに集約されていった。体のどこかがいつも痛いと言うのだ。
その訴えのエネルギーは夜が更けるにしたがって徐々に高まっていき、病棟の消灯時間である午後10時ごろにピークに達した。
(第9回了)
[次回は5月下旬UP予定です。乞うご期待。]
信田さよ子先生の著書
|
アディクションアプローチ もうひとつの家族援助論
定価 2,100円 (本体2,000円+税5%) ISBN978-4-260-33002-2
|
|
DVと虐待 「家族の暴力」に援助者ができること
A5判・192ページ・2002年03月発行 |