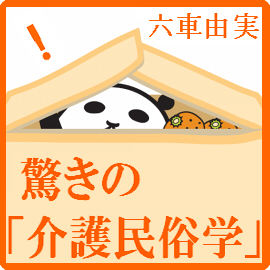かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

医療者のための心の技法 第10回
2011.2.24 update.
1960年生まれ。近畿大学医学部卒業後、大阪府立中宮病院精神科主任を経て、99年、名越クリニックを開業。専門は思春期精神医学。精神科医というフィールドを越え、テレビ・雑誌・ラジオ等のメディアで活躍。著書に『心がフッと軽くなる「瞬間の心理学」』(角川SSC新書、2010)、『薄氷の踏み方』(甲野善紀氏と共著、PHP研究所、2008)などがある。
第9回よりつづく
夜勤というアンチクライマックス(2)
変化を実感できない辛さ
それだけの緊張感を強いる夜勤というのは、睡眠時間とか、過剰な労働という側面はもちろんのこと、人の精神にも独特の負担を与えるものである、という側面も無視できません。人間が必然的に持つ「何か起こるかもしれない」という幻想がもたらす不安や過覚醒ってけっこう強烈なもので、決して慣れるものじゃありません。
うつや引きこもりの人も、事件が起きないことで、ますます身動きが取れなくなってしまう悪循環に陥ることがあります。経済的に余裕があったり、いろんな条件が整っていると破綻しないので、いつまでもそれでやっていけてしまう。そのことがもたらす不安というのは確かにあるんですよね。
エントロピーの法則、仏教の無常観、最近では生物学者の福岡伸一先生が動的平衡という概念で説明しておられますが、世界というのは変化し続けているもので、生き物にとっては、変化することが生きることなんです。
ただ、これだけ社会全体が強固に、いわばコンクリートで固められていると、「すべてのものが朽ちていく、すべてのものが変化していく、何一つそのままではない」ということを実感しづらくなっていますよね。
夜勤も同じで、変化を実感しづらい。そういうなかで過覚醒状態になってしまうと、自分自身がどんどん虚しい、頼りない存在に思えてくるんです。かえって変化や動きがあったほうが、しゃきっとする。生きている実感がある。夜勤のときに何にもイベントが起こらないと、自分自身がどんどん頼りない、朽ちていく存在に思えて、このまま世界から取り残されていくような葛藤・焦燥感に駆られてくるんです。
それはもしかすると、「世界が恒常的に維持されている」という幻想に僕らがあまりに浸りすぎているからかもしれないですね。

夜勤の空気を共有することの意味
そういう夜勤がもつアンチクライマックス性って、人間の精神に独特の緊張感を与えるんだと思います。だから、当直の夜にはけっこう深い話を同僚と交わせたりする。看護師さんとも「ああそうか、そういうことをあなたは考えていたのか」といったことがふとわかったりする。眠れない患者さんから、すごく意外な話が聞けることもあります。
僕がよく覚えているのは、当直の夜にサンドイッチを作ってもってきてくれた看護師さん。みんなで食べたら、美味しくて、すごく絆が深まったように感じました。それは、ずっと「来ないクライマックス」を待ち続けている、独特の緊張感によるところは大きかったと思います。
夜勤の空間というのは、pre-festival(祭礼の前夜)じゃないですが、独特の神聖な空気が流れているんです。ふだんなかなかコミュニケーションが取れなかった医師や同僚に、ちょっとした差し入れをしてみると、意外な関係が開けるかもしれません。
<医療者のための心の技法 バックナンバー>
第1回 3年で辞めないために(1)
第2回 3年で辞めないために(2)
第3回 3年で辞めないために(3)
第4回 愛情欲求から自由になる(1)
第5回 愛情欲求から自由になる(2)
第6回 共感は可能か(1)
第7回 共感は可能か(2)
第8回 共感は可能か(3)
第10回 夜勤というアンチクライマックス(2)