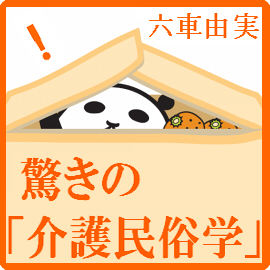かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

【第5話】 最後の晩餐
2010.12.18 update.
1946年岐阜県生まれ。お茶の水女子大学大学院修士課程修了後、駒木野病院勤務などを経て、現在に至る。臨床心理士。アルコールをはじめとする依存症のカウンセリングにかかわってきた経験から、家族関係について提言を行う。著書に『アディクション・アプローチ』『DVと虐待』(ともに医学書院)、『母が重くてたまらない』(春秋社)など多数。最新著に『ふりまわされない』(ダイヤモンド社)、『ザ・ママの研究』(よりみちパン!セ、理論社)がある。
[前回まで]
検査入院のため四人部屋に入った嘉子。母にさすり続けられていた隣のベッドの娘は、突然いなくなった。転棟したのかもしれない。もともと空きベッドが一つあったので、嘉子は、高いびきで寝ていた入り口の女性とふたりきりなった。ところが今度はいっこうに何の音もしない。
パソコンに向かいながら、真衣は腕時計をちらっと見た。そろそろオフィスを退出してもいいだろうか。母親の入院している病院までは、早足で歩いても十五分、バスだと五分で着く。あれほど元気だった母親が心臓の検査入院をすることになり、真衣はひどく動揺し、心配していた。入院準備をする母親は、まるで旅行前夜のような勢いだったので、真衣はつとめてふだんと変わりなく接するようにした。
午前十一時半に入った携帯メールを、何度も読み返した。
「無事入院したよ〜、検査も終わったし、おなかは空くし」
ベッドの上で老眼鏡をかけて、絵文字混じりのメールを一生懸命打っている母親の姿が浮かんだ。
静(しずか)さん、登場
カーテンを閉め切ったなかでの夕食は、妙な気分だった。おまけに隣のベッドが空いたので、もともと三人だった病室は、入口脇の高いびきの女性と嘉子のふたりきりになってしまった。
空腹のあまり、嘉子は食器のふたをわくわくしながら開けた。やけどをしそうに熱いふろふき大根を、まず食べた。甘味噌がこれほどおいしいとは思わなかった。ごはんももっちりとして湯気が立っているし、お吸い物の味付けは塩分控えめなぶん、濃い目のだしで十分カバーされている。心臓病のメニューはまずいですよ、と入院前にさんざん皆から脅されたせいで覚悟をしていたぶんだけ、予想外に満足のいく味だった。
ひととおり味見をして落ち着いたところで、ひとりしかいない同室者に注意を向けた。最初に聞こえたのが高いびきだったことがうそのように、夕方の診察以来、入り口わきのベッドからはなんの音も聞こえてこない。食事をとっている気配もない。高いびきの女性から「静(しずか)さん」に変身してしまったようだ。
嘉子が茶碗をトレイに置く音、箸をつかう音、スープを飲む音は、はたして静さんの耳に入っているだろうか。顔も見たことのない静さんだったが、夕食前の診察時に、主治医にしゃがれ声でけだるそうに話す声を聴いた。どうも退院を渋っているらしい。
入院前は、同室の女性たちとわいわい話しながら食事ができるかと期待していたのに、四人部屋とは思えないこのお葬式のような静けさはどうだろう。嘉子は、できるだけ音を立てないように「白身魚の野菜あんかけ」を食べた。
東京タワーとタラコおにぎり
完食したのにどうも満腹感がないので、売店でタラコおにぎりでも買おうかと画策していたら、携帯にメールが入った。
「あと十五分くらいで病院に着きまっせ!」
真衣からだ。家族のなかで病院からいちばんオフィスが近いのだ。七時くらいには夫や長男夫婦もそろって面会に来る予定だが、この病室でいったいどうすればいいのだろう。静さんにも面会者がやってくれば、バランスがとれるのだが。
思い切って嘉子はラウンジに行ってみることにした。その前に、「売店でタラコおにぎり一個買ってきてね!」と真衣への短い返信を打った。
最近の新しい病院には必ずラウンジがあり、テレビや電子レンジ、インターネット機能をそなえたPCなどが備え付けられている。いわば患者にとって公共空間のようなものだ。
検査の帰りにちらっと眺めたが、天井いっぱいに窓がひろがり、東京タワーがくっきりと見えた。窓際に沿って机が矩形につくりつけられており、ひとりで椅子に座って頬杖をつきながら窓外の景色を眺められるようになっている。
エレベーターホールとラウンジはつながっているので、テレビを見ながら真衣が到着するのを待とう、元気そうな姿を見せてびっくりさせてやろう、と嘉子は思った。
土気色のキリスト
嘉子は病室を出るとき、そっと静さんのベッドをのぞいた。不思議なことに、カーテンは半分開いていた。看護師さんが入りやすいようにそうしているのだろうか。おかげで嘉子は堂々と静さんの顔を見ることができた。
枕元の電気が煌々と点いているせいか、痩せた土気色の顔と目を閉じた表情は陰影に富み、まるでダヴィンチの最後の晩餐の絵に描かれたキリストのようだった。年齢はおそらく四十代後半だろう。退院したくないということは、家族関係があまりうまくいっていないのかもしれない。とすれば面会に誰も来ない可能性がある。やはりラウンジで家族と面会することにしよう。病室の広さと景色のよさは、ツアコンとしてささっと案内すればいい。嘉子は決心した。
ラウンジには、すでに夕食を済ませた患者さんたちが思い思いに座っている。窓の外に目をやるひともいれば、テレビを見ているひともいる。圧倒的に男性が多いせいか、患者さん同士でしゃべっているひとはいない。パジャマ姿のままの中年男性は、みんな所在なげで、ぽつねんと座っていた。
ライトアップされた東京タワーと高層ビルの灯りが夕焼けで赤く染まった空に浮かぶさまは、美しいけれど、嘉子をどこか落ち着かない気分にさせた。不意に、かつて多くのアルコール依存症の女性たちが語った言葉を思い出した。
「夕暮れどきは危ないんですよ、わけもなく不安になってアルコールが飲みたくなっちゃうんです。たそがれは逢魔が時っていいますからね」
だんだん闇につつまれていく紅の空を眺めながら、嘉子はあらためて自分は三日後にはカテーテル検査を控えた入院患者なのだ、と思った。
襟を立てた川久保玲
エレベーターホールがよく見える位置の丸テーブルに席をとり、家族五人がいっしょに座れるように嘉子は椅子を確保した。
準備万端整ってから、落ち着いて周囲をよく見まわすと、一人ひとりの特徴が際立って目に入ってくる。車いすのひと、松葉杖をついているひと、屈伸運動をしているひとなどもいる。ひょっとして、嘉子の病棟とナースステーションをはさんだ反対側には、整形外科の病棟が広がっているのかもしれない。
そのなかにひとりだけ、窓際の椅子に座り、片肘をあごに当ててぼんやり夜景を眺めているひとが目にとまった。ショートカットの横顔は、一見男性のように見えた。細身でノーメイク、風変りなパジャマを着ていたからかもしれない。
入院時は前開きのパジャマと相場が決まっている。嘉子は入院当日に、一階の売店で女性ものの前開きパジャマを購入し、それを着ていた。どのパジャマも花柄で薄いピンク地だったので、選ぶ余地もなかった。ところがその「女性」は、茶系のチェック地のパジャマに、襟元には紺色のタオルを巻いている。おまけに襟を立てていた。
年齢は嘉子より十歳近く若く見えるが、どこか年齢不詳の雰囲気を漂わせている。
性別および年齢不詳。風変りなパジャマと、首に巻いたカラーコーディネートしたタオル。どこかコムデギャルソンの川久保玲を思わせる風貌から、嘉子は目が離せなくなってしまった。
あまりじろじろ眺めるわけにもいかず、テレビを見るふりをしながら、視線の端で彼女の姿をウォッチしはじめた。そしてすっかり真衣のことなど忘れてしまった。
ママ、そのパジャマやめて
「どうしたの?! 病室にいないなんて」
不意に、怒りながら真衣が目の前に現れた。あらかじめ病室番号は知らせてあったので、急いで病室に行ったらしい。
「もう、まったく〜、ベッドがからっぽなんて信じらんない!」
「ごめん、ごめん」
嘉子はあやまりながら、真衣を驚かせようと思ってラウンジにいたことを説明した。
「そんなことかもって思ったのよ、でもタラコおにぎり買ってこいなんて、ママらしい」
うれしそうに真衣が笑うのを見ながら、小学校一年のとき、心臓手術のために入院していたときの顔と重なった。立場は逆になったが、こうして嘉子のことを心配してくれるまでに成長したのかと思うと、安心して老いることができる気がした。
売店で買ってきた牛丼を食べながら、真衣はつくづくと嘉子の姿を上から下まで眺めた。そして厳しい口調で言った。
「ママ、そのパジャマやめて」
そして声をひそめて
「あのひと見た? すっごいおしゃれじゃん」
そう言う真衣の視線の先には、嘉子がすっかり関心を奪われた女性が座っている。
「でしょでしょ? なんか雰囲気あるしね」
「う〜ん、あれは男性用のパジャマだな、間違いない」
「そうか、そういわれれば厚手だし、でも、あんな模様のパジャマ売店になかったよ」
「え〜っ、売店なんかで買ったんだ、だめじゃん、ダサいと思ったよ」
「だって、時間なかったし……」
「わかった、明日来るとき、買ってきたげる。もっとおしゃれなパジャマ着ないとだめだよ」
入院ファッションまでチェックされたのに、嘉子は少しも不快ではなかった。そこに気分を盛り立てるための気遣いを感じたからだ。
ふたりはひとしきり、その女性に感づかれないようにわざと別の方向を見ながら、ひそひそと意見交換をした。
「ねえねえ、手首と裾見た? 男性用だから袖を少しまくってるよ、裾もジーンズみたいに折り返してるし。あと、スリッパじゃないよ。ほらデッキシューズはいてるじゃん」
言われてみれば、袖をたくし上げて、たしかにバレエシューズのような靴をはいている。
「ママもちょっとがんばって、襟を立ててみたら」
「そうか、じゃあやってみる」
嘉子はがんばって襟を立ててみたが、悲しいかな、ガーゼ素材のパジャマの襟はみじめにすぐにくったりと倒れてしまった。
私の素敵な病院ライフ!
真衣の幼いころから、ふたりでいつもこんな会話を続けてきた。小学生になると、真衣は喫茶店や電車のなかで、「ママ、あのひと素敵じゃない?」と目をつけた男性のことを、嘉子に報告するのが常だった。たいていふたりが注目するのは同じひとだったので、いつもイケてる風貌や、特徴ある癖などを観察しながら、ないしょ話のようにこっそり楽しむことができた。
真衣は嘉子と同じ疑問を抱いたらしい。
「あのひと、なんの仕事しているんだろう」
盛り上がったふたりの会話は、最後は職業が何かという究極の焦点にしぼられた。
「そうなのよ、思ったんだけどさ、きっとブティック経営か、それとも自然素材の家具店経営かな。それとも建築士とか」
「そうかなあ……、私は陶芸家だと思う」
「陶芸家?」
「うん、だってあの指見た? あんなスリムな体なのに、指だけがいやにたくましくない? きっとあれは指を使う仕事をするひとの手だと思うな」
「そうか、なるほどねえ」
真衣の観察眼に感心しながらこっそり彼女の指を見ると、たしかに太い。
「いずれにしても『私の素敵な病院ライフ!』だね」
嘉子のキャッチコピーに、真衣はけらけらと笑った。
その声の大きさに彼女が振り向いたので、あわててふたりはテレビのほうを向いて別の会話に転じた。
それから夫と長男夫婦がやってきて、五人で中華弁当、かつ重、牛丼をテーブルを囲んで食べた。旺盛な皆の食欲と会話につられて、「ひと口ちょうだい」と言いそうになったが、検査前ということもあり、さすがの嘉子も減塩のためにがまんをした。真衣に買ってもらったタラコおにぎりを、眠る直前に食べることだけを楽しみにした。
キリスト御一行様
入口から、患者とその家族らしい一団が入ってきた。
振り向くと、それは先ほど目に焼き付けた、同室の最後の晩餐のキリスト、いや静さんの一団だった。夫らしきメタボ体型の男性、それに子どもらしき三人もいっしょだ。もう中学生らしい長男が、急いでテーブルを確保して椅子を用意した。それほど年齢の違わない小学生らしい娘と息子は、父に支えられた母を腫物に触るような目つきで見つめている。
静さんは結婚しており、おまけに子どもが三人もいた。
あのやせ方はひょとしたら摂食障害かもしれない、と心の片隅で想像していた嘉子は、静さんは独身のまま両親と同居しており、日々親との葛藤が絶えないに違いない、だから退院をしたくないのだ、というシナリオを想像をしていたのだった。隣のベッドの母娘については当たりだったが、残念ながら静さんに関しては、嘉子の推理はまったくの外れだった。
よろよろと夫に支えられながらラウンジの椅子に腰かけた静さんは、やはりキリストのように真ん中に座って下を向き、首をかしげている。座を盛り立てようとするためだろうか、夫がいろいろ話しかけるのだが、うなずくばかりだ。静さんを囲むように座った子どもたち三人は、黙ったまま母親をじっと見つめている。
そのうちに長男が紙袋からゲーム機を取り出して、うつむいてゲームを始めた。すると妹、弟も次々と手元のビニールバッグからゲーム機を取り出して、うつむいてピコピコと操作を始めた。
静さんはぼんやりそれを見ながら、表情を変えずにただ座っている。夫は三人の子どもに目もくれず、静さんが聞いているかどうかはおかまいなしに、ずっと話しつづけている。
ゲームに興じる三人の子どもたち、ひたすら相手の反応を無視して話しつづける夫、彫像のように、最後の晩餐のキリストのように無言のままで座りつづける妻。
それでも、そこに存在しているのはまぎれもない家族だった。
今夜はあの病室で静さんとふたりだけで眠ることになるのだ、と嘉子は思った。
(第5回了)
[次回は2011年1月中旬UP予定です。乞うご期待。]
信田さよ子先生の著書
|
アディクションアプローチ もうひとつの家族援助論
定価 2,100円 (本体2,000円+税5%) ISBN978-4-260-33002-2
|
|
DVと虐待 「家族の暴力」に援助者ができること
A5判・192ページ・2002年03月発行 |