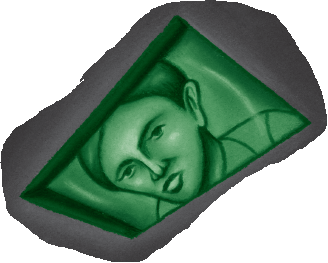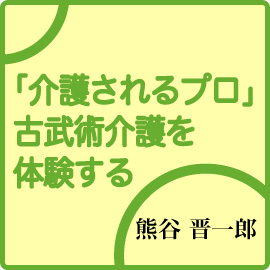かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

夜の語り手――書論『リハビリの夜』
2021.4.29 update.

精神分析家・精神科医。
1953年福岡県生まれ。幼少期は山口県の瀬戸内海岸で育つ。1978年東京大学医学部卒業。専攻、精神分析。上智大学名誉教授。東京神宮前にて精神分析家として個人開業。http://fujiyamanaoki.com/
国際精神分析学会(IPA)認定精神分析家。日本精神分析協会訓練分析家。
単著書に『精神分析という営み〈正・続〉』『集中講義・精神分析〈上・下〉』『精神分析という語らい』(以上、岩崎学術出版社)『落語の国の精神分析』(みすず書房)など。『こころをつかうということ』(笠井清澄氏と共編著、岩崎学術出版社)では、熊谷晋一郎氏と対談をしている。
【イラスト=笹部紀成@『リハビリの夜』】
私の読書はとても場当たり的なものだ。
世の中の知的な動向に絶えず気を配っている人からすると、相当にずっこけている。どんな本が売れていて評判になっているのかにとても疎い。だから世の中の人たちが評価しつくした頃に、ふと手に取ってみて、これは凄い本だ、などと声を出すと、いまごろ何言ってるんだよ、みたいな声が返ってくるという経験をよくする。あるいは、一度読んで感銘を受けたのにしばらく忘れていて、後になって誰かがその本のことを言及したり世間で評判になったりしているのを聞き、ほお、面白そうな本だな、と思って手に取ると、それは以前自分が凄いと思って読んだ本だった、というようなこともある。毎日患者と会うことに忙しくて、たまたまふと出くわした泉で渇きを潤すというような按配で読書をしているせいだろう。この本で頻出する表現で言うなら、本のほうで私を拾ってくれるときしか本を読んでいないのだ。
熊谷さん(書評を書くときにいつも困るのは、著者をどう呼ぶかということである。純粋な学術書を同じ領域の研究者として書評するときは、呼び捨てにするのが正しいような気がしているが、この本の場合、著者の熊谷晋一郎氏とは何度かお目にかかっていて、一方的に親しみを覚えている人なので、ちょっと呼び捨てが難しい。この一文では熊谷さんで通させていただく)の『リハビリの夜』も、たまたま誰かが面白いと言っていたので手に取ってみたら、驚き、唖然とし、凄い本だと思った。だがそれは、すでにこの本が世間に評価されて賞まで取ってから数年経ってからのことだった。
それからもう6~7年経ってしまった。だがこの本は、何度読んでもそのたびに、別の角度からこの本と対話している自分、この本に魅せられている自分を自覚させてくれる。稀有な本である。そういうわけで、この本は私のオフィスのデスクの上の、手の届くところに置いてある。ときどきふと、この本のところどころを無性に読みたくなるからだ。そんな本が私には何冊かある。
精神分析家のウィルフレッド・ビオンという人が書いた『注意と解釈』という無味乾燥なタイトルの本も私にとってそんな本で、その本の原書と訳書が私の机上にはいつもある。とはいうものの、そのふたつの書物はかなり趣が違う。乾いて硬い『注意と解釈』と湿潤で柔らかい『リハビリの夜』。だが私を惹きつけるものは突き詰めれば共通しているようにも思う。粗雑な言いかたに聞こえるかもしれないが、それはこのふたつの本が帯びている真実の感覚だ。なまの事実というものは豊かな解釈の可能性を持っている。その二冊はまさになまの事実のような生々しさを帯びている。何度読んでも何かを考えるように私を誘ってくるのだ。
「さもしい分析家」を惹きつけるもの
毎日患者と会って暮らしている精神分析家なので、どんな本を読んでいても、どうしてもその視線がせり出してくる。しかも、この本には、人が変化し、進展していく過程、そしてそれを助けようとする人物が頻出する。だから、いやが上にもその傾向は強まる。人が人と援助的に交流することがどういうことなのか、そして援助されるということが援助する側の思惑によって、あるいは思惑にもかかわらず、どのように達成されあるいは失敗するのか、そうしたことに引き寄せて読んでしまいがちになるのだ。
それはそれでやむを得ないだろう。どうしたって私は精神分析家であって、それ以外ではないからだ。ほかの職業でもそうなのかもしれないが、精神分析はとりわけそういう職業だ。精神分析家は自分のプライベートなこころを差し出して訓練される。つまり、自分自身が精神分析を受ける。このことは、パーソナルな自分が取り返しのつかない形で変わってしまう可能性を前提として、職業訓練に入るということだ。パーソナルな自分が維持された上でスキルや知識を身に付ける、というのとは根本的に違う。私はもはや、何もかも精神分析のレンズを通して見たり聞いたりするしかできなくなっている。その私がこの本を読むと、ある種の実用書として役立てたくなる私がどうしても出てきてしまう。さもしい話だ。
さもしい分析家としての私がこの本から拾い上げるものはたくさんある。熊谷さんが生きた体験から抽出して、名前を付けた多くの興味深い概念である。
たとえば、「ほどきつつ拾う関係」「まなざし/まなざされる関係」「加害/被害関係」という三つの関係性のモデルがある。このあたりは当然、分析家として患者と一緒にいるときの患者と私のあいだに起きていることと即座につなげて読んでしまうことになる。母子関係的で無媒介的な二者関係のなかに、「法」「基準」「父」というものが導入されて三者関係が生まれる。それは精神分析の営みのなかで日々私が体験している、もしくは体験することに失敗しているなりゆきである。
その私の視点からすると、熊谷さんの描き出したなりゆきは、あまりに強引に第三者性、もしくは「基準」が突きつけられてしまったために、きわめて不毛で反復的な迫害的世界に閉じ込められる過程である。私たち分析家が「言語」という第三者を持ち込む手続き、解釈の供給という介入をあまりに性急におこなったときのありさまを彷彿とさせる。どのような援助の局面でも、援助者側の固有の何かが、あまりに早くあまりに強くそこに持ち出されれば、同じようなことが起こるのだろう。それは援助される側の存在の連続性を壊して断片化に導く。その様子を熊谷さんは、体の言葉でビビッドに描き出している。
あるいは、「折りたたみナイフ現象」から「敗北の官能」に至る受身的なゆだねる快の考察にも、さもしい分析家は惹きつけられる。トレイナーがある緊張を維持しながら脳性麻痺の人の関節を伸展させるべく力を入れる。なかなかうまくいかないにもかかわらずそれを持ちこたえていると、そのある種のパワーゲームがクライマックスに達したときに、突然、脳性麻痺の人の緊張が消え去り、関節はストンと伸びてしまう。そのときに彼にはある種の快が生じる。
これは私たち分析家と患者とのやりとりでの行き詰まりがあるクライマックスに到達したときに、そこで起きているできごとそのものに双方が降伏する局面と似ている。事態が不連続に転換し、変化と進展と安堵が生まれるというなじみ深いできごとである。過程そのものにゆだねること、降伏すること、ということの持つ生産性とある種の快。それは「目標」というものが過程のなかで官能的動因へと脱構築されていくことで実効性を生むという逆説のあらわれだ。こうしたことも熊谷さんはきわめてビビッドな体の言葉で語っている。
このように、分析家としての私の営みにとって、この本はとても有用な示唆を与えてくれる。だが、そんなふうにこの本を概念や要旨に還元することは、さもしく実用主義的に読みたい私の部分を喜ばせるだけだ。私のなかのそうでない部分が面白いと思っているのは、そんなこととは関係ない。それははっきり感じられる。この本を読むという体験は、そのようなさもしさを満たす体験をはるかに超えた何かなのである。そんな節穴のような狭い視野では、この本の面白さの中核にたどり着くことはできない。
とにかく、私がオフィスでこの本をときどき手に取って楽しんでいるのは、そういうさもしい動機からではない。それはまちがいない。
体験したことのないことが私に生きたまま伝わる
この本は脳性麻痺という事態の当事者が自身の体験を語っている本である。熊谷さんが脳性麻痺というありかたを抱えてこの世に生まれ、その障害を生きてこられたおかげで、私たちはこの本が読めている。その事実こそがこの本の面白さの中核にある。この本の面白さを考えるとしたら、まずこのあたりまえのところを出発点にするべきだろう。
もちろん、脳性麻痺を抱えた人たちは過去にも現在にもおびただしくおられる。だがそうした人たちはこの本を書かなかった。書きたいとも思わなかっただろう。だが、何より熊谷さんのようには書けなかったのではないか。
私は脳性麻痺になったことはない。「折りたたみナイフ現象」を経験したことがない。だが、この本を読むと私はそれをいきいきと実感的に思い描ける感じがしてくる。この本を読む前にはとんと想像もできなかった、脳性麻痺になっているという体験がどんな体験なのか、わかる気さえする。なじみ深いとさえ感じる。
体験を体験としての生気を失わない形で言葉にして伝える。熊谷さんはそれに成功している。そのおかげで私たちは、まだ体験したことのない脳性麻痺を生きる体験を、こころのなかで微(かす)かにでも生きることができる。体験をその生気を維持して伝えうるように言葉を用いる。それが途方もなく困難な課題だということは、どれほど強調してもしすぎることはない。その大きなハードルを越えて彼は書いてくれた。このことがまず、なんと言っても重要だ。
体験というものは言葉にはできない。これはあたりまえのことだ。体験という言葉を純粋に使用するなら、言葉を受け取るという体験は、単に声の音波を聞いたりインクの濃淡を見たりすることでしかない。言葉の意味は体験とは違う。どれほど私が言葉を連ねて、旬の鳥貝の甘み、西瓜に似た香り、酢飯と混然となるときのうっとりする感覚について語ったとしても、けっして私が鳥貝の鮨を食べる体験そのものを読者に伝えることはできない。体験は言葉を超えたものだ。だが、にもかかわらず、体験が生気を失わないで言葉になっていると感じられるときがある。書き手の書く体験が具体的に伝わってきたと感じられるときがある。
言葉は体験そのものを描き出せない。したがって体験を伝達することもできない。言葉は体験そのものでないが、体験の帯びる生気を受け手のなかに生み出すことができる。ひからびた生気のない形での伝達と、生気を保持した伝達、その違いは何なのだろう。おそらく、生気を保持した伝達においては、私たちの内部の何か、おそらく記憶のなかの何かが喚起されるのだろう。体験そのものは伝わってこなくても、その体験をとりまく感じ、雰囲気が、その言葉によって読者にきわめてミクロではあっても喚起される。おそらくそうした「感じ」や「雰囲気」は私たちの記憶のなかにすでに蓄えられているものなのだ。「感じ」「雰囲気」が喚起されたとき、書き手の持った体験、言葉にできなかった体験と相似な、私たちの無意識的記憶のなかの体験が、やはりきわめてミクロに動き始める。
体験そのものを言葉が伝えることがなくても、その体験とつながる、受け手にとってなじみ深い何かがこころのどこかで動く。そのとき私たちは体験が生気を保持した形で言葉で「伝えられた」と感じるのだろう。熊谷さんの言葉は私にとってそれを可能にした。そういう力を持っていた。それはなぜなのだろう。

夜でつながる
思うにそれは、熊谷さんのことがとても身近に感じられるからだ。身近、という言葉の文字通りの意味、身体的近接感のようなもの、熊谷さんの体温さえ感じられる感覚が、この本を読む体験のなかで私に瞬間瞬間に生まれてくるからだ。そんなことが起きるのはおそらく、私が熊谷さんと大きな共通基盤の上にいるという感覚を持てるからだと思う。
この書物の題が「リハビリの『夜』」であることに注目するべきだろう。彼はリハビリの昼でなく、夜に着目する。もちろん熊谷さんは医者だから、「協応構造」などという固い言葉で物を考えもする。それはこの本の昼の部分だ。私もさもしい分析家として、先ほど述べたように熊谷さんの概念を理解し、自分の実践にとっての示唆として受け取る。そのとき私も昼の人であり、昼の熊谷さんと話している。しかし、昼は夜があってこその昼である。
人が眠っているとき、みんな誰もが眠っている人だ。みんな夢見る人だ。個人と個人とのあいだの差異は溶けて流れ去り、眠り夢見る同じような人間になる。熊谷さんは自分がふつうに歩いている夢を見ると書いている。逆に私は、夢のなかで自分が手足を動かせず溺れてしまう夢を見ることがある。夜はすべての人を同じ場所に立たせやすい。たとえば、精神科病棟で昼間の患者はそれぞれに病気によって特徴的なふるまい、思考、感情を示してくる。彼らはそれぞれに、まだ退院できない程度に私たちの気を揉ませる人たちだ。しかし、夜が来て彼らが眠ってしまえば、彼らはみんな普通の眠っている人になる。それは、体の病気の人が眠っていてもあいかわらず体の病気を持つ人で、当直医が絶えず気を揉ませられていることとは対照的だ。精神科の当直医は要するに、昼の患者を夜の患者に変えればいい。眠ってもらえばいい。
熊谷さんは昼間、脳性麻痺の人としてリハビリを受けていた。しかし夜の彼を必ずしも脳性麻痺の人であると考える必要はない。夜、たいていの人は彼と同じように「二次元の世界」に憩うのだし、そこで思い描く空想や想起には官能がつきまとっている。熊谷さんも私たちも、昼間のことを思い出したりしながら、官能的な世界に入り込んでいく。
熊谷さんの書く言葉には「色気」がある。「官能的」と言ってもいい。それは絶えず昼の体験を裏打ちしている夜の体験を意識しているからだ。彼はたぐいまれな夜の語り手である。たとえば、「ほどきつつ拾う関係」という、リハビリの進展促進的な関係体験を語るとき、彼はそこが非対称の場であると語り、そこで大きな存在に自分をゆだねることが生む、ある種の「官能的」体験を描き出す。それは「敗北の官能」だ。この「敗北の官能」が熊谷さんにとっては、こころ慰められる、憩いと安堵に満ちた体験であり、進展の基盤を作るものだということは、この本で何度も語られている。この「敗北の官能」こそ、リハビリの「夜」のもっとも中心的で建設的な側面なのだ。そしてその夜の側面こそ、熊谷さんと私の共通基盤なのだ。
豊かな太腿に「敗北の官能」が……
私は脳性麻痺の体験を持てない。そして、リハビリを受ける体験も持てない。つまり、昼のリハビリ体験を持つことができない。だが、ちょっと思い起こせば、リハビリの「夜」の体験、援助されるときの「敗北の官能」を自分が体験していたことが思い出せる気がする。
小児喘息を克服できないまま思春期を迎えた私は、高校生になると親元を離れて進学校である男子校に進んだ。官能などというものの入り込む余地が微塵もない殺伐とした環境で暮らしながら、ときどき発作を起こしては医院に駆け込んだものだった。
点滴をされ吸入を受ける。ベッドに横たわっていると、自分がとても無力な存在だという気がしてくる。そこにつかつかと若い看護婦さん(この当時は看護師という言葉はなく、看護婦さんだった)が近付いてくる。私には白いストッキングの脚が見えるだけだ。看護婦さんはいつもは華奢に見える割に、太腿はとても肉付きがよい。その太腿に頬ずりしたいような、頬ずりしたまま泣いてしまいたいような気持ちになる。そんなことはできない。でも何か懐かしいような気持ちだ。そのままじっとしていると、徐々に体が楽になり、同時に自分が何か大きなものに降伏してしまったような気分になり、わけもなくうっとりする。しばらくうとうとする。
そうしたことを私は一年に何度も繰り返した。看護婦さんと言葉を交わしたことはほとんどない。彼女はひとりの人間というより、私より大きな何かの一部であり、しいて言うなら豊かな太腿だった。それに私は決定的に降伏するしかない、ゆだねるしかないと高校生の私は感じていた。
別のことも思い出す。私はしばしばモノをなくす。失くし物をするという体験は、確信を持ってそこにあると考えていた場所からモノが消えてしまうという体験だ。当然驚く。そして自分というものがあてにならないことに、ひとことでいえばバカであることに傷つくことになる。毎日三回くらいは探し物をしているので、いい加減慣れそうなものだが、そうはいかない。毎回毎回私は傷つき、自分を罵る。その繰り返しだ。
ある日タクシーから降りて家に着いたら財布がない。激しく動揺する。例によって自分をこころのなかで罵倒する。絶望的によるべなく悲しい。領収書をたよりに翌日電話してみる。財布は届いており、営業所に行けば財布は返ってくるということがわかる。ほっとして胸をなでおろす。緊張が緩んで涙ぐみそうになる。行ってみると営業所は祖師ヶ谷大蔵にある。私が五十年近く前大学1年生のときから2年間暮らした町だ。私鉄を降りて営業所に行き、財布をもらってそのあたりを歩く。微かに自分が住んでいたあたりの街並みが同定できる。なにかものすごく懐かしくなる。同時にとてもかなわないという気持ちがしてくる。
自分がモノをなくしてばかりのどうしようもない人間なのに、この世の中は財布を戻してくれただけでなく、自分をこんなに懐かしい甘美な気持ちにもしてくれた。ほんとにかなわない。自分はちっぽけなダメな奴なのに。降参するしかない。
こうした私の体験はおそらく、熊谷さんの言う「敗北の官能」の体験と同質の体験と言えるだろう。熊谷さんと私が昼間体験していることは大きく違う。だが夜の側面は共通しているということだ。私がたまたま喘息だったり、注意欠陥があったりしたからこうした共通基盤が生まれたのだろうか。私はそうは思わない。私たちは誰もが小さく無力な、自分では何もできない存在としてこの世に生まれてくるからだ。
最早期に私たちが私という意識をもたないまま、思い通りのものが環境から手に入るという状況にいるとしたら、そこには他者はいないから、他者というものが必要な「官能」は存在する余地はない。だが、いったん、「私」という意識に乳児が目覚めれば、自分を世話してくれる、大きな圧倒的な他者を意識しないわけにはいかない。その他者に自分をゆだねることでもたらされる安堵と幸福感は、大きな他者に圧倒される感覚とないまぜになって、「敗北の官能」に結実する。他者が出現したとたん私たちは「官能」あるいは「性愛」にからめとられてしまうのだ。
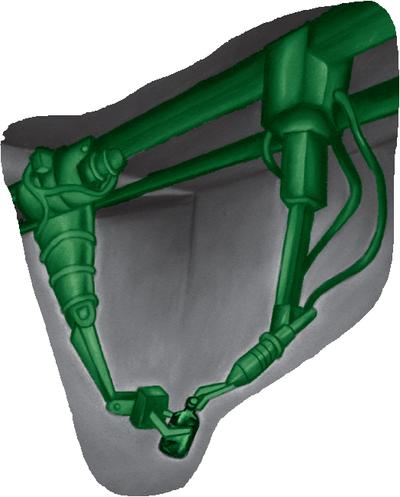
私たちは「夜」を語れるか
他者としての母親への官能的体験を乳幼児が持つという想定は、精神分析の基本的想定である。そうした想定は人間の夜の側面が絶えず活動しているという想定と同義である。そうした想定を十分に身をもって納得するために私たち分析家は、自分自身が精神分析を受ける体験を持つと言えるだろう。精神分析を受けるなかで大きな他者をもう一度体験する機会を集約的に持つことによって、精神分析家は自分のなかの、ひいては人間ひとりひとりのなかの夜の側面の力を知るのである。
そうした訓練とは無縁な熊谷さんが、どうしてこれほど率直に正直に、かついきいきとした生気を保持したままで、リハビリの夜の側面を語れるのか、私には謎だ。それはおそらく子どもの頃から何度もリハビリという形で「大きな他者」にさらされ、「敗北の官能」を経験したことと無関係ではない。だがそれだけでこのような言葉が語れるわけでないことは、他の脳性麻痺の人たちと比べてみればわかる。
この本が面白いのは、夜を語る存在、たぐいまれな夜の語り手である熊谷さんを近くに感じることにもとづいている。そのことによって、読者の私たち自身もわずかでも夜を語れるようになるかもしれない。私たちは熊谷さんの助けを借りて、官能にからめとられている自分のこころ、からめとられてこそ構築される自分のこころを、認識し、深く受け入れることができるかもしれない。
(『精神看護』2021年3月号より転載)
痛いのは困る。気持ちいいのがいい。
現役の小児科医にして脳性まひ当事者である著者は、あるとき「健常な動き」を目指すリハビリを諦めた。そして、《他者》や《モノ》との身体接触をたよりに「官能的」にみずからの運動を立ち上げてきた。リハビリキャンプでの過酷で耽美な体験、初めて電動車いすに乗ったときのめくるめく感覚などを全身全霊で語り尽くし、リハビリテーションを根底から定義しなおす驚愕の書。