かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
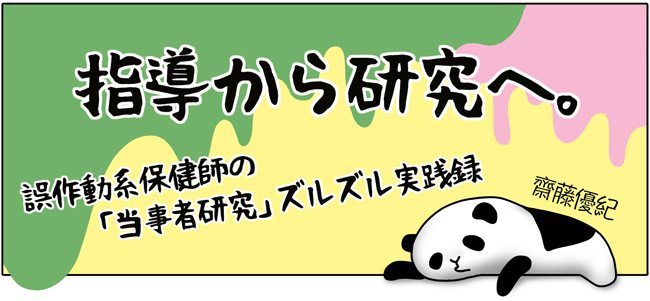
第4回 狂気の最終兵器
2015.3.14 update.

保健師。看護大学を卒業した2013年に札幌市の「なかまの杜クリニック」に勤務。
2014年4月より、釧路市の内科病院にて保健指導などにかかわる。
趣味は踊ること歌うこと、食べること。
最近「夫婦喧嘩の歌」をつくって夫に披露したら怒られた。夫婦漫才のネタを考えて夫に提案したらもっと怒られた。
前回は、ちょっとエラそうに、当事者研究的「支援の3段階説」を開陳させていただきました。復習すると、
①相手の中に入っていく…………苦労の連帯作業
②「人」と「苦労」を分ける……苦労の外在化
③苦労を相手にお返しする………苦労の再内在化
となります。今回はこの三つのエッセンスをもとに、母と私のあいだで起きていたことを振り返るところから始めます。
■①の過剰(相手の苦労に入り込みすぎ)
多くの医療者-対象者間で起こりがちな“怒られ現象”の解明が今回の話の発端でした。母の苦労を通して私にも生じたこの現象は、①の「苦労の連帯作業」で相手に潜り込み過ぎてしまっているがゆえに、②の「苦労の外在化」ができなくなってしまったのではないかと思っています。
私にとって母は特別大切な他者です。その身近さと、ふだん勉強を重ねている病気の情報が合わさって、母の苦労に入り込んだまま抜け出せなくなっていたのです。
医療情報や生活のアドバイスをあれこれしているのですが、本人に届いていないお説教やアドバイスは、潜り込んだ相手の苦労に耐えられない支援者の、不安が暴走した結果に過ぎません。こんなときの“指導”は、相手からすれば怒られているだけです。
とはいえ、この“怒られ現象”は、ある意味で、当事者研究的対話の重要なプロセスなのかもしれません。お互いにモヤモヤしたり疲弊したりして、結果的にはあずましい(北海道弁ですか? 「心地いい」みたいな意味です)対話関係を築くことができていないのですが、「相手の中に入り込めている」というのは、少なくとも希望であり、可能性であると思うのです。
■①なしの②(相手の苦労に降りないで外在化のみする)
これに比べて恐ろしいのは、相手の中に入ろうともせずに、「人」と「苦労」を分けることです。具体的には“指導”だけをする支援者ですね。相手の中に入りすぎて抜け出せないタイプは、当の相手の苦労に耐えられず“指導”に暴走してしまいますが、こちらタイプはその苦しさを経由していません。
だから支援者には負担が少ないかもしれませんが、言うなればこれは、「人」を見ずに「病気」や「症状」だけを相手にしている支援です。それでいて相手の苦労に降り立っていないから、何か問題があれば当人のせいにしがちではないでしょうか。
前回、相手の苦労の渦に溺れないためには「薄着でよいのでいったん白衣を着る必要がある」と書きましたが、こんなダウンジャケットのような白衣までいりませんよ(笑)。保健指導や慢性疾患療養分野に限らず、目の前に見える問題や観察できるデータだけに向き合っていてはうまくいかないことに、医療の世界は既に気がついています。今後医療従事者に問われるのは、ていねいに「相手の苦労に降りていく」力だと、私はこっそり確信しています。
■①②なしの③(何もせずに自己責任論を振り回す)
さらに恐ろしいことがあります。①の連帯、②の外在化のプロセスがなく、③の再内在化のみが行われていたとしたらどうでしょう。あえて言語化するならこれは、「放り出す」ようなものでしょう。
苦労の主人公が自分自身であることはもちろん大切です。しかし、相手の苦労に降りいき、「その苦労はあなたとは別物だ」と宣言するプロセスを経ずに再内在化をするということはつまり、「あなたの苦労はあなたの責任だから、自分でなんとかしなさいね!」と言っているにすぎません。人に対する究極の無関心でしょう。
これは医療でもなければ、ケアでもありません。「自分自身で、共に」はフッサールが提唱した言葉であり、当事者研究の大切な理念の一つですが、自分だけで自分の面倒をみて生きていけるほど、そもそも人間は強くないと思うのです。
■ここで秘策が登場! ってかそれ狂気?
さて、私は相手(母親)の中に留まったまま外に出られずに、こちらから見れば「指導し、指導される関係」、あちらから見れば「怒り、怒られる関係」を続けていたわけです。では、こんなとき、どうしたらいいのか?
ここからは私も実践できていないぼんやりとした話をすることになってしまいますが……もしかしたら大切なのは、にもかかわらず「信じる」ことでしょうか。
しかしこれは、私が当事者研究の理念の中でいまだに信じられない理念でもありますし、向谷地生良の狂気(笑)であるとも感じています。
べてるは信じることを大切にしています。どうしようもない爆発を繰り返す人だって、信じる文化があるから周りのみんなは笑って見守ることができるのかもしれません。
その人の回復を信じるのか、人間性を信じるのか、内なる善意を信じるのか、私にはよくわかりません。以前、向谷地さんに「信じるコツ」をうかがったところ、彼は「無理やり信じる」「ヤケクソで信じる」と言って笑っていました。狂気の沙汰だと思ってゾッとしたのを今でも忘れられません。
私はいまだに手放しで信じることができません。任せることができません。心配になるとついお節介が暴走してあれこれ言ってしまいますし、それでしょんぼりした相手に自分がしょんぼりすることもよくある話です。これだけ当事者研究をしているつもりでも、相手の苦労に入り込みすぎて対話がこじれてしまったり、かかわりが過剰になって結果として苦労を相手から奪ってしまったり……。まだまだ下手くそで残念なのが今の私なのです。
■ギリギリの選択としての「にもかかわらず」
心配したり、お節介を焼いたり、要するにリスクにばかり敏感になっていると、どうにも動きが凝り固まって、悲愴感が生じてしまいがちです。悲壮感にあふれた対話なんて誰もしたくはないですよね。そこでつながりもまた切れてしまいます。
先ほど「任せる」と書きましたが、そもそも相手と連帯するプロセスには、自分自身と相手に対する「絶対的に肯定的な眼差し」が必要なのかもしれません。それで思い出すのは「にもかかわらず」の思想です。
これはドイツ語で「トロッツデーム(trotzdem)」の思想と呼ばれ、V・Eフランクルの『それでも人生にイエスと言う』という本に詳しく書かれています。「それでも」、「それにもかかわらず」、もっと言えば「だからこそ」、生きることを否定せず、人生を肯定して生きていくというギリギリの選択肢なのではないかなぁと思っています。
当事者研究における楽観主義は、甘っちょろい楽観主義や表面上のお気楽主義ではなく、生きることの不条理や耐えられないような試練を踏まえたうえで、困難を、困難を生きることを肯定していくという、ある種の覚悟を伴った哲学だと私は感じています。
起きている問題を自分が解決しようとせずに、相手に苦労をお返しして問題を「眺める」のは今の私にとっては至難の業かもしれません。
苦労に対して楽観的であることや、困難の中にある他者をヤケクソで信じるような境地には若輩者の私はまだ立てていないので、怒られた心地になる母には申し訳ないけれど、もう少し口うるさくお節介な私でいるしかないのかなぁと思っています。
(「指導から研究へ。――誤作動系保健師の「当事者研究」ズルズル実践録」
齋藤優紀 第4回 了)





![[当事者研究]自殺未遂とひきこもり、私の場合。第1回 イメージ](http://igs-kankan.com/article/%E3%81%B2%E3%81%8D%E3%81%93%E3%82%82%E3%82%8A270.jpg)

