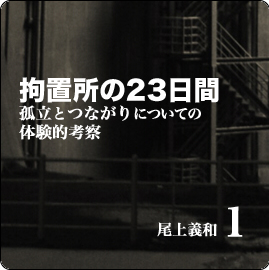かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

最終回 症状 ― それはすでに一つの解決である■大澤真幸
2014.12.13 update.

■社会学者
■1958年、長野県生まれ。
■主な著書に、『行為の代数学』『身体の比較社会学』『ナショナリズムの由来』(毎日出版文化賞)『〈自由〉の条件』『社会は絶えず夢を見ている』『不思議なキリスト教』(橋爪大三郎氏との共著)『〈世界史〉の哲学 古代編・中世編・東洋編』等多数。
最新作は、『〈問い〉の読書術』『現代社会の存立構造/『現代社会の存立構造』を読む』(真木悠介との共著)『「知の技法」入門』(小林康夫との共著)など。 個人雑誌『大澤真幸THINKING「O」』を刊行中。
オフィシャルウェブサイト http://osawa-masachi.com/
当事者研究は、何を研究しているのだろうか。当事者研究は、病の当事者自身が主役となる研究だが、そこで何が探究されているのか。
一般に、人は次のように考える。まず問題が与えられる。われわれは、それに対する解決=回答を知らない。研究は、その解決を探し出すことだ。研究という営みは、これまで、このような構図で理解されてきた。このとき研究は「試験」と同じである。問いが与えられ、われわれ「受験生」は、正しい解答で応じられるかが試されるのだ。
しかし、――私の見るところ――当事者研究は、いやべてるの家で編み出されてきた実践のすべてが、この構図を完全にひっくり返している。どういうことか。さまざまな症状、たとえば幻聴とか幻覚とか妄想とかいった症状として現出している病は、ある意味では、それ自体すでに解決のひとつの形態であると見なされているのだ。当事者は、症状によって、あるいは症状において、すでに答えているのである。つまり、当事者が知らないことは、「何が解決か」ではない。彼らは最初から、その解決をもっているのだから。当事者が知らないこと、理解できていないことは、「それ」が仮に解決だとしても、いったい何の解決なのか、ということである。
一般の研究は、問題が何かは自明であり、それへの解決を探索する。当事者研究では、逆である。自明なのは、これ(症状)が解決のひとつの形態だということであって、探索すべきは、問題の方である。どんな問題に対して、私はこのような解決(症状)を提出しているのだろうか。これが当事者研究的な主題だ。
この先に、さらに転回がある。……と、いうより「症状がすでに解決だ」というとき、さらなる転回がもう用意されている。症状が何の解決だったのかという観点に基づく当事者研究は、探究を通じて、次のことを明らかにするのだ。すなわち、「問題/解決」という二項対立など存在しなかったということ、このような二分法自体が誤りであるということ、このことを当事者研究は、その過程を通じて、自然と示すことになる。
「問題」を消し去る効果をもつような「解決」など存在しない。解決とされていること、症状がそのひとつであるような「解決」とは、問題のさまざまな扱い、問題への反復的な対応である。当事者研究は、このことを確認する過程となっている。問題とは独立に解決があるわけではない。もっとはっきりと言ってしまえば、解決は、問題のひとつの様態、問題の一部である。したがって、問題しか存在しない、と言ってもよい。
つまり、こういうことである。普通は、問題があって、それに対する反応として解決がある、と見なされている。だが、当事者研究の立場は、これとは違う。それぞれの解決は、それ固有の仕方で、問題を定式化しているのである。解決が問題そのものに含まれている、というのはこの意味である。各解決は、それぞれ独自に問題を措定しているのだから、問題を解消したりはしない。この点に着眼すれば、問題と解決は完全に一体である。
当事者研究の実態に即して、説明してみよう。
初めての人が当事者研究にとりわけ驚くのは、病の困った症状とされているものが積極的な活用されていることを知ったときであろう。そのような活用の技法が典型的に現れるのが、「幻聴」の扱いである。べてるでは、幻聴は、「幻聴さん」である。つまり、幻聴は歓待されるべき客人のように見られている。本来だったら、幻聴は、消えて欲しい症状、撲滅すべき敵なのではないか。それがどうして、幻聴さんとして歓迎されるのか。当事者研究では、幻聴を消去させるのではなく、まったく逆に、たとえば、どのようにして幻聴と友好的な関係を築くかが検討される。ときには、幻聴さんと相談する、という手段がとられることさえある。
当事者研究のこうしたやり方の底流にあるのは、次のような考えである。幻聴は、当事者が無意識のうちに採用しているひとつの解決である。言い換えれば、幻聴は、当事者なりの問題の定式化なのだ。そうだとすれば、幻聴がある方が、ないよりもはるかによい、ということになるだろう。幻聴がなければ、問題を「それ」として措定することさえできていないことになるからだ。したがって、幻聴を抑圧したり、排除したりしてはならない。幻聴さんとして大いに歓迎すべきだ。べてるで、「病気で幸せ、治りませんように」などと、何も知らない者にはまったくふざけているとしか思えないことが言われる理由も、ここから明らかになるだろう。病気であること、いろいろな症状が出ているということは、患者がすでに解決へと向かっていることを示しているのであり、症状がない者の方が、解決から遠いところにいるのだ。
ただし、問題の定式化の方法は一通りではない。問題の、よい定式化の方法と、まずい方法があるのだ。われわれは普通、正/誤を云々できるのは、回答に関してであって、問題に対して正しいとか、間違っていると言うのはナンセンスだと思っている。だが、そうではない。正しい/間違っている――は言い過ぎだが、良い/悪い、適切/不適切、うまい/下手といった弁別が意味をもつのは、問題(のたて方)に対してなのだ。当事者(患者)は幻聴などの症状に苦しんでいるとき、彼または彼女は、問題のたて方、問題の出し方に関してまだ稚拙なのだ。当事者研究は、上手な問題の定式化の方法、上手な問題の出し方を探究しているのである。
このように考察を進めてくると、どうして、「当事者」が研究しなければならないのか、なぜ当事者を巻き込んで研究しなければならないのか、つまり、どうして第三者だけで(つまり医者だけで)研究してはいけないのかが、明らかになる。その問題(のたて方)がうまいのか、まずいのかという区別は、当事者の観点に対してしか意味をもたないからだ。与えられた問題に対して適切な回答かどうかという判別であれば、第三者がなしうる。しかし、問題それ自体がよいか悪いかを判定できるのは、当事者だけだ。それは、当事者が感じる快/苦、幸/不幸に依存して決まるからである。
当事者研究のうちに含意されている、問題と解決との関係は、普遍性と個別性(あるいは特異性)の関係だと言ってもよいだろう。「解決」とは、要するに、問題の定式化の仕方、問題のたて方だ、と述べてきた。それぞれの当事者は、自分なりの個性的な方法で,つまり固有の特異的な視点から普遍的な問題を定式化しているのである。ここで重要なことは、普遍的な問題にいきなりアクセスすることはできないということ、つまり、特異的な定式化を媒介にしなくては普遍性の次元に到達できないということである。当事者研究において、各当事者は、「統合失調症爆発依存型」等の自分で納得できる、そしてほとんど固有名のように機能する「自己病名」を付けなくてはならないのは、そのためである。
最後に、ここで述べたことを、現代哲学の概念と対応させておこう。
たとえば、ジル・ドゥルーズは、「シーニュsigne(記号)」と「表象représentation」とを区別している。両者は、どう違うのか。ICD(WHOの国際疾病分類)に基づいて、あなたの病気は「妄想型の統合失調症である」と言えば、これは、ドゥルーズ的な意味で「表象」である。それに対して、「統合失調症・九官鳥型」のごとき自己病名は、「シーニュ」である。ドゥルーズは、表象は間接的で、シーニュは直接的だ、と述べているが、何に対して間接的・直接的なのだろうか。
ここで当事者研究に即して述べてきたことを前提にすれば、こう言ってよいだろう。「問題」に対してだ、と。「それ」が、すでに問題に対する解決という構えをもっているとき、それはシーニュと見なされるのである。状態の記述を代理しているだけであれば、それは表象に留まる。シーニュを通じて接続する普遍的な問題の次元は、ドゥルーズの哲学の用語では、「潜在的なものvirtuel」と呼ばれる。当事者研究は、哲学の動向などまったく考慮したこともないのに、その必死の試行錯誤の中で、意図することなく、哲学の先端と共鳴し合っているのである。

(当事者研究に寄せて「最終回 症状―それはすでに一つの解決である」大澤真幸 了)
*ご購読ありがとうございました。全5回の文章は、こちらのアーカイブへどうぞ。





![[当事者研究]自殺未遂とひきこもり、私の場合。第1回 イメージ](http://igs-kankan.com/article/%E3%81%B2%E3%81%8D%E3%81%93%E3%82%82%E3%82%8A270.jpg)