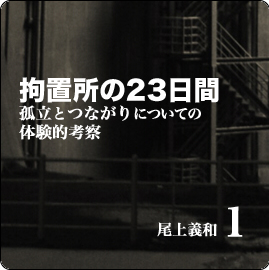かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

第3回 当事者研究と哲学■國分功一郎
2014.12.10 update.

■哲学者/高崎経済大学准教授
■1974年、千葉県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。
■主な著書に、『スピノザの方法』(みすず書房)、『暇と退屈の倫理学』(朝日出版社)、『ドゥルーズの哲学原理』(岩波書店)、『来るべき民主主義』(幻冬舎新書)など。
私は哲学を専門としている研究者であるが、熊谷晋一郎氏の様々な論考を通じて当事者研究に関心をもち、氏とともに、当事者研究から得られた知見を一つの手がかりとした共同研究のようなことも行っている。私はその中で、当事者研究という実践が、哲学の未解決問題、そしてまた、哲学が結局のところ避けて通ってきた問題に対する大いなるヒントを与えてくれることを確信するようになった。おそらくそうした問題はいくつも数え上げることができるだろうが、ここでは私の専門に近い分野から論点を提示してみたい。
私の専門の一つは17世紀の哲学者スピノザの哲学である。スピノザは『倫理学』という本の中で、「善い生き方」をめぐる全く新しいヴィジョンを提示した。それをごく簡単に説明すると、私の行為は、それが行われる同時に、私に私の力がいかなるものであるかを教えてくれる限りにおいて「善い」ものだということである。
たとえば、私が数学の公式を理解する。私はその時、その公式の内容や構造を理解すると同時に、自分にとって「理解する」とはどういうことか、あるいは、自分の場合には「数学の公式を理解する」とはどういうことかを理解する。つまり、理解することが、理解する力の何たるかを教える。
同じことが身体にも言える。『エチカ』に殴打の話が出てくる(第4部定理59備考)。人が怒りや憎しみから拳を固め、腕を振り下ろすということはありうる。その時、我々の認識は混乱している。だが、「殴打という行動は、我々がこれを物理的に見て、人間が腕を上げ、拳を固め、力をこめて全腕を振り下ろすということのみを眼中に置く限り、人間身体の機構から考えられる一個の徳である」。たとえば空手の道場で正拳付きの練習をするとき、人は自分の腕や体にいかなる力があるのか、それはどうやるとうまく使えるのかを理解する。つまり身体を用いて行為しながら、その行為によって身体の力を認識するのである。
人は幼い頃より、自らの精神と身体の力を少しずつ認識しながら生きてくる。熊谷氏の言葉でこれを言い換えるなら、この作業を、「反復構造についての予測モデル」の構築と呼ぶことができるだろう。自らの力を認識するとは、自分の精神や身体がもつ、「こうするとああなるし、ああするとこうなる」という概ね繰り返されるパターンについて、予測を得られるようになるということだ。
この予測が得られないと、たとえば、うまく身体を動かすことができない。あかちゃんは、おしゃぶりしたいものを手にとっても、はじめはなかなかそれを口まで運ぶことができない。手をどう動かすと手に持ったものが口に届くかについての予測モデルが未構築だからである。うまくこのモデルが構築できていくと、人は楽に──スピノザの言葉で言うならば「善く」──生きることができるようになる。
だがどうすればそれをうまく構築していけるのだろうか? また、様々な条件──先天的、後天的、あるいはまた環境上の諸条件──によって、その構築が妨げられてきた場合、人はどうやって構築していったらよいだろうか。
ここでポイントは、そうしたモデルの構築は必ず他との関係の中で作り上げられるということだ。あかちゃんは、自分がおしゃぶりしたいと願う、自分の身体の外にあるもの(おもちゃなど)を手にすることで、自らの腕の動きを学ぶ。とはいっても問題はやや複雑である。自らの力を認識していくこと、すなわち予測モデルの構築は、いわば「自分」そのもののを作り上げていく作業である。あかちゃんにとっては、自らの身体もまた自らのとっての「他者」である。すると、「他との関係」といっても、生成しつつある自分が、他者と関係しつつ生成するという複雑な事態を考えなければならない。
ここはまだ私の考えがまとまっていないところなのだが、スピノザの哲学はやや個人主義的なところがあり、他との関係を通じた予測モデルの構築について、すこしはっきりしないところがあるように思う。当事者研究のもたらす知見は、少なくとも私にとっては、このはっきりしないところに像を与えてくれるものだ。熊谷氏は当事者研究の効果の謎を解き明かすべく、他者を介在させないとうまく発見できない反復構造があるのではないかという問題提起をしている。私はここに一番関心がある。すなわち、スピノザの言う「力の認識」には、他者を介してはじめて可能になる面があるかもしれないのである。
そうすると、ここから問題は更に広がることになる。哲学者たちは他者を専ら知覚の問題の領域で捉えたり、義務論的に「他者に向かわねばならない」と主張したりといったことを繰り返してきた。ところが、どうして我々が他者を欲するのかは説明されていない。
たとえばジャン=ジャック・ルソーは、自然状態にいたら、人間は他人のことなど鬱陶しいと思うに決まっているから、各自はバラバラに孤立して暮らすだろうと言っている。この説は相当な説得力がある。何らの拘束も義務もない状態だったら、別にどこかや誰かのもとに留まっている理由などないのだ。誰かといても面倒なだけである。
だが、そうはいっても、現実の我々はそうではない。我々は他者を欲し、誰かと一緒にいたいと願う。それはなぜなのだろうか? ルソーの言うように、バラバラに、自分の思うがままに、好き勝手に生きたいと、なぜそう願わないのだろうか? ここにこれまで哲学が無視してきた大きな謎がある。もしかしたらスピノザ哲学にはそれを解く鍵があるかもしれない。そして、その鍵を探すにあたって、私が一番関心を寄せているのが当事者研究なのである。
人間は自らの力を認識しながら生きている。これはつまり、人間が「研究」する存在だということである。熊谷氏は「当事者研究」という言葉の中で、「当事者」の部分よりも「研究」の部分に関心があると言っている。人間は「研究」しつづけて生きていく存在なのではないかという問題提起である。すると、当事者研究の経験から次のような仮説を導きだせることになる。人間は「研究」し続けて生きていく存在、「研究」し続けなければ生きていけない存在であるが、その「研究」にはどうしても他者が必要であり、それ故に人間は他者を欲する──という仮説だ。つまり「他との関係」における自らの力の認識というモーメントをより強く捉えてみるのである。
これはあまりにも自分中心的な考え方だろうか。そうかもしれない。とはいえ、他者を欲するのは確かに自分なのだ(スピノザは存在というものの根幹に、個体が自らを維持しようとするコナトゥスという力を見ていた)。そしてまた、このことは、そうして近づいた者たちが、「研究」の必要性を超えて感じ合ったり、愛し合ったり、大事に思い合ったりすることを少しも妨げはしない。たとえ最初は「研究」上の必要性から「研究チーム」を組んだにすぎなかったにせよ。
もちろん以上は完全な仮説である。だが、この未解決問題、これまで避けられてきた問題に対し、当事者研究が極めて有益なヒントをくれることは間違いない。しかも、そうして獲得されるであろう〈新しい哲学〉は、私たちが「善く生きる」ことを可能にしてくれる。私もまた、哲学のためにではなくて、自分が「善く生きる」ためにこの課題に取り組んでいるのである。

(当事者研究に寄せて「第3回 当事者研究と哲学」 國分功一郎 了)
*第4回は末井昭さんです。12月12日頃UP予定。





![[当事者研究]自殺未遂とひきこもり、私の場合。第1回 イメージ](http://igs-kankan.com/article/%E3%81%B2%E3%81%8D%E3%81%93%E3%82%82%E3%82%8A270.jpg)