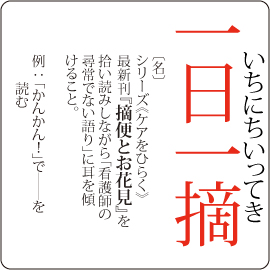かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
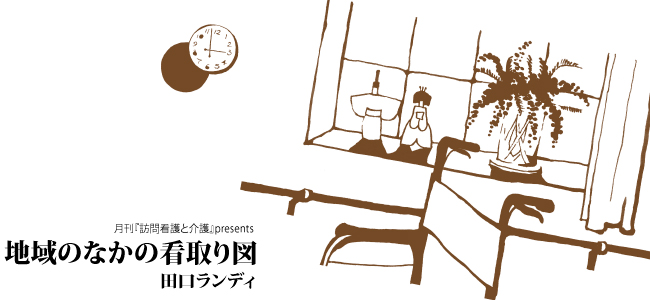
6-3 「夢の中」へ入る方法--「看取り」のかたち〈その3〉
2013.8.28 update.
『訪問看護と介護』2013年2月号から、作家の田口ランディさんの連載「地域のなかの看取り図」が始まりました。父母・義父母の死に、それぞれ「病院」「ホスピス」「在宅」で立ち合い看取ってきた田口さんは今、「老い」について、「死」について、そして「看取り」について何を感じているのか? 本誌掲載に1か月遅れて、かんかん!にも特別分載します。毎月第1-3水曜日にUP予定。いちはやく全部読みたい方はゼヒに本誌で!
→田口ランディさんについてはコチラ
→イラストレーターは安藤みちこさん、ブログも
→『訪問看護と看護』関連記事
・【対談】「病院の世紀」から「地域包括ケア」の時代へ(猪飼周平さん×太田秀樹さん)を無料で特別公開中!
心がここに在るのかどうか
私は、正気の父とはうまくコミュニケーションすることができませんでした。正気の父は長年の癖から抜けることができず、わざと的をはずして矢を射るのです。言葉はいつもあらぬ方向に飛んでいって、私の心に届きませんでした。私はそんな父とのやりとりにくたびれていました。
ところが、父が正気を失っていくに従い、父は的をはずすことすらできなくなりました。押し寄せてくる幻覚妄想をコントロールできず、ただもう内的世界をあふれ出させているだけの状態になってきました。
とても混乱してはいたけれど、その混乱に嘘はありませんでした。それは真実の混乱でした。私は次第に、父が幻覚や幻聴を通して感じている「父の心」を知りたいと思うようになりました。そこには、父の本心、本当の心が現われているように感じたからです。
病院から、父の混乱に配慮して「向精神薬を投与してはどうか?」という提案を受けました。静かな気持ちで最期を迎えたほうが本人にとって楽ではないか、と言われたのです。
私は、それに強く反対しました。薬で落ち着かせてしまったら、父の本来の感情が十分に出せなくなる、と感じたのです。それは……直感でした。父はもともと、気性の激しい人です。多動で、アクティブな父を薬で静かにさせてしまったら、父が伝えたいことがわからなくなってしまう……。父には最期まで自由に自己表現してほしい。でも、そんなのは私の素人考えなのだろうか……。
私は何度も病院の院長と話しあいをしました。そして、結果として父に向精神薬は投与されませんでした。父はせん妄状態で徘徊を続けましたが、看護師さんたちは、私の望みどおり、そんな父を好きなようにさせてくれました。だから父は、他の患者さんとは違い、いつも廊下をうろうろ歩き続け、父だけが見ている世界を見て、傍目には狂気のように映ったでしょう。日に日に特異な行動が目立つようになりました。私はその父にずっと付き添いました。なぜか、せん妄状態の父のほうが私にとって楽でした。父はもう、自分の内的世界のさまざまな妄想と向き合うことで必死で、長いこと身につけていた言動のパターンを切り捨てていました。だから、私に対してようやくまっすぐな言葉を語るようになっていたのです。
うまく言えませんが、私は「父の夢の中」で、初めて、ひねくれていない素直な父と出会ったのだと思います。そのためには、私も父の夢の中に入る必要がありました。そして、死んでいく人の夢の中に入るためには、ホスピスはとても適した場所だと思いました。だって、ホスピスはその場所自体がもう、この世であって、この世でないような、曖昧な場所だったからです。
次第に、私はホスピスに寝泊まりするようになりました。
そこはいつも花が咲き、静かで、人々も穏やかで、日常生活から隔絶されていました。時は止まっているように感じました。外の世界で動きまわって仕事している私にとって、ホスピスの静寂は不気味ですらありました。でも、その場に寝起きしていると、だんだんと場の空気に馴染んで、私のなかの時間もゆっくりゆっくりになり、そうなったとき、やっと父の夢に入り込むことができました。
たぶん、私は外の世界の殺伐とした慌ただしさを身にまとっていたのです。だから、シェーバーを持って父の前に立ったとき、私のその「強引さ」に父は恐怖を覚えたのかもしれません。外から来た人間は「何かをしよう」「すばやくしよう」「合理的にしよう」と必死です。でも、もう死が近づいてきた人には、焦ることも、何かすることも、合理的であることも……苦痛なのだと思います。
何もしないで、1日をホスピス内で過ごすことは、働き盛りの人間には耐えられません。でも、それも2、3日すれば慣れていくのです。私は、執筆することすらやめて、ホスピスの中で父のベッドの寄り添い、本を読んだり、音楽を聞いたり、おりがみを折ったりして過ごしました。父も次第に落ち着いていきました。もちろん、奇妙な言動は変わりませんが、安心したようでした。
その安心は、赤ちゃんが「お母さんはずっとここにいる」とホッとするような安心に見えました。父の心の世界では、私の心が忙しくなった瞬間に、私は消えてしまうようなのです。実態がここに在るかどうかではなく、心がここに在るかどうか……。それを、父は敏感に感じとっているようでした。
転換する世界
ある日、父が言いました。
「墓のことは、おまえに任せた。頼む」
墓のこと……。父は長男なので、先祖の墓のことが気になっていたのでしょう。すでに兄が死んでしまった父の家系は、父が死ねばお家断絶です。先祖の墓をどうするかを、父は気に病んでいたのでした。
「わかった。お墓のことは私がなんとかするから、安心して……」
父は黙ってうなずきました。
船乗りだった父は、若い頃にはよくこう言っていました。
「俺は墓なんぞいらん。俺が死んだら、骨は海にほっぽってくれ。いや、俺は死ぬときは舟に乗って海に行く。そして、魚の餌になる」
そんなことばかり言っていた父でしたが、海の藻くずとなることはできませんでした。海から遠い山の中のホスピスで死を待つ父の気持ちは、どんなだったんでしょうか。そして、人間はそれまで墓のことなどに無頓着であっても、自分があちらの世界に行くことになったときは、あちらの世界で受け入れてもらえるかどうか……先祖が出迎えてくれるかどうかが気になるもののようです。
私は、自分が死ぬときのことを考えました。この世からあの世へ行く。つまり死者の世界に行く。死んだ人たちの仲間入りです。そうなったとき、死者に礼を尽くしていないと「おまえ、生きている時にずいぶん勝手やったなあ」と言われることになる。死者は私たちのすべてを見ているのです。
父が、死を前にして先祖を気にする気持ちもわかります。
死は別れのように思っていましたが、考えようによっては、死は死者との再会でもあります。死ぬ側の立場になったとき、この現世はもう現し世であり、彼岸の世界がより身近になってくる。看取りは、世界の転換を体験する大切な機会なのでした。
○
私が「父の夢」の中に自分も生きてみようと思えたのは、ちょうど父の看取りが始まる前から、精神科医エリザベス・キューブラー・ロスの本を執筆するため、彼女の著作のほとんどを読んでいたからでした。
ロスは、世界のターミナルケアの基礎をつくった人と言っていいでしょう。ロスが登場するまで、医療の現場において、死は科学の対象とされていませんでした。終末期の患者に直接インタビューを試みたロスは、その体験をもとに『死ぬ瞬間』(中公文庫ほか)という本を執筆しました。そして、有名な「死の受容の5段階」を発表します。
私はそんなロスの謎に満ちた人生を追いかけていました。私の看取りは、ロスが残したたくさんの言葉を道しるべにして始まったのでした……。
第6回了

いよいよ高まる在宅医療・地域ケアのニーズに応える、訪問看護・介護の質・量ともの向上を目指す月刊誌です。「特集」は現場のニーズが高いテーマを、日々の実践に役立つモノから経営的な視点まで。「巻頭インタビュー」「特別記事」では、広い視野・新たな視点を提供。「研究・調査/実践・事例報告」の他、現場発の声を多く掲載。職種の壁を越えた執筆陣で、“他職種連携”を育みます。楽しく役立つ「連載」も充実。
7月号の特集は「「緩和ケア訪問看護師」の“実践力”を育てる」。看取りまでを視野に入れた「在宅緩和ケア」の必要性・重要性が高まっています。そうしたなか「緩和ケア訪問看護師」を育てようとする動きがあります。多職種による24時間の「緩和ケアチーム」の要にもなる訪問看護師に必要な“実践力”とは?