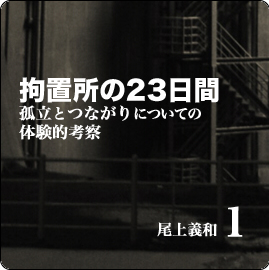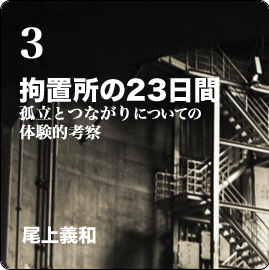かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
![[当事者研究]自殺未遂とひきこもり、私の場合。第1回](http://igs-kankan.com/article/%E3%81%B2%E3%81%8D%E3%81%93%E3%82%82%E3%82%8A%EF%BC%96%EF%BC%95%EF%BC%90%EF%BC%88%EF%BC%93%EF%BC%89.jpg)
[当事者研究]自殺未遂とひきこもり、私の場合。第1回
2012.2.07 update.
群馬県当事者研究会ピアリンクメンバー。
21歳で自殺未遂、それから36歳までの15年間ひきこもる。
現在、41歳。
第1回(2回連載)
視線の先には縁側のある古い家が見える。自分の修行のために1週間、母の実家に泊まりにきた。小学校1年生、7歳の私はそこで誓った。
「なんでも自分で考え、判断する強い人間になろう」
モノトーンのはっきりした記憶。
*
私は母から、「わがまま、甘えん坊、神経質の引っ込み思案。そんなんじゃだめだよ」といつも言われていた。
たしかに私は、親戚の家に行っても挨拶もできない。前を向いて道を歩けない。そのうえみんなと一緒に集団登園するときは、いつも30mくらい先を歩いてしまう。ときどき後ろを振り向くと、みんながわいわいがやがやと楽しそうに歩いてくるのを見て、どこかほっとする。
遊びのときも一緒だ。いつの間にか輪から離れて座り、みんなを眺めてぼんやりしている。そうすると少し安心する。
小学校に入ると、できないことがまた増える。手を挙げることができないで、机より下で手を伸ばす。音楽では声が出ない。ものすごい音痴である。先生に話しかけることもできない。職員室に入ることができなくて用が足せない。何日も何日も過ぎても用事が済ませられず、母に怒られる。
こんな自分は当然登園拒否もしたし、体温計を操作してズル休みもした。体温計をぬるま湯にくぐらして2回振ると微熱ができあがる。ひとりぼんやりと布団の中で過ごす。
そんな自分を、自分自身でうまく認められない。そして何よりも母はまったく認めてくれない。家の空気も、そんな弱い私を認めてはくれない。
「自分自身がひとり静かに内側から変えていくしかない」
そう思い、「夏休みに母の実家に1週間泊まり行こう」と決めた。それは今も鮮明に頭に焼きついている。
*
同じ小学校1年生のとき、文部省推薦の映画を両親と観にいった。
古ぼけた、がらんとした映画館。スクリーンでは15歳の少女が苦しんでいる。骨肉腫で片腕を切断したが肺に転移した。苦しみながら、ほんのわずかな奇跡と死を待つだけ。そのとき何かが自分を捉えた。かすかにしびれる冷たい空気が全身を包んだ。
「こんな痛みには自分は耐えられない。こんな苦しい死に方は嫌だ。こんな痛い思いをして生きていたく(死にたく)ない」
でこぼこふわりとした椅子のなかで、斜め上を見ながらおびえ続けた記憶。
*
私はいま41歳。5月になると42歳になる。21歳のときに自殺未遂をし、それから36歳までの15年間ひきこもった。
以下は、生まれてから自殺未遂をするまで、自殺未遂の前後、それからのひきこもり生活、の3つに分けて自分の記憶を掘り起こしていく。もっとも、15年間のひきこもり生活はA4で1枚にしかならなかった。ぼんやりしていたら、ただ15年が過ぎてしまったということなのだろう。
それはともかく、書き進めてみる。
1 生まれてから自殺未遂まで
■祖父という暴君
テレビのチャンネルが突然、アニメからプロ野球中継のあるチャンネルに回された。午後6時45分。アニメのクライマックスで、野球中継開始の15分前である。私は思わず「なんで!!」と叫んだ。
「なんでじゃあねえ! 野球だ」と祖父は応える。
「まだ15分あるよ」
「俺のテレビだ! 文句言うな」
「嫌だ! 観る」
そこで祖父の決め台詞が飛んでくる。
「てめえ俺の言うこときかねえで、娑婆を通れると思っているのか!!」
私は母に一度だけ訊いたことがあるそうである。
「あれは誰が買ったテレビ?」
「お父さんだよ」
「じゃあ、じいちゃんの言ってることは納得できない」
「しょうがないんだよ。お祖父さんが家でいちばん偉いんだ」
祖父との喧嘩の日々の始まりのころのやりとりである。4~5歳のときだと思う。
祖父は家の暴君であった。自分の欲求・欲望は、自分の内にひとときも留めておけないことが特徴である。そして自分以外の人間を信用せず、とても猜疑心が強い。次から次へと命令や要望が出てきて、それが順調に行っているか常に監視する。
その矛先のほとんどが私の母=嫁である。父も含め、母の味方をする人は誰もいない。黙っているのがいちばん利口な対処なのだ。
■黙っていられなかった
私が30代になったころ、母はよく理不尽な祖父の話をしてくれた。そのなかで強く記憶に残るのは、父が仕事でいないときに嫁ぎたての母が心細く緊張して食事をしていたときの話である。母の顔色を見た祖父は、こう言ったそうだ。
「てめえ、俺たちと食う飯がそんなにまじーなら食わなくていい! むこう行け」
姑の祖母も、義理の妹の叔母も、まったく助けてくれなかったそうである。これに似たエピソードが母の口から次から次へと出てきた。
私は、やり過ごしたり見てみぬふりはできなかったのだ。先ほど書いたテレビのチャンネル権争いから5~6年後の10歳くらいからは、母を助けるために祖父と母のやりとりの中へ入っていくようになった。祖父の言っていることに納得できなければ、怒鳴りつけて喧嘩をした。ものにも当たるようになって、家具や壁を壊したりもした。いわゆる“爆発”である。
どちらも謝ることを知らなかったので、両親、おもに母に止められた。
「なんでまともに相手にするんだ。ものは壊れるし、間に入ってくるのは迷惑だ」
だが私は、「納得できない」「俺がわからせてやる」と言い張った。すると母に「それが迷惑なんだ。気が短いところお祖父さんにそっくり」などと言われた。
こんなことを、私はそれから25年も続けることになった。家の中での爆発人生。
■少女の苦しみに身体を奪われて
小学校3年生のときに肺炎になり、入院せずに自宅療養したため、秋から冬の2か月間は寝ていることになった。
自宅療養の1日目に血の混じった痰を吐いた。止まらない咳、苦しさに翻弄される。そこから妄想的な想像が始まった。
……映画のなかで15歳の片腕の少女が血痰を吐く。肺転移。苦しみながら痛みに耐えながら生きて、死んでいく。
「えっ、まさか俺も」
頭と身体に衝撃が走る。次の朝もう一度血痰が出た。医者からは「気管支が切れたんだね。心配ないよ」と言われたが、いくら答えをもらってもどこか安心できない。
ひとり苦しむ少女の姿と自分の姿を重ねあわせ、苦しみながら、痛みに耐えながら生きていくことを、自分の身体をシンクロさせて味わう。そして「最期くらい楽に死にたい。自分は耐えられない。そんなんなら自殺したほうがいい」と痛切に想う。
ひとり痛みに耐えること、ひとり死んでいくことを、私は何回も何回も味わう。私の頭の中で15歳の少女の苦しみが続き、その苦しみに添いながら私も苦しみ続けた。
■「逆転の人生」に自分が付いていけない
2か月ちょっと学校を休んだことで、勉強はできなくなった。カンニングをして見つかる始末である。
小学校4年生のとき白くてむくんだ薄らでかい私は、女子の集団のいじめに遭う。「げろ! げろ!」と呼ばれる。このときの自分は「うるさい! むこう行け!」と言い返していた。傷ついていたと思う。それが怒りという形をとっていただけかもしれない。
しかし、この同じときに人生が変わりはじめる。
同じ4年生の秋からスイミングスクールに通いはじめた。ただでさえでかいのに、成長期に水泳を始めたことで骨太の見事な逆三角形の身体ができあがった。足は速くなり、運動神経も向上した。リレーの選手に選ばれ、野球部のレギュラーになった。
6年生では水泳の学校記録をほとんど塗り替えて、推薦されて児童会長になった。クラスの書記や、ソフトボール部の副部長などもやった。
中学に入っても成績は優秀だった。バスケット部では1年生からレギュラーでエース。班長、クラスの書記、生徒会の書記等をする。しかし、まるで違う人の人生みたいで、自分自身がうまく付いていくことができないのだ。
■期限を決めて生きてみる
とにかく集団行動がつらかった。特に自分がリーダーとしてやっていく集団行動はすごく負担になった。自分ひとりで考え、みんなを導きながら判断して行動しようとすると、いつも不安で、全身が緊張感にジャックされた。手のひらにはいつも冷や汗。しかし、弱音を吐いてはいけない、相談だってしたらいけない、他人の力に頼ったらそれで負けだと思っていた。
このように学校ではつらいなりに「別の人生」を歩んでいたが、家では相変わらず爆発が続いていた。祖父と毎日のように怒鳴り合い。ときに物損。理解してくれない母との口論。私は、2人とも間違っていて自分だけが正しいと思っていた。私の言っていることは考えていることは理屈に合っていて、みんなが従うべきなんだと思っていた。
ただそのとき、反抗期から思春期にかけて悩みはいつも全身を駆け巡っていた。
この叫びまくる爆発はどうにかできないのか?
理屈ではまったく制御できない、汚らしい性欲はどうにかできないのか?
人間関係のなかで、吐き気がするような不安と緊張にさいなまれる自分をやめられないか?
「楽に死んでしまったほうがましなのか……。会社なんか勤められるような気がしない」
そのころにはもう、期限を区切る生き方をしていた。
「小6まで生きてみよう。何か変わるかもしれない」
「中3まで生きてみよう。きっと何かが……」
期限を決めて、ダメだったら死んでしまえば、つまり自殺してしまえばよいと思いながら生きるようになっていた。するとなぜか気分は楽になった。
■逃げる優等生
自殺をする期限を考えた生活ではあったが、自分なりに必死にもがいた。
バスケット部のときは、ほとんど練習に出てくれない顧問の先生のかわりに、部長として必死に練習メニューを考えた。試合ではキャプテンとしてチームをまとめ、エースとしてチームを引っ張った。
ただ、負けるとほっとする自分がいた。
本当のところ、自分はバスケットボールに関してはまったくの無知、素人であったのに、部長をしていた1年間はバスケットについて誰にも聞くことができなかった。無知な自分は「弱くてダメな自分」と思っていた。そんな弱さを出して、みんな責められて傷つきたくない気持ちから聞けなかったのだと思う。
高校に行き、嫌々させられた生徒会長のときに、アメリカの姉妹校の生徒の歓迎会のスピーチをすることになった。歓迎会の4~5日前に突然、英語の先生から電話でスピーチを頼まれたのだ。
私は英語を話すのが何より苦手だったのでパニックに陥った。はじめから「無理だ」と思ってしまった。ある友達に電話をかけて、スピーチの内容を書いてくれと頼んだが断られたところで、逃げることに決めた。
前日に賞味期限の過ぎたピザをわざと食べて、腹痛を装って救急外来に連れていってもらい、めでたく「食中毒」との診断で入院した。おまけに新しいテレビとビデオデッキを買ってもらった。
■つらくて怖い世界
高校から大学時代にかけて病気の症状はどんどん出てきた。 頻尿、手足の極端な冷え、パニック発作。
あまりの頻尿のため普通に受験できず、指定校推薦で大学に入った。
また高校最後の飲み会で急性アルコール中毒になったが治療をしてもらえず、一晩で11kgも痩せた。それからは電車に乗るとしばしばパニックになった。
大学では食事の後の講義中やバス移動のときに激しいパニック発作に見舞われた。保健の先生は「血圧が90を切ったら救急者呼ぼうと思うんだけど……」と言っていたが、私自身は毎回「血を吐いて死ぬかも」と思って慌てふためいていた。
大学時代にあまりエピソードはない。大学1年の後半にパニック発作がおさまり、頻尿も少しおさまってきてからは、ただ授業に通っていただけである。バイトは自宅で家庭教師をしていた。
これを除いては人が怖くてアルバイトもしたことがなかったのだが、ここでも私は、親や友達に心情を話したり相談したりすることを思いつかない。弱いことを出すことに対して完全に無意識的ストップがかけられていた感じがする。なにせ相談という行為が思いつかないのである。
唯一、夢を見たのはゼミ選びのときである。「公務員になればどうにかなるかも……」と思って選んだゼミには面接で落とされた。悔しかったし、がっかりした。就職活動を始める前の大学3年なのに、完全に追い詰められた感じがあった。
「会社が怖い。そこにいる働いている人が怖い。そこで自分が泣き崩れるシーンが思い浮かぶ。揉めごとを起こして暴れまわる自分が思い浮かぶ。自分の思い通りにはならない。つらくて怖い世界……」
家では爆発し、外ではひとり考え、悩み、孤立して、最後は逃げる自分。さまざまな身体の症状。傷つかずに逃げる道はないのだろうか? そう思い悩む日々だった。
(村岡聡「自殺未遂とひきこもり、私の場合。」第1回了)



![[当事者研究]自殺未遂とひきこもり、私の場合。(2) イメージ](http://igs-kankan.com/article/%E3%81%B2%E3%81%8D%E3%81%93%E3%82%82%E3%82%8A270.jpg)