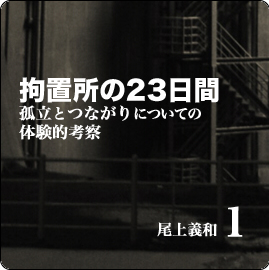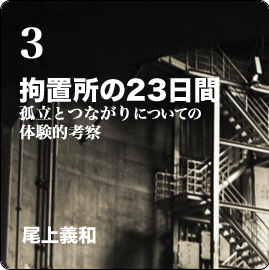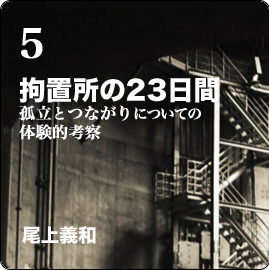かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

第5回(最終回) 私はひとりではない
2011.8.18 update.
2009年に障害者団体向け割引郵便制度を不正利用したとする容疑で、当時の厚生労働省村木厚子局長らが大阪地方検察庁特別捜査部によって逮捕・起訴された(その後村木氏は無罪確定)。
その後捜査を進めていくなかで、社会福祉法人全国精神障害者社会復帰施設協会(全精社協)との関連が浮かび上がった。大阪地検特捜部は2009年10月20日、精神障害者福祉施設「ハートピアきつれ川」(栃木県さくら市)の運営費などに流用する目的で厚生労働省から調査研究名目の補助金計約5100万円の交付を受けたという容疑で全精社協の会長、元副会長、元事務局次長、元常務理事(尾上義和氏)を逮捕した。
2009年11月、会長と元副会長は起訴処分(2010年に執行猶予の判決となる)、元事務局長と尾上氏は起訴猶予処分となった。
――本稿は、本件について大阪地検の取り調べを受けた当事者の尾上氏に、実際の体験を記していただいたものである。
会いに来てくれる妻があり、仲間がいる。
大げさに言えば、
これだけで人は救われるのである。
窓を開けると、鉄格子を通って涼しい風が吹き抜ける。
たった3週間あまりだが、ここへ来たころに比べると少し風の冷たさを感じた。もう11月10日である。
いつもの朝食を終え、小さな洗面台で歯を磨き、顔を洗った。ちり取りとほうきで年季の入ったデコボコの畳を掃く。それを終えると、妻や仲間が差し入れてくれた15冊ほどの本──上橋菜穂子の『獣の奏者』、村上春樹の『1Q84』など──を読む。
これが私の日課だった。
しかし最初は本を読むことさえできなかった。
逮捕されたとき、マスコミの連日の取材や、いつあるかわからない検事からの取り調べに毎日のように怯えていた私は、正直そんな空間から“逃れられた”という気持ちもあった。
だが、この狭い空間では何もすることがない。動ける範囲さえ限られている。「何もない」ということがこんなにつらいとは。息苦しさがすぐに私を襲ってきた。
本でもあれば時間がつぶせるかもしれないと思い、あるとき刑務官に「何か本はないですか?」と声をかけてみた。
彼はしばらくして1冊の本を持ってきてくれた。表紙が取れかかったボロボロの本だった。タイトルは憶えていない。
私は小さな机の前でせんべい座布団の上に正座をして本を広げてみたが、2〜3ページ読んで閉じてしまった。本の内容に興味がなかったせいもあるが、「本を読む」という行為自体に集中できないのである。
この狭い空間は、まるで川の流れがせき止められているようだ。
時間の流れもその場に留められ、淀んでいる。私の気持ちもこの空間のようにだんだんと淀んでいき、やがて底の見えない水の中に深く深く沈み込んでいった。
夢か現うつつか
「尾上さんは起訴猶予となりました」と検事が言う。
「キソユウヨ?」と私が聞き返すと、検事は少し考え「不起訴、みたいなものですね」と言った。
検事の話によると(以下私の解釈も含む)、会長と元副会長は直接的に事件に関与したとして起訴となった。
だが事務局次長と私は、会長・元副会長から指示を受けて書類等の作成をしたという「従属的な関係」であるため起訴猶予になったのである。
「ここから出られるんですね!」
内容はどうでもよかった。“ここから出られる”という事実だけが大きく感じられた。
明日がちょうど拘置期限の切れる23日目だった。
私はうれしいというよりも、なんだかホッとした気持ちになった。安らいだ気持ち、というほうが適当かもしれない。
本来ならば「待ちに待ったうれしい瞬間」なのだろうが、この閉鎖空間では、外の世界のように身体を自由に動かしたくても動かせないのだ。「動けない」という条件に身体が置かれると、心のほうもその条件に従ってしまうようなのが不思議だった。
このように拘置所では自分の意志で動けないという不自由さがあるのだが、夢の中は違った。
拘留されて2日目の夜だった。
長い一日が終わったと思いながら、薄っぺらい布団にゴロンと横になった。デコボコとした畳の感触がもろに身体に伝わってくる。寝心地のいいポイントを探りながら身体を動かすが、なかなかいい姿勢が見つからない。
それに、この閉鎖空間で唯一不自由さを解放してくれる大事な時間が“寝る”という行為なのだが、ここでは就寝時間となっても煌々と明かりが灯っている。
ふだん真っ暗にして眠る私の身体は、眠る時間なのか起きなくてはいけない時間なのかと、その判断力を見失っていた。もっとも、やがて時間とともに意識はだんだん薄れていくのであるが。
……夕方なのか?
木々のあいだから差し込む光は赤色を帯びていた。まわりには大きな木がところ狭しと生えていた。
下を見るとたくさんの落ち葉が敷きつめられているが、私のいるところだけが木は生えておらず、広場のような空間を作り出していた。
私を囲むように人の気配がある。
茶色く錆びた大きなコンテナのようなものに東京のAさんが座っていた。その横のドラム缶の後ろには、神奈川のYさんが立っていた。さらに周囲には、見覚えのある仲間が数人立っている。
仲間うちで何か話をしているようだが、突然Aさんが私に話しかけてきた。
「こんなところにいて大丈夫なのか?」
「大丈夫。外泊中だから」と私は普通に答えた。他の人も納得するように頷いていた。
その横からYさんが「これからどうする?」と聞いてくる。
私は「どうしたらいいかね」と困ったように言いながら、少し動き出そうとした。
すると突然、目の前に薄汚れたコンクリートの壁が私を覆うように迫ってきた! 私は混乱し、「ここはどこなんだ!!」とぐるりと見回した。……独居房だ。
私は現実の世界に引き戻されながらも、夢の中で見た一瞬の自由を噛みしめた。そして薄暗い空を見ながら、遠い朝を待った。
「俺らもわからないんや」
私は検事に「明日は何時ごろ出られるでしょうか?」と聞いた。
「それはわからないな。裁判所の手続きがあるから朝なのか昼なのか。明日は12時まであるから、出るのは明後日ということもありえる」
と検事は困ったような感じで、隣りの事務官を見ながら答えた。
出られると決まると、1分1秒でも早く出たくなるものである。
いつものように掃除をしているつもりであるが、だんだんと掃除の仕方が荒くなってくるのが自分でもわかる。
“いつものように、いつものように”と自分に言い聞かすように呟きながら、丁寧に埃をとっていた。
そんなふうにして掃除に没頭していると、刑務官が横を通りすぎるのが見えた。声をかけると、刑務官は振り返った。
「きのう検事から起訴猶予と言われたんですが、今日は何時ごろ出られるんでしょうか?」
刑務官は少し困ったような顔をしてこう答えた。
「俺らもよくわからないんや、俺らも出る10分前になってから言われるから、わからないんや」
刑務官であればわかっているだろうというのは、私の勝手な期待にすぎなかった。冷静に考えてみれば、ここを出ることを決めるのはここの職員ではなく裁判所なのだから。
刑務官にしても、何もわからないなかで、わからない人たちの対応をしなければいけないのだ。
拘置所へ拘留された初めの日に、刑務官から「何をしたんや?」と聞かれたことを思い出した。
目の前の相手がどんな人なのか、どんなことをしたのかの情報もまったく知らされないなかで、彼らは拘留者を受け入れなければいけないのかもしれない。
これまで何度も書いてきたように、「わからない」という状況は人を不安に陥れる。
しかも何らかの犯罪の容疑があるとされる人へ対応していかなければならないのだから、刑務官は相当な緊張感のなかで仕事をしているのだろう。
刑務官は私たち未決拘禁者に、昼間は机の前に座らせ、朝と昼の決まった時間帯に番号を言わせ、独居房から出るときは身体検査をして番号を言わせる。
もしかしたら──これは私の想像するところであるが──、こうしたたくさんの遵守事項を設け、管理することによって、「拘置所」という世界の秩序を保っているのかもしれない。
しかし私たちは未決拘禁者である。刑が確定し、執行されたというわけではないのである。
なぜここまで管理されなければいけないのだろうか。すでに身体的・精神的な自由を奪われているのに……。
かけがえのない差し入れ
なかば呆然としながら、ふと洗面台の下を見ると、お菓子やジュースがいくつも並べてあるのが目に入った。
「差し入れだ」という声が聞こえ、刑務官が小さな窓からさらに何本ものパックのジュースを入れてきた。
「名前を確認して、伝票に押印して」
名前の記載してあるところに目をやると、神奈川の仲間からだった。
「仲間からです! 来てくれたんですね。本当にありがとうございます」
私は思わず、届けてくれた刑務官に感謝した。刑務官も「よかったな」と優しい声で返してくれた。
拘置所入所中の人には、飲食物を直接差し入れはできない規則になっている。飲食物は、拘置所の外にある「差し入れ屋」というなんとも奇妙なお店を通して、ようやく入所者に飲食物を届けることができる。
つまり彼は、私に会いにここまで来てくれたのである。接見禁止だから、来ても会えないことは知っているにもかかわらず。
そういえば、拘留されてから2日目だったろうか。
検事から「門のところで、奥さんとお会いしました。背の高い男性と、女性の方と一緒にいましたね。あれは尾上さんのご友人の方ですかね」と言われた。
頭の中に即座に浮かんだのが、神奈川の仲間の顔だった。
「たぶんYさんと、Sさんだと思います」
「そうですか。しかしこんなに早く来ることなんて、あまりないですね。しかも面会もできないのに」
本当にそうである。顔を見ることもできないのに、大阪まで来てくれるなんて。
ここにある差し入れは、たかがパックのジュースであり、お菓子であり、コンビニやスーパーに行けばいつでも買える品物である。
しかし、私のために仲間が時間をかけて大阪という地まで来て、購入してくれたものである。
そう思うと、ここにある一つひとつの品物が、私にとってかけがえのないものなのだ。
妻との面会
「面会だ」と刑務官が顔をのぞかせて言った。
「ああ、はい……」と畳をほうきで掃いているときだったので、返事が中途半端になってしまった。
きっと妻だ。今日、この大阪拘置所から出るために迎えに来てくれていたのだ。
思えばここで初めて妻と面会したのは、拘留3日目、裁判所から戻ってきたときだった。
外はすっかり夕暮れ空となっていた。裁判所から戻ってきてすぐに「面会だ」と言われ、私はいつもの“調べ”かと思っていた。もう一度聞き直しても「面会だ」と言う。「誰ですか?」と聞き直すと、「たぶん奥さんだろう」。
すでに夕食時であるし、面会時間もとうに過ぎている。
しかも検事からは、面会はすぐにはできないだろうと言われていたのに。私は逸はやる気持ちを押さえながら、慌てて髪を整えた。
拘置所へ拘留された初めての日、私は鏡で自分の顔を見た。それはひどいものだった。
顔はやつれ、無精ひげがはえている。精気を失い、まるで漫画に出てくる浮浪者そのものだ。情けない。だからその後は鏡を全く見ていなかった。
でも不思議なものである。妻が来たと聞いて、こうして鏡の前で髪を整えているのである。
面会室の小さな窓をのぞくと、向こう側にはキョロキョロとあたりを見ます妻の姿が見えた。
「奥さんか?」と刑務官から聞かれ、「はい」と声を震わせながら答えた。
中へ入ると、とても小さな部屋だった。
向こう側の妻とのあいだには透明のプラスチックのボードが張られ、私のほうにはパイプ椅子が置かれていた。
私の横には、先ほどの刑務官が、私と妻の様子をうかがうような感じで座っている。私はなんとなく会釈をして入っていった。
妻の顔を見た途端に私は「ごめん」とひとこと言うと、それまで抑えていたものが一気に出てくるように涙が溢れてきた。プラスチックボードの向こうの妻も泣いていた。
面会室に行くまでの廊下では、第一声は何を言おうとかいろいろと考えていたが、結局考えていたことのほとんどは言えなかった。
それでも本来は15分間の面会時間であるが、この時間まで待っていてくれた妻を配慮してくれ、刑務官は30分間も面会をさせてくれた。これについては今でも本当に感謝している。
あんなにも涙を流したのは久しぶりだ。しかも人前であんなにも泣いたのは初めてかもしれない。
私以外の誰かとつながれているんだということが、私の身体を通して心に響いた。
妻や、仲間、仕事など、突然にすべての関係を断たれた私であるが、会いに来てくれる妻があり、仲間がいる。
大げさに言えば、これだけで人は救われるのである。つらいと思えることに耐えられる。そして温かい。
私は「このまま時間が通り過ぎるのを待っていてはいけない、この中でできることをやっていくんだ」と、右手の拳を自分の胸に当てて心の中で叫んだ。
すると今まで淀んでいた川が堰を切って流れはじめるように、私の周りの時間もゆっくりと流れはじめてきたのだった。
初めて見る拘置所
「今日は何時に出られるか、わからないんだ」と申し訳なさそうに言う私とは逆に、妻は明るい顔をして「検事さんから電話があって、午前中には出られるって言ってたよ」と言った。
その後は事がとんとんと進んでいった。
面会を終えて独居房に戻るとすぐに刑務官に「出るぞ。10分後に迎えに来るから、荷物をまとめておけ」と言われた。
「はい!」と私はいつもよりも高い声で返事をした。
荷物をまとめながら私は、ここへ来たときにはほとんど荷物がなかったことを思った。はるばる大阪まで私のために来てくれた妻や仲間が差し入れてくれたジャージや、下着、本やお菓子、パックジュースなど一つひとつを23日間の思いとともに、大きなキャリーバックへと詰めていった。
そしてスウェットを脱ぎ、拘置所に入ったときのスーツに着替えた。なんだか身が引き締まるような思いがした。
やっとここから出られるんだという嬉しさもあったが、もしかしたらマスコミが門の前で待ち構えているかもしれないという、ここへ来たときの恐怖が鮮明に蘇ってきた。
もしマスコミがいたら何と言ったらいいのだろうか、芸能人のように頭を下げて謝ればいいのだろうか──。
しばらくすると、刑務官がガラガラと音を立てて大きな台車を引っ張ってきた。
ガチャと鍵の音がすると、刑務官が「荷物はここに置いて」と言い、私はここに入るときに持ってきた大きなキャリーバックを台車へ乗せた。
「もう戻ってくんなや」と後ろから声がした。
私がここに入ったとき、最初に声をかけてくれた刑務官であった。私は「ありがとうございました」と深ぶかと頭を下げた。
荷物を乗せた台車を自分で引っ張りながら、職員が歩いていくほうを追いかけていく。徐々に丸まっていた背筋が伸びていくことがわかった。
ふと後ろを振り返ると、わりと新しいつくりの、大きな建物が見えた。
茶色いレンガづくりのような、行政施設によくある何の変哲もない建物であった。これはなんだ?
逮捕され拘置所へ移送されたとき、私はワンボックスタイプのワゴン車の後ろに乗せられ、両端には事務官2 人が付き添っていた。拘置所へ到着したときはすぐにマスコミに囲まれてしまい、その建物をじっくりと見る暇はなかったのだ。
これが拘置所か──。
それは、私が入っていたはずの建物とは別物に見えた。
ここから見えるのは「表面の顔」であり、この中には時間の流れなどない、こことは違ったもう一つの世界があるのだと心の中で思った。
身にしみる思い
拘置所の門を出た。
門の右横の小窓のついたところで、数人の男女が何か手続きのようなことをしていた。
面会者か? と思いながら正面を見てみると、タクシーが1台停まっていた。
……それだけであった。心配していたマスコミは一人もいなかった。
そんなもんなのかもしれない。私がここへ来たときの騒ぎは、すでに世間から過ぎ去ったものとなったのである。
日々の移り変わりは早い。ちょっとよそ見をしていたら、すぐに追いていかれてしまう。
ホッとしたと同時に、あのころ日々不安にさいなまれていた私は何だったんだろうと、虚しさのようなものを感じずにはいられなかった。
拘置所の門から左手に目を向けると、古い駅の待合室のような建物があった。その中で椅子に座り、足を組んで本を読んでいる女性がいた。
妻である。
声をかけると、いつものように「お帰り」と返してくれた。
この場所でずっと待っていてくれたのか。先の見えない時間ほど長く感じるだろうに。
時計のない生活の怖さを知っている私にとって、それは身にしみる思いであった。
荷物の量はかなりあったが、なんとかコンビニで宅配便などを手配し、一通り片づけ終えた。一休みしようということで、妻と近くの喫茶店に入った。
私は久しぶりに身体を動かしたせいか、氷の入った冷たいアイスコーヒーが飲みたくなり、妻がまだメニューを眺めているのを横目に迷うことなく注文をした。
久しぶりに飲んだアイスコーヒーの香ばしい香りが鼻の周りを漂い、ヒヤっとする感触が、喉からお腹へ流れていくのがわかった。
「うまい!」と思わず声が出てしまい、ちょっと恥ずかしくなり、周りの様子をうかがった。
ふと座った席の窓に目を向けると、幹線道路を目まぐるしく走り過ぎる車や、足早に歩く人が見える。私は誰かに見られているような気がして、窓から目を背け下を向いた。
そんな私の様子に気づいたのか、妻が「Yさん、Kさんへ電話したら」と言ってきた。私が逮捕されたときに妻に電話をくれ、今日まで支えてくれた人であった。
すぐに携帯電話を手にとり番号を押した。だが途中で番号を押す手が止まってしまった。
なんて言おう? どこから話したらいいんだろう?
いざ電話をかけるとなると、どういう振る舞いをしたらよいのか、私はわからなくなってしまった。
こんなことを考えて躊躇している私に妻は「みんな待っていたんだよ」と言う。そうだ。拘置所を出たとき受け取った、たくさんの手紙、ジュース、お菓子は、この私のために差し入れられたものであり、その一つひとつに思いが詰まっている。
私は携帯電話をもう一度取り出し電話をかけた。呼び出し音が鳴っているあいだ、心臓音がバクバク音を立てるのが聴こえてくる。
「おう! やっと出てきたな。元気そうじゃん」
躊躇していた私とは裏腹に、明るい笑い声が電話の向こうから聞こえてくる。それはいつもとまったく変わりないYさんだった。
日々の移り変わりは早いかもしれない。でも変わらないものもある。少なくとも私の帰りを待ってくれている人は変わっていなかった。
拘置所から出て1日目は妻と大阪のビジネスホテルへ泊まり、2日目に久しぶりに神奈川の自宅へ戻ってきた。
どれほどこの瞬間を、この時を、拘置所の中で願いつづけ待ちつづけたことか。
鍵を開けて、玄間に靴を脱ぎ捨てて部屋に入ると、腕を上に伸ばし、思いっきり大きく息を吐き、大きく息を吸いこんだ。
やっと帰ってこれたんだ!
痛みのわかる人間として
翌日、家に帰ったら連絡がほしいとYさんに言われていたことを思い出した。
電話をするとYさんは「明日にでも職場へ挨拶に行こう」と言う。
私は驚いた。出てきて数日しか経っていないし、まだこれからどうしていくのか何も考えられなかったからだ。それに、こんな事件の当事者となってしまい、元の職場へ復帰することはとうてい無理だろうと思っていた。
実のところもう少しそっとしておいてくれ、休ませてくれとも思っていた。
拘置所での閉鎖生活は、思ったより私が外の世界へ戻ることを妨げていたのである。
周囲の人は、私が事件の当事者であることを知っているのではないか──。
マスコミが自宅を張っているのではないか──。
そして、夜寝ているあいだ枕元では、拘置所の刑務官がコンクリートを歩くコツコツという乾いた靴音が聞こえてきた。
これを誰かに伝えたら、間違いなく幻聴や妄想という精神症状の一つとして取り上げられてしまうだろう。
私と同様にマスコミの取材攻撃や検察の取り調べを受けていたUさんも、同じようなことを言っていた。
「あのときは暗い闇の中にいるようだったな」
そしてUさんは一息置いて、どことなく寂しそうに「でも経験していない人には、この闇はわからないよな」と言った。
闇の中を歩いているのは、そのとき、その場だけではない。その後も、この先もその闇は消えずに心の中に潜み続け、何かのふっとした状況で、私たちを支配するのである。
Uさんは冗談めいてこんなことも言っていた。
「車の運転がこんなに怖くなることはなかったよ。なんだか最近、うしろの車が気になる。気のせいだと思っているけど」
そうである。経験した人にしかわからない闇の世界である。
しかし、結局私はYさんのいつもながらの押しの強さに負けて、翌日勤務先に挨拶へ行くこととなった。
駅の改札を出て正面の掲示坂付近を見ると、背の高い男性がこちら向いて立っていた。Yさんである。
Yさんは「おう、元気そうだな」と言いながら、私のほっぺたをつねった。私は“痛い”と思いながら、その痛みが妙にうれしくてたまらかなかった。
*
「罪を知らぬ者だけが人を裁く。罪を知った者は決して人を裁かない」(山本周五郎『赤ひげ診療譚』)
私は自分に問う。目の前にいる相談者を「こんな人だ」「この人はこうである」と決めつけてこなかっただろうか、と。
私は一つの罪に問われ、そして関係性を絶たれた。
罪を問われるとはどういうことかを知ったからこそ、私はこのことの意味をしっかり胸に刻みつけ、“痛み”のわかるひとりの人間として生きていきたいと思う。
(尾上義和「拘置所の23日間」了)
『精神看護』2011年7月号(医学書院)より。