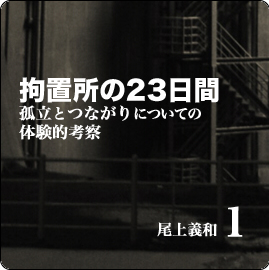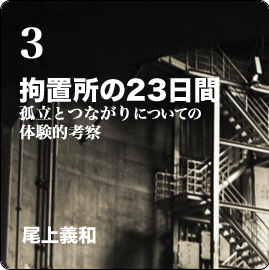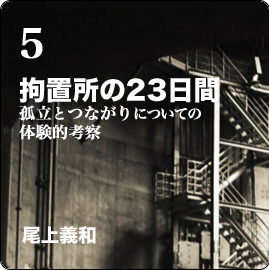かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

第4回 「救い」としての取り調べ
2011.7.25 update.
2009年に障害者団体向け割引郵便制度を不正利用したとする容疑で、当時の厚生労働省村木厚子局長らが大阪地方検察庁特別捜査部によって逮捕・起訴された(その後村木氏は無罪確定)。
その後捜査を進めていくなかで、社会福祉法人全国精神障害者社会復帰施設協会(全精社協)との関連が浮かび上がった。大阪地検特捜部は2009年10月20日、精神障害者福祉施設「ハートピアきつれ川」(栃木県さくら市)の運営費などに流用する目的で厚生労働省から調査研究名目の補助金計約5100万円の交付を受けたという容疑で全精社協の会長、元副会長、元事務局次長、元常務理事(尾上義和氏)を逮捕した。
2009年11月、会長と元副会長は起訴処分(2010年に執行猶予の判決となる)、元事務局長と尾上氏は起訴猶予処分となった。
――本稿は、本件について大阪地検の取り調べを受けた当事者の尾上氏に、実際の体験を記していただいたものである。
逮捕以前はとても不安で嫌だった取り調べが、
いまは担当検事と顔を合わせた途端に
ホッと安らいだ気持ちとなる。
この気持ちは何なのか?
最後のタバコを吹かしながら、拘置所へ向かう車から流れる風景を眺めた。だが、この風景からは、どことなくいつもとは違った世界を感じる。このタバコは、私の横にいる事務官から「拘置所では吸えないから1本吸っておきますか?」と言われ、もらったものだった。
やがて、車が止まると同時に、ドンと物が当たる音がした。窓を見ると小型ビデオカメラを窓の外に押しつけている男がいる。マスコミだ。
「もうほっといてくれ、こんな情けない姿は見ないでくれ!」
そんな思いではち切れそうになった心を隠すように、手錠をはめられた腕を隠した。
鉄の大きな扉が低い音を立てて開く。私を乗せた車は静かにゆっくりと入っていく。ついに、拘置所という世界へ到着したのである。
扉の中は、なんだか昔の古びた銭湯のような雰囲気だった。目の前に銭湯の番頭が座るような背の高い机がある。そこに男が座り、あちらこちらへと人を振り分けていた。横には夏の海の家にあるシャワー室のような、木製の目隠しの付いた個室があり、そこから裸になった人が1人、2人と出てきた。
事務官は、私の腕にはめられていた手錠と、腰に巻かれた紐を解いた。と同時に私の気持ちも少し軽くなった。入口の近くにある受付のようなところでだいぶ軽くなった荷物を渡されると、水色の警察官のような制服を着た男が「はい、こっちに来て」と私を呼ぶ。呼ばれるままに荷物を持っていくと、「ここに荷物を全部置いて。ベルトや時計も、洋服以外はすべて出して」とぶっきらぼうに言われる。
むかし私が働いていた精神科病院では、入院する際、患者さんが持ってきたすべての荷物はいったん看護師や精神保健福祉士が預かっていた。預かる側の私にとってみれば、それは1つの業務として淡々とこなしていた。しかし立場が逆転し、実際に荷物を預ける側になると、なぜか寂しい気持ちになるものだ。大した荷物ではないけど、この世界で唯一、私と関係のあるものはそれだけなのだから。
自分では予測もしなかった入院という事態に晒された患者さんの気持ちとは、こういう感じなのか……などと思いながら、軽くなった荷物をすべて机の上に置いた。
尻の穴まで
「尾上! こっちへ来て」
刑務官から呼ばれ、木製の目隠しのついた個室の前に行くと、「ここで洋服を全部脱いで」と言われた。
「なぜですか?」と聞くと、「健康診断をやるから」と答える。
健康診断? ここで? しかもこの場で服を脱がなくてはいけない?
刑務官やそれ以外の人たちを含めても30人はいると思う。こんなに人がいる場所で服を脱ぐとは。とても抵抗を感じる。
私の前には上半身裸の細い体の若い男性がいて、震えながら脱いだ服を広げたり閉じたり小刻みに足踏みをしていた。おかしな動作だ。
「またお前か。早くパンツを脱いで、こっちへ来い!」と刑務官のイライラした口調の声が響いたが、その男性に言葉が伝わっている様子はなく、同じ動作を繰り返しおこなっていた。私はその男性に「パンツをここで脱ぐんですよ」と小声で教えると、彼は私の顔を見ながらパンツを脱ぎ、呼ばれたほうに相変わらず震えながら小刻みに歩いていった。
その弱々しい後ろ姿を見ながら、何か病気だろうか、障害があるのだろうか、彼は何をしたのだろう、なぜここへ来ることとなったのか……としばらく勝手に思いを巡らせていたが、やがて勢いをつけるように私は一気に着ていた服を脱いだ。
木製の壁で囲われた部屋へ入ると、白衣を着た男性が座っていた。
「ここへ座って。何か病気はありますか? どこか痛いところはありますか?」などといくつか簡単な問診があった。健康診断とはいうから血液検査でもあるのかと思ったが、意外と簡単なものだ。しかし少し余裕を持ちはじめた私に、白衣の男性は平然と言い放った。
「そこに立って後ろ向いて、尻の穴を広げて」
「……えっ! 何ですか?」
「後ろを向いて、お尻の穴を広げるんだよ」
と、今度はちょっとばかりイライラした口調で言われる。
私は、言われるがまま後ろに向いた。そして、尻を両手で広げて見せた。
「はい、いいよ。行って」と、ごく事務的に白衣の男性は言った。
急いで服を着ると、青服の男性から歯ブラシ、チリ紙の束、コップを渡され、こう言われた。
「お前は今日から2180番だ。これからこの番号で呼ぶので覚えておくように」
所有物はなくし、裸となり、尻の穴まで見せ、そして最後には名前もなくなる。ここでは自尊心などという高尚なものは持ってはいけない。極端にいえば、人という存在を消し去らなければいけない。これが拘置所で生きるということなのだ。
「2180番」という名前
刑務官が重そうな鉄の扉を開くと、そこはコンクリートづくりで、廊下の幅は広く、天井は高く、あたりまえだが殺風景だった。しかも暑さが残る昼間の時間であるにもかかわらず、とても暗く、冷たい。
移動するときに言葉を発することは刑務官から一切禁じられた。私を含む数人が重苦しい廊下を一列に歩かされた。キャリーバッグを引きずる音だけが響き、異様な雰囲気が漂う。鉄格子の扉で刑務官の声が廊下に響く。
「止まれ! 2180番は入れ!」
廊下の横にある鉄格子の扉が開き、その中に入る。右側には鉄格子の枠の掛かった大きな窓があり、その向かいには横一列に並んだ部屋があった。独居房(以下、独房)である。
刑務官の後ろをついていくと、ふたたび「止まれ!」と言われる。独房の鉄の扉には格子の入った窓があり、扉の左横にも鉄格子の張られた窓がある。その下には食事を入れるためだろうか、小さな開き窓がついていた。よく見ると、鉄の扉の横には「接見禁止」と札が掛っていた。
そうである。このときから、検事や弁護士以外の人たち─妻や仲間と呼べる人との関係が断たれたのだ。
独房は四畳半ほどの畳部屋である。正面にはベニヤ板1枚に隠されたトイレがあり、その前には小さな洗面台がある。入口の右横にはとても小さな手作りのような木製の机と、薄っぺらい座布団。机の下を見ると『未決拘禁者の心得』と書かれたファイルのようなものが置いてある。
机の後のコンクリートの壁からは、丸い黒いしみのようなものが浮き上がっていた。この空間はきっと、何らかの罪を問われた者、もしくは罪を本当に犯してしまった者が長きにわたり過ごした所なのだ。
今までは刑事ドラマや推理小説で見たり聞いたりしていた世界である。こんなところへは来たくはないと思っていたし、行くこともないと思っていた。正直に言ってしまえば、犯罪者と同じ空気を吸うことで、私自身も犯罪者になっていくような気さえした。私にとってこの世界は、それまでの伝聞や情報の世界ではなく、目に見え、手に触れる、具体的経験の世界となったのである。
伝聞や情報の世界のままならよかった。選べなかったのか? いや選べたのかもしれない。でも、もう遅い。
「何やったん?」
この房の担当らしき刑務官が関西弁で聞いてきた。
私が説明しようとすると、ちょうどその房の入口のすぐ上の埋め込まれた四角いスピーカーから、なんと「全国精神障害者社会復帰施設協会の会長ら3名が、補助金適正法違反の容疑で本日逮捕されました」という趣旨のラジオの音が流れてきた。よりによって私のことだ! もう何も隠すことはない。私は「これです」とラジオが流れるほうを指差した。刑務官は「おお、そうか」と驚いたような声を出し、しばらく私が荷物を置くのを見ながら「あんたは早く出られそうな気がするわ」と言ってくれた。
何の根拠もない、何気ない言葉であったが、私はなんとなく心が軽くなるのを感じた。人とは単純な生き物である。言葉ひとつで気持ちが軽くなったり重くなったりする。だからこそやっかいなものなのかもしれないが。
何もしてはいけない
朝から私の意志とはまったく関係なく、あれよあれよという間に、まわりが目まぐるしく動いている。私はどうすることもできず、いまこの場に居る。いや、居させられている。壁際を見ると、あずき色の薄い布団や枕が積み上げられていた。
どれくらいの時間がたったのだろうと思いながら、壁際の布団に寄りかかり物思いにふけっていた。これからどうなるんだろう、妻や仲間、職場の人へはこのことが伝わっているんだろうか、みんなどう思っているんだろう、もうどうすることもできないんだ……。
すると、「そこ! 昼間は机の前に座っていろ」と、鉄格子の張ってある窓越しに先ほどの刑務官が強い口調で言ってきた。突然のことに私は動揺し、「あっ、すみません」と答えると、「昼間は机の前に座っていること。正座でもあぐらでもいいが、昼間はそこにいろ」と命じられた。
拘置所では、日常のほとんどの時間を、この机の前で過ごさなくてはいけないのである。机の後ろの黒く浮き上がる不気味なしみが、なぜここだけにあるのかわかった。大半の時間を机の前に座り、その際に壁によりかかっていたのだ。そして何年何十年とかけて、このような模様が出来上がったのであろう。黒いしみはそう語っていた。
机の下には薄い座布団が引いてあった。まさにせんべい布団である。座ってみると、硬いというより、下の畳の感触がそのまま伝わってくる。
ここにずっと座って何をやれというのか? 何もかも取られてしまい、何もすることがない。というより、「何もしてはいけない」ということなのである。
机の下の『未決拘禁者の心得』を見てみる。はじめに拘置所での用語集が記されてあり、最後のページには1日の生活が時系列に書かれていた。午前7時00分起床、7時30分点呼、8時朝食、10時ラジオ体操……。その下の注釈に目をやると「作業をするものは……」などと記載されてあった。それを見て真っ先に考えたのが、私は作業へ行けるのだろうか、ということであった。ここで何もしないで、どのように時間を費やすことができるだろうか。何かやることがあれば何でもしたいと私は思った。
私は仲間からはマグロと呼ばれ、「何かしていないと死んでしまうじゃないか?」とさえ言われることがあった。それほど落ち着きがなく動くことが好きな人間だと思われているが、本当は出不精で、家にいるほうが好きで、隙あらば仕事を休んで家でゴロゴロしたいとも考えているのだ。でも今この場所で、何も持たず、誰かと会話することさえ許されず、やることすべてを奪われてしまうというのは……。苦しさ、不安のすべてが混ざり合って、私を丸ごと包み込んでしまうようである。
この空間で「何もやれない」ということは、決してホッと一息をつけるわけではない。現在のことやこれからのことなど、考えたくもないことが頭をグルグルとかけ巡り24時間フル稼働状態となって、休みは訪れないのだ。早く時間が経ってほしい。ここから早く出してほしい。そう思えば思うほど虚しさと苦痛は増してくる。
希望のシラベ
午前8時。いつもように刑務官に連れられた、あずき色の作業服を着た若い男性が、味噌汁を入れた大きな鍋や、おかずの入った皿、ご飯の入った箱を台車に乗せて、ガラガラと音を立てて運んでくる。この拘置所には刑務所があると聞いていた。彼は服役をしていて、その作業としておこなっているのだろうか。
私はあらかじめふたを開けておいたポットを小さな窓から出して置き、そこにお茶を入れてもらう。次にプラスチックのお椀を出し、味噌汁を入れてもらう。最後にハガキくらいの大きさで、厚さ10cmほどのご飯の入ったプラスチックの重箱を受け取る。
重箱のふたを開けると、いつもとおりの麦飯が入っていた。麦飯のお供として、きのうはビニールの容器に入った海苔だったが、今日はふりかけがついている。おかずはプラスチックの平皿容器に鶏肉を炒めたものらしいものが載っているが、冷めきっている。箸を一口だけつけて、後は麦飯にふりかけをかけて半分だけ食べて、また小さな窓へ戻した。
ここに来てからは、食べようと思ってもどうしても喉もとに何か詰まっているようで喉を通らなかった。それ以前に、食べるという気分にはなれなかった。
私は机の前に座り、もう4度目であろうか、『未決拘禁者の心得』を開いた。鉄格子の掛かった外側の窓に目をやる。空がほんのり赤くなっていた。
突然、鉄格子の張られた窓越しに「シラベがあるから用意しておけ!」と刑務官が声をかけてきた。驚いて「あっ、はい」と気が抜けた返事をしたが、シラベとは何だろうか?
しばらくすると鍵を鳴らした刑務官が私の独房の前で立ち止まる。ガチャッと止め金が外される音がして、横びらきの扉が開かれる。一瞬、私の横を風が吹き抜け、解放感に似た気持ちがせり上がってきた。
「こっちへ来い」と命じられ、ドアの近くまで行くと「ポケットの中身を見せろ」
私は言われるがままポケットの中身を出すと、「手を上げて」と指示される。こうして刑務官は、足の先まで身体検査をした。
「番号!」
「2180番」
「はい出て。窓のほうを向いて立って待て」
独房を出るときと入るときは、いつもこの同じ行為を繰り返しおこなわなければならない。しかも歩くときは、ポケットに手を突っ込んではいけない、サンダルは引きずってはいけないなどの規則を守らなければいけない。私は24時間「〜しなければならない」という、徹底的な管理と監視のもとに存在するものになったのだ。
「進め!」という声が独房中に響き、私はどこへ行くかもわからぬまま刑務官についていく。夕方ということもあるだろうが廊下はとても薄暗い。これだけ広い廊下であれば、電灯が等間隔にあってもよさそうなものなのに、1つもないのである。
途中、私と同じように黙って刑務官に連れられて歩いてくる人に出会うが、もちろん無言である。そうかと思うと突然、何を言っているかわからないが、刑務官の大きな声が古い建物を響かせる。何か異次元空間の世界へ入っているような感じだ。
いくつかの階段を降り、長い廊下をしばらく歩くと、刑務官が止まった。扉を開けると古い学校の教室のような部屋がいくつも並んでいた。その真ん中あたりの部屋の扉の上に、丸い赤い電灯が灯っている。よく見ると奥のほうの部屋もいくつか同じような明かりが灯っていた。
そのうちの1つの部屋の前で刑務官は立ち止まり、「ここでいつもシラベがあるから覚えておくように」と言う。扉を開くと、やはり古い教室のような部屋であった。とても年季が入っている。10畳ほどあろうかと思う部屋の正面には、畳一畳ほどの大きな木製の机が置かれ、担当検事が座っていた。その右横にL字を描くように設置された事務机に事務官が座り、目の前にはノートパソコンが置かれていた。シラベとは「取り調べ」のことだった。
検事に会いたい……
なぜだろう……。
逮捕以前はとても不安で嫌だった取り調べが、いまは担当検事と顔を合わせた途端にホッと安らいだ気持ちとなる。この気持ちは何なのか?
今までの私は、妻や仲間、あるいは職場の同僚や上司と、私自身の意志と選択のもとに連絡をとることができた。いつでもその人の声を聞き、話をすることができていた。あたりまえのように彼らとの関係性を保てていた。しかしある瞬間、一気にすべてのつながりや関係性が絶たれることになったらどうだろう。つながりを持てるところに、すがりつきたいと思うのではなかろうか。少なくとも私個人の体験としてはそう感じた。と同時に、私は今までどれほどの人とのつながりのなかで生き、生かされてきたのか。そう思うと急に、妻や仲間の顔を見たくなってきた。
「関係のない話ですが、尾上さんの仕事はどんな仕事なんですか?」
私は得意気に「障害者の方の相談です」と答える。
「私たちのところにも障害のある方も来ることがありますが、対応が大変ですよね」
検事の取り調べで話すのは事件のことばかりではない。趣味のことや今の仕事の話、検事自身の話もある。読者の皆様はとても変な話だと思われるかもしれないが、私はいつしかこの時間がくるのが待ち遠しくなっていた。
取り調べというと多くの人は、検事と被疑者の対立構造を思い描くだろう。しかし、それは少し違う。拘置所の生活というのは朝起きてから寝るまでのあいだ、誰とも接することができず、何もやることがないのだ。やれることといえば、朝食後のラジオ体操くらいのものである。何もないという空間で生きていかなくてはならない。そのつらさは並大抵のものではない。
検事は午後に来て、夕方には帰っていく。検事が帰ってしまってから後の時間は、明日の午後までは、ふたたび何もない、つらく、苦しく、長い長い時間が訪れるのだ。拘置所で唯一話をし、接することが許されるのは、検事だけなのである。
裁判所の地下深く
「おい、裁判所に行くから用意しておけ。タオル以外は持っていってはダメだ」
刑務官にそう言われた私は、「いつでも大丈夫ですよ」と思いながら待っていた。最初の取り調べのときに、「拘留手続きがあるので3日後に裁判所に行くと思います」と検事から言われていた。何もわからない私は「やっと外に出られる、外の空気に触れられる」と少々うれしい気持ちにもなっていたのだ。
いつものように身体検査を終えると、私以外にも何人かの人が窓のほうを向いて立たされていた。私は1人だけだと思っていたので、少し驚きながら刑務官の後ろをついて行く。しばらくすると1つの部屋に到着した。中に入ると、学校の教室くらいの大きさのところに、5人ほどが一列になって20人以上がいくえにも並んでいた。こんなに私と同じ日に逮捕拘留された人がいるのか。
刑務官から手錠と腰ひもを巻かれた。腰ひもは他の人と1つにつながれた。まるで小学校のときによくやった電車遊びのような格好である。手錠は2回目であるが、やはり心に響く重さだ。
窓に網状の鉄格子がついたマイクロバス、いわゆる護送車にへ乗せられ、私は窓際に座らされた。拘置所を出た車は大阪の街を抜けていく。今までも街を走っている護送車を見たことはあったが、護送車の中から街を見ることになるとは……。
はじめは外の景色は私を新鮮な気持ちとさせたが、やがて自転車に乗っている人、信号待ちの人、子どもを連れている人などを見ていると、あちら側に行きたいという、届かない思いがわいてくる。だんだんと切ない気持となってきて、いつしかあの輝いた外の景色も灰色に見えてきた。
1時間ほど走っただろうか。バスは裁判所へ到着し、地下へ地下へと潜っていった。
裁判所の拘留手続きは、とても簡単なものだった。検事が書いた調書が読み上げられ、間違いがないかを確認され、私が「間違いない」と言えば調書に母印を押し、それで10日間の拘留が決定するのであった。
私の手続きは午前中には終わったが、それで帰れるわけではない。他の人が終わるまでのあいだ、今度は裁判所の地下にある独居房に居なければならない。この四方を白い壁に囲まれた窓もない部屋には数冊の本が置いてあった。開いてはみるものの、字を追っていくだけで内容が頭に入ることはなかった。
この部屋から唯一外と繋がるものはといえば、鉄の扉の入口についたA6判ほどの窓だけだ。ここでは外の空気と触れることは一切できない。閉鎖され、密閉され、何もかもから遮断されている。閉所恐怖症の人であれば1分ももたないだろう。健常な人でもこの中に2〜3日いれば、その精神は保てなくなるのではないかと思う。裁判所にこんなところがあるのか、ということにも驚く。
――どのくらいの時間が経ったのだろう? 私は四方に囲まれた白い壁を見ながら、重くるしさと息苦しさに苛まれはじめていた。
そのとき、外からガラガラと何かを引くような音がして、何かを配っているような感じがした。そろそろ昼食の時間だろうか。不思議なものである。何かも遮断されると、他の感覚が研ぎすさまれるようなのだ。ガチャガチャと鉄の扉が開き「差し入れだ」と、刑務官が持ち帰り弁当のような白い容器が2つ私に渡された。
「この人からの差し入れだ。差し入れの人の名前を確認して、ここに人差し指で印を押して」と伝票のようなものが差し出された。
見ると妻の名前だった。胸の奥のほうから何かが込み上げてくる。私は何回も何回も伝票を見直した。たしかに妻の字である。伝票を見つめながら、私は右手の人差し指で伝票に印を押す。
刑務官から渡された2つの白い発砲スチロールの容器を畳の上に置き、私はただ見つめ続けた。
何の変哲もない弁当であるが、そこから妻の想いが伝わってくるような感じがした。すると今まで抑えていた感情が一気に噴き上がり、熱いものが溢れ返ってきて、私はその場に思いっきり泣き崩れた。
(尾上義和「拘置所の23日間」第4回了)
『精神看護』2011年5月号(医学書院)より。

本記事が掲載されている『精神看護』5月号の特集は「多飲症看護」。水を何リットルも飲んでしまう病気が精神科にはあるんです。これまでの「いかに水を飲ませないか」から「おいしく水を飲んでもらう」対策に変更したら、なんとすごい成果が! 山梨県立北病院看護部の新津さんの感動のレポートです。ぜひご購読ください。