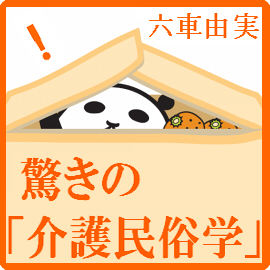かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

第3回 幻覚と昔話
2011.1.26 update.

1970年、静岡県生まれ。大阪大学大学院文学研究科修了。博士(文学)。民俗学専攻。東北芸術工科大学東北文化研究センター研究員、同大学芸術学部准教授を経て、現在、静岡県東部地区の特別養護老人ホームにて介護職員として勤務。
論文に「人身御供と祭」(『日本民俗学』220号、第20回日本民俗学会研究奨励賞受賞)。『神、人を喰う――人身御供の民俗学』(新曜社、2003年)で2002年度サントリー学芸賞受賞。
『クロワッサン』(マガジンハウス、2011年1月10日、25日発行号)「おんなの新聞・介護」に2号連続で取材記事掲載予定。
幻聴幻視あれこれ
認知症の方の周辺症状のひとつに、幻聴や幻視などの幻覚症状がみられる場合があると言われている。実際に、私が施設で接している利用者さんのなかにも、私たちには聞こえない声が聞こえたり、見えないものが見えたりする方が何人もいる。まずは、ここで少し紹介してみたい。
楠本サエさんは、認知症が進行して日常会話も成り立たないことが多く、「あーあーあー」と高い声を上げている。また、天井の隅を遠い目で見つめたり、何も乗っていないテーブルの上へ何かをつかむかのように手を伸ばしたりすることがよくある。
ある日、私がサエさんに「こんにちは。サエさん、今日はいいお天気ですねえ」と話しかけていると、急にサエさんが私のちょうど胸のあたりに視線をとどめて、こう叫んだのである。
カズヨシ、あんた何やっているの。靴下をちゃんと履きなさい。いつも言ってるじゃない。まったくあんたは。
その声はいつもの「あー」と叫んでいるサエさんからは想像がつかないくらい低く、しかも口調はしっかりとしている。
私は多少戸惑いながらも、「サエさん、カズヨシって誰ですか。息子さん?」と尋ねてみた。すると、サエさんは私の胸から視線をそらさずに低い声でゆっくりと「そうよ」と答えた。
どうやら、サエさんには、私の胸のあたりに子どものころの息子さんの姿が見えているらしかった。5分もしないうちに、サエさんはまた天井の隅を見上げて「あー」という声を上げたが、息子さんを叱っていたときのサエさんはまさに母親の顔をしていたのが印象的だった。
青島まさ子さんは、認知症でうつ症状の強い方であり、「私なんてなんにもできない。死んでしまえばいいんだ」と自分を責め嘆いていることが多い。
落ち込んでいるまさ子さんに声をかけてみると、少しずつ状況を話してくれる。そこには、いつも小さな子どもたちが登場してくる。
家の2階で一人で寝ているでしょ、そうすると子どもたちが来るんです。それで、「お母さんを殺せ、殺せ」って騒ぐでしょ。だから私嫌になっちゃうの。殺せって言うんだから死んだっていいだけど、そう思ってもなかなかそうすることもできないし。もう本当に嫌だし、眠れないの。
「殺せ、殺せ」と騒ぐ子どもたちの姿をまさ子さんは見たことがないが(というより嫌なので見ようとしないのだという)、ベッドのまわりでいつも騒ぐので、その物音や声で来たことがわかるのだそうだ。
子どもたちは、ときには針でまさ子さんの足を刺すこともある。だから、歩こうと思っても足が痛くて歩けないのだとまさ子さんは訴える。
子どもたちがなぜまさ子さんに「殺せ」と言ってくるのか、その理由はまさ子さん自身にもわからないという。まさ子さんが嫌だという子どもたちだが、ときにはまさ子さんが心底心配する大切な存在として登場することもある。
ショートステイのある利用日、いつものように顔を曇らせてベッドに横になっていたので、どうしましたと尋ねると、「子どもたちが来た」と言う。気分転換に、「天気がいいので少し散歩をしましょう」と庭に誘い、ベンチに二人で腰かけていると、まさ子さんからまた子どもたちの話をしはじめた。
昨日も夜眠れずにいると、子どもたちが今度は助けてと叫んで逃げ込んできたというのだ。前に何人かの大人たちがやってきて、「子どもを殺した」というようなことを話していた。それでまさ子さんはもう子どもたちが死んでしまったのではないかと心配していたが、誰かに助けてもらって無事だったことがようやくわかり、心から安心して、嬉しくて仕方がなくて涙が出てきてしまったんだというのだ。
そう私に話してくれるまさ子さんは目に涙を浮かべていた。
助けを求めてきた子どもがいつもの「殺せ」という子どもと同じかどうかは確認できなかったが、その日子どもたちは我が子のように大切な存在としてまさ子さんの前に現れたことは確かである。
また、子どもたちは、ときにやんちゃな面も見せる。
まさ子さんはすぐにお腹がいっぱいになってしまうが、残しておいたご飯やお菓子をまさ子さんが寝ているあいだに子どもたちが全部食べてしまうのだそうだ。それに、ここ(ショートステイ)にいるとお風呂にも入れてもらえるから嬉しいといって喜んでいるという。
ほかにも、まさ子さんは、困ったときには今でもおばあちゃんが来てくれて助けてくれるんだとよく言う。子どものころにおばあちゃんに育てられたまさ子さんにとって、おばあちゃんは何よりも親しく大切な存在である。もちろん、とうに亡くなっているが。
幻聴幻視といった幻覚は認知症の周辺症状として問題化されることが多く、レビー小体型認知症と診断された場合には幻覚症状を抑える薬が処方される場合もあるという。
しかし、こうしてみてみると、サエさんにせよ、まさ子さんにせよ、幻覚はときに本人を苦しませることがあるが、しかしときにはその方を支えたり、優しい気持ちにさせてくれることもあると言えるだろう。
幻覚の物語性
幻覚症状のある利用者さんに話をうかがっていると、その方の語る幻覚世界の豊かな物語性に驚かされることがたびたびある。
渡邉美智子さんは普段はあまり他の利用者や職員たちと話をすることはなく、一人でいることが多いが、話しかけるとそれには訳があることがわかった。
美智子さんには死者の声が聞こえるのだという。
夜になると、部屋の中からどこからともなく声が聞こえてきて、話しかけてくる。姿は全く見えず声だけが聞こえてくる。
怖くて怖くてたまらなく、窓や戸を全部閉めて鍵をかけて、そして電気はつけっぱなしで寝た。それでもどこかの隙間から入ってくるのか、声が聞こえてくるのだという。
声の主は一人ではなく何人もいた。彼らによると、この世では死んでいるという。
あまりにもうるさいので、大きな声で「出ていけ!」と叫んだが、彼らは「美智子さんが怒っているから静かにしよう」と言い合ったりしているだけで出て行こうとしない。
あるときには、押し入れのほうから声がする。押し入れに収納した布団の上で寝ているらしい。それで布団を全部取り出して、杖を振り回して、「出ていけ!」と追い払った。
ある晩には、二人の子どもがやってきて、「おばちゃんおなかすいたよ、パンちょうだい」と催促してきたことがある。もちろん姿は見えないが、声の感じで子どもだとわかったという。
子どもには、「そんなにお腹がすいたのなら、勝手にパンを持ってけ」と言ったが、結局持っていかなかったそうだ。
家にばかりいるとそういう声が聞こえてくるんだ、とその声が聞こえない息子が、この施設へ通うことを勧めてくれた。
でも施設に来ていても、最近はときどき声が聞こえてくることがあるという。他の利用者さんたちと楽しく歌を歌っていると、彼らが一緒に声を合わせて歌ったりすることもある。そんなことについて、ほかにやることがなくて暇なのじゃないかと美智子さんは分析する。
そういうときには鬱陶しくて「もう帰ってくれ!」と言ってしまうことがある。
息子からきつく注意されているから、大きな声は出さないようにしているけれど、それでも口が動いてしまう。
そういう自分の姿を見て、他の利用者さんたちや職員たちが変に思ったり怖がったりするのではないかと思うと悲しくて仕方がない。それが心配だから、施設では自分から話をすることはない、そう美智子さんは肩を落とした。
美智子さんは自身の幻覚症状に戸惑っているが、幻覚症状そのものというより、息子さんやまわりの人間がそれを理解してくれないということに苦しんでいるように見える。
さて、そうした話を「へー、そうなんですか、それで?」と興味津々に聞いている私を、美智子さんは最初こそ訝しげに見ていたが、話を進めるうちに、さらに詳細に幻覚の内容を教えてくれるようになっていった。
声の主の姿はまったく見えないが、彼らによると、みんな洋服も着ていなくて裸であるそうなのだ。食事もとらなくてもいいという。
でも、それじゃあ寒いだろうとか、お腹がすくだろうと美智子さんが思わず心配してしまうと、寒い、お腹がすいたと言ってくる。それで、「じゃあお金をあげるから、これで洋服でも買ってこい」とお金を渡そうとするが、彼らはそれを受け取ったことは一度もないそうだ。
美智子さんの耳に聞こえてくる死者の声は、こうしてリアルな姿で現れる。そしてそれはまるで昔話に登場する妖怪のようにチャーミングだ。語っている美智子さんも、「もうまったく!」とため息をつきつつも、何だか彼らに親しみを感じているように見えた。
そんな死者の声が、美智子さんに頼みごとをしてくることもあった。美智子さんによるとこういうことだ。
ある日、むかし地元の福祉センターで一緒にカラオケを楽しんでいた仲間(がんで亡くなったそうだ)がやってきた。よくわからないが、自分が何かの犯罪の疑いをかけられているから、自分をよく知っている美智子さんに証言してほしいと言ってきた。
その人は生前とても義理堅くて、美智子さんにもよくしてくれた。だから放っておけなくて、一緒に警察に行こうと思ったが、施設に行かなければならなかったので、「自分で警察か役場に行って調べてこい!」と言って出てきたそうだ。
すると、彼は「それじゃあ後で施設に行く」と言った。だからずっと待っていたが、とうとう現れなかった。たぶん、自分で警察に行ったんじゃないかと思う、そう美智子さんは語った。
実際、この日、美智子さんは施設の送迎車が自宅に到着する前に、警察方面に一人で歩いて行ってしまっていたし、施設に来てからも、廊下に出てみたりと落ち着かない様子が見られたのである。
徘徊の原因がこうした幻覚にあったり、またそうして一人で歩き回って転倒したり事故にあったりするリスクを考えたら、幻覚症状を認知症の問題行動として抑制しようとすることもわからなくはない。しかし、私が注目したいのは、声の主の死者たちが生き生きとこの世を闊歩している様子を、美智子さんが推理小説家かもしくは昔話の語り部のように雄弁に言葉豊かに語ってくれることである。
さらに言えば、ときに翻弄されながらも彼らとともに物語世界を生きることが美智子さんの日常になっている、ということである。そんな美智子さんが生き生きと生きている世界を単に認知症の問題行動とだけ認識してしまっていいのだろうか、という思いを私は強く持つのだ。
昔話の語りと幻覚の境目は?
こうした利用者さんの幻覚について聞いていると、私はいつも心躍るような、でもちょっと恐ろしいようなそんな不思議な感覚を覚える。それは、大学に勤務していたころに、学生たちとともにある東北のムラでドキュメンタリー映画の撮影をしていた際に、老夫婦に狐の話を聞いたときの感覚に似ている。
私たちは、大正二桁生まれの老夫婦のお宅におじゃまし、カメラをまわしながら、村にある荒神さまのお祭りについて取材していた。話は、隣村の祭りの話へと移っていった。
すると、おばあさんがそういえばと言って、唐突にこんな話をしはじめたのである。
昔は、この辺にも、騙す狐がいたもんだ。おれの舅さまが隣村の祭に行ったんだ。菰にいっぱいのお土産を包んでもらってきたんだ。餅とかよ。で、それを腰に提げて夜道を帰ってくるだろ。酒いっぺえ飲んでて、いい気分で境内さ寝てしまったんだと。そうするとよ、朝起きるだろ、腰に提げてた土産さそっくりなくなってたんだと。これは、狐に騙された、すっかり狐に持ってかれてしまったって、舅さま、騒いでたっけ。
学生たちが狐に反応して、「えっ、狐が騙すんですか」と問うと、さらにおばあさんはこんなことを教えてくれた。
狐は形は見えないんだ。夜一人で歩いてるだろ、そうすると後ろでカランコロンカランコロンと音がするんだ。そういうときは狐がついてきてるから、後ろ見たら駄目なんだ。後ろ見ないで、「なに狐、ついてくるな」って脅して追っ払うんだ。
おじいさんもうなずいている。
そうして、最後に夫婦そろってこう言って口をつぐんだ。
昔はそういう狐がいたもんだ。今はいなくなったな。
薄暗い灯りの下で聞いた狐の話は、私たちを不思議な幻想世界へ誘ってくれたように覚えている。
私はそのとき、この老夫婦が最後に口にした「今はそういう狐がいなくなったな」という言葉の意味を考えた。「昔は狐が人を騙すなんてことを言ったが、今は誰も言わなくなったな」ということを比喩的に言っていたのか、それとも言葉どおり、「昔は人を騙す狐がいたが、今はいなくなったな」と「騙す狐」の存在そのものの有無について言っていたのか、ということである。
両者の決定的な違いは、「狐が人を騙す」という物語世界に対する語り手の距離のとり方である。すなわち、前者は、物語世界をフィクションとして見ているのであり、後者は、物語世界を生きているのである。
私は、この老夫婦は「狐が人を騙す」という物語の世界を生きてきた人たちだと思う。というより、薄暗い部屋での語りの場の雰囲気は、騙す狐をリアルな存在として私たちの間で共有させるものがあったのだ。
民俗学の世界では、昔話の伝承には、語られる内容とともに、語られる場そのものに重みがある、とされている。
基本的に、昔話は、薄暗い部屋のなかで囲炉裏を囲んでいる子どもたちに、その家のおじいさん、おばあさんが語り部となって伝承されてきたものである。人影や物の影が後ろの壁にゆらゆらと映り、囲炉裏の火のぱちぱちという音だけが響く静寂さ、そのなかで、みんなでおじいさん、おばあさんたちの声にひたすら耳を傾ける。
そんな雰囲気のなかで昔話が語られてこそ、狐も河童も鬼たちも、この世の闇を跳梁跋扈できたのである。子どもたちは、登場する妖怪たちの姿や息遣いをリアルに感じ、その物語世界を語り部とともに共有していったのだろう。
そして、もうひとつ重要なのは、そこにおいて物語世界を共有するのが、老人と子どもであるということだ。
民俗学では、老人も子どもも神に近い存在として説明される。つまり、生まれて間もない子どもと死を間近に迎えた老人は、世俗にまみれたこの世の両端に生きる存在であり、したがって両者ともあの世に近い、神に近い存在として民俗世界では認識されてきた、というのである。
神に近い存在である老人と子どもであるからこそ、世俗的な説明など必要とせずに、語られる物語世界をそのまま素直に受け入れることができるのである。
そう考えたときに、「人を騙す狐」の物語世界を生きる老夫婦と、「殺せ」とやってくる子どもたちの存在を感じるまさ子さんや、死者の声が聞こえる美智子さんとのあいだには、決定的な違いなどあるのだろうかと思えてくる。
一方を昔話の語り部であり民俗学の調査対象になり、一方を認知症の高齢者であり治療の対象になると分ける根拠も曖昧になってはこないだろうか。
認知症という病気やその治療を否定しようとしているわけではない。ただ、今、こうして介護の世界で認知症の利用者さんと関わりながら見えてきたことがひとつあるのだ。
それは、年を取るということは、個人差はあるにせよ、いずれみなそれまでは見えなかったものが見えたり、聞こえなかったものが聞こえるようになることであり、そうして跋扈する狐や死者たちを拒絶せず、否定せず、彼らとともに腰を据えて生きていくということなのではないか、ということなのである。
認知症の幻覚と昔話との関係について、まだまだ考えるべきことは多いように思う。いずれまたこのテーマについて論じてみたい。
(web第3回了)
[次回は2月中旬UP予定です。乞うご期待。]