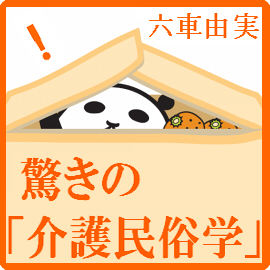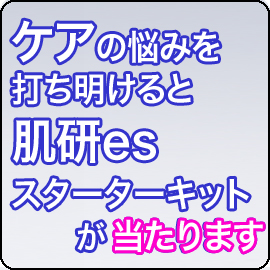かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

第2回 カラダの記憶―トイレ編
2010.12.22 update.

1970年、静岡県生まれ。大阪大学大学院文学研究科修了。博士(文学)。民俗学専攻。東北芸術工科大学東北文化研究センター研究員、同大学芸術学部准教授を経て、現在、静岡県東部地区の特別養護老人ホームにて介護職員として勤務。
論文に「人身御供と祭」(『日本民俗学』220号、第20回日本民俗学会研究奨励賞受賞)。『神、人を喰う――人身御供の民俗学』(新曜社、2003年)で2002年度サントリー学芸賞受賞。
『クロワッサン』(マガジンハウス、2011年1月10日、25日発行号)「おんなの新聞・介護」に2号連続で取材記事掲載予定。
トイレは小さなワンダーランド
老人ホームの利用者さんたちとじっくりとつきあってみると、人間の行動と記憶との深いかかわりに驚かされることがたびたびある。
私は以前にそのことを『看護学雑誌』の連載でジェスチャーゲームの例などを挙げながら述べたことがあるが(2010年8月号:連載第5回目「体に刻み込まれた記憶」)、今回は、排泄介助の場面から、特に認知症の利用者さんたちの見せる「不思議な行動」の背景にあるカラダの記憶について見てみたい。
排泄介助というと、ベッド上でのオムツ交換が真っ先に頭に浮かぶ方が多いかもしれないが、私の施設では、認知症の進んだ利用者さんでも自立歩行が可能な方、および車椅子を使用していても立位保持が可能な方についてはトイレで排泄してもらうことを基本としている。したがって、排泄介助としては、尿意便意の確認やトイレ誘導、排泄の見守り、パッドやパンツ型オムツの交換の介助が必要となる。
そのような場合の介助については、利用者さんの尊厳を守るため、トイレへ誘導した後はドアの外で様子をうかがって必要な場合にのみ介助を行うべきだとする考え方もあると思う。
たしかに、排泄というのは生活のなかで最もプライベートな行為であり、人の人生のなかでも幼児期を除いては家族に対してでさえ自分の排泄行為を見せないのが一般的であろう。
だから、私も最初は利用者さんとともにトイレの個室へ入ることに少なからず抵抗があった。利用者さんのほうも、耳元で「トイレに行きましょう」とささやく私にしぶしぶ従いトイレに入ったものの、すぐにパタンとドアを閉め、カギをかけてしまう方もいる。
しかし、日常的なやりとりのなかで利用者さんと私との関係が縮まっていくのにともなって、トイレでの関わり方も変わっていく場合もある。
斎藤由紀子さんは利用を始めた当初は職員が一緒にトイレに入ろうとすると杖を振り回して嫌がっていたが、何回かのトイレ誘導時、由紀子さんが便座に座ったのを確認して私がトイレから出て行こうとすると、大きな声で「ちょっと!」と声をかけてきた。そして、間髪をいれずに、「あのね、これなんだけどね、なんだか変なのよ」と言って、付けていたパッドを引き抜き見せた。
由紀子さんは便失禁がたびたびあるので、ご家族の希望でパッドを常にあてている。パッドを使うことについての抵抗は本人にはないが、パッドが少しでも汚れていたり、また綿が薄くなっていたりということについては気になるようだ。
そのときに見せてくれたパッドは、その前にトイレに行ったときに本人がいじったせいか、綿の一部が薄くなっていた。
汚れていないのでもったいないと思った私はまだ使えることを伝えたが、本人はまるで納得しない。仕方なく新しいパッドを持ってきて渡すと、すぐにそれをあてなおして満足げな顔をした。
以来、由紀子さんは、私がトイレに誘導するたびに、パッドについてのさまざまな要求をするようになり、必然的に私は由紀子さんとともにトイレの個室にいる時間が長くなっていった。そのうちに、由紀子さんも気を許してくれるようになったのか、自分が頻繁に尿意便意を感じトイレに行かなければいけないことに関して、便座に座ったまま、こんなことを私に語りかけるようになった。
男の人はいいわよね。おしっこ一回行けばいいし、簡単にできるし。女は、おしっこにも行かなければならないし、便もしなければならないでしょ。だから、夜中にも何度もトイレに来なきゃいけないのよ。
女性のほうが男性よりもトイレの頻度が多い、という由紀子さんの認識が何に基づいているのかよくわからないが、トイレのことがいま一番の切実な問題である由紀子さんにとっての男女観が披露され、私は思わずうれしくなった。
さらに、「あなたも女だから、トイレに結構来るでしょ?」と同意を求めてくる。
「そうでもないですけど」と正直に答えると、由紀子さん、続いて
「まだ若いからよ。あなたいくつ? 私の半分もないでしょ。私は大正15年10月20日に生まれたの。何歳になったかしら」
と語りかけ、トイレの会話は弾んでいく。
こうしたトイレの個室でのユニークなやりとりは、他の利用者さんとも(多くの場合女性利用者さん)楽しめるようになった。
たとえば、鈴木のり子さんは便失禁が頻繁にあり、あてているパッドを交換するためにトイレまで職員が同行する。便座に座っているときにのり子さんは、ときどきプププーと大きなおならをする。すると、のり子さん、「屁っぴり大将って言われちゃう。あはは」と屈託のない笑顔をみせる。
聞くと、子どものころ、のり子さんの育った地域では、子どもが大きなおならをすると、「屁っぴり大将」とあだ名をつけられたそうだ。こんな会話も、トイレでだからこそできる。
極めてプライベートな空間であるトイレではあるが、だからこそ利用者さんの普段とは違った言葉や不思議な行動に接することができる。それによって、利用者さんとの関係がさらに深まっていくきっかけになる。
介護職員にとって、トイレは小さなワンダーランドなのである。
トイレをトイレとして認識するのは難しい
認知症の利用者さんをトイレに誘導したときに、しばしば利用者さんが戸惑いの表情をみせることがある。
佐々木洋子さんは、トイレの個室に入ったとたんに、便器のなかを覗き込んで、「なんだか怖いようだね」と呟いて、個室を出て行ってしまった。また、橘ちゑさんは、「ちゑさん、こちらにどうぞ」と言って個室のなかに誘導すると、便器に向って手を合わせ深々とお辞儀をし後退りして出て行った。
この二人の不思議な行動は何だろう。
推測してみると、洋子さんは昭和4年生まれ、ちゑさんは大正10年生まれと、生まれた年代には多少の違いはあるが、二人とも農家の育ちであることからすると、当然、トイレは和式であり、しかも水洗ではなく、汲み取り式だったことが想像できる。
施設のトイレはすべて洋式便器で水洗である。とすると、二人のカラダには昔の生活記憶がよみがえっていて、現在の洋式水洗トイレをトイレとして認識できなかったのではないか、と考えられる。
ちゑさんの手を合わせて拝む様子は、民俗研究者からすると便所神を拝んでいると言いたいところだが、彼女が拝んだあと後退りして出て行ってしまって、ここがトイレだと説明しても中に入ることを拒んだことからすると、そう都合のよい説明はできそうもない。
やはり、ちゑさんにとっては訳のわからない場所に入りこんでしまったわけで、そこから無事に逃れるために、ていねいに拝んで後退りしたのだ、と考えるほうが適当であるように思われる。
ちなみに、ちゑさんをはじめとして、認知症の利用者さんの何人かは、「トイレに行きましょう」と言っても通じないのだが、「お手洗いに行きましょう」というと、「そうそうお手洗いね」と言って素直に従ってくれることがある。
ほかにも、「便所」「雪隠」、あるいは「ニホンバシ」などという言い方がある(昔の農家の外便所では、穴の上に二本の板が渡してあるだけだったから、トイレに行くときには「ちょっとニホンバシに行ってくる」と言っていたのだと、ある女性利用者さんが教えてくれた)。
トイレという言葉は、彼女たちも知っているだろうが、小さなころから親しんできた言葉ではないから、カラダの記憶が昔に戻っている際には、同時に言葉の記憶も昔に遡ってると言えるだろう。
利用者さんの安全のために施設では洋式トイレに統一しているのだろうが、このようにカラダの記憶が昔に戻ることを考えると、ひとつぐらいは和式トイレがあった方が、認知症の利用者さんは安心してスムーズにトイレで排泄ができるようになるのではないかと、私は浅はかにも思ってしまう。
男はやっぱり立たないと……
男性の場合は、洋式トイレというのがさらに厄介な代物になる。
施設には、立ちション用の男性トイレもあるのだが、足腰が弱ったり、認知症が進んだりした男性利用者さんについては、洋式便座に腰掛けて用を足してもらうことにしている。その理由は大きくは二つある。ひとつは、転倒予防のため。もうひとつは、排泄の失敗によって床が汚れてしまうことを防ぐためである。
しかし、小さいころからおそらくごく最近まで立位で用を足していただろうから、要介護になってから、長年染みついた生活習慣から新しいスタイルに変えようとしてもそれは容易にできることではない。認知症の男性利用者さんの多くが便座に座ることを拒絶する。
大正13年生まれの外山守さんのトイレにまつわる次のような話を、自宅で介護している息子さんが、先日聞かせてくれた。
自宅での介護は主に息子さんのお嫁さんがしていて、トイレに連れて行くのもお嫁さんなのだが、守さんはなかなか洋式便座に腰掛けようとせず、お嫁さんの手を振り切ってトイレから出てきてしまうことが度々ある。そういうときには息子さんがトイレに連れて行き、力づくで無理やり便座に座らせるそうだ。
息子さんはそれが大変だと言いながらも、こんなことを付け加えた。
守さんはずっと農業で生計を立ててきた。毎日忙しく働いていたから、用を足したいときもわざわざトイレに行くことはせず、畑で立ちションベンをしていた。今でもよく庭に出たがるし、トイレで座らないのは、そのせいじゃないか、というのだ。
昔からお父さんの働きぶりを見てきた息子さんには、お父さんの現在の行動の背景が見てとれているようだった。ただそうわかったからといって、今の困った状況をどうすることもできない、というのが介護家族の現実なのだと思う。
ところで、先ほどの「屁っぴり大将」の鈴木のり子さんは、しばしば職員に、男性の立ちション用のトイレの縁にお尻をつっこんでいるところを目撃されている。
残念ながら私は一度もそれに遭遇したことがないので詳しいことはわからないのだが、立ちション用トイレを後ろにして腰をかがめ、お尻を突き出して用を足していたらしい。
おそらく女性トイレが空いていないときにのり子さんは男性トイレの方へ足を延ばし、入り口付近にある立ション用の便器を見つけたのだろう。
職員から聞いた様子は、昔の農家の女性が畑でしていたという立ションの姿を彷彿とさせる。ある日、私はトイレのなかでのり子さんに率直に聞いてみた。
「のり子さんは、むかし、立っておしっこしていましたか」と。
すると、のり子さんはあっさりと「そりゃしてたさー。百姓だもの。みんなしてたよ」と認めたのであった(ただし、男性の立ション用トイレで用を足していたことは覚えていない)。
大正一桁生まれで、農家に生まれ育った女性たちは、今ではすっかりすたれてしまった立ションの経験者なのである。利用者さんたちのトイレの行動を注意深く観察していると、そんな貴重なカラダの記憶に触れることができる。そんなとき、私は秘かに幸せを感じるのである。
さて、外山守さんに戻って、息子さんからさらに興味深い話を聞いたのでそれもここに記しておきたい。
守さんが便秘気味なので、排便を促そうとトイレ改修をして洗浄便座にしたそうなのだ。守さんを便座に座らせて落ち着くように息子さんがその前に膝をついて座った。ところが、お尻洗浄のためシャワーが出てくると、守さんはびっくりして飛びのいてしまったというのだ。
勢いよく飛び出してきたシャワーは息子さんの顔を直撃した。とんだハプニングである。息子さんは、「せっかく気持ちがいいだろうと思ってわざわざ親父のために洗浄便座にしたのに……」と肩を落としていた。
お父さん思いの息子さんの奮闘とそれが虚しく終わったことによる落胆ぶりはよくわかる。だが、洗浄トイレのような私たちにとっては画期的な便利グッズも、認知症の方にとっては理解のできない不可思議な物としてしかとらえられないということがよくわかる例だと言えるだろう。
アタマもカラダも昔の記憶を生きている認知症の利用者さんにとっては、水洗化し、洋式化し、そして便利にもお尻洗浄までできる多機能型トイレのある空間は、不思議、不可解なことだらけ世界、これこそまさにワンダーランドだと言ってもいいのかもしれない。
自動水洗という不可思議な現象
これまで、洋式、水洗、お尻洗浄といった最近のトイレ事情に対する利用者さんの困惑ぶりについて述べてきたが、私の勤務している施設のトイレは、さらにそれに加えて、自動水洗という「便利な」機能がついている。
自動水洗は、決まった時間に自動的にトイレの水が流れ、便器が洗浄される機能である。入社当初、この機能にまだ慣れていなかった私は、一日の仕事の終わりにデイルームで翌日の準備をしていると、突然トイレのある方向から、ジャーっという水の流れる大きな音がして何度も驚いた覚えがある。
さて、この自動水洗、認知症の利用者さんにはなかなか理解しがたい機能であるようだ。トイレのなかでご自身の男女観を披露してくれた斎藤由紀子さんは、ショートステイの利用時の朝に、こんなことを私に訴えてきた。
ねえねえ、あなた、聞いてよ。きのうの夜ね、おしっこに行きたくて起きたの。それでトイレに行ったんだけどね、でもね、私、おしっこするまでに時間がかかるでしょ。だって、おしっこだけじゃなくて、便も出るんだから。そうしたら、誰だかわからないけれど、急に誰かが入ってきて、ジャーっと流してしまったの。私おったまげたのよ。あれって、私があんまり何度もおしっこに行くから、もう帰れ! って怒ったんじゃないかと思うの。私、帰ったほうがいいのかしら。
由紀子さんはかなり興奮して甲高い声を出していた。
まさか、夜勤の職員が帰れなんてことを言うわけはないし、いったい何があったんだろうと、最初は私は由紀子さんの訴えていることを理解することができなかった。だが、次に一緒にトイレについて行ったところ、事の真相が明確になった。
尿意を訴えた由紀子さんの手をとって一緒にトイレに入ると、由紀子さんはおもむろに下着を降ろし、便座に腰掛けた。しばらく時間が流れた後、急に私に向って叫んだ。
「ほら、ジャーって。やっぱり帰れってことなんだね」
由紀子さんは明らかに私に腹を立てていた。
私は驚いて、「どうしました。何のことですか」と聞き返すと、由紀子さんは興奮したまま、「ジャーって流したでしょ」と問い詰める。
私は気がつかなかったのだが、どうやら自動洗浄機能が作動したようなのだ。それを由紀子さんは、嫌がらせのために私が水を勝手に流したと理解したのだった。
そこで私は、由紀子さんに、自動で水が流れるトイレであること、そして、それについては何も気にしなくてもいいことを伝えた。
すると、由紀子さんは、「それは便利ね」といったんは自動洗浄機能そのものについての評価を示してくれたものの、再び水がジャーっと流れると、「ほらまた。あなたも聞いたでしょ。何なのかしら」と怒りはじめた。
私は「犯人」であることから何とか免れたようだが、自動洗浄に対する由紀子さんの理解と怒りは変わらなかった。
未知の現象は経験知から理解する
自動洗浄に対する由紀子さんの不信感は、ショートステイの次の利用日には、さらに増していた。由紀子さんは今度はこう訴えてきた。
さっきね、おしっこがしたくてたまらなくなって、トイレに行ったの。おしっこがしたくて、おしっこがしたくて、本当にたまらなかったんだけど、トイレに行ってね、それでこれ(パンツ型オムツ)を降ろそうとしたら、急にジャーって出たの。それでびっくりしてすぐに降ろしてみたんだけど、何も濡れていないし汚れていないのよ。どういうわけだか、さっぱりわからないの。もうおしっこ出なくなっちゃうし。
はじめは何を言っているのかさっぱりわからなかったが、「ジャー」という表現に、もしや自動水洗のことではないか、とピンときた。私は、「不思議ですね。それじゃ、私にちょっと見せてくれませんか。一緒にトイレに行きましょう。」とトイレに誘導してみた。
由紀子さんがトイレに入り、「さてと」と下着を降ろそうとしたとき、またもや自動水洗が流れた。
由紀子さん、すぐに下着を降ろしパッドを確認する。そして、すばやく私の方へ顔を向けたかと思うと、「ほらね、ジャーってたくさん出たのに、濡れてないのよ。おかしいでしょ」と叫び、困惑した表情で首を傾げている。
なるほど、今度は由紀子さんは、自動水洗のジャーという音を自分が排尿した音として理解したわけだ。
切羽詰まってトイレに駆け込んだ。そして、大きな音がしておしっこが出た。なのに、下着をみても全然汚れていない。それは由紀子さんにとってどれだけ不思議な現象であっただろうか。
トイレからリビングに戻ると、由紀子さんはまだ納得がいかないといった顔をして、私に聞いてきた。「あなたもこういうことあるの?」
「私はないですね」と答えた私の顔を由紀子さんは不思議そうに眺めていた。そして、今度は、他の女性利用者さんたちに、大きな声で尋ねはじめた。
「ねえ、あなたは、生理がある?」と。
生理??? 唐突な質問に、利用者さんたちはぽかんと口を開けていた。私も、この予想外の言葉と今までの発言との間がすぐにはなかなか結びつかなかった。
しばらく様子をうかがっていると、他の利用者さんたちが、「あるわけないじゃない、こんなおばあちゃんが。あんた、生理っていうのは子どもができる人がなるんだよ」とちょっと馬鹿にしたように由紀子さんに言った。
それを聞いた由紀子さんは、さらに目をまん丸にして、
「じゃあ、私、子どもができるのかしら。もう80歳なのに」
と呟いた。リビングに大きな笑い声が響いた。
というわけで由紀子さんは、自動洗浄をめぐる不思議な現象を、さらに、生理によるものではないか、と理解したのであった。
由紀子さんにとって、自動洗浄トイレがどんなに不可解なもので、それに対してこれまでの経験知を総動員して何とか理解可能なものにしようとしていたかと思うと、その涙ぐましい努力に感動さえ覚える。
その方の歩んできた人生に基づいたカラダの記憶と、現在のトイレ設備との間にある大きなギャップに、利用者さん自身が困惑し、そしてなんとか理解しようと奮闘している。だからといってなかなか施設の既存の設備を換えることは難しいが、それでも利用者さんたちのそんな思いを受け止めておくだけで、利用者さんの「不思議」と思われる言動への理解も深まるのではないかと思う。
トイレ介助には、利用者さんを深く知るためのカラダの記憶のかけらが散りばめられている。
(web第2回了)
[次回は1月中旬UP予定です。乞うご期待。]

『看護学雑誌』2010年08月号 (通常号) ( Vol.74 No.8)
特集 カラー写真でわかる 褥瘡ラップ療法
定価 1,260円 (本体1,200円+税5%)