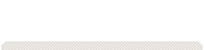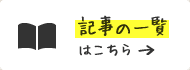かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

劇作という活動 | 第二部 他者をわかるということ
2025.10.03 update.

胡桃澤伸(くるみざわ しん)
精神科医。劇作家。1966年長野県生まれ。
1995年、阪神淡路大震災直後の神戸で精神科医として勤務を開始。以後、大阪、東京、千葉で勤務。2003年から、北区つかこうへい劇団戯曲作法塾、伊丹想流私塾で劇作を学び、「くるみざわしん」の筆名で劇作家として作品を発表。放射性廃棄物の最終処分場をテーマにした『同郷同年』で2016年「日本の劇」戯曲賞最優秀賞と2018年第25回OMS戯曲賞大賞を受賞。古典を現代思想の観点から改作した『忠臣蔵・破 エートス/死』が2019年文化庁芸術祭賞新人賞を受賞。単著に精神科医としての勤務経験を作品化した『精神医療連作戯曲集/精神病院つばき荘・ひなの砦』、2011年の東電福島原発事故後の世界を作品化した『反核・反被曝連作戯曲集 同郷同年/蛇には、蛇を』。共著に『中井久夫講演録統合失調症の過去・現在・未来』(以上、いずれもラグーナ出版)。編著に『安克昌の臨床作法』(日本評論社)がある。
西堂行人(にしどう こうじん)
演劇評論家。2023年3月まで明治学院大学文学部芸術学科演劇身体表現コース教授。1990年代以降大学で演劇教育に関わり、近畿大舞台芸術専攻教授(1998~2016)。
専門は60年代以降のアングラ・小劇場演劇。および日本/世界演劇史。2006年より現在まで伊丹アイホールで「世界演劇講座」を開講。主な著書に『演劇思想の冒険』『ハイナー・ミュラーと世界演劇』『劇的クロニクル』『韓国演劇への旅』『現代演劇の条件』『蜷川幸雄×松本雄吉 二人の演出家の死と現代演劇』『日本演劇思想史講義』『ゆっくりの美学――太田省吾の劇宇宙』『新時代を生きる劇作家たち』『日本演劇史の分水嶺』他多数。大学生との共編著に『近大はマグロだけじゃない』『コロナ禍を生き抜く演劇論――学生が見た2020/2022ドキュメント』がある。最新刊に、『新版 日本のアングラ』がある。
■共感について
西堂 「楽しめる」って言葉は結構意味合いが広いですよね。単にエンターテインメントではなく。
くるみざわ あ、そういう意味じゃないですね。
西堂 そうじゃなくて、苦しい、けど楽しい。
くるみざわ そうですね。充実感とか、確かさとか手ごたえとか、そういうものです。
西堂 発見があるとか、興味を引き起こしてくれる。楽しませるって言うと、わりと通俗的な楽しさに通じちゃうことが多い。
くるみざわ そうなっちゃうと困るんです。むしろそこから回復するために演劇があるんです。
西堂 例えば「共感」っていう言葉もそれに似ている気がするんですよ。
くるみざわ ああ、共感ね。
西堂 共感って言うと、「そうそうそう、あるあるある」みたいなかたちで受け止められている。けれど、共感の下には「共苦」、苦しみ、痛みがあるからこそわかり合えるっていう部分があって。だからもう一つ回路を持ったうえで、「共感」や「楽しめる」って使わないと、流通しているイメージに回収される。気を付けたほうがいいかなって思ってます。
くるみざわ それは気を付けたほうがいい。共感っていう言葉は、要注意ですね。もともと共感っていう言葉は、カウンセリングの実践の中から出てきた言葉ですね。
西堂 ああ、心理学の。
くるみざわ 心理学の実践の中から出た言葉なんですよ、共感は。で、共感って「そうそう、わかるわかる」じゃないんですよ。今西堂さんが言った「共苦」ね、苦しみを共に感じるっていう要素が入ってるんです。さっき言いましたけど、「わかった」っていうのはそれまでわからなかったことがわかるときなんです。その時、共感が起きる。つまり、ずっと話を聞いてて、今まで全然聞けてなかった、本当はこっちだったんだってわかったときが、共感なんです。だから、相手の苦しみと自分の理解力のなさが同時にわかる。そして、相手の苦しみの原因の1つは自分の理解力のなさにあったことがわかる。これはつらいですよ。だからこれがわかったって時はね、大変なことが起きるんですよ。自分は思い違いをしていた、この人はこういう気持ちを持っていたんだ、あのいきさつはこことつながっててこうなってたんだ。なのにそれを聞いていたはずの自分はわかってなかった。わかったような気になっていただけだとわかった時、ほんとにびっくりする。それが「共感」なんですよ。だから、驚きとか苦しみとか、今までわからなかったっていう、がっかり感。そういうものが全部入り混じったようなものなんです。「わかるわかる」にはそういうプロセスが何にもないわけ。もともとあった状態が脅かされないでずうっと続いているでしょ。
西堂 そうだね。
くるみざわ それは別に何でもないんですよ。一緒ってだけ。ほんとに一緒かどうかは吟味しなくちゃいけないけど、一緒なんだなっていうのを確認する方便ですよ。
■劇作家の仕事
西堂 この前、くるみざわさんのおじいさんが関わられた事柄について書かれた舞台『鴨居に朝を刻む』を拝見しました。これについてお聞きしたいのですが、よろしいですか?
くるみざわ いいですよ。
西堂 満蒙開拓団という、戦前の中国に出かけて行った開拓農民についての芝居でした。実は古川健さん(劇団チョコレートケーキ、1978生まれ)も同じ題材で書いています(『血のように、真っ赤な夕陽』)。
くるみざわ 書いてますね。
西堂 古川さんに聞いたら、これは歴史の教科書には載っているけどあんまり詳しく載っていないんで、こういうのは戯曲の素材に使えるって彼は言っていました。満蒙開拓団は歴史の教科書では聞いているけれども、実態がよくわからない。結局長野県の人が一番出かけているんですね。
くるみざわ そうですね。
西堂 まさにくるみざわさんの祖父が関わっていたことを書かれている......これ絶対僕観に行かなくちゃと思って。
くるみざわ いやあ、ありがとうございます。
西堂 (会場が小さいので)30人ほどの観客でしたが、そこらへんのことを残しておかなきゃいけないっていう気概が、くるみざわさんの中にあったんですか?
くるみざわ これは......気概というか、避けて通れない。いつかは書かなくちゃいけないと思ってました。満蒙開拓っていうのは開拓じゃないんですよ。開拓してないんです。もともと中国東北部の農地になっていたところを、日本が安い金で、しかも軍の力をバックにつけて奪い取り、そこに日本から農民を送って入植させた。いま、パレスチナにイスラエルがやっているようなことです。土地を取り上げて、そこに自分の国の人間を送って、そこをまるで自分の国のようにしちゃうっていうことを、日本は中国の東北部でやってたんですよ。1931年の満州事変から1945年の敗戦まで。で、僕の実家は長野県の山の奥の方にありまして、貧乏な村だったんですよ。僕のお祖父さんは村長をやっていまして、「満蒙開拓」という国の政策に従って、自分の村の人たちを中国に送ったわけ。百名くらい満州に行って、分村をつくったんです。ところが、日本が負けそうになると日本軍は「満州」からこっそり引き上げてしまった。で、日本が戦争に負けると、土地を奪われていた人たちが取り返しにやってきた。「満州」に渡った男の人たちは軍隊に招集されないっていう約束だったんだけど、もう軍人がいないから招集されたんですよ、日本に。そのせいで分村には、若い女性と幼い子供とお年寄りしか残らなかった。そこへ、家や土地を取り戻そうとする人達がやって来たから逃げることになったけれど、逃げられない。もう日本に帰るのは無理だろうということで諦めて、その分村は73名が自分たちで死んだんです。お母さんは自分の子供を殺して、お母さん同士も殺し合う。その知らせが翌年ぐらいに、うちの実家に届きました。その知らせを聞いたうちのお祖父さんは自宅で首をつって死んでしまったんです。それが僕の生まれる20年位前の話。で、僕はその家に生まれたんですけど、そういうことがあったことを誰もしゃべらない。うちのお祖父さんがどういういきさつで死んだのかとか、村の人たちが戦争中にどういう目に遭ったのかとか、しゃべらない。学校でも教えてくれないんです。知らないなら知らないで別に困らないんですよ。学校も行けるし。でも、ただ......、なんというか......うまく言えないんですけど、心のなかにはどうにもうまくゆかないものがありました。
劇作のことに限ってお話しすると、なんとなく芝居を書き始めてて、先ほど言いましたように、サークルの人の話をたくさん聞いてお芝居を書くなんてことをやっていました。ところがある日、分村の集団死やお祖父さんの自殺の経緯を知ったわけです。驚きましてね。自分の家とか自分の村にそんなことがあったんだって。で、これは書かなくちゃと思ったんだけど書けないんです。自分の村、お祖父さん、そして自分自身のことですからね。
自分の家でそういうことがあって、いっさいそのことについてしゃべってくれる人がいない。そういうなかで育って、いざそのことについて考えたいとか、しゃべりたいとか、作品に書きたいとか思っても、まったくできないんですよ。今の僕はこうやってしゃべれますけど、こうやってしゃべれるようになるまでに10年くらいかかってます。書けるようになるまでにはもっとかかった。家の事実を知った時、僕はもう芝居書き始めていたんですけど、僕の先輩にあたる劇作家の人が、僕の家のことを知って、「もし僕がくるみざわさんだったらそのおじいさんの日記を全部読んで反吐を吐いてでも戯曲書くよ」って言ったんです。確かにそれが創作に携わる者としては正しい道だなと思ったんです。自分もそれをやりたいなと思ったんですけど、いざ自分がそのおじいさんの日記を読むために手を伸ばそうとすると、これができないんですよ。怖くて、怖くてできない! ましてや読むなんてことは体が変になりそうで、できなかったんですよ。自分にはまだその実力がないなと思って諦めてました。ただね、石にかじりついてでも書けるようになりたかったんです。
で、僕は大阪で、文学学校に通って詩を習ったりした。僕と同じような思いをもった書き手っているんですよ。僕が一番学んだのは、在日の朝鮮人で詩を書いている金時鐘(キム・シジョン)さんです。金時鐘さんの母語は朝鮮語です。でも、日本の植民地支配で言葉を奪われて日本語で創作するしかなくなっている人たちっているわけ。そういう人たちと金時鐘さんは詩のサークルを作って在日朝鮮人として日本語を表現の手段に選んで詩を書いている。そういう書き手のあり方に学ぼうとする人たちと交流したんです、大阪で。その人たちの実践も見たし、一緒に飲み食いしたり、話し合ったりした。そういう経験をすることで、だんだん書けるようになりました。僕は、この前西堂さんが見てくれたお芝居を、古川さんみたいにこれはいい題材だからっていう姿勢で書いたのではなくて、書かなくちゃいけないから内側から掘り起こして、自分で自分の言葉を獲得して、表現しないと納得できないから書いたんです。これをやらないうちは死ねない、くらいに思った。お祖父さんが書き残した日記が目の前にあるし、その日記に関心を持って読んでいる地元の人もいるわけですよ。くるみざわの家のお祖父さんの孫が芝居やってる、いつか書くんじゃないかみたいな(笑)って感じもあるわけ。そうなると相当なプレッシャーがかかる。でもやろうとなって、やったわけです。
■上演の条件
西堂 創作者の地獄、ですね。
くるみざわ そうですね
西堂 それを引き受けるのにやっぱり10年、20年かかった......。
くるみざわ かかりますね。
西堂 ふんぎれた動機ってなにかあったんですか? 今がその時だと思った......瞬間。
くるみざわ あ~、それは。演じてくれる役者さんと出会った時ですかね。それが大きいです。あと、上演しようといってくれる制作会社っていうんですか、仲間がいたこと。これが一番大きいかな、今やらなくちゃと思えたのは。
西堂 その人たちが背中を押してくれたということですか? それと同時に、祖父を演じる代弁者がいた?
くるみざわ 代弁者っていうか......誰にでも託せる内容ではないので、託してみようと思える俳優さん、制作者に出会ったっていうことですね。出演してくれたのは川口龍っていう役者さんなんですけど。しばらく前から一緒に芝居を作ってるんです。そうすると、今作ってる芝居の話だけじゃなくて、自分がどんな家に生まれてどんなふうに育ったとか、だんだんわかるんです。そうすると、僕の家やお祖父さんのことを知った川口さんが、くるみざわさん、いつかそれを書くんでしょ、みたいになるんですよ(笑)。彼と一作、従軍慰安婦の一人芝居を作ったんですよ(『あの少女のとなりに』)。ハードな題材を一緒につくることってやっぱり相当な信頼関係がないとやれないわけですよ。そういう創作を経験して、次何を作るかなっていうときに、もうそろそろお祖父さんのことを書かなくちゃっていう感じが、ありましたね......。
 マートルアーツ『鴨居に朝を刻む』
マートルアーツ『鴨居に朝を刻む』作・演出=くるみざわしん
2024年11月23日(土・祝)~24日(日))/ギャラリー古藤
撮影=マートルアーツ