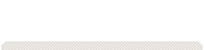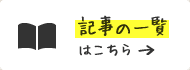かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

劇作という活動 | 第一部 臨床も創作も対話から立ち上がる
2025.10.03 update.

胡桃澤伸(くるみざわ しん)
精神科医。劇作家。1966年長野県生まれ。
1995年、阪神淡路大震災直後の神戸で精神科医として勤務を開始。以後、大阪、東京、千葉で勤務。2003年から、北区つかこうへい劇団戯曲作法塾、伊丹想流私塾で劇作を学び、「くるみざわしん」の筆名で劇作家として作品を発表。放射性廃棄物の最終処分場をテーマにした『同郷同年』で2016年「日本の劇」戯曲賞最優秀賞と2018年第25回OMS戯曲賞大賞を受賞。古典を現代思想の観点から改作した『忠臣蔵・破 エートス/死』が2019年文化庁芸術祭賞新人賞を受賞。単著に精神科医としての勤務経験を作品化した『精神医療連作戯曲集/精神病院つばき荘・ひなの砦』、2011年の東電福島原発事故後の世界を作品化した『反核・反被曝連作戯曲集 同郷同年/蛇には、蛇を』。共著に『中井久夫講演録統合失調症の過去・現在・未来』(以上、いずれもラグーナ出版)。編著に『安克昌の臨床作法』(日本評論社)がある。
西堂行人(にしどう こうじん)
演劇評論家。2023年3月まで明治学院大学文学部芸術学科演劇身体表現コース教授。1990年代以降大学で演劇教育に関わり、近畿大舞台芸術専攻教授(1998~2016)。
専門は60年代以降のアングラ・小劇場演劇。および日本/世界演劇史。2006年より現在まで伊丹アイホールで「世界演劇講座」を開講。主な著書に『演劇思想の冒険』『ハイナー・ミュラーと世界演劇』『劇的クロニクル』『韓国演劇への旅』『現代演劇の条件』『蜷川幸雄×松本雄吉 二人の演出家の死と現代演劇』『日本演劇思想史講義』『ゆっくりの美学――太田省吾の劇宇宙』『新時代を生きる劇作家たち』『日本演劇史の分水嶺』他多数。大学生との共編著に『近大はマグロだけじゃない』『コロナ禍を生き抜く演劇論――学生が見た2020/2022ドキュメント』がある。最新刊に、『新版 日本のアングラ』がある。
■劇作活動と精神科医
西堂 今日は劇作家で精神科医のくるみざわしんさんをお迎えしました。
くるみざわ 初めまして。よろしくお願いします、くるみざわです。
西堂 くるみざわさんのプロフィールを簡単に紹介します。長野県生まれで、37歳の時に北区つかこうへい劇団に入団し、そこで戯曲創作を学びました。その後2005年から伊丹アイホールで北村想さんが運営する想流私塾という戯曲講座に参加して、本格的に演劇を学びました。2007年に初めて自作の上演のために「光の領地」という集団を創ります。それから15年以上にわたって旺盛な執筆活動を続けられています。 今回くるみざわさんをお呼びした最大の理由は、この1年間演劇界を見渡してきて、もしかしたらくるみざわさんの作品を1番多く見ているのかなと思いました。そのいずれもが非常に印象深い作品で、世間での評価とは違うと思うんですけれども、僕にとっては今年の演劇界のMVPかな。
くるみざわ (笑)
西堂 僕はそう思っていますが、それはなぜかというと、彼の作品が上演されている場所が非常に小さい場所だからです。例えば1か月程前に観たのはギャラリーで、30人くらいの観客の前で一人芝居を上演しました。本当に小さな所で上演されているので、観客の人数で言えば、何十回公演やっても大劇場1日分にも満たないくらいです。けれど、その小空間の中で非常にクオリティの高いことをやられている。これはいったい何なんだろうかと思って、このことをくるみざわさんに聞いてみたいというのが今回お呼びした理由の1つです。
もう1つの柱として、くるみざわさんは精神科の医師をされていて、これと戯曲を書くことがどうつながっているのか、ここをおうかがいしたい。実は医者で芸術家っていう方はかなり多くいるんですね。その中で、とりわけ精神科医ということがどういう意味を持っているのかというのも併せて聞いてみたいし、今、若い世代にも、鬱だとか精神的な病を持ってる人たちが増えていて、くるみざわさんなりの分析をしてもらえると、若者に対するアドバイスにもなるんじゃないかと。というようなことで、お招きしたという次第です。今までのことで何か付け加えることはありますか?
くるみざわ いきなり2つ、かなりの直球ですね、。僕は、普段は人の話を聞く仕事をしているんですよ、精神科医ですからね。患者さんの話を聞いて、どっちかっていうと自分からあまり話さない。でも今日は話してみようと思って来ました。西堂さんもこんなふうに質問してくださいますし、もし皆さんも質問があったらしていただけると僕もそれに応えて、話すことができる。質問するというのはすごく大事なことなんですよね。何かを生み出す初っ端にあるのは「問い」です。皆さんが「問い」を出してくれると僕も助かるし、そこから新しい言葉や表現が生まれてくるんですよ。そんなことをまず言いたくなりました。
西堂 今ふと思ったのは、僕も聞くほうが得意ですね。僕は批評家なので、自分でこういうことを言いたいとか世界観を主張するより、他人の話を聞きながら、それと併せて自分のことも言うっていうスタイルでずっとやってきたんです。対話集が多いのはそのためで、聞くのは上手いほうなんじゃないかなということが1つあります。劇作家の人と会うと、聞くことが下手な人のほうが多いような気がするんですよ。
くるみざわ そうですね。
西堂 一般的に言うと、劇作家は自分の言いたいことは山ほどあるけど、それについて聞く耳持ってるかというと意外に持っていない。だから、くるみざわさんみたいなタイプの劇作家って非常に珍しいんじゃないかなと、聞いていて思いました。
くるみざわ 僕も投げるほうではなくて受けるほうですね。西堂さんがおっしゃるみたいに投げられたものを一所懸命に受けて、その結果、作品ができるという執筆スタイルです。
西堂 あらかじめこういう世界を見せたいとか、感動させたいとかっていう芸術家魂とはちょっと違うのかなと。
くるみざわ ああ、そうですね。
西堂 自己主張の強い劇作家って多いですよね。
くるみざわ 多いですね。あまり誰とは言えないけど(笑)。
西堂 逆に演出家っていうのは、わりと聞き上手だと思うんですね。
くるみざわ はい、そうですね。
西堂 演出家は自分の世界があるというよりは、劇作家の書いた世界を通して自分のものを出す。だから媒介者になっているのが演出家だし、批評家だと思うんです。劇作家ってのは自分の世界を構築してぶつけるっていうイメージが強い。
■聞くことと書くこと
くるみざわ 僕は、最初は自分の内側に表現するものがあると思えなかったんですね。でも、芝居は好きなんですよ。だからやりたいと思ったけれど、自分が表現したいものが何なのか、あるのかないのかがわからなかったんです。でね、たまたま演劇もやってるサークルみたいなのに入ったんです。そこで、自分の家族はこうだとか、自分はこういう経験をしたとかを語るプログラムがあったわけ。そういうのをいっぱい聞いたんです。来てたのは学校の先生が多くて、授業が上手くできないとか、自分の子供が不登校になってしまったとか。そういう方々。そしてその子供たちが集まるようになって、そこでたくさん話を聞いているうちに、「ああこういうストーリーになるな」というのが思い浮かぶわけです。それを脚本にして書くっていうのを毎回やっていました。聞くっていうことと創作するということはそんなに遠くないんですよ、実はね。
西堂 非常に本質的なことだと思うんですね。聞くこと、あるいは読むこと。
くるみざわ ああ読むことね。
西堂 人間って、あらかじめ何かあるわけじゃなくて、何もない空っぽなわけですね。そこで本を読んで、読んだことからイマジネーションをはたらかせて、それを書き換えていく。
くるみざわ はい。
西堂 だから、本当の意味でゼロから生まれるオリジナルってないんじゃないかなと僕は思うんですね。本を読んだことを書き換えていく。それが現代劇の作家の常道なんじゃないか。今くるみざわさんが言われたように、いろんな人がいて、いろんな面白い事をいっぱいしゃべってくれる、それは自分にないものですよね。自分よりもはるかに多様なものが、他人によって持ち込まれてきて、それをいわば変換していく「マシーン」。
くるみざわ そう「マシーン」。
西堂 (笑)
くるみざわ 自分はこんな家に育ったとか、こんな目にあったとか話す人は、自分でもそれを持ちきれない。
西堂 ああ、そうですね。
くるみざわ 持ちきれないから話す。そしてそれを舞台にあげて、観てもらって、伝えたいんだけど、他人が観て楽しめるものにするのは大変だから、そこまでの力はないわけ。でも誰かが脚本を書かなくてはってことになって僕が書くようになったんですけど、結局そういうふうに話を聞いて脚本を書くっていうことは、やっぱり共同創作なんですよ。その人が「ああ伝わった!」って思えるところまで、僕も一緒に心を動かして、頭で考えて、伴走して書くわけです。これが、ちょっと伝わるかわかんないけど、滅茶苦茶楽しいんですよ。達成した時の興奮といったらないです(笑)。 「やったあ!」みたいな感じになるわけ。稽古も大変苦しいんですよ。僕に話してくれた、その体験の当事者が自分自身のことを演じるからね。だけど舞台に立ってそれをお客さんが観て、伝わってるなっていう実感を持った時の喜びは大変なものなんです。そういう渦の中にいました。だから、聞くことと書くことと創ること、あと西堂さんは本のことをおっしゃったけど、本を読むことも創作の一部です。世の中にはその分野の研究者がいて、家族の問題とか、歴史とかについて優れた研究をしている。そういう人の本をやっぱり読まないと創作の手掛かりが見つからない。独りよがりになってしまう。そういうふうに本を読みながら書くっていうことをやっていくと、著者との出会いがあるんです。例えば、去年ここ(明治学院大学)でも上演した『あの少女の隣に』っていうお芝居は「従軍慰安婦」がテーマですから、その分野の研究者の本を読むわけ。で、何冊も読んでいると、「この人だ!」っていう研究者がいるわけ。そういう人を発見すると後はすごくやりやすいです。その人の本を読むことで考えが深まるし、ただ深まるだけじゃなくて、ここが表現したかったんだなっていうのがわかってくる。共同創作に勝手に持ち込んでしまう。そういうことが起きますね。
 マートルアーツ『あの少女の隣に』
マートルアーツ『あの少女の隣に』作・演出=くるみざわしん
2023年2月4日(土)~5日(日)/下高井戸HTSスタジオ
撮影=マートルアーツ
■対話を成立させるために
西堂 基本的に他人への興味というか関心から、いろいろ受け取ったことを自分なりに変換していく。でも自分なりに変換する時に自分がないと変換できないですね。
くるみざわ できないです。
西堂 その変換する自分ってなんなのか。
くるみざわ それはですね......。他人の話を聞いてそれをそのまま受け取るだけでは聞いたことにならないし、相手も話したことにならないでしょう。一所懸命に話していて相手が、ふんふんってうなずいてくれたらそれはそれで満足かもしれないけど、新しい閃きってのはなかなか出ないですよ。閃きがないと創作にならない。だから「新しい閃きが出るような聞き手」っていうのは、実は話し手と少しズレがあるわけ。あれ?そこ、私と考えが違う。あれ?そんなふうに私は思わないっていうところを大事にできるか。
西堂 うん。
くるみざわ それをないことにして、ただ従順なままやっていても書けないですよ。
西堂 そこがたぶん今の学生には難しいと思う。
くるみざわ 難しいですか。
西堂 すぐうなずいちゃう。ああそうなんだって。そう思った瞬間に対話が終わってしまう。
くるみざわ ああ、そうか。
西堂 だから対話は、その言われたことに対する違和感の表明とか、それに対してむしろこう思うよっていう意見をぶつける、対立が生まれる。そこがみんな苦手なところなんです。
くるみざわ それはね、今の若い人たちだけじゃなくて、僕も苦手ですよ。ぶつけるまでやると、せっかく話したのに反論されたっていう経験になっちゃうからね。ぶつけるまでやると......やりすぎかもしれないですね。だから、あれちょっと違う、もう少しそこ詳しく話してくれないとわからないと伝えるぐらいにしておく。
西堂 突っ込むっていうことかな?
くるみざわ 柔らかく突っ込まなくちゃいけないんですよ。突っ込む側がやり過ぎたと思っちゃって萎縮するようだと良くないし、突っ込まれた側が不安を感じたり、怖いって思ったりしないように。
西堂 気持ちよく突っ込む、相手が喋りたがるように突っ込む。
くるみざわ そうそう、そうです。
西堂 それが上手い質問者だと思うんですね。本当はこういうこと言いたかったんだけどって、その背中を押すみたいな。
くるみざわ そうです。
西堂 だから反論というよりは、AとBの対話がCになるような。
くるみざわ そうです、そういう感じです。だから対話してる時は、こうやって西堂さんと1対1で話をしていますけど、実は話題っていうのは西堂さんと僕の間にあるわけですよ。演劇とは、創作とはと語りながら、僕らの真ん中にある話題を2人で見てるわけ。で、「あ、西堂さんから見るとそう見えるんですか。こっちから見るとこう見えるんですけど、どうですか」っていうことを喋るんですよ。自分1人じゃ一部分しか見えないからね。言葉を使って、自分が相手にどう見えているかを知って、自分に見えているものと突きあわせて考える。そういう聞き方、喋り方を続けていけば、お前間違ってるとかそういう論争にならない。
西堂 批判していると、人格を否定しているみたいに兎角なりがちなんですけど、本当はここにある中間項の対象について批判しているんです。
くるみざわ そうですね。
西堂 その中間項がないと、攻撃になってしまう。今日、このたった10分ぐらいの間でいろいろ閃きありました。
くるみざわ ありました?
西堂 ありました(笑)。
■能におけるワキの重要性
西堂 聞き手とは、能で言えばの「ワキ」的なところですね。
くるみざわ そうですね。能にはシテとワキという役割があって、ワキがシテの話をじっと座って聞くんですね。僕はそのこと知らなかったんです。ある時、「世界演劇講座」っていう西堂さんが大阪でやっている講座に来ている、能に詳しい人が僕に向かって、「くるみざわさんはワキです」って言ったんですよ。言われた時はピンと来なかったんだけど、その後いろいろ調べてみると、あ、本当にそうだなと思ったんですよ。つまり能では、ワキの前には、もうすでに死んでしまったけれど、無念の思いが残っていて死ねずに彷徨っている人が現れるんですよね。それがシテです。誰かに話を聞いてもらいたいと思って現れるわけ。そのシテの語りをワキが聞くことで、シテの無念が晴れて、成仏するんです。これは精神科の診察によく似ている。いろんな思いを抱えて診察室に来た人が話をして、「もう、いいです」っていうふうになったら去っていくわけです。精神科の診察も能も、そういう出会いと別れですね。
西堂 うん。能におけるワキの役割の重要性ですね。
くるみざわ それが本物の出会いになり、本物の別れになるためにはワキがシテの無念を語って話すっていうことが実現されないといけないんです。それを実現してるのは、喋っているシテももちろんだけど、聞いているワキがいるってことが大事なんですよ。誰も聞いてくれないところで話し続けることはできないですからね。
西堂 うん、そうですね。
くるみざわ で、聞いているワキがシテの無念を受け止めて、「ああこの人はこういう経緯でこうなっていたのか!」と腑に落ちる。これがとても大事なんですよ。誰とでもそんな出会いをしてたら身が持ちませんけど、ここぞという時はそういうふうに出会わないと、人は生きていけない。それを演劇でやっているのが能だと思うんです。
西堂 理解するってことが大事なのね。相手を受け入れて、理解する。
くるみざわ そうですね。理解する。わかるっていうことが大事で、わかるというのは実はそれまでわかってなかったんだということがわかった時ですよね。わかった後はわかってなかった時の自分と変わってないといけないんですよ。だからワキの方はじーっとして話を聞いているだけだけど、心のなかでは大きな変化が起きるんですよ。それはわかっていなかった自分を知るという大変つらい変化です。だからわかってもらったっていう経験の裏側には、今までその人のことをわかっていなかった、そういう発見がセットでくっついていると思う。
西堂 非常に深い話ですね。
■診察
西堂 それをくるみざわさんは生業としてやられているわけです。1人の患者さんと向き合う時間はどのくらいですか? 1時間くらい?
くるみざわ いや、今は短いんですよ。1時間も話を聞ける人はいなくて、長くても30分、普通は10分とか15分。
西堂 いろいろな悩みとかを聞いてうなずいたり励ましたり、言葉を返したりというような形で、診療が進むわけですか?
くるみざわ そうですね。それを診察と呼んでいます。
西堂 その時に繰り出す言葉、テクニカルタームみたいなものってあるんですか?
くるみざわ テクニカルタームと言えるほどのものがあるかどうか。というより、テクニカルタームは専門用語ですから、自然な対話のじゃまをしてしまいます。できるだけ使わないほうがいいんです。その場で生まれる生の言葉に治療の力がありますから、前もって用意しすぎるとよくないんです。先輩がやってるところを見たり、こういう時はこういうふうに言うんだよということを教えてもらったり、本で読んでこれはいいと思う言い回しを覚えたりして、自分の言葉にしていくんです。医者になったばかりの時は、診察で使える自分の言葉が何もないわけ。医学部は出て、医師免許は取ったけれど、患者さんの前に行っても何にもできない......というかしゃべれないわけ。何をどうしゃべっていいかわからない。で、さらに精神科の場合は、無理やり入院させなくちゃいけないとかがあるんですよ。入院を嫌がる人を説得してね。そういう場合どうしゃべるかっていうのはすごく難しい。それが精神科医の腕なんですけど、自分1人じゃ言葉が出ないんですよ。無理に出そうとすると「入院しなさい」みたいな命令口調の言葉しか出ない。
どうしてたかっていうとね、僕が研修の時に教授だった中井久夫さんが本を出していて、僕は中井さんの言葉が心にすごくフィットしたから、中井さんの本を診察前に医局で読んで覚えて、セリフ覚えるみたいに一字一句正確に覚えて、できるだけそのまま患者さんの前でしゃべるっていうのをしてました。でもやっぱり、そのまましゃべろうと思ってもしゃべれないんですよ。患者さんの反応が途中で返ってきて、それがその人その人でちょっとずつ違うから。途中で言葉が入れ替わったり、順番が変わったり、もっとわかりやすい言葉に置き換えたりすることで中井さんの言葉をだんだん消化して、自分の言葉にしていった。それが診察で使える言葉の蓄えになっています。
西堂 15分くらいでそれができるんですか?
くるみざわ いや、15分では......入院の説得は無理ですね。1時間ぐらいかかる。普通の診察は10~15分ぐらい。
西堂 診察は1時間くらいたっぷり聞いてっていう感じがイメージとしてあったんですが。
くるみざわ 1時間たっぷりっていうのは難しい。でも、やっぱり40分から50分くらいあったほうがいいですね
西堂 あったほうがいい?
くるみざわ あったほうがいい。ただ、今は病院の経済的事情で診察時間をそんなに長くは取れないんですよ。売上げを上げるために1日何人診察しなくちゃいけないっていうのがあるからね。あと、診察を求めて来ている人はもう話したいことが決まってるんですよ。それに焦点を絞って話をすると10分とか15分でも結構長いですよ。2週に1回、そういう話をするだけで変化が起きたりします。
■精神科医にたどり着くまで
西堂 くるみざわさんは医学部に入られて最初から精神科医を目指されてたんですか?
くるみざわ そうです。最初から精神科医でしたね。
西堂 その前にもう1つ大学行かれてますよね。
くるみざわ 行ってました(笑)。
西堂 それでなんで医学部にもう1回入り直して、しかも精神科医にたどり着いたのか。
くるみざわ ああ、そこですか。最初は工学部に行ってたんですよ。入学したのが1984年。卒業したのが1988年。だから、バブルがこれから来るぞっていう時だった。就職先もいっぱいあったんです。で、1986年にチェルノブイリ原発事故がありました(現在はチェルノーブリ)。今はなきソ連の、チェルノブイリ原発の事故が春に起きて、その年の秋ぐらいに大学の生協に原発事故が起きたらどうなるのかとか、原発がどういうものかっていうのを書いた本が置かれてたんです。工学部の生協なのにね、いえ、だからこそかもしれませんけど、原発の本当のところはどうなんだみたいな本を置くような生協だったんです。で、たまたま僕、その本を手に取って読んじゃったんですよ。で、読んだら、あ、原発ダメだわって思ったんです。あれは本当にダメですよ。技術的にも無理で事故は必ず起きる。どんなに防護をしても、原子炉の掃除に入る人の被曝は防げない。ウランの採掘現場でも被曝が起きる。もともと核兵器を作る兵器産業から原発が生まれてて、人の健康を損ねることを見越した上に成り立ってる産業だってことが、本を読んですぐわかったし、それが日本では電力料金にうまく組み込まれていて、絶対に損をしない仕組みになってるんです。作ったら儲かるようになってる。ということは、どんなに人が放射性物質に汚染されても金儲けのために原子力産業は回り続けるんです。このまま工学部にいたら原子力産業で働くことになるかもしれないと思ったんですよ。
西堂 うん。
くるみざわ 大学4年になる春(1987年)に、工場見学で関東への一泊旅行があって、就職先を探すために企業に行くんですけど、その行き先が、東芝、日立。つまり原発メーカーだったんですよ。笑うでしょ(笑)。血の気が引きました。どうしても嫌だったんですよ。人の体や生活を破壊するようなものを作る仕事につくのは。で、原発を作っているからもしかすると日本の製造業は軍事産業もやってるかなあと思ってね、調べてしまったんです。そしたら潜水艦とか戦闘機とか作ってるわけ。僕は家が農家だったんですけど、これから農業じゃなくて工学を学んだほうが良いと思って大学入ったんです。だけど、このまま就職したら作りたくないものを作らなくちゃいけなくなる。そう思って、やめたんです、工学部で就職するのをね。それで、もう1回何がやりたいかなって考えたときに、機械じゃなくて人間ととことん付き合える仕事をやってみたい。特に僕は人の心に関心があったから、そして人の心の明るい面じゃなくてどっちかというと暗い面、闇を知りたい。そこに入っていって仕事として成り立ち、かつ学問としても成り立っていて、資格職であること。資格がないと使われるだけで、1人で自分の思うように立ち向かえないからね。自由がない。こういう条件を満たす仕事は精神科医だなと思った。それが22歳ぐらいの時で、工学部をあきらめて、医学部に入りなおしたという次第です。
西堂 医学部でも、外科だとか、もっと人を救えるものもあるんだけど、そっちの方にはいかなかった?
くるみざわ 行かなかった。やっぱり人の心に関心があったんですよ。
西堂 心の問題。
くるみざわ うん、心。小説とか好きだったし。
西堂 でも、ある意味で芸術学科に来る学生の動機と似てますね。
くるみざわ 似てますかね?
西堂 似てると思う。少なくとも工学部に行くメンタリティとは対極でしょ。工学系と一番対極にあるものを選びたいって言って芸術学科に来る学生もいるんですよ。
くるみざわ ああ、なるほどね。僕は自分の将来をちゃんと考えるのが遅かったんですよね。いよいよ切羽詰まってからだったんです。しかもあそこでチェルノブイリ原発事故がなかったら気が付かなかったのかもしれないなあ、と思って。
西堂 やっぱり1986年というのは、世界的な意味での大きな転換期でもありましたね。あの後にベルリンの壁崩壊だとか、いろいろ歴史も大きく変わるわけで。
■精神科医と劇作家
西堂 そこで精神科医と劇作家を両立させるというか......。両立という感じなんですか? むしろ 精神科医を劇作に活かしているのか。そこらへんの因果関係ってどういうふうに考えているんですか?
くるみざわ 僕は、精神科医も劇作家も同じ仕事だと思ってるんです。
西堂 イコール?
くるみざわ イコールです。「二足の草鞋を履かれているんですね」とよく言われるんですけど、そういう時には、「一足の草鞋で両方やってます」って答えるようにしています。どこがどう一足かっていうと、精神科の診察室にやってくるような方々は、困っていて不自由で遊びがない。遊べなくなってるんですよ。遊べないというのはつまり、楽しめない。こうしなくちゃいけないという思い込みとか、自分はこうだ、こうなってしまったらダメだとかいう決めつけに縛られて、余裕がなく、きつきつの中にいる。緊張していて、話題が自由にあっちに行ったりこっちに行ったり、あんまりしないんですよ。やっぱり、硬く固まっているわけ。遊びがない。Playできなくなってる。
「Play」っていうのは日本語に訳すと「遊び」ですよね。スポーツとか楽器の演奏もPlayですよね。演劇もPlay。あるルールの下で自由に動き回ることができる。それが人間の健康な営みにとって大事だと思うんですけど、精神科の診察室に来る方ってそれができなくなってる、いろいろな事情でね。だからそのPlayできなくなってる人と診察室でお会いして、話しを聞いたり質問したり答えたり、気持ちにはたらきかけたり、よくやってますねって励ましたり、こういう理由があったんですねって受け止めて、その人にない視点を提供したりすることで、ちょっとずつゆとりが生まれてほぐれて、遊べるようになっていくんです。自分はこんなふうに思ってましたとかこんな気持ちでしたということを語れるようになっていく。こういうふうにしたら病気が良くなっていくような気がしますというアイデアが出たりとか。そういう状態に患者さんが変わっていくのをアシストするのが診察なんです。
だからPlayをつくっているわけ。診察で、Playできない人と一緒になってPlayをつくるということが精神科の仕事なんですよ。で、劇作家の仕事はどういうものかというと、もう忘れ去られて、誰もそれについて思い出さなくなっている題材とか、あるいは議論が白熱していて、対立もすごくて、にっちもさっちもいかなくなってるような題材を取り上げて、新しい言葉で視点や広がりを生みだす。言葉がないわけですよ。空間もない。それはいったい何なのかとか、どういうところがぶつかり合って動けないのか、行き詰って固まってるのかに触れる言葉がないし、やり取りが生まれる時間や空間の広がりがない。そういうところにくさびを打って、登場人物を置いて動かし、言葉を見つけて脚本にしてゆく。舞台に上げて、みんなが見て楽しめるようにする。考えられなかったことを考えられるようになるとか、この視点でしか見られなかったものが別の視点で見られるようになるとか、そういうことが僕は劇作だと思ってるんです。だから劇作と精神科の診察はイコールで、僕がやってることは両方とも同じだと思っているんです。
エイチエムピー・シアターカンパニー「ハムレット 例外と禁忌」
作=くるみざわしん
演出=笠井友仁
2023年11月3日(金・祝)~5日(日)/扇町ミュージアムキューブ CUBE01
撮影=中谷利明