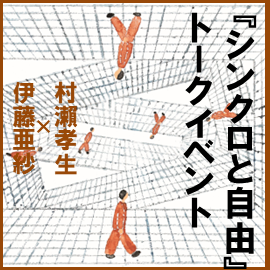かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

涙の出方が変。【前編】
2022.12.15 update.
村瀨孝生(むらせ・たかお)
特別養護老人ホーム「よりあいの森」、「宅老所よりあい」、「第2宅老所よりあい」の統括所長。東北福祉大学卒業後、出身地である福岡県飯塚市の特別養護老人ホームに生活指導員として8年勤務。その後福岡市で「宅老所よりあい」にボランティアとしてかかわり、現職。著著に『ぼけてもいいよ』(西日本新聞社)、『増補新版 おばあちゃんが、ぼけた。』(よりみちパン!セ、新曜社)など。
繁延あづさ(しげのぶ・あづさ)
写真家。桑沢デザイン研究所卒。雑誌や広告の撮影をおこなう傍ら、ライフワークとして出産・狩猟などを撮る。著書に『うまれるものがたり』(マイナビ出版)、『山と獣と肉と皮』(亜紀書房)、『ニワトリと卵と、息子の思春期』(婦人之友社)など。連載は、長崎新聞でフォトエッセイ、『母の友』(福音館書店)の「こどものひろば」写真担当など。亜紀書房ウェブマガジン「あき地」(https://www.akishobo.com/akichi/)にて「鶏まみれ」の連載がスタート。
白石正明(しらいし・まさあき)
医学書院看護出版部。シリーズ「ケアをひらく」担当編集。
『シンクロと自由』刊行記念
この記事は、2021年10月16日、長崎市の「すみれ舎」(障害福祉サービス生活介護事業所)で行われたトークイベントの内容を加筆修正のうえ再構成したものです。当該イベントの内容はこちらで見ることができます。
当日司会をしてくださった編集者/ライターのはしもとゆうきさん、動画を作成していただいた山田聖也さん、会場を快く貸してくださった「すみれ舎」の山下大介さん、そしてご参加いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。
*本文中の写真は繁延さん撮影による「すみれ舎」の日常です(ⒸA.shigenobu)。
【目次】
前編【このページです】
Ⅰ 死ぬまで生きる
Ⅱ 記憶と作話と、複数の自分
後編【明日更新です】
Ⅲ 母の介護は何の修行か
Ⅳ 事前の思想(コントロール)から、事後の思想(付き合う)へ
Ⅴ 質問コーナー
Ⅰ 死ぬまで生きる
繁延 長崎在住の繁延あづさと申します。写真をやっています。『山と獣と肉と皮』(亜紀書房)という本を一昨年に出して、去年『ニワトリと卵と、息子の思春期』(婦人之友社)を出しました。
村瀨 こんにちは。「宅老所よりあい」というのが福岡市にありまして、お年寄り、特に認知症、ぼけのあるお年寄りが通って泊まって、いざとなったら住めるというところで30年前に始まりました。その「宅老所よりあい」と、「第2宅老所よりあい」の2か所と、2015年に26名定員の小さな特別養護老人ホーム「よりあいの森」を運営しています。その3つの「よりあい」を統括する形で代表を務めている村瀨と申します。
白石 医学書院で「ケアをひらく」というシリーズをやっている白石です。8月に出た村瀨さんの『シンクロと自由』がシリーズ最新刊です。
◆生体に興奮する二人
白石 この本が出来上がるころ村瀬さんに「繁延さんと対談しませんか」と言ったんです。そのとき「繁延さんと村瀨さんは、きょうだいみたいにそっくりなんですよ」みたいなことをメールに書いたらしいんです。あまり覚えていないんですが(笑)。一方は介護の現場の人だし、一方は写真家であって直接は関係ないんだけど、でも、たしかに似てるんですよね。
繁延さんの『山と獣と肉と皮』は、狩猟に行って、動物が死ぬ瞬間から始まります。そのときに繁延さんがものすごく興奮してるんです。なんていうかな、生体そのものに興奮してる感じがものすごく鮮烈だったんですね。村瀨さんも『シンクロと自由』で、老人が死ぬ間際って体が活発に動いてると書きながら、なんか興奮してる。その二人の興奮度合いが似てるんじゃないかなと思いました。ケアって「いい話」のようにみんな思うんだけども、この「興奮」というのがケアにとってすごく重要な気がするんですね。
今回のトークのタイトル「涙の出方が変。」は、繁延さんの本を読んで村瀨さんが漏らされた感想をそのまま使っているんですが、繁延さんは『シンクロと自由』を読んでどう思われましたか。
繁延 とにかくすごかった。夢中で読んで、Twitterに「すごい本を読んだ」ってそのままの感想を書いたんです。白石さんから「トークをしませんか」って言っていただいて、何に自分が反応したかを分かりたいなと思ってます。
いちばん大きかったのは「人が老いて死んでいく風景が描かれている」ところですね。私は10年ちょっと出産の撮影もしてるんですけど、なぜ人が生まれてくるところを自分は撮っていたのかは深く考えてなかった。でもこの本を読んで、自分を発見したような気持ちになりました。
じつは私は、資格を取って介護をやってみたことがあるんです。こんな言い方をするとひどい人だと思われそうですが、人はどんなふうに老いていくのか、そこにある可能性を知りたかった。でも結局見れないまま辞めてしまったんですけれども、私が見たかったものは、村瀨さんの本にたくさん書かれていたんですね。それが私のなかでいちばん大きな興奮でした(笑)。生まれる風景を見たい気持ちと、老いて死んでいく風景を見たい気持ちは通じていたことに気づきました。
さっき白石さんが言ってくださったように、私はたしかに獣が死んでいくときの「かわいそうだな」とか、見ていて苦しいような気持ちの一方で、死んだ後に解体が始まると、特に同じ哺乳類だったりすると、「こんなふうにできてるんだ」という生き物の成り立ち方に魅了されていたなと思います。
でもそれは村瀨さんの本にもあったような気がしたんですよ、解体はされないですけど(笑)。死んでいく人の体を触ったりして。
村瀨 介護って最終的に、体を触ることに集約されていくんですね。どんどん「できなくなっていく体」に、こっちの「まだできる体」をシンクロさせる。見えなくなった目や耳に代わって見聞きをしたり、できなくなった手に代わって何かをしたり。こっちの体と向こうの体をシンクロさせて補完するような形で、二人で生活を成り立たせていく。体と体が本当に密着していくわけです。
そうやって接していくうちに、どうしたら寿命って分かるんだろうと思うようになりました。この体が自然の摂理に導かれて死んでいく、という寿命ですね。やっぱり触り続けた人間が手の感触によって知るしかないんですよね。「もうこれが寿命なんだな」と了解するために触り続けるんです。
◆「隠される死」と「にぎやかな死」
繁延 村瀨さんが、寿命を迎えお年寄りが死んでいくのに触れたのは若いときですか?
村瀨 ぼくは最初、100人が暮らしてる特養ホームに勤めていたんです。23歳から31歳まで。そのときはお年寄りは施設で死ねなかったんですよ。寿命だろうがなんだろうが関係ない、とにかく病院に運ぶというのが看護師さんの仕事でした。当時は生活指導員って言ってましたけど、ぼくはそこに付き添う。寿命とか関係ないんですよね。「施設じゃもう対応できないから」みたいな感じで運ばれていく。施設でみることができるのは、急に心肺停止しちゃったとか、突然亡くなった人だけです。
繁延 「死をここで迎えちゃいけない」という空気があるんですか。
村瀨 それがねぇ......何なんでしょうね。
繁延 なんかボールを渡すような感じに聞こえました。
村瀨 いや、本当にそういう現実でしたね。ぼくが最初に勤めた特養は福岡県下でも3番目ぐらいにできた古いところなんです。病院の霊安室って、誰の目にもつかない地下にあったりするじゃないですか。だけどその特養には、食堂の横に霊安室があったんですよ。仏壇があって畳の間になっていて。
繁延 リビングみたいな感じ?
村瀨 そう、リビングですよ。お年寄りがご飯を食べる普通の食堂の、その横に一緒にあった。だから看取って亡くなって、自然にそこに横になってた時代があったはずなんですよ。でもぼくが就職したときにはもう、とにかく死は伏せるものだった。でも隠しきれないですよ、お年寄りはみんな知ってるから。「あの人、死んだっちゃろ~」とか言って。
繁延 村瀨さんは今は「この人は寿命で死んだな」と分かるようになった。でもその話のころはまだ隠されていた。その間はどうつながるのでしょう?
村瀨 31歳ぐらいのとき「宅老所よりあい」に勤めたんですね。「よりあい」は大場ノブヲさんっていうたった一人のおばあちゃんからスタートしたんですが、このおばあちゃんが亡くなったんです。じつはその同じ日に、ぼくの祖母が亡くなったんですよ。
その日ぼくはたまたま仕事が休みで祖母の面会に行ったら、処置が始まっていて、同居してる叔父が来るまで延命されている。病院も一生懸命だと思うんですけど、何の説明もなく病室から出されちゃうわけですよね。廊下でずっと看護師さんの出入りとか、叔父とかが集結するのを見て、はじめて「祖母が亡くなろうとしてるんだな」っていうのが分かる感じです。息を引き取る瞬間に、ぼくは本当は運よく立ち会えたはずだったんですが......。
繁延 廊下に出されちゃった。
村瀨 はい。で、その夜に呼び出しがあったんですよ、「大場さん、亡くなるから」って。今日は祖母が亡くなったんだけどなぁと思いながら、大場さんが亡くなるところに立ち合うことになったんです。
「よりあい」というのは、(会場を見回して)こういう築100年くらいの民家なんですね。こういう空間のなかに大場さんが寝てて、末期の水とかありますよね、あれもビールで浸されてて。「ビール好きだったんもんねぇ」とか言って(笑)。
そのとき地震があって揺れたんです。みんなが「これ、大場さんが呼び出されてるんだよ」って。「そんな人やった」とか。話されてることはほとんど悪口なんですよね、「もう大変なばあさんだった」みたいな。でも悪口が悪口ではないんですよ。みんな勲章のように話してる。そこに自分がつきあったんだ! みたいな感じ。
その時間と、祖母の亡くなり方があまりにも違っていた。人の死に方に良い悪いなんて、ぼくはまったくないと思うんですよ、野垂れ死のうがどんな亡くなり方をしようが。でもやっぱり亡くなり方があまりに違うなって。
その後も「よりあい」に関わってる人たちがどんどん亡くなっていくんだけど、寿命を迎えて亡くなるのであれば、病院に連れていくんじゃなくてこのまま見守ろうと。そんな実践が「よりあい」では始まってました。そこにぼくは最初から関わることができたわけです。
◆死にゆく体は絶好調!
村瀨 寿命かどうかっていうのは、日本社会ではどうしてもリビングウィル的になっちゃう。本人の意思で死を選択するっていう。「意思を書き残してもらったら、それに則ってやればいいのね」みたいな流れがある。でも、ぼくは全然それは了解できないです。それよりも体で触る。脈は電子計だと最終的には拾えないでエラーになるんですよ。それでもとにかく動く脈を探して、それが速いとか遅いとか、強いとか弱いとか、体だったら温かいとか冷たいとか、体のなかでも足先は氷のように冷たいのにちょっとここは汗ばんでるだったりとか。そうやって触ることで、人間の体が躍動してるっていうのが分かってくるんですね。やがてこの体が死んでいくんだなっていうのを感じ取れるようになる。
繁延 『シンクロと自由』のなかに、死にゆく人の体は絶好調だっていうのがありますよね。
村瀨 そうなんです。ぼくには絶好調に感じられる。人が飲み食べしなくて亡くなるまでに、「よりあい」では最高17日なんです。
繁延 17日......。
村瀨 はい、17日間、飲み食べしないで生きられるかっていうと......もしかしたら会場のみなさんは死んじゃうんじゃないかな(笑)。限られた自分のなかにあるエネルギーを、体が連携し合って、分け合って、循環して、燃やし尽くして亡くなっていくんですよ。もう体史上、最高の連携があって、「オレたちいま、最高だよね!」って。「連携し合ってるよね!」って。そんな声が聞こえてくるんですよ。
繁延 脳は置いてきぼりって感じですかね。
村瀨 脳も肉体の一部ですよね。勝手に観念化されたり、精神のなかで脳だけが体のなかで特別扱いされていた。でもそれがやっと、なんていうんですか、脳はホッとしてるんじゃないですかね。やっと体の一部に戻って、何も考えずに、"全からだ"の求めに応じて「なんか俺、やることある?」みたいな状態になってる気がするんですよ。
繁延 おもしろいですねぇ。私はそこを読んだときに、人はこうやって死んでいくんだって思いました。
あと、これはあまり喜ばれない話かもしれないんですけど、ウチはよくニワトリも含めて解体をして食べるんですが、それとすごく似てるというか、「やっぱりそうだったかぁ」と思った箇所でもあります。肉の部分はある程度時間が経ったらパサパサになってきて月齢を感じる肉になっていきますが、心臓とか肝臓とかはわりと――山の獣でもニワトリでも――特に固くなることもなく、味わいもほぼ同じなんですよ。最後までの現役感っていうのがある。だから、読みながら「やっぱそうだったか!」と。
白石 筋肉は衰えるけど、内臓は最後まで現役!
繁延 食べる側からすると、(太腿あたりを指して)ここは古くなるとダシになっちゃうんですけど、心臓とかは最後までおいしく焼き鳥で食べられる。
白石 なるほど......。やっぱりお二人は、きょうだいみたいですね。ぼくの感覚は正しかった(笑)。
村瀨 人が年を取って最後に「亡くなる」という印象が、観念的にはあると思うんです。でも実際にお年寄りを見ていると、体というもの、生体というものが、最後まで「生き切る」のを感じるんですね。『山と獣と肉と皮』に出てくるイノシシも、最後まで生きてるっていうんですかね、手首が取れても、そのまま逃げられるはずなのに、もう一回Uターンして猟師さんに突っかかってくる。
繁延 ただ生きてる、って感じがすごくあるんですよね。「死なないように生きてる」じゃなくて。
村瀨 イノシシもそうだけど、人間も本当は生き物である以上は、死そのものの概念なんてないんだろうなって。
白石 生と死を反対物として捉えて、「生から死へ移行する」みたいに考えるけれど、本当は生しかないってことですよね。最後に生がなくなって、まわりの人はそれを"死"という言い方をするだけで。
村瀨 そうですね。そのイノシシも最後まで生きた、お年寄りも寿命を迎えて最後まで生きたんだっていう。その最後まで生きたところに立ち合った者には、何かが生じちゃうんです。なんて言っていいか言葉がむずかしいけど。
繁延 それはある。今までも生き物を食べてきたはずなんですけど、山へ行くようになったらやっぱり、自分の生きている感覚が変わってきたんですよね。何が変わったのかっていうのはちょっと言いづらいんですけど。
村瀨 そこは似てるかもしれないですね。だいぶ看取りに立ち合ってる就職して4年目になった20代の若い職員に、「看取りってどう?」って最近聞いたんですよ。死って怖いというイメージが最初はあったらしいんだけど、「今は死が怖いっていうものではなくなりました」みたいな感想が聞けるので。人が亡くなっていくところに立ち合うと、その人のなかで何かが変わってるんです。
Ⅱ 記憶と作話と、複数の自分
◆え、なんでここで涙が?
白石 お二人とも死を迎える生体のエネルギーに圧倒されて、「参りました」っていう感じがあるじゃないですか。その一方で、冒頭に言ったように興奮もあるように感じます。「涙の出方が変だった」というのは、そのあたりのことをおっしゃっているのでしょうか。
村瀨 ......説明できないから「変」なんですよ。
繁延 説明が聞けると期待してました、今日(笑)。
白石 涙が耳から出るとかじゃなく?(笑)
村瀨 なんていうんですかね......。ふつう映画を観たり本を読んだときの涙って「何かのフレーズでグッと来て」みたいな出方なんです。でも繁延さんの本は2冊ともそうだけど、「えっ、ここで出る?」みたいな涙の出方。じゃ、そのフレーズがどこですかって言われても、別にどこでもよかったのかもしれない。ずっと読んでるあいだに、無意識のなかに何かが蓄積されて、ふとしたときにポロッと出るんですよ。
白石 「そこで感動したんですね」って言われると、「いや、そこじゃないんだけど」って言いたくなるような?
村瀨 そうなんです。「この本のどこですか?」って聞かれて、「ここですね」と言えないんですよね。
白石 なるほど。でも、そう言う村瀨さんの本も意外に引用しにくいんですよ。「ここはどうだ!」と思って人に言っても、意外に普通のことを言ってる感じがあって。あの感動は何だったんだろうかって(笑)。まず文脈があって、その文脈に乗っていってこその最後の一言なんですよね。
繁延 村瀨さんの語りにやられたなって感じなんですね。
白石 そう、そうなんです。
繁延 一つひとつに、強烈な言葉が入ってるわけじゃないんですけど、順を追って語りを聞いていくと、じわっとくる。
白石 だから書評を書くのは大変じゃないですか。
繁延 長崎新聞で『シンクロと自由』を紹介したときに、すでに何人かの方が書評で取り上げている部分を私も使ってしまいました。100歳のおばあちゃんと2歳のお子さんが一人の人のなかで......。
村瀨 夜中にね、100歳のおばあちゃんが「おかあさん、おかあさん」って呼ぶんです。すると職員が、おかあさんのように登場する(笑)。
じつはこれ、どの職員もその経験をするんですね。ぼくのようなオッサンでも「あぁ、おかあさん」って言ってくれるんですよ。呼ばれるたびに「ふみちゃん」とか言って行くんだけど、3回目までは「おかあさん」って言ってくれたのに、4回目は「おじさん」って(笑)。たぶん途中でおじさんであることを認識されたんですね。
本の話に戻りますが、大学を卒業してすぐ働いた22歳の子が、そうやって対応したときに「あぁ、おかあさん来てくれた」っていってグ~って抱きしめてくれた。そして耳元で「おかあさん、入れ歯がないの」って(笑)。タイムスリップの仕方がとてつもない。
◆記憶と作話のふしぎな関係
繁延 人の記憶ってどういうものなのか、最後はどうなっていくのかなぁっていうのにすごく興味があります。私はよく「今しかないんじゃないか」という不安にかられるんですよね。過去って見えないし、もう今は消えつつあるし、そうやって考えると未来もない。結局、この今しかない。これは私が写真を撮ってることにも関係しているかもしれないです。
福岡伸一さんの本にもチラッと書いてあったんですけど、思い出というのはフォルダとかアーカイブみたいなものに入っているんじゃないらしいですね。脳に同じように電流が流れたときに記憶がよみがえる。そうだとしたら実態があまりになさすぎると思う。
以前介護の仕事をしていたときに、ぼんやりしたおばあちゃんがいらしたんですね。私はその方とお留守番をしていて、いつもぼんやりされてるから、その人のことをどんな人だったか知りたくて、私は手掛かりが欲しいわけです。いろいろやるんだけど、全然反応がない。
二人きりの留守番だから、あるとき、恥ずかしさもなく歌をうたってみることに。私が「ぞ~うさん、ぞ~うさん♪」って歌ったら、そのあとを合唱コンクールみたいな感じで歌い出したんですよ。そのとき初めて「この人を見た!」みたいな感じがしました。さっき食べたものも分からないけれども、じつはこうした記憶を最後まで握りしめてるような感じがするんですよ。もしかしたら、ご自身がお子さんのときにタイムスリップしたのかもしれないし、あるいは子育て中に自分が歌ったほうなのかもしれない。
その同じ方なんですけど、だんだん誤嚥がひどくなってきたときに、スプーンの向きと本人の感覚が合ってないんだろうなと思って、私が後ろに回って二人羽織みたいにしてみたんです。体の記憶を思い出すんじゃないかと思ってやって。すると本当に誤嚥が減ったんですよ。
村瀨 記憶って変ですよね。なんかよく分からないなぁって思うんです。都合よく改ざんされてもいくと思うし。
繁延 さっき打合せのときに聞いた作話の話が、すごく面白かった。
村瀨 ああ......作話っていうのは、ほとんど記憶に基づいてないと思うんですよ。むしろ今この瞬間に即興的に立ち上がってくるものだから。
すごいお年寄り見たことがあって。バザーが終わったあとに、ボランティアさんのお宅で打ち上げをしたんですよ。そのお宅は無垢材がたくさん使ってあって、木の香りがするような家です。伝統的な日本家屋の建築とは違って、天井がなかったり、骨組みが見えていたり。「おしゃれで、だけど木の香りがする」っていう感じですね。
そこで、ちょっとぼけのあるおじいさんにバザーの打ち上げの挨拶をしてもらったんですよ。最初はちゃんとバザーの打ち上げという認識があって、「バザーもみなさんのおかげで」とか挨拶が始まった。でもだんだん話しているうちに、それが新築祝いになっていって(笑)。「もうちょっとで完成します。そのときはもう一度みんなで集まって......」みたいな話に変わっていくんですよね。
◆状況をつなぎ止めるための知性の振る舞い、それが作話
繁延 それにもやっぱり経験が含まれてますよね。
村瀨 そうそう。そこにはやっぱり自分の経験があって。場所の記憶でしょうね。
繁延 経験と経験をつなぎ合わせて......。
村瀨 時と場に応じた対応をしようと思って、本人は必死なんですよ。
白石 脳内がのすごく活発に動いて、この状況をなんとか説明しようと必死に考えている。ということは、ものすごく頭を使ってるわけですよね。
村瀨 そうなんですよ。
白石 それを「作話」って言ってしまうのはちょっと失礼というか。こちら側はボ~っとしているのに。
村瀨 ぼくらのほうは、この時と場を不動のもの、揺るぎないものと勝手に規定していて、じつはぼけのあるお年寄りのほうが「この時と場でいいのか?」みたいに推測している。こっちの顔色とか振る舞いとかで、「どうも自分の感じてる時と場と、なんか違うんじゃないかな」って感じてくると、こっちの時と場に合わせようとする。つまり、お年寄りがいま感じてる時と場と、ぼくらが共通概念的に捉えている時と場が全然違うんですが、つなぎ止めようとしてるのはお年寄りの側なんですよ。それをぼくらは「作話」って呼んで、「だいぶおかしくなってきたね」なんて言ってる。
繁延 そのお年寄りのほうがこの世界を分かろうとしているのに。
村瀨 「いま、この瞬間が何なのか」ということに、いちばん向き合ってるんですよね。
白石 この不可解な状況を説明しようとして、ものすごいトライをしている。
村瀨 トライしているからこそ途中から新築祝いになってきて、「この家が完成の暁には......」と始まってくると、みんながクスクスクスクスって(笑)。
繁延 笑いが止まらない。
村瀨 みなさんもお分かりだと思うんですけど、それは決してバカにしてるのではまったくない。「スゲェな、じいさん」っていうふうに思えてくる。だから時と場、記憶っていうのは不思議なんですよ。我々は観念的に固定化してそれを自分自身に命令しているけれど、その規定が外れたときの知性の振る舞いっていうんですかね。今の時と場を捉えるために、記憶から何から縦横無尽に活用しているんですよね。
繁延 いやぁ、おもしろい。記憶というのは最後になるとどんどん減ってくって感じがしますが、村瀨さんはどう思われますか?
村瀨 さっきの100歳のおばあちゃんが2歳になったりするっていうのは、記憶ということよりも、「自分のなかにある2歳が生きてる」ってことのような気がするんですね。......ぼくはいま母の介護してますけど、母の振る舞いに、ある時点でどうしてもキレちゃうんです。
繁延 どんなときですか、それ。
村瀨 母はせっかちの心配症。だからすごく疑り深いんです。「どうなの?」「大丈夫なの?」みたいのがいつもあって、それにせっかちが加わると......分かりますよね。せき立てられながら、ず~っと疑われてるみたいな。これはね、58歳になって初めて「そういう母に育てられたんだな」というのが了解されたんです。そのせっかちの心配症が母から立ち上がってきたときに、ぼくはキレるんですよ。
白石 それ、いい話ですねぇ。
繁延 いい話っていう、白石さんも不思議です(笑)。
村瀨 58歳のぼくがキレてる感じじゃないんですよ。13歳の、たぶん思春期あたりのぼくと、それこそ2歳ごろのイヤイヤ期のぼくが同時にキレてる。自分のなかで生きている2歳とか13歳が、「イヤ~っ!」って言ってる。それは記憶じゃない感じがするんですよ。
白石 昔を思い出してどうこうじゃなくて、自分のなかにいる2歳なり13歳なりが勝手に暴れてる。それはもう制御できないんですね。
村瀨 そう、制御できないんですよ。58歳のぼくが分析してるという部分もあるけれど、抑えることはできない。過去を思い出して「あぁはぁはぁ、なるほど」となって「よし、怒るぞ!」ではないんです。もう13歳が制御不能に立ち上がってきている。それを「記憶」と呼ぶのか、「13歳がいまだにまだ生きている」と言うのか。
繁延 なんか分かる気がする。私は『ニワトリと卵と、息子の思春期』で、「子どもを産むたびに母が生じる」みたいな言い方をしています。「その子の母」が、自分のなかに勝手に生じてしまう。そうすると、もう自分の意思とは関係ない。たとえば、その子がいま何をしてるかをず~っとアンテナがキャッチしようとしてしまうから、家で仕事をしていても全然集中できない。自分でそうしようとしてるんじゃなくて、そういう自分になってしまっている。
その本のなかで「母殺し」という書き方をしたんです。何かが殺されるようなことがないと「母」を手放せないんですね。生じてしまってるものに対する「どうしようもなさ」みたいなのがある。だから村瀨さんの「どうしようもない」っていうのも、ちょっと分かる気がする。
村瀨 ぼくもこの本のなかに母殺しというフレーズが出たときに、本当に「ぼくもいま母殺しをしている」って(笑)。
繁延 村瀨さんのなかの母、みたいなことですか?
村瀨 そこが分からない。ウチの母はマスヨっていう名前なんですけど、マスヨという一人の人間としての性分なのか、繁延さんが書かれているように、立ち上がってくる「母」のせいなのか。そういう意味では、母もその「母」に支配されてるし、せっかちで心配性という母の性格もあるのかもしれないですけど......。
繁延 せっかちも心配性も、人を守ろうとする動きですもんね。
村瀨 そうなんですよ。だからぼくが向き合ってるのは、マスヨという一人の人間なのか、「母」的なものなのかっていう部分は不可分なのかもしれない。もしかしたら「母」的なものに対して母殺しをしてる......58歳になってですよ(笑)。でも13歳が生きてるもんで。
白石 じゃ、いま喋ってるのは13歳の村瀨さんであって......。
村瀨 そうそう。13歳のぼくが、58歳のぼくの力を借りて初めて弁明している可能性がある。
白石 なるほど、弁明!
村瀨 というふうに、自分のなかでは感じている。
(前編了)
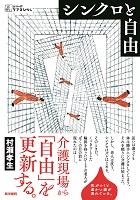
介護現場から「自由」を更新する!
「こんな老人ホームなら入りたい!」と熱い反響を呼んだNHK番組「よりあいの森 老いに沿う」。その施設長が綴る、自由と不自由の織りなす不思議な物語。万策尽きて、途方に暮れているのに、希望が勝手にやってくる。誰も介護はされたくないし、誰も介護はしたくないのに、笑いがにじみ出てくる。しなやかなエピソードに浸っているだけなのに、気づくと温かい涙が流れている。