かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
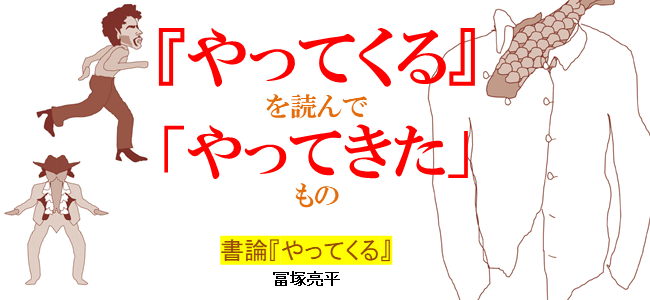
ダサカッコワルイの極の映画を頼りに、異形の書を読み解く!
2021.10.28 update.

東京都生まれ。米文学/文化。慶應義塾大学大学院文学研究科後期博士課程修了。博士(文学)。慶應義塾大学ほか非常勤講師。
博士論文The Moment of Transition: Plasticity in Ralph Waldo Emersonʼs Writingsが公開中。近年の主な論文・論考に「「客間」と「書斎」―─ 空間表象に見るエマソンの家政学」(『アメリカ研究』54号)、「恩寵を見ること─―ジョナサン・デミ『愛されし者』Beloved における「再記憶」との遭遇」(『ユリイカ』51巻17号)など。
『ユリイカ』『キネマ旬報』『図書新聞』『新潮』『ジャーロ』などに寄稿。
(『精神看護』2021年9月号より転載)
デイヴィッド・リンチが監督した映画『マルホランド・ドライブ』(2001年)の序盤には、その後展開する物語とはほとんど無関係な、ある印象深い場面が登場する。ハリウッドのサンセット大通りに位置するチェーン店のダイナー、ウィンキーズ。ただならぬ表情を浮かべたダンは、他の店舗ではなく「この」ウィンキーズに来たかったのだという。彼は、「この」 店の裏で謎の男を壁越しに目撃する夢を見て感じたという恐怖について語る。そして、その恐怖をぬぐい去るために、同行者を夢で見た場所 へと連れて行く。するとそこには、実際に毛むくじゃらの謎の男がおり、ショックを受けたダンは気絶してしまう。
また、ドナルド・バーセルミの小説『雪白姫』(白水社、原書1967年)にも、物語の本筋からは逸れる次のようなジェインと母の会話が現れる。「あの猿みたいな手は何かしら、ほら、わたしの郵便受けのなかへ伸ばしてきてるでしょ?」「何でもないわ。気にしなくていいの。何でもないったら。〔……〕猿なら猿でいいじゃない。変哲もない猿よ。もう気にすることないったら。それだけのことじゃない」「あなたって、こういうことをいとも簡単にうっちゃってしまうのね、ジェイン。それ以上の意味があるにちがいありません。あれは異常です。何か意味があるんです」「そんなことないったら、お母さん。それ以上の意味はないんです。わたしのいった意味以上は」
ダイナーの裏に潜む「毛むくじゃらの男」。あるいは、郵便受けに出現した「あの猿みたいな手」。本書『やってくる』の第1章で紹介される、オペラのような美声で「ムールラー」と歌う男性の声をめぐる幻聴のエピソードを読み直していた時、不意に私の脳裏によぎったのが、幻覚をめぐるこの2つのシーンだった。かつて10 年以上前に関心を抱いていたものの、その後全く思い出すことすらなかったこれらのイメージが、突如として「やってきた」のだ。この2つの例はそれぞれ、本書の言葉でいえば、ダンとジェインの母にとって「知覚できないものに対する圧倒的な恐怖」を喚起したと考えられる。
「前縁の神」と「境界の神」
郡司は第7章で、そうした人間の理解を超えた対象を、「原始的な神」あるいは「前縁(フロンティア)の神」と呼んでいる。彼によれば、「こちら側とあちら側の両方を知っていて、その間に引かれる線を意味する」境界(バウンダリー)に対して、前縁は「こちら側しかわからない」限界を指すとされる。前縁は、「地平線や水平線のように」、「その向こう側は 存在するかどうかさえ確信できない」ものであり、だから認識や思考の限界は前縁であるのだという。この区分をもとに彼は、「原始的な神がどのように形成されてくるかを想像する」ことで、「窺い知れない外部に対する圧倒的な恐怖が、どのように捉えられ、出現してくるのか」を考えようとする。
「原始的な神は、こちら側とあちら側が断絶しながら接続しているからこそ、 生まれ得る」。この、前縁の向こう側に形成される「知覚できなくとも存在する」神である「前縁の神」は、人間に無関心で、人間と無関係にやってくる不条理なものであり、その意味で「向こう側として感じられる死」と一致するものとされる。それに対して、「恐怖の対象」であり「畏怖すべきもの」でもある「前縁の神」に、安心感や安堵感を持ち込む」方法として郡司があげているのが、「境界の導入」である。
改めて思い返せば、その頃の私は最初に紹介した2つの場面を比較することで、「前縁の 神」がもたらす恐怖といかに向き合うかについて考えていたのだろう。リンチ映画のダンのように恐怖に押しつぶされないためには、バーセルミがそうしたように、「やってくる」対象にどうしても意味を見出してしまう人間のあり方を俯瞰して笑い飛ばすしかない。
当時の私が至ったこの暫定的な結論は、本書の言葉で言い換えれば、「知覚できない向こう側」である「前縁の神」を「目に見える向こう」である「境界の神」へと置き換える、物象化の作用をめぐるものであったように思われる。「猿なら猿でいいじゃない」として知覚できないものを受け入れようとするバーセルミのユーモアが、例えば『幻聴妄想かるた』(医学書院、2011年)などを思わせる形で「やってく る」異物を物象化することで、「猿みたいな手」は不条理な恐ろしいものではなくなる。しかし、郡司も強調する通り「原理的に前縁の神でしかないわたしの死は境界の神に置き換えることで理解されることはない」。その時の自分には、「毛むくじゃらな男」や「猿みたいな手」をそのまま受け入れ、理解する方法はわからなかった。つまり、決して経験できない「わたしの死」と結びついた恐怖の対象は、決して消えることはなかったのだ。
ダサカッコワルイの極、『レディ・イン・ザ・ウォーター』
バーセルミをめぐる卒業論文を書き終えたものの、前年に就職活動を全くしていなかったことから留年生となった私は、春に就職先を決めると、釈然としない思いをかかえたまま、その後1年近く大学にもバイトにもあまり行かず「考え、やきもきして、焦って、諦めて、ぼんやりして」いた。もしかすると、この時期に私のなかでも「無意識のうちに、認識することと感じられることの間は違和感を帯び、通常当たり前のように感じられるリアリティは失われ、何かを呼び寄せる準備だけが着々と整えられていた」のかもしれない。自らに「ムールラー」が聞こえた理由をこのように振り返る郡司は、その経験を幽霊やUFOを見る経験と並べて、「外部を呼び込んだ」事例として解釈しているが、偶然にも、その頃の私に 外部から「やってきた」のもまた、幽霊や宇宙人を見てしまった人物を描いた映画作品であった。
幽霊をめぐる『シックス・センス』(1999年)や、宇宙人とある家族の闘いを描いた『サイン』(2002年)で若くして成功を収めた M・ナイト・シャマラン監督の映画は、いずれも「やってくる」サイン=兆候を受け入れることで、喪失をかかえた主人公が再び何かを信じる力を取り戻す物語を描いていた。なかでも、本書終盤の記述を読んで私がすぐに想起したのが、『レディ・イ ン・ ザ・ウォーター』(2006年)だ。おそらく、批評家にも観客にも酷評されたこの作品こそ、「前縁の神」と「境界の神」をめぐるジレンマに突破口を開く、「動物とも人間の世界とも違う、より大きな世界の圧倒的力を受け取る者」であるワイルドマン=カブトムシの存在を最もはっきりと描いた、郡司の言葉でいう「ダサカッコワルイ」映画だったのではないか。
*
物語の舞台は多様な住人が暮らすアパート。主人公で管理人のクリーヴランドはある夜、中庭のプールから出てきた少女ストーリーを発見する。彼女は、自らがブルー・ワールドという別世界からある目的のためにやってきた海の精「ナーフ」であり、目的を果たしたのちに元の世界に戻らなければならないと告げる。しかし、アパートの中庭には、ナーフを襲おうとする怪物スクラントが待ち伏せしていた。もともとは住人たちに対して心を閉ざしていたクリーヴランドは、彼女の出現を機に、住人たちと協力して彼女の目的を達成させ、元の世界へと送り帰そうと奮闘する。
まず重要なのは、ストーリーや木の上に住み異世界の正義を守る獣タートゥティックといったキャラクターが、前縁の向こう側に位置する異界であるブルー・ワールドと、アパートが属する人間の世界を媒介するわけではないという事実だろう。この映画には、ブルー・ワールドの様子が映し出されることは決してない。彼女たちは、本書でワイルドマンについて語られる通り、「むしろその二つの世界の間を象徴的に開き、人間世界や生命の全体のさらに外側にある力を呼び込む存在」であるように思える。
アパートの住人たちに何がやってきたのか
そしてさらに興味深いのは、ストーリーがアパートへと「やってきた」目的と、彼女が元の世界へと帰る方法を、住人たちが協力して探ろうとする過程だ。アパートの住人たちは、プールの底とつながっていると思しき、「知覚できない向こう側」に位置する異世界であるブルー・ワールドを決して目にすることができない。にもかかわらず、彼らのほとんどは突如アパートに「やってきた」ストーリーによる、自分は海の精「ナーフ」であるという荒唐無稽な主張を疑うことはない。
さらに彼らはなぜか、何の裏づけもないそれぞれの住人たちが持ち出す推理もまた、一切疑わずに信じ込んでいる。はじめクリーヴランドは、さまざまな住人がそれぞれに語る物語を信じ、それらを頼りに彼女の目的に関する仮説を組み立てていくのだが、「通訳者」や「癒し手」、「守護者」、「ギルド」などと呼ばれ、それぞれ物語のなかで重要な役割を果たす人物たちが誰なのかをめぐる仮説は、いずれも後に否定されることとなる。
住人たちの仮説やストーリーの残す予言といった、本作の中盤までに登場するあらゆる疑問に対する解答は、郡司がパトカーの写真を示したTさんに「これなんだ?」と問われた際の答えであった「カブトムシ」と同様に、いずれも少しずつ間違っていた。しかし、この映画では、新たな解釈(答え)が付け加えられるごとに、そもそものゲームの規則(問い)もまた書き換えられていく。それらは郡司が対話におけるワイルドマン=カブトムシの特徴とした、「相手の言葉を引き取り、何かを限定して答えになるのと同時に、質問として開かれている言葉」でもあった。
実のところ、「かつ」と「または」を混同する、コンピューターのバグ(≒「カブトムシ」) を思わせるそれらのずれは、住民たちの間で繰り返し受け渡されることで有意味な言葉となり、やがて「答えでありながら同時に意図の読めない問い」として、「意味の限定と意味の解放の間」、あるいは「理解を召喚するずれ=スキマ=ギャップ」を開いたと考えられるのだ。ストーリーがやってきてそこへと帰っていくブルー・ワールド、すなわちプールの底の向こう側は決してわからない。「にもかかわらず、決して知覚できない向こう側の存在が、確信できるようになる」。
例えば、自らが「守護者」であるというクリーヴランドの見立ては誤りであったが、実際には彼には別の役割が与えられていた。次々に変更される解釈を再び信じようとする、明らかに常軌を逸した住人たちの姿勢に打たれ、数少ない懐疑派の住人もついには皆と同じ物語を信じるに至る。アパートの住人たちは、恐怖の対象として「毛むくじゃらな男」や「猿みたいな手」を恐れる態度とは逆に、「境界を通して理解される前縁の向こう側」に「ストーリー」が存在することを信じる。最終的に住人たちが辿り着く正しい役割の解釈は、複数回の誤りを経ることで初めて「他でもあり得たにもかかわらず、それしかない」ものとして立ち現れる。つまり、「他でもあり得たことへの気づき」によってこそ、我々は「関係自体が固定できず、関係を指定する文脈がたえず逸脱し、本質的に動的であることに気づかされる」。
「ストーリー」を受け入れる――徹底した受動性へ
郡司は本書の最後で、こうした気づきを経て「初めて私たちは、外部に対して徹底して受動的になれる」と強調する。『レディ・イン・ザ・ウォーター』の末尾、ストーリーが消えた後にブルー・ワールドへと通じるプールの水面を見つめるアパートの住人たちの姿は、映画館のスクリーンを見つめる観客の姿勢を強く想起させるが、ここでの水面≒スクリーンもまた、1つの境界として機能しているように思われる。「境界(スクリーン)を通して理解される前縁の向こう側」が同時にその逸脱でもあること。スクリーンに映し出されるイメージや「ストーリー」(=物語)が予想された文脈からずれ続ける様子に目を凝らしてきた私を含むこの映画の観客たちもまた、そのことに気づくことで外部から「やってくる」理解を待ち受ける徹底した受動性を獲得し、少女ストーリーと彼女をめぐる「ストーリー」を信じることができるようになる。
初めてこの映画を観た時に、こうしたことを意識していたわけではもちろんなかった。しかし振り返ってみれば、その後幾度となくこの映画を観直すごとに私が涙してきたのは、外部から「やってきた」「ストーリー」をそのままに受け入れて信じるまでの徹底して受動的な過程を、そのたびに繰り返し経験してきたからだったのかもしれない。
(『やってくる』を読んで「やってきた」もの――書論『やってくる』 了)

「日常を支える人々」に捧げるアメイジングな思考!
生ハムメロンはなぜ美味しいのか?
対話という行為がなぜ破天荒なのか?
――私たちの「現実」は、既にあるものの組み合わせではなく、外部からやってくるものによってギリギリ実現されている。
だから日々の生活は、何かを為すためのスタート地点ではない。
それこそが奇跡的な達成であり、体を張って実現すべきものなんだ!
ケアという「小さき行為」の奥底に眠る過激な思想を、素手で取り出してみせる郡司氏。その圧倒的に優しい知性。






