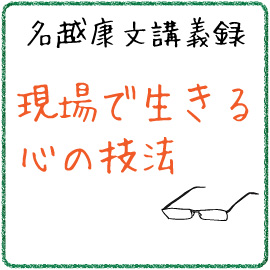かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
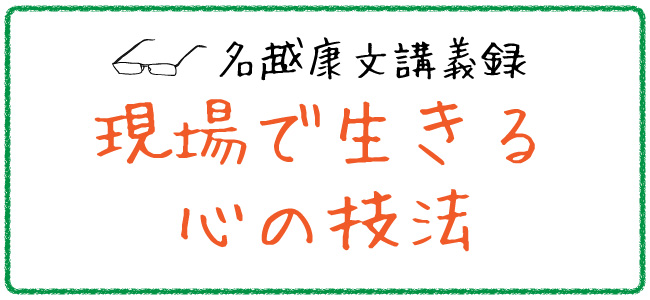
講演録「心の技法」(12) 死生学編
2012.3.14 update.

1960年生まれ。近畿大学医学部卒業後、大阪府立中宮病院精神科主任を経て、99年、名越クリニックを開業。専門は思春期精神医学。精神科医というフィールドを越え、テレビ・雑誌・ラジオ等のメディアで活躍。著書に『毎日トクしている人の秘密』(PHP研究所、2012)、『心がフッと軽くなる「瞬間の心理学」』(角川SSC新書、2010)、『薄氷の踏み方』(甲野善紀氏と共著、PHP研究所、2008)などがある。2011年4月より「夜間飛行」(http://yakan-hiko.com/)にて公式メルマガスタート。
本稿は、2011年6月29日に行われた「名越康文連続講義 現場で生き残るための心の技法」での名越康文氏の講義を元に再構成したものです。
(12)医療者として死をどう捉えたらよいか
(質問)死に対しての考え方は様々で、本人家族間でも違いがあります。死に瀕した患者・家族とかかわっていくときの心構えを教えてください。
これは本当にすばらしい質問で、このテーマだけで1日講義をさせていただきたいぐらいです。それくらい、大問題なんです。例えば最近では、いわゆる「喪に服する」ということを医療現場に取り入れるという意味で、「グリーフケア」ということが言われるようになっています。もちろん、それがすばらしい取り組みであるということは確認した上ですが、僕は、日本においてはグリーフケアの取り組みの前に、乗り越えておかなくてはいけない課題があるんじゃないか、という考えを持っています。それこそが「死をどう捉えるか」という、宗教的な問題なんです。
日本社会では、「魂がどうなるのか」ということについて公の場で口にしない、ということがある種の不文律になっています。そうですよね? 死んだらどうなるのか、ということが話題にならない。それは実は、現在行なわれているグリーフケアにおいてもそうだと思うんです。
ペットを亡くした、親を亡くした、子供を亡くした、兄弟を亡くした、親友を亡くした……そういう人の気持ちを聞いてあげるのがグリーフケアですが、じゃあどう聞けばいいのか? どう声をかけるのか、というと、とたんに芯が通らなくなってしまう。もちろん、「こういうときはこうしましょう」というマニュアル的なものはあるんだけれど、拠って立つ立脚点は常にあいまいです。
個人的な見解としてですが、僕は少なくとも今のところ、日本社会ではグリーフケアの立脚点になるような死生観は共有されていないと思います。はっきりとした宗教を持っていないから、死んだらどうなるのか、魂はあるのか、ないのか、という問題を考える軸を持ち合わせている人はほとんどいません。だから、亡くなられた方の家族の方はもちろん、それにかかわる医療者も、死にかかわろうとするとどうしても息苦しくなってしまう。
これは、死生観について学ぶ機会を与えられてこなかったんだから、当然のことだと思います。ただ、その一方でこの状況は、非常に奇異なことだということも認識しておくべきです。だって、ここにいる僕らは、100年も経てば全員死んでいるわけですよね。
でも、僕らは死をどう迎えるのか、どう看取るのか、ということを考える軸を何一つもっていない。だから、患者さんも、家族も、医療者も、看取りの場面では必然的にバラバラにならざるを得ない。ここをどう捉えていくかは、医療にとどまらず、僕ら日本人がどこかで答えを出さなければいけない最大の課題ではないかと思います。
ですから、ご質問の方が「どのように援助していいのか悩んでいます」というのは本当に率直で、かつ深い問いかけだと思うんです。医療現場にいて、そこを問いかけないわけにはいかないし、根本的なところから、考え、取り組まないわけにはいかない課題です。
具体的にどう対応するかは、この講座の主題である怒りへの対処ということと深くかかわってきますが、少なくともマニュアル的に「こうすればよい」という答えが出せるようなものではない、ということだけは確かだと思います。
このテーマは、次の質問にあるような、がん患者さんへのケアというところにもつながってくるでしょう。
(質問)がん病棟に勤めています。がんの患者さんは、病名の告知や将来への不安などによる精神的な苦痛で悩んでおられる方が多いため、そうした方にとっての「よい聞き手」となるためのヒントを教えて下さい。
これについては、まずその人の命はその人のものだということ、それはかけがえのないものだという敬意を胸に置くということが、何より優先されると思います。そのうえで、浮わつかない程度に、例えば朝の挨拶は心が落ち着いている状態でできるだけ爽やかにしていただく、ということでしょうか。あるいは1週間に一度でもいいから、何かひとつ、笑顔の出るような会話を交わす。僕の経験上、それくらいしか言えないですね。
答えの出ない現場の中で毎日七転八倒しながら、結果的には、むしろ自分たちが患者さんから毎日勇気づけられていた、という医療者は多いと思います。でも、そういうふうに思えるなら、必ずしも卑下する必要はないと思う。それは少なくとも、患者さんとの気持ちの交流があった、ということだと思うからです。
それからもうひとつ、これは畏友の安克昌先生ががんで亡くなったときに思い知らされた問題があります。安先生は精神科医で、阪神大震災の経験を書いた『心の傷を癒すということ』という本で、サントリー学芸賞を授賞されています。彼が言うには、がん患者さんには2つ辛いことがある、というんです。もちろん、ほかにもいっぱいありますよ。ここであえて2つ、といったのは、それらがあまり本では書かれていないことだからです。
それは、「自分の死を覚悟した後になって、治癒の可能性があるとされる治療法を呈示されること」なんです。覚悟したあとに「こんな治療があるらしいよ」といわれること。それが一番辛いんだと言っていました。なぜなら、その言葉によって、すごく心が揺れるからです。心が揺れるということは、欲が出てきて、怒りも出てくるということです。それが辛いのだというんですね。
もうひとつは、がんになってある段階を越えると、周囲の世界と自分との間にフィルターがかかる瞬間があり、それが辛いのだそうです。例えば周囲の医療者が、「この人、もう死ぬんだな」とわかった瞬間、妙に優しくなる。妙な言い方になってしまいますが、その人に対して“ツッコミ”がきかなくなる。会話をしていても、どこか話を早く済まそうとしてしまうような空気が生まれる。
そういう空気の中でがん患者さんは、周囲の世界との間にベールのような壁を感じるようになる。
この2つって、頭で考えると矛盾してますよね。一方では、死への覚悟を揺さぶられたくないといい、もう一方では、生者と死者の間に「びしっ」と線を引かれることへの疎外感がある。でも、臨床的には、その2つが同時に起きている。僕がクライアントさんと会う時に心に留めるのも、やはりその2つです。
この矛盾が示しているひとつのことは、死に瀕した人を前にしたときの対応の本質的な部分は、どうあってもマニュアル化できない、ということでしょう。もちろん、マニュアルがあるなら、それは読んでおくべきですよ。ただし、結局現場で大切になるのは、自分の持てるリソースをすべて注ぎ込んで、渾身の力でかかわった経験をどれくらい持っているかということなんだと思う。それがあるのとないのとでは、同じマニュアルを使っていても、ずいぶんかかわりかたが変わってくると思います。