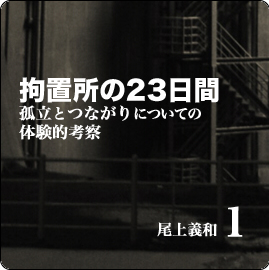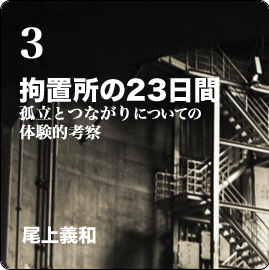かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
![[当事者研究]自殺未遂とひきこもり、私の場合。(2)](http://igs-kankan.com/article/%E3%81%B2%E3%81%8D%E3%81%93%E3%82%82%E3%82%8A%EF%BC%96%EF%BC%95%EF%BC%90%EF%BC%88%EF%BC%93%EF%BC%89.jpg)
[当事者研究]自殺未遂とひきこもり、私の場合。(2)
2012.2.14 update.
群馬県当事者研究会ピアリンクメンバー。
22歳で自殺未遂、それから36歳までの15年間ひきこもる。
現在、41歳。
第2回(2回連載)
2 自殺未遂前後
■ゼミ面接に落ちる
トイレにすぐに行きたくなる。だから一定の時間をみんなと行動を共にできない。怒られるのが怖くてバイトもできない。注意されるシーンを考えるだけで胃が熱くなり、ずーんと腹に重く圧迫がくる。……自分が目指した社会人とはほど遠い。
公務員になれるかもしれないとわずかな希望を賭けていた1年半前のゼミ面接は、前述のようにすげなく落とされた。その面接は先輩の4年生がやっていたものだった。
後に教授からじきじきに「ゼミに来ないか」と言われたが、私は断った。その4年生に遠慮していたのもあるが、別の理由もある、実は、落ちて安堵したのも感じていたのだ。
「今の自分では仕事はできない」と思いながら、うつろに1年半を過ごした。だんだん自分の視界から色合いが失われていくように感じられる。
ある日学食から下の売店に下りていくと、大学のOBの人たちが、集まっている新4年生に向けて熱弁をふるっていた。……・私の耳に言葉は届いている。ただ自分のまわりには薄膜が張られているように、遠く感じた。
■二つの事件
大学4年の4月、あと数週間で22歳というときだ。私は自分の母親と激しいセックスをしている夢を見る。
目覚める前に射精をしたときから悪寒が身体を駆け抜ける。目覚めてあらためて口の中に毒々しい苦味を感じる。仕方のないことだが、精液はたっぷり下着に出ている。頭はパニックに襲われる。
混乱した頭のままに大学に出かけた。駅のプラットホームから入ってくる白い電車を陽炎とともに眺めた。小さい衝動が胸を叩く。
「走って飛び降りろ!」
自分自身がすごくびっくりする。瞬間的に人の後ろに隠れる。また、小さい衝動が襲う。
「背中を押すんだ」
ひやりとした氷のような感覚が身体に走る。一呼吸おいてゆっくりと後ろを向いて、プラットホームのいちばん後ろに進むと少し落ち着ついた。そのときはなんとか電車に乗れて大学に向かった。
母とのセックス、電車での衝動……、自分自身が信じられなくなった。
■平穏な2~3日
その夜、気分転換にレンタルショップにビデオを借りに行ったが、そこで、絶対観たくなった映画に手が伸びた。
「ペアレンツ」
人肉を代々食べている家系、それを引き継ぐ両親。主人公の男の子は頑なに肉類を食べない。その子に食べさせようとするストーリーである。その男の子が救われるかどうかもわからない。
その映画を観て、また何かが信じられなくなる。自分の身体が冷たく硬くなり、心も冷たく硬くなる。
「自分自身が信じられない」
時間が経つにつれて、何を見ていても、何に触れていても「自分自身が信じられない」。
息をしているのさえつらくなる。ずっとそわそわしている。ずっと胸が圧迫されつづけ、息が詰まりつづける。
「死のう。死んでしまおう」
本気ではじめてそう思うと、今までの圧迫感がすーっとどこかに消えてしまった。それから、スムーズに考えが流れ出した。
「酒を飲み、手首を切り、入水する」
「手馴れた農業用ナイフ、ウイスキー、想い出の利根川の河川敷」
「夜中がいい。錘も必要かな?」
「俺みたいなのは、家族のためにもいないほうがいい」
人生のなかで、いちばん平穏な2~3日が過ぎた。
■決行!
1992年4月25日、午前2時。家をひとり静かに出る。遺書のようなメモに「誰も悪くありません。自分が弱いだけです」と書く。
堰を切ったように自転車を漕いだ。10分もしないうちに最初のミスに気づく。
「ナイフを忘れた!」
戻る気がしなくてコンビニでいちばん丈夫なナイフを買った。先へ先へ急ぎたい。
ウイスキーを飲みながら先を急ぐ。ガツンと衝撃が走る。道路のアスファルトの窪みにタイヤを落としてしまう。タイヤだけでなくウイスキーのびんも落ちて木っ端微塵に砕ける。2度目のミスである。「ちっ」と思うも先を急ぐ。
利根川の河川敷は思ったよりもずっと遠い。漕ぎに漕いだ。やっと到着したが、ここで3度目のミスをする。錘りに持ってきたリュックを先に背負ってしまったのだ。それは後ろによろけてしまうくらいの重さだった。
背負って不自由な右手にナイフを持ち、思いっきり左の手首を切る。2回。でも足りなくて、持ち替えてまた2回切る。
ものすごく興奮している。ナイフを捨て、そのまま葦に突入しながら川へ走り出す。しかし何十キロの錘りが邪魔になる。捨てた。息が上がった自分には葦が煩わしくて仕方がない。小径沿いに歩き出す。血はそこそこの勢いで流れたままだ。
どうにか歩いて、やっと水に出会った。
「川だ!」
崩れて抱擁するように水に入っていくと、とても安心した。手首から血が流れつづけているほのかな感触のなか、水に浮かびつづける。
一度目、目を開けた。
「満月?」
頭の中に青空と日光が浮かぶ。そのとき「忘れられたくない!!」という強烈な思いが湧いた。
二度目、目を開けた。
「満月? ……生きづらいだけなんだ!! 死にたいわけじゃない!! 死にたくない!!」
右斜め上を向くと、なぜかそこに岸があった。必死で這い上がった。
「助かった……」
一呼吸置いてから、そこが船着場であることに気づいた。救急車を呼べるところまで歩かないといけないと思ったが、脚が重い。めがねもない。河川敷を歩ききったところに、家が見えた。
「でも、こんな時間に人を起こしちゃいけない」
それにしても手足が冷たくて重い。血も流れている。それにもう眠い。
「サイクリングロードで眠っていたら、自転車の人に危ない」
もう少し歩こう。それにしても手足が動かない。眠い。
「芝生で寝ようか。でも、犬の散歩のおばさんなんかが驚くよな」
そのとき、砂利集積場の事務所の光が見えた。そこまで歩いて自分で救急車を呼んだ。待っている何分間かは、いちばん深く気持ちのよい眠りを体験した。
■逃げ場がなくなった……
自殺未遂後の1日半いた病院では、恥ずかしさと申し訳なさから、看護師に手伝ってもらわないで自力でトイレに行っては貧血で倒れた。
病室で一人の女性看護師さんに「もう、こんなことやっちゃ駄目よ」と言われて、か弱くだけど本心から「はい」と言った。でもそれ以外に会話をした記憶がない。点滴を受けながら、同じ日、同じ時刻に亡くなった尾崎豊のことを考えながら不思議な気持ちになった。あんなに人気のある人が亡くなって、どうして俺なんかが生き残ったんだろう、と。
病院ではそんなことを考えながら寝ているだけだったのでそれほどの苦労はなかったが、家に帰って来てから、本当のつらさが始まった。自殺前のように、自分自身への不信感や混乱が再び襲ってきた。ただ、今度は逃げ場がない。
これまでは「行けるところまで行こう。駄目なら死ねばいいや」と考えていた。実はこの考え方は、私の逃げ場にもなってくれたのだ。しかし実際に自殺未遂をして、「自分は本当は死にたくないのだ」とわかってしまった後では、それは逃げ場として機能しなくなってしまった。結局、精神科クリニックに通い、薬を飲み、しばらく時間が経つまで混乱は続いた。
当時の私は、「妄想から自殺未遂をしてしまった」と感じていたが、いま思うと、就職をまえに怯えきっていた自分を妄想が助けてくれたように感じる。そして、自殺未遂という逃げ場へスイッチを押してくれたように感じる。孤立してどうにもならなくなってきている自分にとって、自殺は生きていくために必要な自分の逃げ場であり、セーフティーバルブだったのだと今は考えている。
いずれにせよ、この行き詰まりでも「弱さの情報公開」ができなかった私は、それから15年半の間、ひきこもり生活に入らざるを得なくなった。
3 ひきこもりの構造
私は、ひきこもりといっても半ひきこもりである。家事は毎日のようにやっていた。炊事、洗濯、掃除、買い物。そして祖父母の世話など。
22~36歳までひきこもったが、27歳で自動車の免許を取ってからは、プールと喫茶店に通ったりしていた。祖父の病院通いも手伝った。同じころ、自宅でわずかな生徒をとり、塾もどきの仕事を5年くらいしていた。
29歳のときに、はじめて彼女ができた。既婚の年上の女性だった。通っていたプールで知り合い、病気をオープンにして3年間つきあった。つきあっている間は誰にも話さなかった。しかし、結局彼女がご主人と別れられず、自分もそれに耐えることができず、恋愛が落ち着いた3年目に、別れを切り出した。私が彼女の夫のことを考えると眠れなくなったのだ。
彼女とつきあっている時期に、祖母の介護を少しした。33~36歳までは両親とともに祖父の介護をした。おしめを取り替えたり、血圧を計ったりとかなり本格的なものであった。介護の終了とともに、私は今のデイケアとつながることになった。
私のひきこもりの特徴は、家族の間に入ってコミュニケーションを独占することである。父や母のスケジュールを把握しておくこと、祖父の要望を何気なく聞き出しておくこと。祖父の無理な要求を予測しておいて、母や父の予定を正直に伝えればよいか、嘘をつけばよいか見当をつけておく。それを母や父にはあらかじめ伝えておく。
要介護状態になっても、祖父との激しい言い合いは数限りなくあった。そのたびに、私は言葉で爆発した。それで血圧が上がったりすれば、面倒をみた。それは、祖父が101歳で他界するまで続いた。
このころは、介護されてもうまく感謝できない祖父を哀れと思いはじめていたから、介護もできたのだろう。しかしもっと別の動機もある。家族が安心して生活できるには、自分が祖父と喧嘩してまでも面倒をみることが大事だったのだ。自分の力で、家をコントロールしていたかったのかもしれない。家族の安全を守る「上位者」のような気持ちである。
また、このことで母や父に認めてもらえたことも重要だった。実際、私が祖父の面倒をみることで家の中がうまくまわって、母や父も助かっていることは明白だった。
そのとき私は36歳だった。私自身は15年半もひきこもっている自分に焦っていた。実際に本を見て、自助グループを探したりしていたが、真剣には探さなかったと思う。その理由として、「家族には必要とされていて、それが居心地がよかった」ということがあったと思う。
今、ほとんどの同級生が仕事をして結婚して子どもを持っている。社会的地位が安定していっているなかで、私は狭い家の中で思い通りに家族をコントロールする努力をしながら、そこに安住していた。苦しくもつらくもあったが、楽な道でもあったのだ。
*
仲間とともに当事者研究をして、ここまではわかった。これから先はどうなるかわからないが、日々の日常生活を大事にしていきながら、仲間とともにさらなる研究を続けていきたいと考えている。
(村岡聡「自殺未遂とひきこもり、私の場合。」了)



![[当事者研究]自殺未遂とひきこもり、私の場合。第1回 イメージ](http://igs-kankan.com/article/%E3%81%B2%E3%81%8D%E3%81%93%E3%82%82%E3%82%8A270.jpg)