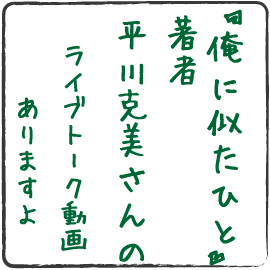かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

『俺に似たひと』刊行!!
2011.7.20 update.
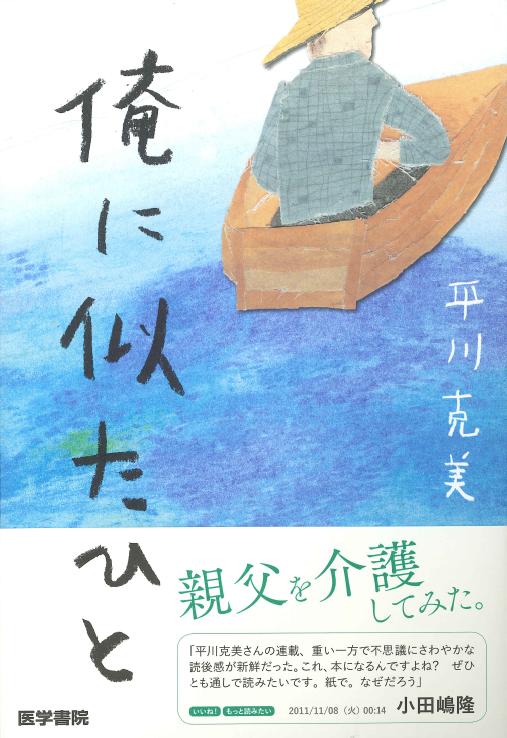
1950年、東京都生まれ。早稲田大学理工学部機械工学科卒業後、渋谷区道玄坂に翻訳を主業務とするアーバン・トランスレーションを設立。1999年シリコンバレーのBusiness Cafe Inc.の設立に参加。現在、株式会社リナックスカフェ代表取締役。
本連載を大幅加筆した『俺に似たひと』は、1月20日発売!! 定価1680円(税込)です。
なお『小商いのすすめ――「経済成長」から「縮小均衡」の時代へ』(ミシマ社、1680円)も同時刊行。こちらもよろしく!
『俺に似たひと』1月20日発行!
(四六版、240頁、税込定価1680円)ISBN978-4-260-01536-3
物 語 と い う 形 式
これから「俺に似た人」について語ろうと思う。「俺に似た人」とは、ついひと月ほど前に亡くなった俺の父親のことである。
この二年間、俺は父親の介護をするために、実家に戻り、毎日毎日、朝晩の食事を作り、風呂に入れ、散髪をしてやり、下の世話と汚れ物の洗濯をした。それ以前、つまり介護生活に入る以前は、父親とは会話らしい会話をしたこともなく、かれが何をしているのか、どのような気持ちで毎日を過ごしているのかについてほとんど何も知らなかったといってよいと思う。
もちろん、父親の仕事は知っていたし、結婚してすぐに埼玉県番場村から大田区の場末の町に家を構え、町内会の会長職をその立ち上げから長年続けていることや、腕のよいプレスの型職人であり、町工場の社長であることは知っている。でも知っているのはそれだけであり、それ以上のこと、つまりかれの内面に関しては何も知らなかったし、特段の興味を持たなかったのである。
これから語ることは、八十六歳で亡くなった父親について、その最後の二年間で俺が知りえたかれの内面についてのことである。
とはいえ、それが事実であり真実であるという保証はない。なにしろ、人間の内面というものは見ることができないし、形のあるものでもないからである。
自分自身にとってさえ、人間の内面は暗がりであり、触れることができない。フロイトはあまたの臨床データをたずさえて、この暗がりのいちばん近くまで行き、それを覗きこもうとしたひとりである。そうやって発見されたものは「無意識」というものであった。
フロイトは、ヒステリー患者の治療を通じて、その心的な傷がどこにあるのかを捜し求めたわけだが、その行きついた先にはなにもないもの(意識の不在)の存在であった。
なにもないものがある。
精神分析医ではない俺には、フロイトが発見したこの「無意識」について、何か分析したり、臨床的な知見を語ることはできない。
ただ、父親の「無意識」が死の直前で、かれに何を思わせ、何を語らせたのか、そしてかれの欲望がどのような形で表出されたのかについては記憶している限り記述してゆくことはできると思う。
あるいは、老いの意味(俺はそんなことを考えたこともなかったのだが)について、介護の体験の中から拾い集めた断片を再構成することはできると思う。
したがって、以下は「俺に似た人の物語」である。物語という形式でしか語りえないものがあると言ったのは、わが盟友である内田樹だが、俺が体験した二年間こそが、その語りえない時間だったということだろうと思う。
母 親 の 入 院
二〇〇九年も終わりに近づいた頃(十二月二十日)、俺の母親がほとんど唐突に旅立っていった。八十三歳だった。
最初はちょっとした事故だった。
その夜は大阪で以前より約束していた講演をする予定になっていた。講演が始まる時刻になったので、携帯電話のスイッチを切ろうとしたらブルブルと電話が鳴った。出てみると、母親が玄関先で躓いてころび、大腿骨を骨折したという知らせだった。
「いまから、講演なんです。今日は帰れないので、明朝新幹線で帰って直接病院へ伺いますのでよろしくお願いします」
俺は、知らせをくれた従兄にそう告げて電話を切り、スイッチをオフにした。
ラジオの収録中でも公演中でもよく携帯電話のスイッチを切り忘れ、そういうときに限って、電話が鳴るのである。普段はほとんど鳴らないのに、鳴ってはいけないときに限って鳴り出すのが携帯電話というものなのかもしれない。
もともと俺とは相性が悪いのだ。
単なる偶然なのかもしれないが、たびたびそれが重なれば何かの暗示が隠されていると思いたくなるものである。
その電話のスイッチを切る直前に鳴り出したこの日の電話は、暗示というよりはもうすこし積極的なものを含んでいるかのように思われた。
不安とか、予兆といったほうがよいのかもしれない。
それでも、何もなかったかのように、聴衆のみなさんに
「いや、おふくろが骨折したらしい。でも重篤というわけでもなさそうなので、すぐに帰る必要はないと思います」と継げて、講演を始めた。
翌日、病院へ駆けつけると母親は笑いながら「やっちゃったよ」と言った。
それ以前にも腰が痛い、膝が痛いといって何度も病院通いをしていたので、これを期にじっくりと足腰の治療したらよいではないかと俺は告げた。
そのとき、なんとなくひょっとしたら彼女はこのまま自宅へ帰れなくなるかもしれないという感じが胸をよぎったのを覚えている。
あくまでも、なんとなく。
老人が一旦寝込むとなかなか立ち直ることが難しいとよく耳にしていたし、その原因が足腰の骨折である場合が多いということも聞かされていたからかもしれない。
その翌日、医師に呼ばれた。
治療法に関して話しておきたいことがあるということであった。
話したいこととは、大腿骨の骨折について、ひとつ厄介な問題があるということだった。
骨折した骨の一部が粉砕しており、骨折両端を手術をしてボルトでつなぐ必要があるのだが、接合する部位の骨密度が低いのでボルトを支えきれないかもしれない。そこで、部位の両端にセメントのようなものを詰めて繋ぐという方法をとりたいということであった。
骨粗鬆症に関しては若干の知識しかなかったが、まあ老人の骨が脆くなっていることは感覚的にはよく理解できる。
母親は、埼玉県では有数の染物屋(「紺元」という屋号を言えば、草加駅からタクシーが連れて行ってくれた)の四女であったが、幼いときより身体が弱く、戦争をはさんで食糧事情も芳しいとはいえなかった。
母親の場合は、偏食というよりは習慣からか、カルシウムを十分に採れるような食生活ではなかった。俺が彼女の腹の中にいたときは、甘納豆ばかり食べていたというような話を聞いたことがある。まあ、食糧事情に関しては、よほどの金持ちでもない限りは、日本全体で似たりよったりのひもじいものであった。
それでも、他人の目には元気いっぱいで、健康そのものといった様子に写っていただろう。
こまねずみのようによく動き、大声で笑い、大雑把な性格で、弱音を吐くことはなかった。
俺の父母の世代、つまり現在の八十五歳ぐらいの年齢の老人たちは、後続世代に比べて確かに一本筋が通ったようなところがあり、根性が座っていると思うことが多々あるのだが、身体的には戦前、戦時中に成長期を送ってきたわけで、滋養という点では、もともとハンディキャップを負っていたといえるのかもしれない。
ただ、その気力に関しては今の世代には想像もできないような強靭さを備えた世代でもあった。特に、おんなの生活に関しては今日のそれとは隔世の感がある。
俺の生年は昭和二十五年であるが、昭和三十年代までの日本の家族構造には、まだまだ長子相続、権威主義的な封建遺制が色濃く漂っていた。
母親は、夏でも冬でも毎朝五時には起床し、工場の周囲を清掃し、朝食の支度をし、工場の住込みの職工さんたちや、通いの職人さんたちが始動するまえの準備万端を整えるという生活をずっと続けてきた。俺にものごころがつきはじめて以来、裏方として働きずくめに働いた一生だった。
大腿骨骨折での入院だったが、俺にはそもそも母親が怪我や病気で入院したという記憶がない。だからこの度の入院は、嫁いできて初めての骨休みだったのかもしれない。
骨折が骨休みだという連想に、俺は苦笑いをした。
第二京浜国道沿いにある救急病院は、近代的な大病院というようなものではなく、地元に密着した、小ぶりで親近感の持てる病院だった。
入院して数日後に見舞いに行くと、「ここは天国だよ」と母親は呟いた。
当たり前のことだが、上げ膳据え膳のうえ、風呂にまで入れてあれこれ面倒を見てくれる病院は、働きずくめできた母親にとっては天国のような場所だったのかもしれない。
医師から説明を聞いた翌日に手術は行われた。
一時間程度といわれた手術は、しかし、思いのほか難航した。
俺と女房、従兄とその母親(俺の母親の姉)は、夜の八時ごろから始まった手術を、手術室の手前の廊下のベンチに腰掛けながら、手術が終わるのを待っていた。
途中、輸血が必要だということで、何度が手術室のドアが開いて、輸血用の血液が運び込まれた。
「かわいそうに」と、母親の姉は何度も呟いていた。
俺は、いったいどこで手術が難航しているのかが気がかりであった。
事前の医師の説明では、手術自体は大丈夫だが怖いのは合併症であり、その場合には生命にかかわる危険もあると告げられていた。
手術を待つあいだに不安が徐々に膨らんでいった。
何か、輸血の拒否反応でも起こしているのではないか。
大腿骨を開いてみたら、粉砕骨折の状況が思った以上にややこしい状態になっていて、うまく接合することができないのではないか。
そもそもこのような長い時間の手術に、老人である母親は耐えられるのだろうか。
ベンチで待つ四人は無言のままで、ただ不安な時間がゆっくりと経過していくのに身をまかせるほかはなかった。
もう限界じゃないのかなと思ったときに、手術室のドアが開き医師が出てきて、終わりましたと告げた。
難航はしたが、手術は成功したということであった。
母親は麻酔がかかった状態で、眠っていた。
手術後の経過は順調であった。
母親のベッドは六人部屋で、まわりを見渡すと同じような年齢の年寄りばかりであった。
母親の病床には、毎日だれかしらが見舞いに来て賑やかな会話が続いた。
一度、女房と見舞いに行って帰ろうとすると、同室の老婦人に帰らないで話を聞いてくれと泣訴されたことがあった。
その老婦人の病状に関してはわかるすべもないのだが、なんでも誰も見舞いに来てくれないのが寂しいということであった。
延々と嫁の悪口が続いた。
「あなたたちは、やさしい。うちは誰もこないよ。見捨てられているんだ……」
それ以来、何となく母親を見舞いに行って笑いながら楽しそうにすることが憚られた。
二週間程度で退院できそうだと医師もいい、俺も以前にちらりと感じた「もう帰れないのではないか」という不安が杞憂であったと安堵した。
父親もまだまだ矍鑠(かくしゃく)としており、自宅から二キロほど先にある病院までの道のりを、何度か歩いて見舞いに行っていたようだ。
母 親 の 転 院 か ら 死 ま で
母親は血色もよく、表情も明るくなって、退院まで秒読みといった印象であった。
そろそろ退院後の準備をしなくてはというときになって、医師から相談したいことがあると連絡を受けたのである。
何かあったのかと思い聞いてみると「出血が止まらない」というのだ。
「傷口がふさがらないんでしょうか」
俺は思わず聞きなおした。
そうではなかった。
子宮からの出血があって、そちらは専門外なので大学病院を紹介する。そちらで精密検査をしてくれというのである。
数日後、俺は紹介状をもって超近代的な大学病院まで、母親を車椅子に乗せて連れてゆくことになった。
雨がしとしと降る寒い朝だった。
大学病院の待合室は診察待ちの患者であふれていた。
紹介状を受け付けに渡してから、「だいぶ、待つことになりそうだな」と母親に告げて、持参した本を開いた。
ところが、一時間たっても、二時間たっても名前を呼ばれない。
待っているあいだに、母親が足がだるくてかなわない。気分もよくないと言い出したので、長いすに寝かせて、足を揉んだ。
両足首から先が、ぱんぱんにむくんでいて、つらいだろうことが見ているだけで察することができた。
「帰ろうよ」
と母親はいったが、どこに帰ろうというのか。
いまからもとの病院へ帰るというわけにもいかない。
何度か、受付に患者の具合がよくない旨を伝えたのだが、かんばしい返答はなかった。
三時間ほど経過し、待っている患者が誰もいなくなってから母親の名前が呼ばれた。
結局最後にされてしまったのである。
その間に、スタッフが一度でも様子を見に来てくれていればと、俺はすこしこの病院を恨んだが、まあいろいろな事情があるのだろうと自分で自分を納得させた。
名前が呼ばれたとき、母親はぐったりと疲れきった様子であった。
ひととおりの病状説明ののちに、カーテンの奥で教授が子宮の具合を見始めた。
するとすぐに「こりゃ、ひどいな。すぐに入院の準備……」というような声が聞こえた。
ちょっとした検査のつもりで、この病院を訪れたのだが、すぐに入院の手続きがとられ、そのまま入院することになったのである。
末期の子宮頸癌ということであった。
唐突に、この病名を聞いて俺はすこし動転した。
母親はそのことを知っていたのだろうか。
そういえば、十年ぐらいまえに、排便が困難になって、痔の手術をしたことがあったと聞いていた。そして、痔核の奥に癌が見つかったとも聞いたことがあった。
入院ということになったらしいのだが、そのときには俺に連絡はなく、数日で退院してきた。
「癌なんて気力で治してみせる」と母親は言い、事実、数日で退院してきて、以後癌のはなしはしなくなり、すっかり治癒したものだと思っていた。あのときの癌と今回のものは関係があるのだろうか。
それにしても、末期の子宮頸癌とは。
俺は母親に対して、済まないという気持ちであった。
母親の病状に関して、何の根拠もなく大丈夫だろうとたかをくくっていたのである。
実際に会ってみれば、血色もよく、大声で話し、いつもよく笑っていた。
それでも母親は、何度か俺に電話をしてきて、実家に様子を見にきてくれと告げていた。
仕事が忙しかったこともあったが、なんとなく不機嫌な父親に会いに行くのが鬱陶しいという気持ちが強く、せいぜい月に一度様子を見に行くといった程度の訪問だった。
実家での滞在時間も、一時間か二時間程度であった。
たぶん、いちばん大きな理由は、これから先、親の面倒を見るつもりがあるのかと問いただされるのを避けたいという気持ちがあったからである。
「これから先」
そこには、いろいろと面倒なことが待ち構えているに違いない。
できれば、今は考えたくない、先のばしにしたいという気持ちがあったのだろう。
このあたりの経緯と心理的な葛藤に関しては、後でまた詳しく書くことになるだろうからここではこれ以上は述べない。
ただ、この時点、つまり母親が入院する直前の実家の状態は、俺が考えていた以上に危機的なものがあったということに、後に気付くことになる。
八十歳半ばの老人ふたりの生活というものに対して、俺の想像力はまったく無力であったか、あるいは想像力を働かせるということをどこかで拒む気持ちがあったということである。
ときたま実家に戻ると、母親は床にごろんと寝転んでおり、父親はテーブルの椅子に腰掛けて無言でテレビを見ているといった光景に出くわすことがあった。
耳が遠くなり、毎日の買い物もしんどくなり、料理らしい料理もできなくなっていた母親と、母親の作る食事がおいしくないし、言うことが支離滅裂になっているといって不平をいう父親の姿がそこにあった。
ネクタイの結び方がよく分からなくなったという父親が、悄然としてテレビを見ている光景は、ひとつの家庭が生きる活力を枯渇させつつあることを誰かに知らせようとしていたのかもしれない。俺はそのことに、もっとはやく気付くべきだったのだと思う。
転院後の母親の病状は、見る見る悪化していった。
意識がはっきりしない日が続き、誤嚥を回避するということで飲食を禁じられ、手に拘禁用の手袋をはめられ、荒い息をするようになった。
「お母さんはもうだめかもしれないね」
いつも強気であった母親がはじめて弱音を吐いた。
数日後の日曜日、母親はあっけなく旅立っていった。
(平川克美「俺に似た人について知っていること」第1回了)
続きは、1月20日発行の単行本
『俺に似たひと』で!
オビ推薦文は、小田嶋隆さん!!
絶賛発売中!!!