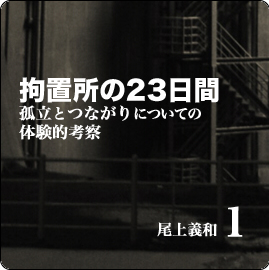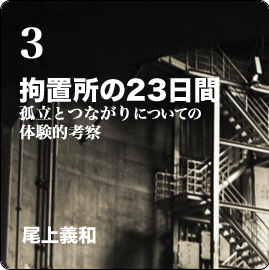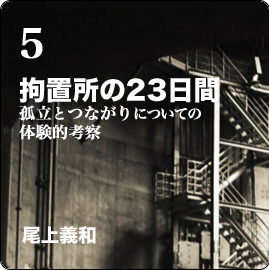かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

第2回 押し寄せるマスコミ、待ち受ける検事
2011.4.21 update.
2009年に障害者団体向け割引郵便制度を不正利用したとする容疑で、当時の厚生労働省村木厚子局長らが大阪地方検察庁特別捜査部によって逮捕・起訴された(その後村木氏は無罪確定)。
その後捜査を進めていくなかで、社会福祉法人全国精神障害者社会復帰施設協会(全精社協)との関連が浮かび上がった。大阪地検特捜部は2009年10月20日、精神障害者福祉施設「ハートピアきつれ川」(栃木県さくら市)の運営費などに流用する目的で厚生労働省から調査研究名目の補助金計約5100万円の交付を受けたという容疑で全精社協の会長、元副会長、元事務局次長、元常務理事(尾上義和氏)を逮捕した。
2009年11月、会長と元副会長は起訴処分(2010年に執行猶予の判決となる)、元事務局長と尾上氏は起訴猶予処分となった。
――本稿は、本件について大阪地検の取り調べを受けた当事者の尾上氏に、実際の体験を記していただいたものである。
なんで大阪地検が
私の携帯電話へかけてくるのか。
では俺も疑われているのか!?
電話相談が終わり、A4判の記録用紙に相談内容について記載しているときだった。
「尾上さん、○○新聞からお電話です」
保健予防班の女性職員は、「なんでマスコミから電話があるの?」と言いたげな顔で(私にはそう見えた)、電話がきたことを告げてくれた。
私の職場は保健所の保健予防課である。
保健予防課は、感染症や特定疾患を取り扱う保健予防班と、メンタル面の相談を行う精神保健班の2つの班からなっていた。当時の私は精神保健班に在籍していた。
電話へ出る前から、どのような用件であるか見当はついていた。
嫌なことに対応しなければいけない、ましてやそれが自分のことであると思うと、このまま電話を切ってしまいたいという衝動にかられる。
電話に出なくても何かの罪に問われるわけでもないし、悪いことでもない。「何も答えなくてもよい」という自由だってあるはずである。
「○○新聞の××です。尾上義和さんですね。前職の補助金のことについてお聞きしたいのですが」
私は「仕事中ですので、そのことについてはお答えできません」と答える。
「では仕事が終わる時間にお掛けします。どちらにお掛けしたらよいでしょうか?」
口調は丁寧だが、勢いでたたみかけるような雰囲気が電話の向こうからジワジワと伝わってくる。
「もう私は、全精社協を辞めたので、現会長の許可なく安易にお答えすることはできません」
こちらもできるだけ丁寧に言い返すが、しつこさにだんだん怒り口調となってくるのが自分でもわかる。
それでもなんとか相手のペースに乗せられないように気持ちを抑えつつ答えようとするが、
「ですが、△△理事さんにはお答えいただきましたよ。そのことについて尾上さんからもお話をおうかがいしたくて」とさすがに切り返しが早い。
いつになったら終わるのか、先の見えないこのやりとりに、うんざりしてくる。
それよりも職員の目が気になる。この会話を聞いている周りの人はどう思っているんだろう……。
しかしこれだけでは終わらなかった。
携帯電話や自宅の電話、さらには職場にも取材と称して押しかけてくる。
極めつけは自宅の前でテレビカメラが張っているなど、まったく芸能人さながらである。自分では間違ったことはしていないという自信はあったが、どこからどのように私の居所を調べてくるんだろうかと思うと同時に、「この先どうなっていくんだろう」という不安が一気に押し寄せてきた。
答えない自由は、あるけどない
もはやプライバシーが脅かされ、強制的に何もかもが曝け出されているようである。
「マスコミの質問なんか、答えなければいいじゃないか」と言われそうであるが、私もそうしようと思っていた。だが、そうはいかない。なぜそうはいかないのか?
一言でいえば、「そのときだけのことではない」からである。
ごはんを食べているとき、仕事をしているとき、仲間と話をしているとき、テレビを見ているときなど、朝から晩まで、すべての時において、私の頭の中に「マスコミ」という存在が張りついてしまい、離れてくれないのである。
さらに重症になってくると、テレビや新聞で騒ぎ立てている事件や事故を見ただけで「私もいつかこうなってしまうのか」という何の根拠もない考えに、頭の中がだんだんと支配されていく。
この支配から逃れようと、意識的にテレビや新聞を見ないなど、できうる限りの抵抗を試みるが、それは一時的な対処療法でしかない。マスコミからの電話ですぐに現実に引き戻されていく。平静さを保とうと思えば思うほど落ち着きがなくなり、無意味な行動をとっている。
「俺は何やっているんだ!」と思いつつも、これが現実の私であった。追いかけられる者に選択肢はない。
先の見えるものであれば、なんとか我慢もできる。しかし、いつ終わるかわからないと、うんざりしてくる。
この繰り返しの日々へ終止符を打つためには「俺が話さないから追いかけてくる。だったら一度話せばいいんじゃないか」「それにちゃんと話せばわかってくれるんじゃないか」「そして終わるのだ」という結論に至る。
というより、こんなふうにしか考えられなかったのである。
発達心理学者の浜田寿美男氏は、「選びえるはずだと思いながら、現実的に選びえないというときに不自由さを感じる」(『心はなぜ不自由なのか』PHP新書)という。
まさに私はこの「不自由さ」により、話さないというわけにはいかなくなったのである。
不自由さとは、どれだけの不安と苦痛を人に与えるのであろうか。
だが同時に、この不自由さとは人がつくり出すものである。言いかえれば人は、そのような苦痛を与え続ける根源としての不自由さをつくり出すことさえできるのである。
一人の生活に負の力を毎日与え続けることができるのであれば、その人の自由を奪い、その人を支配することさえ可能かもしれない。
ただ、誤解があるといけないので一言お断りしておくが、私はこうした状況からつくり出される「不自由さ」の姿を、私のつたない体験を通してお伝えしようとしているものであって、マスコミのやり方一般について批判をするつもりではない。
検事からの電話
大阪へ移動する新幹線のなかでは、通り過ぎていく風景を見ているばかりだった。
前職の全精社協時代には、全国団体ということもあり、講師依頼などを受けていい気になって全国のあちらこちらへとお邪魔させていただいた。多いときは1か月に5?6回は出張し、新幹線や飛行機のお世話になっていた。
特に行き帰りの移動中は、講演内容の整理をしたり、時間がなくて溢れてしまった仕事を片づけたり、読みかけの本を読んだりするなど、とても貴重な時間だった。
しかし今は……。
「私たちは私たちなりにしっかりとやってきた」という事実を検察官に伝えにようという意気込みもあった。
だからいつものように読みかけの本やパソコンを持ってきたのだが、とてもそんな気持ちにはなれず、大阪へ着くまでのあいだ一度もかばんを開くことはなかった。
前日のことである。
昼休みに携帯電話を見たら、「着信あり」と留守番電話の通知が出ていた。
「新聞社の取材か」と聞く気にもなれなかったが、また職場にかかってくるのもそれはそれで困ると思い、留守電をまず聞いてみることにした。
「大阪地検特捜部の検事の□□です。至急折り返しご連絡をいただきたい」と入っていた。
なんで大阪地検が私の携帯電話へかけてくるのか?
やはり新聞報道のことか?
では俺も疑われているのか?
なぜ電話をかけてきたのかを知りたかった私は、すぐに折り返しの電話をした。
「尾上さんですね。新聞報道でもあったように今回の事件のことで詳しいことをお聞きしたく、お電話をさせていただきました。明日ですが、大阪地検までお出でいただきたいのですが」
翌日は金曜日で仕事もあったため難しいと伝えると、
「そうですか。どうしても来ていただかなくてはいけないので、こちらから上司の方にお話しさせていただいても構わないのですが」と言う。
とても丁寧な対応であるが、ある種の押しの強さを感じた。
任意取り調べであるにもかかわらず、もはや私には「選ぶ」という権利は存在していないことを実感させられた。
職場の上司、仲間、そして妻にはどう言えばいいのか。どう思われるのか――。
しかし私にはもう選択肢は残されておらず、目の前にあるのは、明日行くしかないという明白な事実だけだった。
任意取り調べ
最寄りの駅から重い荷物を持ち、歩いて移動した。この日は晴れていて、スーツのなかで汗がにじみ出ていた。
途中、見覚えのある新聞社の看板が2社ほどあり、ここから取材に来ていたのかと思いながら歩くと、わりと幅のある川が緩やかに流れており、そこにかかる橋を渡るとすぐ目の前にガラス張りの近代的な大きな高層ビルがそびえ立っている。
それが大阪地方検察庁、すなわち大阪地検だった。
受付で案内された階へ行くと、エレベーターの前で職員と思われる方が待っていた。
待合室のようなところへ案内され、しばらく待つように言われる。
緊張感と不安感を押さえるように窓の外を見てみると、さすが高層ビルである。眺めがよい。
遠くに飛行機が着陸するのが見える。「あれはどこの空港だろう」などと思いながら待ち続ける。
壁を見てみると、「検察で調べを受ける方へ」という注意書きが張ってあり、そこには「話したくない内容については、話さなくてもよい」という意味のことが書かれていた。
しかし、自分は本当に「話さない」という選択ができるのだろうか。ここへ来ないという選択肢はすでになくなっていただけに、自分自身への疑いは大きい。
それにしても「待つ」という時間はとても嫌なものだ。この先、検察と相対していかなければいけないという不安だけが募る。
果たして新患さんが診察を待っているのは、こんな感じだろうか。
精神科を初めて受診する人のほとんどは、家族や福祉関係者に連れてこられる。
しかしご本人は今の私のように何が何だかわからないまま、自分がどうなっていくのかもわからないまま、不安をかかえたまま待っているのではないだろうか――。
そんなことを考えていたとき、「尾上さん」と先ほどの男性が呼びにきた。荷物を抱え、後ろからついていく。
待合室から部屋は離れておらず、男性が扉を開けてくれ、入るとそこは私が想像していた以上に大きな部屋だった。
正面と横には大きな窓ガラスがあり、その前には分厚い青いファイルがいくつもきれいに並べられていた。ここも外の眺めがいい。
部屋の真ん中あたりに大きな机が正面に置かれ、そこに座った検事が私を迎え入れた。検事の右横には縦に机が置かれ、案内をしてくれた男性が座った。
私は机を挟んで検事の前に座り、まず挨拶をした。
任意の事情聴取は結局5時間以上も続いた。
(尾上義和「拘置所の23日間」第2回了)
『精神看護』2011年3月号(医学書院)より。

本記事が掲載されている『精神看護』3月号の特集は「主任はつらいよ、楽しいよ」。看護管理職としての第一歩である、主任のリアルな本音が載っています。特別記事「痛い!」対談、研究調査報告「患者が期待するトラブル時の看護介入とは」など盛りだくさん。ぜひご購読ください。