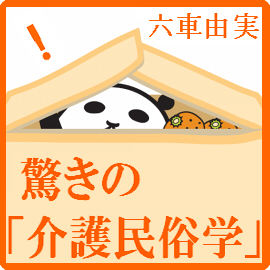かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

第5回 喪失の語り
2011.4.08 update.

1970年、静岡県生まれ。大阪大学大学院文学研究科修了。博士(文学)。民俗学専攻。東北芸術工科大学東北文化研究センター研究員、同大学芸術学部准教授を経て、現在、静岡県東部地区の特別養護老人ホームにて介護職員として勤務。
論文に「人身御供と祭」(『日本民俗学』220号、第20回日本民俗学会研究奨励賞受賞)。『神、人を喰う――人身御供の民俗学』(新曜社、2003年)で2002年度サントリー学芸賞受賞。
『クロワッサン』(マガジンハウス、2011年1月10日、25日発行号)「おんなの新聞・介護」に2号連続で取材記事掲載。
身体の喪失を語る
渡邉美智子さんは、歌を歌うのが大好きだという話をしたあと、唐突にこうつぶやいた。
歌を歌うことで私は死ななくていられたの。
私は予想外の言葉に一瞬たじろいだが、気を落ち着かせながら、そのまま美智子さんの口からゆっくりと発せられる言葉に耳を傾けた。
美智子さんは、昭和6年、山梨に材木屋の娘として生まれ育ち、さまざまな経緯の末、静岡の布団屋へ嫁に来た。
ご主人は機械で綿を打ち、美智子さんがその綿を布団に仕立てた。美智子さんはいろいろな布団屋をまわりながら独学で技術を習得し、そのおかげで店は繁盛した。ところが、機械を扱っていたご主人が癌を患って仕事ができなくなってしまった。
家族で話し合った末、ご主人の代わりに美智子さんが綿を打つ機械を使うようになったのだった。慣れない機械の仕事は大変だった。
機械を使い始めて3回目だったかな。お父さんができないから、私一人で仕事をしていたの。そうしたら急に機械がガリガリ、ガリガリという大きな音を立てたんだよ。それで、あれ何だと思って、機械に近寄って覗き込んだのね。その瞬間、右手の指が機械に挟まってしまったの。それであっという間に右手全体が巻き込まれてしまって。うわーっと思ったんだけど、右手が使えないから機械を止めることができなくて。なんとか全身を使って必死で右手を引っ張ったら手首のところからひょいっと外れた。本当にひょいっとね。たぶんの手首の関節がはずれたんだね。それで助かった。血はものすごい出たよ。びっくりするほどね。でも、不思議なことにその時は何も痛いとは感じなかったの。
美智子さんは右手首がない。それでも、食事のときなどは器用に左手でスプーンやフォークを使っている。ただ、右耳に補聴器をはめるときは不便そうだ。
利用開始前のフェイスシートには右手の欠損の理由に「事故」と書かれていたが、それ以上の情報はなく、また職員もそれについて触れることはなかった。というより、利用者さんの負の記憶には触れてはいけない、という介護現場の暗黙の了解のもとに、あえて触れないようにしていた、というのが正直なところかもしれない。
ところが、この日は何のきっかけだったのか、美智子さんのほうから手首の喪失の記憶について語りだしたのであった。
「こんなこと恥ずかしくて今までは話したことなかったんだけど……」と美智子さんは言うが、その語り口は淀みなく、しかもリアリティたっぷりの表現であり、私はその話に一気にひきこまれていった。
さらに、話は続いていく。美智子さんが失ったのは右手首だけではなかった。
美智子さんが一命をとりとめて入院している間に、ご主人が事故のショックで食事が全くとれなくなり、容態が急激に悪化してしまったのだ。ご主人はやせ細り、顔色も悪くなった。お見舞いにきた様子をみて、美智子さんはご主人を説得して入院させた。病院ではあと半年しかもたないだろうと言われたが、それよりももっと短く、10日余りで亡くなってしまったという。
入院中であった美智子さんは、仮退院をして葬式に出た。本当はまだ入院治療が必要だったのだが、そのまま病院に戻ることはなかった。
右手とご主人という、美智子さんにとって大切なものを一気になくしてしまった絶望感はどれほどのものだっただろう。美智子さんは生きる希望をすべて失って死のうとしたという。
伊豆の崖っぷちに行ったし、それから富士の樹海にも行ったりしたよ。死にたくて死にたくて。こんな体になっちゃったから死ぬしかないと思った。もう仕事もできないし、お父さんもいないし。なんで生きていなきゃいけないのかなとね。
でもね、どうしても死ぬことができなかったんだよ。崖の上から下をのぞいてね飛び込もうと思ったの。だけど途中に木が生えているでしょ、そこにひっかかって死ねなくて結局生き恥をさらすことになるのではないかと思うとね。どうしても死ぬことができなかった。
生き恥をさらしたくない、だから下手な死に方はできない、というのは、ぎりぎりのところで自死を思いとどまった人のリアルな感覚なのだろう。
私は息を飲んで美智子さんが発する言葉に聞き入りながら、涙が流れるのをとめることができなかった。美智子さんはそんな私を覗き込んで、「あんたが泣くことじゃないじゃないよ」と少し呆れながらも、さらに話を続けた。
死ぬことを諦めた、もう生きるしかないと思ったという。そして生きる希望を持つために、いろんなことを試した。最初は、他人に勧められて押し花をやってみた。それはそれで面白くてがんばったが、額縁を買うのにお金がかかることもあって、2年間続けて結局やめたという。
その後に出会ったのが歌だった。
三島市のカラオケセンターで歌を本格的に習いはじめた。先生から浜北市にある歌手の養成学校の入学試験を受けてみろと言われるぐらい上達したし、とにかく自分の好きな歌をみんなの前で歌うのが気持ちよかった。
最初はね、右手がないことが恥ずかしくてさ。みんなが何だろうって手を面白そうに見るだろ。だから、見られないように見られないようにって、ポケットの中に隠してたんだ。
だけどさ、気分よく歌ってたらさ、右手がポケットから勝手に躍り出てきてさ、腕を上にこうやって大きく上げてたんだよ。それからは右手を恥ずかしいなんて思わなくなったんだ。
そう言いながら、美智子さんは手首のない右手を天井に向けて思いっきり突き上げて笑っていた。
それからはさらに一生懸命に歌うようになった。昔の歌だけではなく、新曲が出るとその歌がはやる前にレコードを買ってきて一番に覚えて歌った。負けん気が強かったから、と美智子さんは言う。どの歌手が好きだったのか尋ねると、歌手が好きというのではなく、歌がいいと思うと何でも買ってきて練習したと答えた。
カラオケの後は飲み屋に繰り出した。沼津や三島の飲み屋はほとんど渡り歩いたんだよ、と美智子さんは言う。手のけがをしたときにおりた保険金は、カラオケ代や飲み代にほとんどを消えてしまった。
「でも、悲しいときにも歌を歌い、楽しいときにも歌を歌い、歌のおかげで死のうなんて思わなくなった」と美智子さんは大笑いしていた。その屈託のない笑顔が印象的だった。
絆の喪失を語る
右手の喪失のことをお聞きしてから1年近くたったある日、久々にじっくりとお話を聞く時間ができたので、私は美智子さんに山梨で育ったという子どものころのことをお聞きしたい、とお願いした。すると、美智子さんは、「子どものころは本当に貧乏でみじめだったから今まで話なんてしたことなかったんだよ」と少しためらっていたが、しばらくすると口を開き、両親のことを語りはじめた。
美智子さんの母親は、美智子さんが子どものころに離婚して家を出たという。父親に妾ができて、父親が母親を追い出したのだ。また、父親の母親に対する暴力もひどかった。母親はとてもきれいな人だった。だから、ちょっとでも母親が男の人と口をきいたりすると嫉妬して、背負子に背負った薪で殴ることもたびたびだった。
そういうこともあって、母親は家を出たのだった。だが、幼い美智子さんにはそんな事情は理解できず、なぜ自分たちを捨てていったんだと、ずいぶんと母親のことを恨んだそうだ。
親に捨てられた子どもが一番恨むのはやっぱりお母さんだよ。それはお母さんのことが大好きだから、その気持ちの裏返しなんだ。
そう語る美智子さんの瞳は少し潤んで見えた。
母親は家を出た後に富士駅のすぐ近くにある旅館で仲居として働いていた。それは母親の親戚が経営する旅館だった。ある日、父親が、「お前らの母親はあんな旅館でなんて働いていてみっともないから、連れて帰ってこい」と言って、お金を持たせて美智子さんと弟さんを富士に行かせたことがあった。
美智子さんはまだ小学校1、2年生のときだったから電車に乗るのも初めてだったし、ましてや富士に行くのも初めてだった。だから、弟とたった2人で電車に乗っても不安で情けなくて、「富士ってどこだろうねえ」と不安がっていた。すると、同じ車両に乗っていた人が親切に「富士は終点だよ。私も富士で降りるから一緒におりようね」と声をかけてくれたりした。
そんな親切もあって終点で電車を降りて、なんとか旅館についた。玄関先に行くと、女将さんらしき人が「ヒサノ(美智子さんの母親の名前)、子どもたちが来たよ」と奥のほうへ大きな声をかけた。すると母親が出てきた。母親は驚いた顔をしたけれども、やさしく「どうしたの、何の用? 早くおあがりなさい」と旅館の中へと促してくれた。
私はね、そのお母さんに向かってさ、言っちゃったんだよ。「お父さんが、お母さんをうちに連れてこいと言ってお金をくれたんだよ。旅館なんかで働くなんてみっともない、って言ってたよ」ってさ。
お母さんは悲しそうな顔をしたよ、そのとき。だけどそれでも優しく、「おばあちゃんの具合が悪いから手伝っているんだよ。おばあちゃんの具合がよくなったら、家に帰るから、お父さんにはそう言っといて」って言ったんだ。そしてね、旅館の外へ連れ出してくれて、私と弟においしいものをたくさん食べさせてくれた。それから電車に乗せてくれたんだ。電車の中で、「お母さんになんてことを言ってしまったんだろう」ってものすごく後悔して、おいおい泣いてしまったよ。
そう語りながら美智子さんは目に涙を浮かべていた。私も涙で手元のメモが見えなくなっていた。美智子さんはその後生きているうちには一度も母親に会うことはなかったそうだ。自らが望まないうちに親子の絆を喪失してしまった美智子さんの悲しみは深い。
だが、美智子さんはある日を契機に救われたような気持ちを抱くようになったという。美智子さんが母親の実家へと墓参りに毎年通うようになってから、夢の中にきれいな女の人が出てきて、にこやかに笑っていたのだ。手には藤の花を持っていた。
母親は生前藤の花が大好きで、いつも藤色のものを身に着けていた。だから美智子さんは「お母さんだ」と確信したという。
それより前はね、お母さんが夢に出てきても、いつもかわいそうな顔をしていて、泣かされるばかりだったけどね。お墓参りをするようになったからだと思うのよ。それからはそういうにこやかなお母さんが出てくるようになったの。
美智子さんは、「本当だよ」と言いたげに私の潤んだ目を覗き込んだ。私も、美智子さんの赤い目を見てうなずいた。二人のまわりには何か言葉にできない熱くて、だけど穏やかな空気が満ちていたように感じられた。
涙と違和感
美智子さんはその後も、幼いころにお兄さんが川で溺れて亡くなったことや、一緒に貧しさを乗り越えてきたお姉さんが駆け落ちしてしまったなど、いくつもの喪失の体験を語ってくれた。
それらはいずれも私の意図したところではなく、別の話からの展開で語られるのだが、私はそのたびに感情が高ぶり涙を流していたように思う。
ところでこうした美智子さんの話を聞きながら、人は生きている間に大切なものをどれだけ失うのだろうと私はしみじみと思った。そして、喪失のたびに時間をかけても何とかその絶望から立ち直って生きてきた美智子さんのたくましさに感動するのである。
だが一方で、冷静になって振り返ってみると、美智子さんが喪失を語るときの語り口の滑らかさに、少なからぬ違和感を感じなくもない。
たとえば美智子さんは、ときに擬態語や身振り手振りを交えながら、声に抑揚をつけていて、まるでその語りは講談師のようだ。既に述べたように、聞いている私はいつも自然と惹きこまれ感情移入し涙を流してしまう。
私が泣くと、「まったくあんたは泣き虫だね」と言いながら、それを意識してか、さらに語り口を盛り上げていくようだった。また、語りの内容も、本人が「私の人生を小説にしたら面白いよ」と言うほどドラマティックであり、語りの構成も起承転結がはっきりしていてわかりやすい。
美智子さんが、実は本連載3回目「幻覚と昔話」で死者の声が聞こえる渡邉美智子さんであることからすれば、その喪失の語りもいくばくかの脚色がなされているか、もしくは語りそのものが幻覚によるものではないか、と疑ってもおかしくないほどだ。
だが、そうした講談師のようなオーバーとも思える語り口は美智子さんばかりに見られるものでは決してない。他の利用者さんによる喪失の語り方もそれによく似ているように感じられることが多いのだ。
思うに、おそらく喪失の語りには二通りあるのかもしれない。
ひとつは、未だ絶望の淵にいるときの血を吐くような救いを求めた語りであり、もうひとつは、絶望を時間の経過とともに何とか乗り越えてからの語りである。
絶望の淵での語りは、言葉にならない感情を吐き出す叫びのようなものであり、語り手にとっても予期せぬ鋭い刃のような暴力的な言葉が羅列されることがある。聞き手はそこから言葉のもつ底知れぬ力強さを受け止めるとともに、語り手の存在の危うさや不安定さを感じとる。そのため語り手と聞き手との間には緊張関係が生じ、かえって聞き手は感情移入したり共感したりしにくくなるのではないだろうか。
一方の時間を経てからの喪失の語りは、つらい出来事について語り手のなかで自分なりの再解釈がなされたうえで発せられたものであるといえる。言葉にならなかった絶望は何度も咀嚼され、そして血肉へと消化されて生きる強さへと変化している。
だから、発せられる言葉も穏やかである。聞き手は語りに安心して身をゆだねて語りの世界へ没入することができ、最後には語り手の生き方の力強さに圧倒され、淡い光に包まれたような温かさを覚えるのである。
それからすると、美智子さんら利用者さんたちの語りは明らかに後者に属するだろう。私が彼らの語りにいつも感情移入し涙した(できた)のは、深い絶望を乗り越え生き抜いてきた存在だからこそもっている大きな懐に安心して身をゆだねていたからだったのではないだろうか。
美智子さんたちも実はそれをよく心得ていて、聞き手である私がより心地よく語りの世界に入り込むことができるように、ときに身振り手振りを交えたり、独りよがりではないわかりやすい表現を使ったりして、語りを盛り上げていたのかもしれない。
「昔話」のエネルギー
そうした喪失の語りの場面における語り手(利用者さん)と聞き手(私)との関係は、講談における講談師と聴衆との関係、あるいは演劇における演者と観客の関係にも似ているとも言えるが、民俗学を専門としてきた私には、昔話の語りの場が思い浮かんでくる。
薄暗い部屋のなかで囲炉裏を囲んで語られる昔話。語り部のおじいさん、おばあさんは、頬を赤く染め、目を真ん丸に見開いた子どもたちの顔を時折のぞきながら、昔話を語り聞かせる。
昔話には、社会の理不尽さや生きることの切なさとともにそれを乗り越えていく人間の強さが込められている。そして、語りの場では語り部自身の歩んできた人生がそれに重ね合わされて再解釈がなされ、さらにリアルに語られていくのだ。
そこでは、昔話の世界と語り部自らの経験との境が曖昧になっていく。重要なのは、聞き手である子どもたちの素直な心にどれだけまっすぐに語りが届くかということである。
利用者さんの喪失の語りに涙する私は、まるで昔話を語り聞かされる子どもだ。
語られる喪失の体験は、もしかしたら誇張されていたり、あるいは虚構であったりするかもしれない。しかし、語り部の圧倒的な存在感を前に私にはもはやそのことはそれほど問題ではなくなる。私は、体全体を高揚させてその語りの世界に夢中になり、そして、熱い涙を流した後には、絶望を生き抜く力に変えていく知恵とエネルギーをもらうことができるのである。
それが高齢者のケアをする介護職員として正しいあり方なのかどうかは自信がない。また、冷静に事実を見極め、それを資料として積み重ねていかなければならない民俗研究者としては失格なのかもしれない。
けれど、利用者さんとのそうした一つひとつのかかわりが、介護職員として、そして介護民俗学を実践しようとする民俗研究者としての私の意欲を支え、動機を与えてくれている。それだけは確かだ。
(web第5回了)
[次回は5月中旬UP予定です。乞うご期待。]