かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
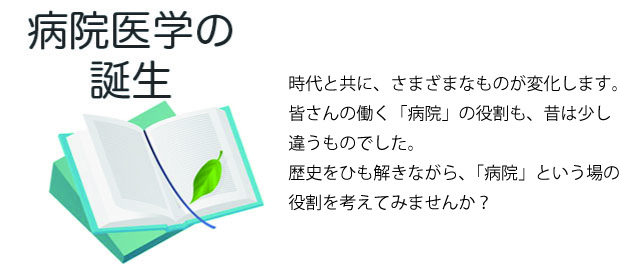
その2 アンシャンレジーム下の病院
2013.4.15 update.

東京女子医科大学名誉教授、メディカルクリニック柿の木坂院長。
「人」に対する興味に端を発して、東京大学医学部へ入学。その後、東京女子医科大学神経内科主任教授、同大学医学部長を歴任し、現在に至る。人を「観る、診る、視る」神経内科医。
文学や音楽といった芸術にも造詣が深く、著書も多数。主なものに、『神経内科医の文学診断(白水社)』、『見る脳・描く脳(東京大学出版会)』、シリーズ『脳とソシアル』などがある。
パリにおける死ぬ場所としての病院のうち最大のものは、ノートルダム大聖堂に附属するオテル・ディユー(Hôtel Dieu de Paris)病院であった。この病院が一体いつから存在していたのか、正確なところはわからないが、少なくとも7世紀中頃には、ノートルダムの傍に、病者を受け入れる施設が存在していたと言われている。そうすると、現在もその名を残すこの病院の組織は、およそ1400年ほどの歴史を持つということになる。しかしこれほど長い期間のうち少なくとも1200年ほどの間、病人にとってのオテル・ディユー病院は、治療の場ではなく死ぬ場所であり続けてきた。オテル・ディユー病院の病室で、1つのベッドに、全裸の複数の患者が臥床している15世紀の有名な絵があるが、実際は1つのベッドに3人も4人も寝かされていたことすらあった。また、病気の診断というものが存在しない時代であったから、伝染性の感染症の患者とそうでない患者が一緒のベッドに寝かされていることもあったし、それどころか、既に息を引き取った患者が、まだ生きている患者と同じベッドに横たわっていることさえあった。

15世紀に描かれたパリのオテル・ディユー病院の病室
(Pecker A: La Médecine à Paris du XIIIe au XXe siècle. Editions Hervas, Paris, 1990, p 121より)
フランス大革命前夜の1785年、すなわちアンシャンレジーム(旧体制)の末期に、ルイ16世の命を受けて病院の実態調査を行った外科医トゥノン(Jacques-René Tenon: 1724-1816)は、パリのオテル・ディユー病院の劣悪な環境について詳細な報告を遺している。それによると、オテル・ディユー病院の基本方針は、1つの部屋にできるだけ多くのベッドを入れ(その頃のオテル・ディユー病院のベッド数はおおよそ1,400床程度であったと思われる)、1つのベッドにできるだけ多くの患者を寝かせることだったという。生きている人、死に掛けている人、既に死んだ人が同じベッドに寝かされており、手術は病室の中、しばしばベッドの上でなされ、手術の痛みに耐えかねた叫び声は病室中に響き渡るし、ノコギリで腕や脚の切断を行うといったような手術操作そのものも丸見えだった。別の病棟では、売春婦と妊婦が同じベッドに寝ており、産み落とされた子供は、どんな感染症に罹患してもおかしくはない状態だった。全ての病室は暗く、湿っていて、空気はよどみ、化膿や腐敗による悪臭がたちこめていた。このような状況を見たトゥノンのは、オテル・ディユー病院は全ての病院のうちでもっとも不健康かつ不快な病院であり、9人の患者のうち2人が死ぬと結論づけている。
こんな状況下の病院が、パリには48箇所もあり、そこに2万人以上の病人が収容されて、死ぬのを待っていた。フランス、特にパリにおけるこのような病院事情は、世界的に見て極めて例外的なものであった。当時の他のヨーロッパ諸国においける病院の規模はずっと小さく、医療における病院の社会的重要度は、比べものにならないほど小さかった。アンシャンレジームの最後の頃、死ぬ場所としての病院は、パリの人々にその陰惨な最後の姿を見せていたのである。しかしその一方で、病院改革の大きなうねりが、既に始まっていたのである。

