かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
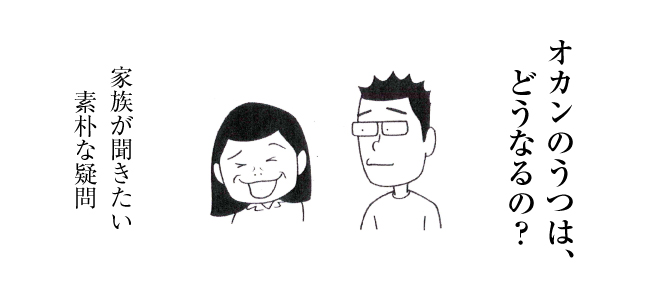
第1回 オカンはうつ病だったんだ!
2013.1.22 update.

さぐちけんさく◯1973年10月10日生まれ。93年よりフリーライターに。以来、オカンのうつに右往左往しながら雑誌、Web、書籍と原稿を書きまくり、生計を立てる。2010年5月、うつ病の家族を向き合う人に向けたコミックエッセイ『ぼくのオカンがうつになった。』(PHP研究所)を出版。オカンの病状は良かったり、悪かったり。ブログ「狛江ライター雑記」はこちらhttp://saguchi.jugem.cc/。
1989年。まだ、家の電話は黒電話で、携帯電話が24時間戦うビジネスマンのものだった頃、僕のオカンは耳鳴りやめまいに悩まされるようになった。
今、思い返せば、これが「うつ」の始まりだったのかもしれない。
当時、高校生だった僕は何が何やらよくわからず、思春期の息子らしい突き放し方で「病院行ったら」と言うだけ。オカンは自らの異変の原因を突き止めようと、さまざまな病院へ通い始めた。
耳鼻科、眼科、神経内科。当時としては先端医療だったMRIでの脳の画像診断も受けていたと記憶している。
転々とした末の診断結果はメニエール病だった。三半規管に原因があるとされる病気で、めまいや耳鳴りの症状が出る。薬が処方され、病状は落ち着いたように見えた。しかし、40代となり、再婚していた義父との関係が悪化。別居をし、離婚調停を行い、祖父が亡くなり、長年飼っていた愛犬が亡くなった頃から、様子が変わっていった。
「体が重い。なにもする気が起こらない」
そう言いながらも、オカンは踏ん張った。ほぼ毎日、炊事、洗濯、掃除、買い物を誰かに強いられているかのようにがんばる。しかし、それ以外の時間は、ぐったりと横になっていることが多かった。
どこか、おかしい。
そう自分で判断したのだろう。
オカンは、のしかかっている症状を耳鼻科や内科の先生に伝え、紹介された心療内科へ通い始めた。いつの間にか、メニエール病という診断名はどこかに消え、睡眠薬が処方され、それを飲むと「よく眠れる」と喜んでいるオカンがいた。
その笑顔を見て「よかった」と思う一方、「メニエール病という診断はどうなったのだろうか?」「こんなに転院を繰り返して大丈夫なのだろうか?」「心療内科ってどんなところなんだろうか?」という疑問も感じていた。
何度目かの通院日、オカンが「ついてきて欲しい」と言い、高校生だった僕はどぎまぎしながら心療内科へ行くことになった。まだ、インターネットがなかった頃のこと。図書室で拾い読みした本には、「心療内科≒精神科」というニュアンスのことが書いてあった。
精神科には精神病の人が通っている。
当時、住んでいた街には大学付属の大病院があった。そのエントラスを経由する路線バスに乗ると、車内でぶつぶつと独り言を言い、見えないものを見えると言い、聞こえないものを聞こえると言う人たちと乗り合わせることがあった。激昂し、手すりに怒りをぶつけるおばさんがいた。笑いながら話し続ける若者がいた。周りの大人は見て見ぬふりで、運転手も何も言わない。郊外に住む高校生だった僕にとって、それが精神病の人たちだった。
オカンの通院の日が近づくにつれ、行ったこともない心療内科のイメージが膨らんでいった。白壁の古い建物に、暗く薄暗い診察室。年配の猫背で陰気な先生と、小太りで無表情な看護師。待合室では、喜怒哀楽をコントロールできない人たちがうろうろと落ち着かずに歩き回っている。完全に漫画や映画からの空想だった。しかし、自分の母親が、そんな患者の集まるところでどんな診察を受けているのか。そして、先生からどんな話を聞かされるのか。
不安だらけだったが、義父と別居している今、付き添えるのは、自分だけ……と気を張っていたのを覚えている。
ところが、先生は思いのほか、若く、やさしく話す人だった。
「何度かお話を聞いて、診断したところ、お母さんは『うつ病』を患っています。怖い病気のように思うかもしれないけれど、きちんと薬を飲み、しっかりと休養を取っていけばゆっくりと治っていくから大丈夫ですよ」
この日が、長らく続く「うつ病と診断されたオカン」との出会いだった。診察室を出て、勝手な空想とは違う明るく静かな待合室に戻った後、オカンの具合の悪さを示す病名があることと、休めば治っていくという言葉にホッとしたのを覚えている。
オカンが「起き上がれない」「夜、眠れない」と言うのも、病気のせいだったのだ。病気ならば病院に通ううちに治るはず。しかし、クリニックでは注射をするわけでもなく、聴診器を当てるわけでもなく、問診して、薬を出すだけだった。
今、振り返ると、あの若い先生はとても丁寧な診察をする人だったように思う。それでも外科や内科での治療とは異なるやり方が不思議で、「うつ病ってなんだ?」という疑問はむくむくと膨らんでいった。その後、オカンの病状は一進一退。落ち着いてきたかと思えば、沈み込み、薬を調整して対処する。
それからかれこれ20年とちょっと。オカンは今日もうつとの付き合いを続けている。その間には、パニック障害、せん妄、被害妄想、過呼吸と、バラエティ豊かな病状が顔を出しては治まっていった。もちろん、本人が希望しての入院もあれば、医師の判断による処置入院もあった。
結論から言うと、これだけの長い時間、投薬治療を行ってきたにもかかわらず、オカンのうつ病は治っていない。母子家庭の一人息子としてはもう、一生ものの付き合いだと覚悟して、付かず離れずの距離でそばにいる。
2010年、僕はそんなオカンとうつとの日々を『ぼくのオカンがうつになった』(PHP研究所、漫画:サトウナオミ)というコミックエッセイにまとめた。
この本を書くきっかけとなったのは、「うつ病」という言葉がポピュラーなものになる一方で、うつと関わる家族をフォローする情報は少ないままだと感じたことだった。うつ病を患って一番つらいのは本人だ。しかし、周囲にいる家族も本人の病状に引っ張られ、影響を受けながら暮らしていかなければならない。うつが重く出ているとき、その表情は能面のようになり、話しかけても答えてもらえず、着替えることも億劫らしく、滅多に寝床から出てこない。
「水を持ってきてくれ」「熱いからエアコンをつけてくれ」「うるさいから電話で話をするな」
イライラを当たりちらすような無茶を言ってくるかと思えば、「私なんか生きている意味がない」と泣き始める。論理的ではない行動パターンに揺さぶられ、家の中には重苦しい雰囲気が漂う。それでも誰かが家事をしなければならず、仕事もあり、日常は続いていく。
見守る側の心にも疲れがたまり、誰かに打ち明けてみても、そのしんどさをわかってもらえることは少ない。かと言って遊びに出かけても、「どんなふうに過ごしているだろうか」「自殺しようとしたりしていないだろうか」と気になり、帰り道では「またあの能面顔に向き合うのか」と暗い気持ちになる。
僕は「こんなことなら、いっそいなくなってくれた方が楽なのに」と思う日もあった。そして、そう考えたことで自己嫌悪に陥る。「一番つらいのはうつをこじらせている本人なのだから」と。そんなことはわかっているのだが、塞ぎこんだままの大切な人と同じ屋根の下で暮らす家族もつらい。
家族がうつを抱え込みすぎず、しかしながら、こじらせている本人ときちんと向き合っていくために必要な心構えはあるのだろうか? 自分自身に問いかけるところから『ぼくのオカンがうつになった』を書き始めた。結局、答えは出たような、出ないような、他の家族への助けになったような、ならなかったようなまま、出版から3年が過ぎようとしている。
前著には書き切れなかったことがたくさんあるなと思っていたら、幸運にも「かんかん!」から「書きませんか?」と声をかけていただいた。今でもオカンのメンタルクリニック通いは月に2回ペースで続いている。完治も寛解もないまま、安定と不安定の間を行き来する日々の中で感じてきた医療関係者の皆さんへの素朴な疑問。
この連載では、うつ病と向き合う家族の本音を医療の現場に立つ方々へ率直にぶつけていきたい。
イラスト◎サトウナオミ、『ぼくのオカンがうつになった。』(PHP研究所)より転載

2008年、気分障害での通院患者数が100万人を突破しました(厚生労働省調べ)。しかも、患者の半数以上である約57万人が50代~80代。つまり、うつ病に悩む人の多くが、30代、40代にとっての親世代なのです。
もし、自分の家族がうつ病を患ってしまったら……。頼れる存在だった親が、ふさぎ込んでしまうもどかしさ。もちろん、一番苦しいのは本人ですが、周囲の家族もまた、「うつ」という病に巻き込まれていきます。投げ出したくても投げ出せず、身近で接することの苦しさを吐露し合える仲間はなかなかみつかりません。
僕のオカンがうつ病と診断されたのは、16年前のこと。パニック障害を併発したこともあれば、ヒステリックな行動に出るオカンにがく然とし、涙したことも多々あります。それでもなんとか寄り添いながら、今日まで歩んできました。
うつ病によって、人が変わってしまったように思える親や家族とどう付き合えばいいのか? うつ病になってしまった母親とぼくの、激動の16年間を書いたコミックエッセイです。

