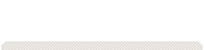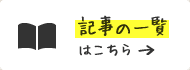かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-
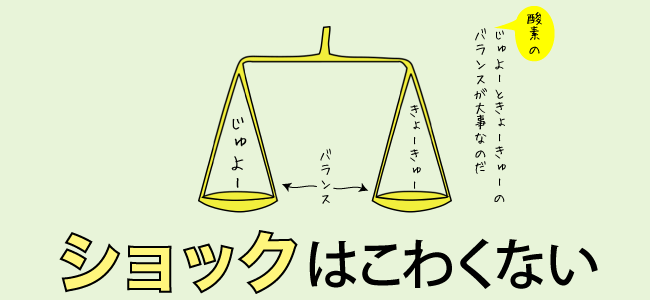
第3回 ショックの分類
2000.2.24 update.
ショックは大きくわけると4つに分類されます。
| 代表的疾患 | |
| 心原性 |
急性心筋梗塞、不整脈、心筋症、心筋炎 |
| 循環血液量減少性 | 出血(外傷、上部消化管出血)、脱水 |
| 血液分布異常性 | 敗血症、アナフィラキシー、神経原性(脊髄損傷) |
| 閉塞性 |
心タンポナーデ、緊張性気胸、肺塞栓症 |
それではそれぞれの生理学的変化をみてみましょう。先程の、酸素供給量と血圧の式を見直し、どこが下がってショックとなっているかを確認して下さい。
|
|
心拍出量 |
左室充満圧 (前負荷) |
末梢血管抵抗 |
|
心原性 |
↓ |
↑ |
↑ |
|
循環血液量減少性 |
↓ |
↓ |
↑ |
|
血液分布異常性 |
↑or→ |
↓or→ |
↓ |
|
閉塞性 |
↓ |
↓or→ |
↑ |
■心原性ショック
急性心筋梗塞や心筋炎、不整脈などによって、心収縮力が低下することで、心拍出量が低下します。
■循環血液量減少性ショック
外傷による出血や消化管出血、または嘔吐・下痢などによる脱水、などにより循環血液量(前負荷)が減少し、心拍出量が低下します。
■血液分布異常性ショック
敗血症やアレルギー、脊髄損傷による自律神経障害により、末梢血管が拡張し、末梢血管抵抗が低下します。循環血液量が十分にあれば、最初は代償的に心拍出量は増加します。そのため末梢の血管拡張により、四肢は温かくなりますが、その後心拍出量が低下してくれば、四肢は冷たくなります。脊髄損傷は、通常のショックと異なり、代償機構が働かないため、徐脈となります。
■閉塞性ショック
その特徴は、心臓への血液灌流の障害と後負荷の増加です。心タンポナーデでは、心臓周囲の心嚢液増加により心室の拡張が障害され、心拍出量が低下します。緊張性気胸では、気胸による圧迫で静脈還流が低下し、心臓へ流入する血流が低下するので、心拍出量が低下します。肺塞栓症では、右室の後負荷が増大し、右室からの心拍出量が低下します。
第3回「ショックの分類」了
次回は「ショックの治療」についてです。